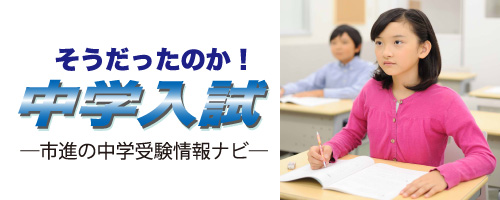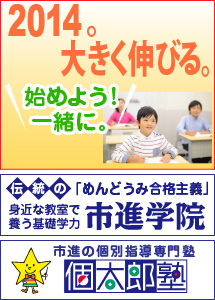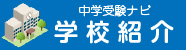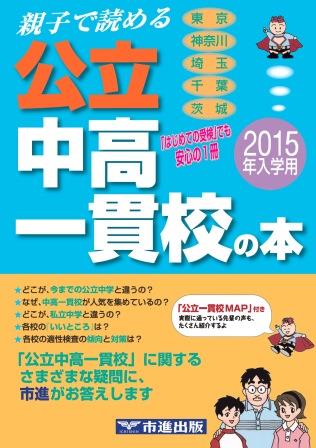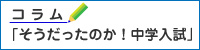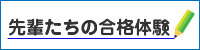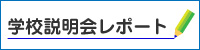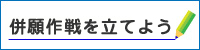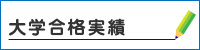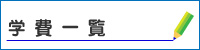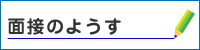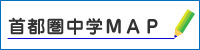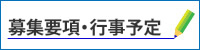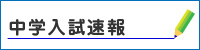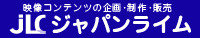トップページ > コラム「そうだったのか!中学入試」第11~20話 > 第11話 「午後入試の話」
第11話 「午後入試の話」
2011年1月24日
千葉,埼玉の1月入試も終盤戦に入っています。すでに合格をもらっている受験生の皆さん,おめでとうございます。さて2月に入ると東京,神奈川の入試が始まります。すでに合格をもらっていても,これから始まる東京,神奈川の有名校,難関校の入試を目指してがんばっている受験生も多いと思います。
最近は東京や神奈川の学校を受験するとき,何校かの受験校のなかに1~2校は「午後入試」を入れるのが当たり前になってきました。昔ながらの午前中だけの入試を行っているのは,御三家レベルかそれに次ぐレベルの学校などの上位校および中堅校の中でもトップレベルの学校だけと言ってよいでしょう。中堅・下位校のほとんどでは少なくとも1回,多くの学校では2~3回は「午後入試」を実施しています。したがってトップレベルの一部の受験生は別として,恐らく半数以上の受験生は併願パターンに「午後入試」を組み込んでいるものと思われます。今回は東京,神奈川の入試直前にあたり,ここまで広がってきた「午後入試」について考えてみます。
中学入試の世界に初めて「午後入試」が登場したときは,ずいぶんと「きわもの」扱いされたこともありましたが,ここ10年あまりで「午後入試」はすっかり定着し市民権を得たようです。2011年入試で「午後入試」を実施する学校は1都3県で中学から公募をする全私立中学286校中133校で47%と半数近くに達します。(茨城は実施校なし)また「午後入試」実施校は東京と神奈川に集中していて,東京94校,神奈川26校あわせて120校で,1都3県の全実施校133校の90%となっています。さらに東京の私立中学179校のなかで「午後入試」実施校94校は53%と過半を超えています。神奈川では59校中の26校ですから44%です。また東京の実施校94校について男女別の区分でみると男子校が33校中10校で30%,女子校が75校中39校で52%,共学校が71校中45校で63%です。
さらに東京,神奈川の「午後入試」実施校を偏差値帯でみると大半は偏差値55以下の学校です。偏差値55以上の学校もわずかにありますが,60以上になると男子校では高輪中(算数),女子校では普連土学園中,共学校では国学院久我山中(ST)の3校だけです。ようするに「午後入試」の実施校はほとんどが中堅以下の学校であり,また中堅以下の学校では一部の大学の付属校などを除いて,ほとんどの学校は「午後入試」を実施しています。
それでは「午後入試」はそもそも何のために行われているのでしょうか。これは誰でもすぐわかることですが,多くの学校が入試を行う午前中の時間帯を避けて受験しやすい午後に入試を行うことによって,多くの受験生を集めるためです。すなわち「ウチを併願校につかってもらって,午前中はどうぞウチより上のレベルの学校を大いにチャレンジしてください。そして残念な結果だったら是非ウチにきてください。」というわけです。「午後入試」を併願校として受験するのは従来のその学校の受験生より学力的には上の層です。本来の受験者層より高い受験者がそれなりの人数受験してもらえるのであれば,その学校にとって大変大きなメリットがあるわけです。
また受験生の側にとっても「午後入試」は大きなメリットがあります。志望順位の高い難関校,有力校は午前入試しかやっていませんから,午前に併願校の受験日を1日とるとそれだけ選択肢が狭くなってしまいます。併願校を午後入試で受験できれば午前に受験できる学校の選択肢が広がるわけです。学校と受験生の双方にとって大きなメリットがあるためにこれだけ「午後入試」が広がったのでしょう。
さて東京で「午後入試」が広がった背景には学校数の多さと入試日程の問題があると思われます。言うまでもなく東京は全国最大の「中学受験市場」で受験生の数は多いのですが,学校数も前述のように私立中学がこの20年で31校も増えて179校もあるうえに,以前からある国立大付属中8校に加え,公立中高一貫校がここ6年で11校も開校しています。周辺3県の私立中学は神奈川59校,千葉24校と埼玉24校をたしても107校ですからいかに東京に私立中学が多いがわかります。そしてその179校中偏差値55以上の学校は40数校ですから,7割以上の学校は中堅以下の学校ということになり,入学者の確保をめぐって競合する中堅レベルの学校の争いは相当に激しくなっていて,普通に午前の入試をやっているだけでは受験生を集めることが難しくなってきているのです。
また東京と神奈川の中学入試は2月1日から始まり3日までが前半戦で4日から6日あたりが後半戦です。特にトップレベルの学校はほとんど前半戦で入試を終えますから,千葉や埼玉に比べてはるかに短期決戦です。強い集客力を持つ上位校はともかく,中堅校にとって179校の入試がひしめく前半の3日間の午前に入試を新設して新規参入するのは成算が立ちませんから,結局は「午後入試」しかないわけです。また4日以降の後半戦になると「市場規模」が急激に縮小します。前倒し傾向が強くなって,前半3日間の受験者数合計は約8万4千名ですが,後半戦の受験者数合計は約1万6千名と実受験者数は激減です。後半にも多くの入試が行われていますが,実態は上記のようになってきているため4日以降では受験生を集めること,そして入学者を確保するのが困難になっているわけです。
以上のような事情により前半戦の午後というのが現実的な選択ということになったのでしょう。また「午後入試」実施校が10校,20校・・と増えて「午後入試」に対する違和感が無くなってきた頃から実施校が急激に増えて,今では当たり前になってしまいました。特に東京では「午後入試」が急激に拡大して,「午後入試」自体が競合するようになってきているため,このところは受験生が集まる学校と集まらない学校の差が出てきています。都内では「午後入試」をやれば受験生が集まるといった時期は終わりつつあると言ってよいでしょう。また神奈川でも「午後入試」同士の競合が強まってきたためか,「午後入試」を新設した学校に受験生が集中して,他の学校の「午後入試」に影響が出るようになっています。
さて一口に「午後入試」と言っても学校によっていろいろです。従来からの午前入試を同じ日の午後に移す場合と,午前入試は今まで通り実施し,同じ日の午後に入試を新設する場合があります。また単に午後に実施する入試というだけではなく,高輪(算数1科目)や江戸川女子中AO(2科基礎学力)などのように入試科目や選考方法で特色付けをしたり,足立学園中(特奨),大妻中野中(アドバンスト)や国学院久我山中(ST選抜)などのように特進クラスなどの選抜や,特待生(特奨生,給費生)の選抜機能を合わせた入試とするなど,午前入試とは異なる特化した入試にする工夫をしている学校が目立ちます。前述のように「午後入試」の受験者は午前の受験生より学力上位生が多くなりますから,上記のような選抜機能を付加するのは妥当なやりかたです。逆にいえば,より多くの学力上位生を集めるための付加価値をつけた入試ともいえます。

山手学院中 それでは「午後入試」の入試状況をいくつか具体的にみてみましょう。
最初に取り上げるのは昨年初めて「午後入試」を導入して神奈川の中学入試の台風の目となった横浜南部の山手学院中です。これは中高一貫教育強化の学校改革と連動した入試改革です。4回の入試をおこなっていますが,昨春入試から2日のB入試を「午後入試」に変えました。これによりB入試の応募者はなんと293名から747名に,受験者数でも214名から528名に激増しました。合格者を97名から303名と増やしたので倍率は2.20倍から1.74倍に下がりましたが,受験者層のレベルは大きく上昇しています。前年までは試験時間が重なっていて受験者のいなかった栄光学園中,聖光学院中,鎌倉女学院中,湘南白百合中などのトップレベルの上位校との併願受験者が,ねらい通りドッと集まっています。他の回の入試も増えていて,定員160名のところ入学者が大幅に超過して251名となってしまいました。山手学院中の場合は予想以上に受験生が集まった例ですが,これは山手学院中が偏差値で60に近い,中堅校では最も高いレベルにある学校だからです。

聖セシリア女子中 次にやはり「午後入試」初年度だった,神奈川でも大和市という中心部からはずれた地域の小規模なカトリック校,聖セシリア女子中の場合をみてみます。1学年4クラス,130名の小規模校でアットホームな雰囲気と面倒見のよい学習・進路指導でそれなりに人気のある学校です。地味な学校なため今まではあまり脚光をあびることもありませんでしたが,「午後入試」の導入で俄然注目を集めました。併設小学校からの進学者を除いた定員105名を4回の入試で募集していましたが,2月3日の2次を2日に移し「午後入試」とした結果,2次の応募者は322名から451名に,受験者では177名から302名と大きく増え,また今まで全くいなかった偏差値60台の受験生が相当な人数受験しています。合格者を55名から138名と大幅に増やしたため,実倍率は3.2倍から2.2倍に下がりましたが,合格ラインの偏差値は変わっていません。入学者は138名中34名(前年は35名)で,普通は合格者中の中下位者が多くなりますが,上から下までまんべんなく入学しているそうです。なお歩留まり(入学率)が24.6%で中堅校の「午後入試」としてはかなり高めといえます。また併願校がレベル的にも学校のタイプでも拡大し,上位校では女子学院中,立教女学院中,共立女子中など今までなかった学校です。また今まで併願先は女子校が中心でしたが,森村学園中,関東学院中,桐光学園中などの共学校が増えているのも注目されます。
「午後入試」の導入にあたってはカトリック校らしく学内に慎重な意見が強かったそうですが,ここ数年わずかながらも応募者数の減少,倍率の低下傾向が続いているため,「もっと下がってからでは遅い,まだ余力のあるうちに『午後入試』を実施したほうがよい」と決断したとのことで,どうやらその判断は正解だったようです。

青稜中 最後に「午後入試」を導入して16年になる,「午後入試」では老舗ともいえる品川区の青稜中をみてみます。この学校は‘95年に女子校から共学化して校名変更し,それと同時に「午後入試」を開始(日本橋女学館中についで2番目)しました。「午後入試」を始めた頃はまだ競合する学校は無く,毎年右肩上がりの倍々ゲームで受験生を集め入試レベルも急上昇していきました。‘04年には応募総数が3,459名と人気が頂点に達しましたが,その後は増減を繰り返しながら減少傾向が続きここ2年は2,000名を切っています。定員200名を2回の入試で募集しますが,2月1日と2日は午前(A),午後(B)ともに入試を行います。1回Bのここ3年間の応募者は817名→530名→531名,受験者では722名→441名→458名,また2回Bの応募者は1,093名→565名→606名,受験者では676名→240名→295名と‘09年に大きく落ち込みがあったことがわかります。この要因としては,受験者のレベルが上がって競合校も手強くなってきていること,‘08年入試で応募総数が一時的にピークの‘04年に近い3,267名に急増した反動などもありますが,「午後入試」を実施する有力校がここ数年で急激に増えていますから,以前のように受験生を独占的に集めることは困難になってきたということもありそうです。
今や多くの受験生にとって「午後入試」抜きで併願作戦を立てることは不可能に近くなってきました。おそらく第2,第3あるいは第4志望で考える方が多いでしょうが,この「午後入試」や「当日発表」の拡大によって受験校のバリエーションは大きく広がっていますから,「午後入試」を上手に組み込むことがお子さんの受験を成功させる上でも重要なポイントになってきています。ただし今回お話したように,その学校の受験生の今までのレベルより1~2ランク上の受験生が受けてきますから,午前の入試とはかなり性格の異なる入試になります。そのことを十分理解したうえで受験されることをおすすめします。
最近は東京や神奈川の学校を受験するとき,何校かの受験校のなかに1~2校は「午後入試」を入れるのが当たり前になってきました。昔ながらの午前中だけの入試を行っているのは,御三家レベルかそれに次ぐレベルの学校などの上位校および中堅校の中でもトップレベルの学校だけと言ってよいでしょう。中堅・下位校のほとんどでは少なくとも1回,多くの学校では2~3回は「午後入試」を実施しています。したがってトップレベルの一部の受験生は別として,恐らく半数以上の受験生は併願パターンに「午後入試」を組み込んでいるものと思われます。今回は東京,神奈川の入試直前にあたり,ここまで広がってきた「午後入試」について考えてみます。
中学入試の世界に初めて「午後入試」が登場したときは,ずいぶんと「きわもの」扱いされたこともありましたが,ここ10年あまりで「午後入試」はすっかり定着し市民権を得たようです。2011年入試で「午後入試」を実施する学校は1都3県で中学から公募をする全私立中学286校中133校で47%と半数近くに達します。(茨城は実施校なし)また「午後入試」実施校は東京と神奈川に集中していて,東京94校,神奈川26校あわせて120校で,1都3県の全実施校133校の90%となっています。さらに東京の私立中学179校のなかで「午後入試」実施校94校は53%と過半を超えています。神奈川では59校中の26校ですから44%です。また東京の実施校94校について男女別の区分でみると男子校が33校中10校で30%,女子校が75校中39校で52%,共学校が71校中45校で63%です。
さらに東京,神奈川の「午後入試」実施校を偏差値帯でみると大半は偏差値55以下の学校です。偏差値55以上の学校もわずかにありますが,60以上になると男子校では高輪中(算数),女子校では普連土学園中,共学校では国学院久我山中(ST)の3校だけです。ようするに「午後入試」の実施校はほとんどが中堅以下の学校であり,また中堅以下の学校では一部の大学の付属校などを除いて,ほとんどの学校は「午後入試」を実施しています。
それでは「午後入試」はそもそも何のために行われているのでしょうか。これは誰でもすぐわかることですが,多くの学校が入試を行う午前中の時間帯を避けて受験しやすい午後に入試を行うことによって,多くの受験生を集めるためです。すなわち「ウチを併願校につかってもらって,午前中はどうぞウチより上のレベルの学校を大いにチャレンジしてください。そして残念な結果だったら是非ウチにきてください。」というわけです。「午後入試」を併願校として受験するのは従来のその学校の受験生より学力的には上の層です。本来の受験者層より高い受験者がそれなりの人数受験してもらえるのであれば,その学校にとって大変大きなメリットがあるわけです。
また受験生の側にとっても「午後入試」は大きなメリットがあります。志望順位の高い難関校,有力校は午前入試しかやっていませんから,午前に併願校の受験日を1日とるとそれだけ選択肢が狭くなってしまいます。併願校を午後入試で受験できれば午前に受験できる学校の選択肢が広がるわけです。学校と受験生の双方にとって大きなメリットがあるためにこれだけ「午後入試」が広がったのでしょう。
さて東京で「午後入試」が広がった背景には学校数の多さと入試日程の問題があると思われます。言うまでもなく東京は全国最大の「中学受験市場」で受験生の数は多いのですが,学校数も前述のように私立中学がこの20年で31校も増えて179校もあるうえに,以前からある国立大付属中8校に加え,公立中高一貫校がここ6年で11校も開校しています。周辺3県の私立中学は神奈川59校,千葉24校と埼玉24校をたしても107校ですからいかに東京に私立中学が多いがわかります。そしてその179校中偏差値55以上の学校は40数校ですから,7割以上の学校は中堅以下の学校ということになり,入学者の確保をめぐって競合する中堅レベルの学校の争いは相当に激しくなっていて,普通に午前の入試をやっているだけでは受験生を集めることが難しくなってきているのです。
また東京と神奈川の中学入試は2月1日から始まり3日までが前半戦で4日から6日あたりが後半戦です。特にトップレベルの学校はほとんど前半戦で入試を終えますから,千葉や埼玉に比べてはるかに短期決戦です。強い集客力を持つ上位校はともかく,中堅校にとって179校の入試がひしめく前半の3日間の午前に入試を新設して新規参入するのは成算が立ちませんから,結局は「午後入試」しかないわけです。また4日以降の後半戦になると「市場規模」が急激に縮小します。前倒し傾向が強くなって,前半3日間の受験者数合計は約8万4千名ですが,後半戦の受験者数合計は約1万6千名と実受験者数は激減です。後半にも多くの入試が行われていますが,実態は上記のようになってきているため4日以降では受験生を集めること,そして入学者を確保するのが困難になっているわけです。
以上のような事情により前半戦の午後というのが現実的な選択ということになったのでしょう。また「午後入試」実施校が10校,20校・・と増えて「午後入試」に対する違和感が無くなってきた頃から実施校が急激に増えて,今では当たり前になってしまいました。特に東京では「午後入試」が急激に拡大して,「午後入試」自体が競合するようになってきているため,このところは受験生が集まる学校と集まらない学校の差が出てきています。都内では「午後入試」をやれば受験生が集まるといった時期は終わりつつあると言ってよいでしょう。また神奈川でも「午後入試」同士の競合が強まってきたためか,「午後入試」を新設した学校に受験生が集中して,他の学校の「午後入試」に影響が出るようになっています。
さて一口に「午後入試」と言っても学校によっていろいろです。従来からの午前入試を同じ日の午後に移す場合と,午前入試は今まで通り実施し,同じ日の午後に入試を新設する場合があります。また単に午後に実施する入試というだけではなく,高輪(算数1科目)や江戸川女子中AO(2科基礎学力)などのように入試科目や選考方法で特色付けをしたり,足立学園中(特奨),大妻中野中(アドバンスト)や国学院久我山中(ST選抜)などのように特進クラスなどの選抜や,特待生(特奨生,給費生)の選抜機能を合わせた入試とするなど,午前入試とは異なる特化した入試にする工夫をしている学校が目立ちます。前述のように「午後入試」の受験者は午前の受験生より学力上位生が多くなりますから,上記のような選抜機能を付加するのは妥当なやりかたです。逆にいえば,より多くの学力上位生を集めるための付加価値をつけた入試ともいえます。

山手学院中 それでは「午後入試」の入試状況をいくつか具体的にみてみましょう。
最初に取り上げるのは昨年初めて「午後入試」を導入して神奈川の中学入試の台風の目となった横浜南部の山手学院中です。これは中高一貫教育強化の学校改革と連動した入試改革です。4回の入試をおこなっていますが,昨春入試から2日のB入試を「午後入試」に変えました。これによりB入試の応募者はなんと293名から747名に,受験者数でも214名から528名に激増しました。合格者を97名から303名と増やしたので倍率は2.20倍から1.74倍に下がりましたが,受験者層のレベルは大きく上昇しています。前年までは試験時間が重なっていて受験者のいなかった栄光学園中,聖光学院中,鎌倉女学院中,湘南白百合中などのトップレベルの上位校との併願受験者が,ねらい通りドッと集まっています。他の回の入試も増えていて,定員160名のところ入学者が大幅に超過して251名となってしまいました。山手学院中の場合は予想以上に受験生が集まった例ですが,これは山手学院中が偏差値で60に近い,中堅校では最も高いレベルにある学校だからです。

聖セシリア女子中 次にやはり「午後入試」初年度だった,神奈川でも大和市という中心部からはずれた地域の小規模なカトリック校,聖セシリア女子中の場合をみてみます。1学年4クラス,130名の小規模校でアットホームな雰囲気と面倒見のよい学習・進路指導でそれなりに人気のある学校です。地味な学校なため今まではあまり脚光をあびることもありませんでしたが,「午後入試」の導入で俄然注目を集めました。併設小学校からの進学者を除いた定員105名を4回の入試で募集していましたが,2月3日の2次を2日に移し「午後入試」とした結果,2次の応募者は322名から451名に,受験者では177名から302名と大きく増え,また今まで全くいなかった偏差値60台の受験生が相当な人数受験しています。合格者を55名から138名と大幅に増やしたため,実倍率は3.2倍から2.2倍に下がりましたが,合格ラインの偏差値は変わっていません。入学者は138名中34名(前年は35名)で,普通は合格者中の中下位者が多くなりますが,上から下までまんべんなく入学しているそうです。なお歩留まり(入学率)が24.6%で中堅校の「午後入試」としてはかなり高めといえます。また併願校がレベル的にも学校のタイプでも拡大し,上位校では女子学院中,立教女学院中,共立女子中など今までなかった学校です。また今まで併願先は女子校が中心でしたが,森村学園中,関東学院中,桐光学園中などの共学校が増えているのも注目されます。
「午後入試」の導入にあたってはカトリック校らしく学内に慎重な意見が強かったそうですが,ここ数年わずかながらも応募者数の減少,倍率の低下傾向が続いているため,「もっと下がってからでは遅い,まだ余力のあるうちに『午後入試』を実施したほうがよい」と決断したとのことで,どうやらその判断は正解だったようです。

青稜中 最後に「午後入試」を導入して16年になる,「午後入試」では老舗ともいえる品川区の青稜中をみてみます。この学校は‘95年に女子校から共学化して校名変更し,それと同時に「午後入試」を開始(日本橋女学館中についで2番目)しました。「午後入試」を始めた頃はまだ競合する学校は無く,毎年右肩上がりの倍々ゲームで受験生を集め入試レベルも急上昇していきました。‘04年には応募総数が3,459名と人気が頂点に達しましたが,その後は増減を繰り返しながら減少傾向が続きここ2年は2,000名を切っています。定員200名を2回の入試で募集しますが,2月1日と2日は午前(A),午後(B)ともに入試を行います。1回Bのここ3年間の応募者は817名→530名→531名,受験者では722名→441名→458名,また2回Bの応募者は1,093名→565名→606名,受験者では676名→240名→295名と‘09年に大きく落ち込みがあったことがわかります。この要因としては,受験者のレベルが上がって競合校も手強くなってきていること,‘08年入試で応募総数が一時的にピークの‘04年に近い3,267名に急増した反動などもありますが,「午後入試」を実施する有力校がここ数年で急激に増えていますから,以前のように受験生を独占的に集めることは困難になってきたということもありそうです。
今や多くの受験生にとって「午後入試」抜きで併願作戦を立てることは不可能に近くなってきました。おそらく第2,第3あるいは第4志望で考える方が多いでしょうが,この「午後入試」や「当日発表」の拡大によって受験校のバリエーションは大きく広がっていますから,「午後入試」を上手に組み込むことがお子さんの受験を成功させる上でも重要なポイントになってきています。ただし今回お話したように,その学校の受験生の今までのレベルより1~2ランク上の受験生が受けてきますから,午前の入試とはかなり性格の異なる入試になります。そのことを十分理解したうえで受験されることをおすすめします。
(おわり)