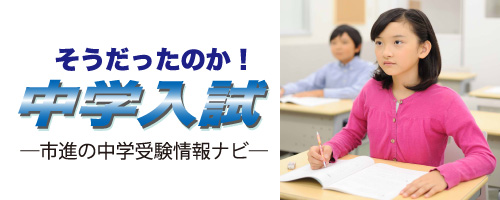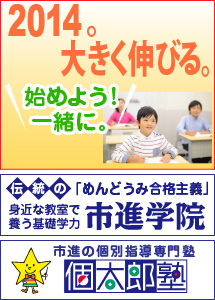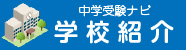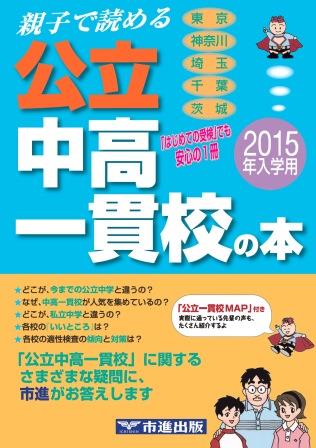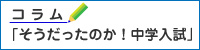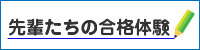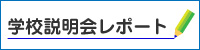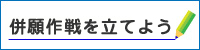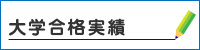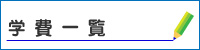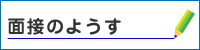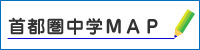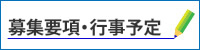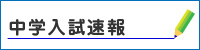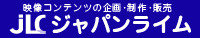第10話 「入試における歩留まり(ぶどまり)の話~入学率をめぐって~」
2011年1月6日
明けましておめでとうございます。とはいっても受験生とご家族の皆さんにとって,今年は正月どころではなかったかもしれませんね。年が明けて,いよいよ千葉・埼玉の私立中学の一般入試が始まります。そして2月1日からは東京・神奈川の私立中学で一斉に入試に突入していきます。
今回は入試について考える際にとても重要なのにもかかわらず,一般の学校案内や受験雑誌などでほとんど語られる事がない「歩留まり」について考えてみます。「歩留まり」とは合格者に対する入学者の割合のことで,言いかえれば最終的な入学手続き率のことです。実はこの「歩留まり」の変動が各私立中学の入試難易度や補欠の繰上げなどを規定する大きな要因になっています。今回はいささか専門的で,また学校側の立場からの話になりますが,知らないと困るわけではありませんから,気楽にお読みいただければと思います。
中学入試に限らず,入試とは学校の立場からすれば生徒募集(の一形態)のことです。したがって学校にとって最終的には「合格者」ではなく「入学者」が問題になります。 「入学者」の何が問題になるかといえば,普通は入学者の数とその学力レベルです。 言うまでもなく「合格者」と「入学者」はイコールではありません。合格者全員が第一志望であれば全員が入学するはずですが,千葉や茨城の推薦入試などは別にして,一般入試では現実にはそんな学校はほとんどありません。
さて「歩留まり」の幅は学校によって非常に差があります。一般的にいって入学レベルの高い学校ほど第1志望者の比率が高いため「歩留まり」も高くなります。中堅校になるにしたがい第1志望者の比率が低くなって併願受験者が増えますから,当然「歩留まり」は下がっていきます。また一般的な傾向として,上位合格者の「歩留まり」は低く,ボーダーに近づけば近づくほど「歩留まり」が上がってきます。
ただし中学入試の場合は別の事情も関係してきます。ひとつは都県による入試日程のズレによるもので,東京や神奈川の受験生が入試日の早い千葉・埼玉・茨城の学校を大量に「試し受験」します。ほとんどは第一志望者ではないので「歩留まり」は低くなります。 もうひとつが「午後入試」です。こちらもほとんどの場合は午前に志望順位の高い別の学校を受験していますから「午後入試」の「歩留まり」は当然かなり低くなります。

開成
次に具体的な事例をみてみましょう。男子御三家のひとつ開成は募集定員が300名で昨年は1,072名が受験し,399名が正規合格しました。その後人数は非公表ですが,約30名と推定される追加合格が出ました。ここで仮に30名として考えると合格者の総数は429名ということになりますが,4月に入学したのは305名ですから124名は他校へ進学したわけで,昨年の開成中学の「歩留まり」は305÷(399+30)×100=71%ということになります。みなさんはどう思われますか。意外に「歩留まり」が低いと感じる方も多いのではないでしょうか。実はこれは関西方面からの受験生がかなりいるためなのです。

桜蔭
女子御三家をみてみると桜蔭は定員が240名で昨年は528名が受験し,253名が正規合格しました。その後11名が繰上げ合格となり,総合格者数は264名,そのうち240名が入学しましたから「歩留まり」は91%です。桜蔭といえば全国の女子校の中で並ぶところのない進学実績の学校ですが,それでも国立大付属や渋谷教育学園幕張中を選ぶ受験生が少数はいるようです。

女子学院
女子学院は定員が240名で昨年は781名が受験し,267名が正規合格しました。その後6年ぶりとなる追加合格が8名出たので,総合格者数は275名ですが,入学者は223名(定員割れ!)ですから「歩留まり」は81%となります。やや低い数字のようですが,リベラルな校風のせいか慶應中等部などの共学校との併願者が多く,進学先にそちらを選ぶ受験生もいるためと思われます。

雙葉
雙葉は規模が小さく,併設の小学校からの進学者を除く定員100名に374名が受験し118名が合格,そのうち111名が入学ですから,「歩留まり」は94%と非常に高くなっています。言ってみれば固定ファンによってささえられている学校であり,カトリック・ミッションの教育に賛同する第一志望者中心の入試になっているためと思われます。

専修大学松戸
次に中堅校の場合をみてみます。まず開校10年にして3,000名を超える応募者を集める人気校,専修大学松戸について。総定員は150名で3回の入試で募集をしています。第1回は1月20日で100名の定員ですから最もメインの入試ですが昨年は1,253名が受験し523名が合格,入学者は91名ですから「歩留まり」は17%です。第2回は1月26日で629名が受験し132名が合格,入学者は50名で第1回不合格のリベンジ受験者が多くなるため,「歩留まり」はかなり高くなり38%です。
以上の2回が1月中の入試です。特に第1回の場合は前述のように東京や近県から大量に「試し受験」する受験生がいるために,(もちろん本気の受験生もいます)上記のように低い「歩留まり」となるわけです。なお2月3日の第3回は東京の入試日と重なるため地元中心の小規模な入試となっています。
さらに公表されている全受験者と全入学者の都県別の人数(合格者の都県別人数の掲載はなし)から,第1回入試における都県別の「歩留まり」を,受験者と合格者および各回の都県別の割合が同じと仮定して推計してみると,千葉が21%,東京が13%,埼玉が12%,神奈川は0%です。実際には各回の都県別の割合が同じことはありえないので,千葉はさらにこれより高く,東京はこれより低いはずです。学校の所在地が千葉県内でも最も東京寄りで,東京の江戸川区,江東区あたりからは入学者も多いのですが,それでも都県別の「歩留まり」にこれだけの差が出てしまっています。

本郷
次は中堅上位の男子校で豊島区の本郷の場合について考えてみます。2月2日の第1回の定員は140名で昨年は847名が受験し,349名の合格を出して入学手続きをとったのは81名,その後に繰上げ合格を7名出しましたが,手続き後の辞退者もいて入学者は79名でした。最終の「歩留まり」は22%です。実は前の年の「歩留まり」は32%だったので相当に率が下がっていますが,これは受験生のレベルが上がると同時に競合校が変わってきて,よりてごわい相手になってきているからでしょう。
2月3日の第2回は定員60名に458名が受験し,107名が合格で72名が手続きをとり,その後に繰上げの19名をあわせて91名が入学ですから,「歩留まり」は72%と1回よりずっと高くなっています。これは第1回の不合格者のリベンジ受験が多いのですから当然といえます。
さらに2月5日の第3回は定員40名に513名が受験し,81名が合格で55名が手続きをとり,その後25名を繰上げましたが,手続き後の辞退者もいて入学者は78名ですから,「歩留まり」は74%で第2回入試とほぼ同水準です。この回は再リベンジと上位校を不合格になった駆け込み受験者が多いので,これまた当然といえます。
以上の3回の合計でみると,合格者が589名で入学者が248名ですから全体の「歩留まり」は42%ということになります。各回の「歩留まり」の大きな差は受験者層が異なるためであることもご理解いただけたでしょう。

戸板
次は午後入試の例として世田谷区の戸板をみてみます。「歩留まり」は第一志望が多い2月1日の第1回AMは34名が合格,30名が入学で88%ですが,第1回PMは97名が合格し,18名が入学で19%,2月2日の第2回AMは30名が合格し,10名が入学で33%,第2回PMは49名が合格し,5名が入学で10%です。すべての回の合計では252名が合格で73名が入学ですから全体の「歩留まり」は29%です。
ここで特に午後入試についてみると第1回が19%,第2回が10%と相当に低くなっていますが,午後入試の「歩留まり」が低いのは他校にもみられる一般的現象です。結局昨年は共学化したすぐ近くの学校に受験生をとられ,併願者が多いワンランク上の近隣の女子校が合格ラインを下げて入学者の確保をしたために「歩留まり」も下がり,入学者が一昨年の91名を大きく割り込んでしまいました。

桜美林
今度は午後入試でも逆に「歩留まり」が予想外に高くなってしまった例として,2年前に初めて午後入試を導入した町田市の桜美林の場合をみてみましょう。
2月1日の第1回AMは定員40名に対し受験者が375名で,午後入試の新設を考慮して合格者を少し押さえて65名,入学者は41名ですから「歩留まり」は63%です。そして初の午後入試の第1回PMは定員50名に対し受験者が714名と前の年の総受験者数を軽く超えるという予想外の人数で,採点をしたところ高得点者が多く,今までは受験していなかったような相当に高いレベルの併願受験者がいることがわかり,何人合格を出せば何人手続きしてくれるのか見当もつかず,結局他校へ手続きする方が非常に多いと判断して327名の合格者を出しました。ところが予想を超えて64名が入学したため,「歩留まり」は学校が予想した10%前後をかなり上回る20%です。そのために2月2日の第2回,3日の第3回では合格者数を絞らざるを得ず,受験生にとっては厳しい入試になってしまいました。
学校の立場で言えば,その年の入試で応募者が何人集まるか,そのうち何人が受験してくれるか,受験生の学力レベルはどうか,そして最後に「歩留まり」がどうなるかが大きな関心事ということになります。しかし時には「歩留まり」の予測が大きくはずれることがあります。どこの学校でも過去の入試回ごとの「歩留まり」のデータを踏まえて合格者の決定をしますが,競合状況の変化などを読み切れなかったり,入試日や定員の変更などの入試要項変更により,予想外に手続き者が多かったり,逆に少なかったりすることがあります。前述のようにボーダーライン近辺では「歩留まり」が高いため,合格点が1~2点上下すると入学者数がすぐ±10名ぐらいは変動してしまいます。さて予定の人数に足りなければ追加合格を出すことになりますが,タイミングを逸すると他校に手続きを取ってしまう方が多くなるため「歩留まり」が下がってしまいます。それを恐れて手続きの締め切りを待たずに,見込みで追加合格を出したら今度は入学者が予定を超過してしまった学校がありました。「歩留まり」を予定通りに着地させるのはなかなか難しいようです。
長々と「歩留まり」についてお話してきましたが,学校ですら「歩留まり」を読み違えることがあり,受験生の側で予測するのはほとんど不可能と思います。しかし受験生の側から言えば「歩留まり」によって,より正確に言えば学校が「歩留まり」をどう予想して合格者数を決めるかによって合否が左右されているとも言えるわけで,入試を考える上では「歩留まり」が重要なキーワードの1つであることはご理解いただけたものと思います。
(おわり)