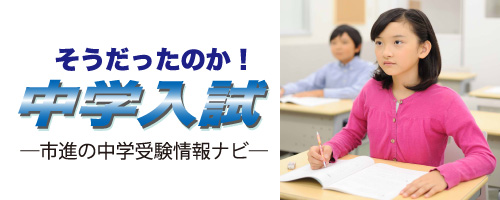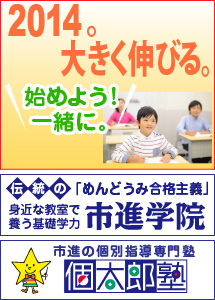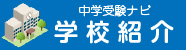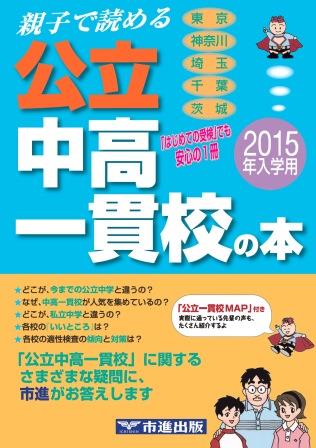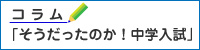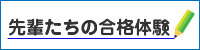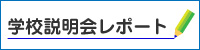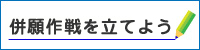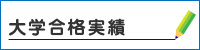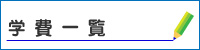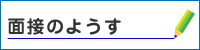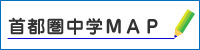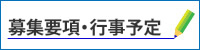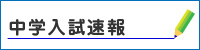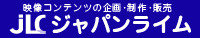第5話「学校説明会の歩き方(つづき)」
2010年10月12日
前回では「学校説明会」の中身に入る前の話に終始してしまいましたので、今回はさっそく本題に入りましょう。ここでは「学校説明会」について、「校長先生の話」「各論の話」および「教職員の対応」という3つの面から考えてみます。
1.校長先生の話
通常最初に登場する校長先生の話は学校の教育理念(建学の精神)や教育目標など学校の根幹についての話です。ここでのチェックポイントは以下のような点でしょう。
第一には教育理念が単なるお題目ではなく、日々の教育活動のなかでどのように具体化されているのかという点です。創立時の「建学の精神」を急速にグローバル化する現代社会のなかでどのように再生させていくかは、私学にとって存立根拠にも関わる重大なことがらのはずです。それは四文字熟語を今風の言葉に言い換えるといったことではなく、子供達を取り巻く現在の社会状況や将来の世界環境をふまえて再定義された「建学の精神」を学校のなかで実現させていくための「てだて」を語ることに他ならないでしょう。学校がすすむべき方向、あるいはグランドデザインについて、またそれを実現するための具体的方策について、校長先生がどのように語るのか、これが第一の点です。なお、第3話でも触れましたが同じ学校の説明会に2年、3年と続けて参加すれば、校長先生の話にブレがないかどうか、また学校改革の進捗状況なども見えてきます。
第二は校長先生のリーダーシップという点です。とりわけ学校改革を進めている学校では、内外のさまざまな困難にたじろぐことなく教師集団を動かして方針を実現させていかなくてはいけません。時には理事会やOB会・OG会を説得しなければならないこともあり、また非協力的な一部の教員と正面から向き合って対決しなければならないこともあります。やはり学校という組織の指導者である校長先生には強いリーダーシップが必要でしょう。いくつかの学校で校長先生の話を聞いていて、自分の考えている方向に学校をドライブしているという自信を強く感じたことがあります。力強い話を聞いて「この校長先生の学校ならわが子を託するに足る学校だ!」と考える人も多いでしょう。「発展途上校」ではしばしば校長先生の個人的魅力が人気上昇の大きな要因になることがありますが、それは学校の将来ビジョンについての構想力と強いリーダーシップに対する期待感なのでしょう。
2.各論の話
校長先生の話を総論とすればその後に続く各先生の話は各論ということになります。ここからの進行は学校によっていろいろですが、それは説明会終了後の校内見学や個別相談の設定の都合や、何をアピールしたいのか、また話をする先生を誰と誰にするかといった事情にもよるようです。各論の主な項目は、「学習」「進路」「学校生活」そして「入試」といったところです。説明会を2回程度しか開催しない学校では各回とも同じ内容で主な項目を一通り説明しますが、回数の多い学校では各回にテーマ性をもたせてシリーズ物のように設定している学校もあります。回ごとにスピーカーの先生の顔ぶれを変えたり、若手の先生を起用するなどの工夫もされているようで、例えば10月は「学校生活」、11月は「学習と進路」、12月は「入試傾向と対策」を中心にといった具合です。学校からすればリピーターを増やすための戦略ですが、「学習」や「学校生活」などについて現場の先生から聞く詳しい情報はありがたいものです。また最近では生徒や卒業生あるいは保護者による学校紹介などで、生の声が聞けてとても参考になるのですが、多少の演出の形跡を感じることもあります。
さて最近は学校の魅力のアピールの仕方もずいぶん上手になってきましたが、逆に問題点を感ずることもあります。それはその学校がアピールしたい点、例えば急速に充実してきた学習支援システムとか、新校舎の最先端の設備の紹介とか、大きく伸びている大学進学実績などが力強く語られて強烈な印象を与える一方で、それ以外の面に目がいかなくなって、少し言葉は悪いかもしれませんが「まんまと乗せられてしまう」危険性です。いきなり人気が出てものすごい数の受験生を集める学校を見ていて危惧を感ずることもあります。いくつかの学校を見て比較したうえで冷静な判断をすべきでしょう。
ではここでいくつかの見落としがちのポイントを述べておきます。
- カリキュラムについて
ほとんどの学校では中学の学習内容が話の中心になっています。それは良いのですが、高校への接続(特に高校からコース制をとっている場合)、大学進学にとって最も重要な高2、高3のカリキュラムについてもしっかり確認しましょう。(第2話、第3話を参照してください)また授業の形態としては少人数分割授業、習熟度別授業、授業外では補習、講座、夏期講習、個別指導などの学習支援システムについては実施の有無、実施学年、実施教科、実施方法など学校によってさまざまです。このあたりの細かいところもチェックしておきましょう。 - 家庭との連携について
保護者会、保護者面談、三者面談などいろいろあるはずですが、それがどのような頻度でどのような形式、内容でおこなわれるのか確認しましょう。中学と高校で異なる場合もありますから注意してください。 - 入試について
複数回受験者にたいする優遇措置の有無、優遇の具体的な内容は重要です。また補欠になったときの扱いも、いざとなった時にあわてないためにもしっかり聞いておくべきです。なお出題傾向について詳細な話をする学校ではしっかりメモをとっておきましょう。なかには「えっ!そこまで言っちゃっていいの?」と驚くようなサービス精神満点の学校もありました。 - お金について
入学金、授業料また入学手続きについては募集要項を見ればわかるのですが、なかなか見えにくいのが入学後にかかる経費です。例えば宿泊をともなう学校行事や任意参加も含めた海外研修、また入学前に確認するのは難しいかもしれませんが部活関係(合宿、遠征試合、用具、夏冬のユニフォーム)などはかなり高額になることもあります。また国の子供手当や入試の成績で決まる奨学制度とは別に独自の学費支援制度のある学校もありますから個別相談などできいてみるとよいでしょう。
3.教職員の対応について
最後に「学校説明会」における教職員の対応について考えてみます。
最寄り駅から会場(通常は学校)までの案内、会場に入っての受付、会場内の案内また校内見学をともなう場合の誘導などにあたる職員の様子も重要なチェックポイントです。ほとんどの学校では丁寧な挨拶をされますし親切な対応をしてもらえますが、どうも一部の学校では会の運営の不手際や無愛想な職員の対応に違和感を感ずることがあります。この問題の背景には教員の意識の問題があるようです。生徒募集という仕事の意義が教職員の中で共有されていなくて、一般教員にとっては雑用にすぎない、といったとらえ方がされていている場合です。「学校説明会」など生徒募集にかかわる仕事は私学の教職員にとって全員で取り組むべき仕事です。しかし生徒募集は営業活動であり、営業などは教師の本来の仕事ではない。好きなヤツ(得意なヤツ)にやらせておけばいいという感覚は、少なくなったとはいえ、まだまだ根強く残っているようです。管理職の先生と入試広報担当の先生だけが一生懸命で、他の先生はわれ関せずという雰囲気を感じる学校はいささか問題ありです。どんなに話の内容がよくても教員集団が一つの方向にむかっているかどうか不安が残ります。逆に先生達が全員で協力して説明会を成功させようという雰囲気を感ずる学校は今後の伸びが期待できる学校かもしれません。
今回は触れることができませんでしたが、オフィシャルな学校説明会以外にも、「ミニ説明会」「ナイト説明会」「個別訪問」「学校見学会」など、規模も性格も異なるさまざまな学校を知る機会があります。うまく組み合わせて活用することをお勧めしたします。また秋は毎週土日に多くの学校で説明会が開かれていますが、希望している学校の説明会の開催日が重なっていたりすることもありますから、早めに計画を立てておいたほうがよいでしょう。
(おわり)