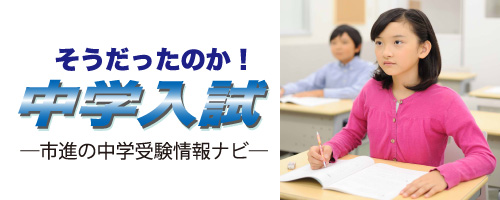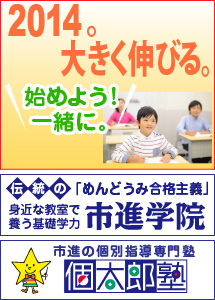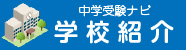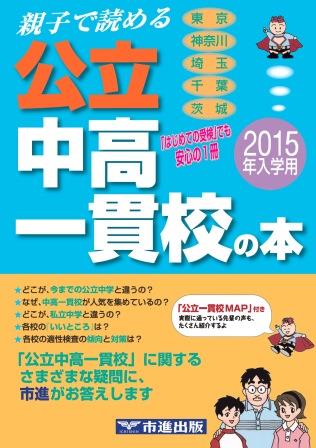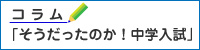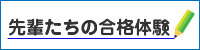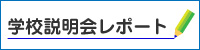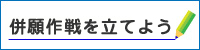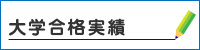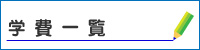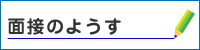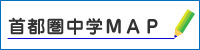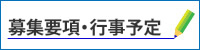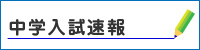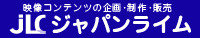第61話 「2014年 大学合格実績が伸びた中高一貫校、その躍進の秘密を探る(1)」
2014年9月29日
大学合格実績については、さまざまな視点、切り口での分析が可能ですが、今回は次の2点に注目します。幅広い視点から大学合格実績の伸びているいくつかの学校をケース・スタディとして取り上げ、その実績伸長の背景を探ってみます。
1.最難関大学合格者数―東大の場合―
まずなにかにつけて話題となる東大合格者について。以下は今春の東大合格者ベスト10です。学校名の後ろの( )は今春の卒業生数で,合格者数は現・浪合計で2012年~2014年の3年間の推移を示しました。また今年の合格者数の後ろの( )は合格者数の卒業生数に占める割合(%)です。
なお東大にかぎりませんが週刊誌、受験情報誌などで合格者の人数が異なっていることがあります。これは主に各学校の集計状況・集計時期の違いによるもので(特に過年度生、いわゆる浪人生の集計が遅れることが多い),取材した時期によって違いが出るためです。また一部の大学は高校別合格者数を発表していますが,高校が発表する合格者数と食い違いがあることもあります。これは高校が本人からの報告に基づいて集計するためです(つまり進学する大学以外は合格していても報告しない生徒もいるということです)。
■東大合格者数1位~10位
| 順位 | 学校名(卒業生数) | 2012→2013→2014(卒業生数に対する割合) |
|---|---|---|
| 1位 | 開成(398) | 203→170→158(40%) |
| 2位 | 筑波大附駒場(162) | 83→103→104(64%) |
| 2位 | 灘(220) | 103→105→104(47%) |
| 4位 | 麻布(295) | 90→82→82(28%) |
| 5位 | 駒場東邦(231) | 69→59→75(32%) |
| 6位 | 聖光学院(239) | 65→62→71(30%) |
| 7位 | 桜蔭(236) | 58→66→69(29%) |
| 8位 | 栄光学園(178) | 70→52→67(38%) |
| 9位 | 東京学芸大附(332) | 55→68→56(17%) |
| 10位 | 渋谷教育学園幕張(354) | 49→61→48(14%) |
これを見ていくつか気がつく点をのべていきます。
①実はこの10校は順位こそ変わっていますが前年と全く同じ顔ぶれです。しかも1位から4位まではまったく同じです。(今年は筑波大附駒場と灘が同数の104名なので両方とも2位)このことは上位10校の東大合格者数がいかに安定しているか,言い換えれば他の学校が上位10校に入るのがいかに大変かということです。
②さらにこの10校の中での合格者数についていくつか注目される点をあげてみれば、
-
- 開成の2年連続の減少
- 開成(荒川区)は1982年以来東大合格者数全国トップを続け,今年ももちろんトップですがこの2年連続の減少です。2012年の203名が特に多かった(200名を超えたのは1998年の205名以来14年ぶり)ためにずいぶん減っているように見えますが,過去10年ほどを通して見ると平均が170名で170±30名の幅で変動していますから,開成としては今年の158名は近年の水準よりやや少ない程度です。
-
- 増減が大きい学校
- 増加で目立つのは駒場東邦(世田谷区)の16名増と栄光学園(鎌倉市)の15名増です。逆に減少で目立つのは東京学芸大附(世田谷区)の12名減と渋谷教育学園幕張(千葉市美浜区)の13名減です。
-
- 東京のライバル校
- この10校のなかで東京のライバル校は「開成と麻布」も考えられますが,直接的に強い競合関係にあるのはむしろ「麻布(港区)と駒場東邦(世田谷区)」です。両校はともに東京城南部と横浜方面を地盤とし受験生の学力レベルでも重なっています。東大合格者数の差は21→23→7名と急速に縮まっています。
-
- 神奈川のライバル校
- 神奈川の宿命のライバル「聖光学院(横浜市中区)と栄光学園」の関係も注目されます。両校はともにカトリックミッションの男子校で,受験生の学力レベル・居住エリアともに重なっており、東大合格者数が翌年の受験動向へ大きく影響します。前年は聖光学院が3名減の62名でしたが,栄光学園が18名減の52名だったため,聖光学院が神奈川トップの座につきました。今春は栄光学園が15名増で67名と大きく回復しましたが,聖光学院も9名増で71名となったため栄光学園はトップの座を奪い返すことができませんでした。
-
- 人数でなく割合で見ると
- 学校規模を考慮して合格者数ではなく合格者数の卒業生数に占める割合(%)で見ると、筑波大附駒場(世田谷区)の64%が群を抜いています。
また麻布と駒場東邦の関係も卒業生数に占める割合(%)では合格者数とは逆に駒場東邦の32%が麻布の28%を上回っています。
神奈川の聖光学院と栄光学園の関係でも卒業生数に占める割合(%)では合格者数とは逆に栄光学園の38%が聖光学院の30%をかなり上回っています。
一方、学校規模が大きい東京学芸大附と渋谷教育学園幕張は,卒業生数に占める割合で見ると他の8校に比べかなり低くなります。
なお参考までに東大合格者数11位~20位をあげておきます。
■東大合格者数11位~20位
| 順位 | 学校名(合格者数) |
|---|---|
| 11位 | 海城(40) |
| 12位 | 都立日比谷(37) |
| 13位 | 浅野(34) |
| 14位 | 豊島岡女子(33) |
| 14位 | 県立浦和(33) |
| 16位 | 都立西(31) |
| 17位 | 筑波大附(29) |
| 18位 | 巣鴨(26) |
| 18位 | 早稲田(26) |
| 20位 | 女子学院(24) |
| 20位 | 都立国立(24) |
2.難関私大実績を伸ばしている中堅校
ここでは大学合格実績を伸ばしている学校の中で,いままであまり注目されていなかった中堅レベルの学校を数校取り上げて見てみます。
【成城】

成城
2015年に創立130周年を迎える成城(新宿区)は新校舎の建設や,都立名門校の校長だった女性校長の栗原卯田子先生を迎えての学校改革によって人気が上昇しています。その背景にはこの2年間で難関大合格実績を伸ばしていることもあるでしょう。学校規模は高校の人数が各学年300名前後の7~8クラス編成で中学からの入学生は各学年5クラス。最近3年間の卒業生数は292→316→290名です。
この3年間の国公立大合格者数の推移は28→42→41名と2013年に大きく増えて今年は前年並みです。しかしその内訳を見ると,東大0→1→2名,一橋大0→0→2名,東工大2→3→2名,また東大を含む旧7帝大に一橋大・東工大を加えた最難関レベルの国立大9大学の合計では3→7→12と合格大学のレベルが大きく上がっています。
次に難関私大の実績を見ると,早慶上智大が73→80→72名と前年は増えましたが今年はやや減っています。逆にGMARCH大は226→216→262名で前年はやや減って今年は大きく増えています。
栗原校長の就任以来急速に学校改革が進められており,受講料無料の夏期講習・冬期講習の充実やキャリア教育の充実により、さらに実績が向上していきそうです。まだ学年による上下があり安定した実績とは言えず、世田谷学園・攻玉社・本郷・城北のレベルとは言えませんが,今後確実にこれらの学校の実績に近づいていくでしょう。
【東京都市大付】

東京都市大付
周知のように東京都市大附(世田谷区)はここ数年中堅上位の男子校で一番人気の学校です。2009年に併設大が改組されて「東京都市大学」と校名変更されると同時に付属中高も「東京都市大付」と校名変更し,2010年には高校募集を停止して完全中高一貫校になりました。かつて武蔵工業大付だった時は併設大への進学が主流でしたが,完全中高一貫校となって難関国公立大・難関私大への進学が急増しています。(今年の併設大への進学は7%)1学年は240名前後の学校規模でこの3年間の卒業生数の推移は238→226→225名です。
次に高校募集を停止した完全中高一貫1期生が2012年に卒業して以降の3年間(2012~2014年)について大学合格者数の状況を見てみます。
国公立大の合計は48→66→54名と今年は少し減っていますが,東大・京大・一橋大・東工大の最難関国立4大学は1→6→11名と大きく増えて質的に高いレベルになってきている様子がわかります。早慶上智大は50→79→142名,GMARCH大は150→201→256名です。現高3以下では国公立大志向がより強くなっているとのことですから,都内の男子校では御三家・駒場東邦・海城に次ぐ2番手グループのポジションに確実に定着していくでしょう。
【八雲学園】

八雲学園
英語教育に強い女子校として知られる八雲学園(目黒区)は1996年に中学校の募集を再開した学校です。学校規模は中学校の人数が各学年160名前後の4~5クラス編成で高校募集もありますが、高校からの入学生は10数名です。この3年間の卒業生数は153→172→158名です。
ここ数年で早慶上智大やGMARCH大への合格者が少しずつ出てきましたが,今春は国公立大で合格者を5名出したうえに,GMARCH大の合格者を大きく伸ばしました。国公立大は1→0→5名,早慶上智大は5→11→13名, GMARCH大32→43→67名,女子大御三家(津田塾大・東京女子大・日本女子大)は9→16→21名です。
今年の卒業生が伸びた要因を探ると、必ずしもこの学年で特別な対策をとったわけではなく,今までのキャリア教育などの積み重ねが実を結んだということのようです。この学年で目立ったのは推薦・AO受験者が減って一般受験が増加したことです。自分の成績(内申)から見て合格できそうな学校を探すのではなく,積極的にチャレンジしていく雰囲気が出てきたということです。実はこれが推薦やAO入試にたよる生徒が多い中堅女子校で大学合格実績を伸ばしていくための大きなポイントなのです。
今まで国公立大受験者がほとんどいなかったので、国公立大対応のカリキュラムや講座設定になっていないため、国公立受験者にはセンター試験で必要な科目を個別指導で対応したとのことです。ただし数年前から放課後の補習などで八雲学園の先生だけでなく予備校の先生(特定の予備校との契約ではなく個々の先生との契約)の授業が導入されています。これは単に受験対策のノウハウを持った予備校の先生の授業が受けられるということだけではなく,八雲学園の先生と予備校の先生との間での情報交換やカリキュラムの調整などでよい結果を生んでいるようです。今年の高3はさらに進路希望が高く成績もよいとのことで、今春以上の実績向上が期待できそうです。今後は難関私大や国公立大志望者が増えてくることが予想され,個別対応ではなく学校をあげての組織的な対応を進めていくことになるでしょう。
また卒業生の活躍の最も大きい影響は現高3などの下の学年に大きな刺激を与えていることにありそうです。特に女子校では先輩の活躍が後輩に大きな影響を与えます。
【和洋九段女子】

和洋九段女子明治30年(1897年)千代田区九段で創立され創立117年目の伝統校です。和洋女子大学の付属校で,このレベルの中堅校では数少ない高校募集のない完全中高一貫校です。この3年間の卒業生数は236→243→257名ですが,ここ数年入学者が減り、中学では各学年100名前後です。
卒業生の進路を見ると,併設大への推薦率は6%まで下がっており、ほぼ進学校化していると言ってよいでしょう。特にここ2年間で大きく他大学合格実績を伸ばしていますが,今春の内訳を見ると,成蹊・成城・獨協・国学院・日大・東洋大などの中堅私大よりも上位私大の伸びが大きいようです。早慶上理大6→10→20名,GMARCH大33→28→54名,女子大御三家(津田塾大・東京女子大・日本女子大)3→14→32名などです。また理系合格者が44→100名と急増しているのも注目されます。
3年ほど前から始まった学校改革により学習・進路およびキャリア教育の体制は、かつての付属校のころの体制から完全に進学校の体制に変わっています。主要教科の教科担当の先生は6年間持ち上がり,高校進学時に「特進コース(文系)」,「特進コース(理系)」,「一般A1コース(文系)」「一般A2コース(栄養系などの理系)」「一般Bコース(理工系など)」の5コースに分かれます。また昨年設置された個人ブース型自習室「スタディステーション」や課外講習・補習などシステム的にも内容的にも充実してきたことがここ2年間の実績向上につながったものと思われます。
夏期講習で設定されている講座を見ると,高2は18講座で「数学ⅠA入試問題演習」など入試問題に触れ始め,高3では39講座が設定され「総合受験英語」「日本中世史講義」などのほか,「いまさら聞けない国語常識」「振り返れ日本史~君はまだあきらめていないはずだ~」「へこたれないぞ!数学!(数学ⅠA)」「どんとこい数学Ⅲ」など生徒たちのやる気を起こさせるような講座も設定されています。
またこの学校でも今まで学年の3分の2が推薦・AO入試を利用していましたが、今春の卒業生の推薦・AO入試の利用はほぼ半数で,一般入試でのチャレンジに大きく舵を切っています。
【かえつ有明】

かえつ有明かえつ有明(江東区)は明治36年(1903年)に開校した創立111年目を迎えた伝統校です。しかし伝統に甘んずることなく新時代にふさわしい学校づくりに取り組んでおり,2006年に千代田区から江東区東雲(しののめ)の新校地に移転と同時に共学化。グローバル時代にふさわしい21世紀型の教育を目指して様々な取り組みを行っています。2013年からは共学校ながら中1から高1までは授業別学制を導入し話題を呼んだのは記憶に新しいところです。
中学の定員は160名ですが中1・2は入学者が超過して200名前後,中3は150名弱と学年によってばらつきがあります。この3年間の卒業生数の推移は212→184→163名です。
2012年以前と以降の大学合格状況を見てみると,中学の共学1期生が卒業した2012年以降に大きく大学合格実績が伸びていることがわかります。2012年以降の3年間の大学合格状況は,国公立大は8→8→11名とまだ少ないですが,東工大は0→1→1名,今年は阪大1名も出ています。注目すべきは上位私大の大幅増加です。早慶上智大は26→24→45名,GMARCH大は48→76→81名で,特に早慶上智大の実績が大きく伸びていることがわかります。
共学化により1期生・2期生の入学レベルが急激にアップしましたが,3期生以降については入学者のレベルがさほど変わっていないので3期生の実績のアップの要因は別にあります。石川副校長によれば最も大きな要因は1期生・2期生を指導してきた教員集団の経験の蓄積です。共学化以来採用した先生が現在半数近くになっていて,ほとんどは若い先生です(スカウトされた進学校での経験が豊富な先生も各教科に1~2人ずついます)。若手の先生はトップレベルの大学を卒業した優秀な先生が多いのですが(ほとんどは大学院卒),なんといっても足りないのが経験です。その優秀な若手の先生たちが1期生・2期生を指導する中で密度の高い経験を積んだことが今春の成果を生んだのでしょう。
また進路希望の傾向として学力レベルのアップにともない理系志望・医学部志望・国公立大志望が増えるケースが多いのですが,グローバル時代の教育実践を行うこの学校らしく国際系学部や海外大学を希望する生徒が多いとのことで,このあたりにかえつ有明らしさが出ているようです。
【湘南学園】

湘南学園湘南学園(藤沢市)は昭和8年(1933年)に幼稚園と小学校が設立され,戦後すぐの昭和22年(1947年)に中学校が,3年後の昭和25年(1950年)に高校が設立された学校です。県内有数の高級住宅地として知られる鵠沼海岸にあり,4割程度が併設小学校からの入学者で富裕層の通う学校のイメージが強い学校でした。しかし数年前からの学校改革の結果,リベラルで家庭的な校風は変わっていませんが急速に進学校化が進んでいます。
2012年春の大学合格実績が,東大2名,東工大2名,一橋大1名など国公立大計で15→19名,早慶上智大が23→64名,GMARCH大が64→136名と大躍進。翌年の入試では大人気となり応募者が激増しました。実はこの学年は前後数年の中でも入学時の偏差値が高かった学年なのですが,それだけでなく部活動や学校行事などにも積極的に取り組み,学年の団結力が強く,一口で言えば「非常にノリの良い学年」だったそうです。
しかし2013年と今年の2014年と難関レベルの大学の実績は下がっているように見えます。2012年の大躍進は「まぐれあたり」だったのでしょうか。これを検証するために2010年~2014年の5年間の大学合格実績の推移を見てみます。なおこの5年間の卒業生数の推移は,181→197→193→174→175名です。
- 国公立大 17→15→19→16→11名
- 早慶上智大 26→23→64→31→24名
- GMARCH大 75→64→136→85→103名
- 中堅私大 70→76→95→95→98名
※中堅私大は成蹊・成城・明治学院・国学院・武蔵・日本・東洋・駒沢・専修の9大学合計
この5年間の実績の推移を見ると2012年の実績が突出していることがわかります。特に早慶上智大の実績が顕著です。
さて2013年・2014年は合格者数こそ下がっていますが,よく見ると大躍進だった2012年より前の2010年・2011年の水準に戻ったわけではありません。この2年間卒業生数が少なかったことを考慮すると,国公立大と早慶上智大などの最上位層は薄かったようですが,ボリュームゾーンである GMARCH大,中堅私大の状況から見て学年全体ではかなり底上げが効いてきているようです。また推薦・AO入試の利用者も減って指定校推薦の多くは返上しているそうです。(今春の推薦・AOの利用者は17%ぐらいとのこと)
大躍進した2012年卒の学年以降は生徒募集で苦戦して人数的にも偏差値的にも現高2がボトムとのことですが,現中3から入学時の偏差値も上がって人数も増えています。またここ数年で学習指導,進路指導体制が急速に充実してきています。
また湘南学園らしいのが、4年前から始まった卒業生が全面的にバックアップする学習・進路指導の「卒業生サポーターバンク」で、後輩たちにも好評です。卒業生が後輩に自分の勉強や受験を熱く語り,放課後の自習などにチューターとして協力、大学のキャンパス見学で案内役を務めるなどの活動をボランティアで行っています。
今後多少のジグザグはあっても確実に大学合格実績が伸びて行く学校と思われます。
(おわり)
[次回予告] 「2014年 大学合格実績が伸びた中高一貫校、その躍進の秘密を探る(2)」
次回は今回に続き大学合格実績の伸びているいくつかの学校をケース・スタディとして取り上げ、その実績伸長の背景を探ってみます。