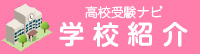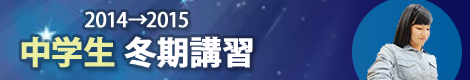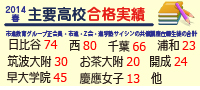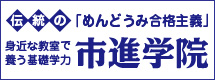市進受験情報ナビでは首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城)の国立・私立・都立・県立高校受験に関する偏差値、難易度、入試システム・入試制度、入試状況、学費などを塾ならではの視点から総合的にお伝えしていきます。
過去問を解くうえで知っておかなければならないことは、その年その年で問題の難度が違うということ。 「ある年の過去問はできたのに、次の年の過去問はあまり解けなかった」とがっかりするのは間違いです。問題が難しかったのであれば、ほかの受験生が解いても同じことになるからです。
そこで参考になるのが入試平均点。その年の問題がやさしかったのか難しかったのかを確認しながら過去問に取り組んでいくと効果的です。
また、入試制度の変更にともなって受験者層が変わると平均点も変わるということに注意しましょう。推移表の下に、受験者層の変化を考える「ヒント」を掲載しましたので参考にしてください。
そこで参考になるのが入試平均点。その年の問題がやさしかったのか難しかったのかを確認しながら過去問に取り組んでいくと効果的です。
また、入試制度の変更にともなって受験者層が変わると平均点も変わるということに注意しましょう。推移表の下に、受験者層の変化を考える「ヒント」を掲載しましたので参考にしてください。
─ 埼玉県公立高校入試問題 過去の平均点 ─
500点満点の平均点が38点上昇した2013年に対し、2014年(平成26年度)春の学力検査は26点低下して、前々年の平均点に近づきました。2012年の入試一本化以降3年間とも5教科平均点は安定していませんので、過去問演習の際には得点の上下だけで一喜一憂するのではなく、このページを参考に平均点の推移を加味して分析することが大切です。2010年から1教科100点満点になり、点差のつく記述問題の重要度が高まりました。記述問題の解答づくりをしっかり練習することが大切です
埼玉公立 学力検査の受験者平均点
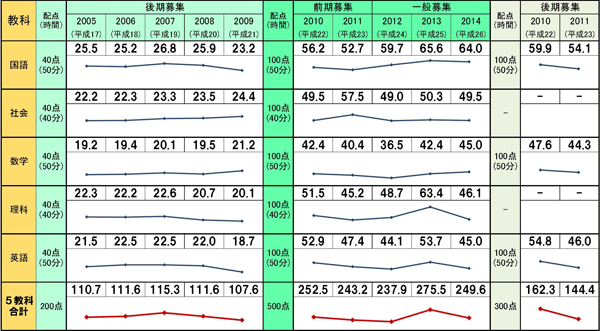
ヒント ①後期募集(~2009) ? 公立志望者のうち前期に合格した受験者は受けない
②前期募集(2010・2011) ? 公立志望者がみんな受験する(受験機会は後期にもう一度ある)
③一般募集(2012~) ? 公立志望者がみんな受験する(受験機会は1回)
よって②、③は公立受験者のほぼ全員の平均値であることに対し、①は前期(定員の20%前後)に合格した高い内申をもつ受験者が抜けている平均値。さらに2009年以前は配点や指導要領が現在と異なります。過去問演習における点数比較は参考程度にしましょう。
④後期募集(2010・2011) ? 前期に80%程度の選抜を行った後の募集で3教科の実施。
受験者層が①~③とは大きく異なるので、受験者平均との比較は参考程度にしましょう。
②前期募集(2010・2011) ? 公立志望者がみんな受験する(受験機会は後期にもう一度ある)
③一般募集(2012~) ? 公立志望者がみんな受験する(受験機会は1回)
よって②、③は公立受験者のほぼ全員の平均値であることに対し、①は前期(定員の20%前後)に合格した高い内申をもつ受験者が抜けている平均値。さらに2009年以前は配点や指導要領が現在と異なります。過去問演習における点数比較は参考程度にしましょう。
④後期募集(2010・2011) ? 前期に80%程度の選抜を行った後の募集で3教科の実施。
受験者層が①~③とは大きく異なるので、受験者平均との比較は参考程度にしましょう。