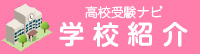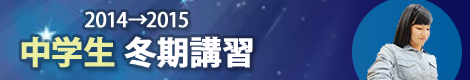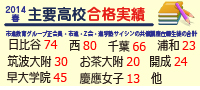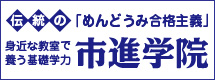東京都立高校入試問題分析
【英語】
| 2014年 | 2013年 | 2012年 | |
|---|---|---|---|
| 1 | リスニング(5問) 対話文3題から各1問,ラジオ放送でのイベント情報の内容から2問。内容についての英問に対し,適切な応答文を記述。 |
リスニング(5問) 対話文3題から各1問,留学生が教室で行ったスピーチの内容から2問。内容についての英問に対し,適切な応答文を記述。 |
リスニング(5問) 対話文3題から各1問,外国人歌手がインタビューで語った内容から2問。内容についての英問に対し,適切な応答文を記述。 |
| 2 | 対話文完成・英作文(4問) 地図とパンフレットに関する対話文の完成,スピーチの内容合致,深く学んでみたいこととその理由を3つの英文で記述。 |
対話文完成・英作文(4問) まとめの表を参考に対話文の完成,リサイクルに関する対話文の完成,手紙文の内容合致,人の役に立つために取り組んでみたいことを3つの英文で表す。 |
対話文完成・英作文(4問) 動物園の案内を参考にした対話文の完成,花の育て方に関する対話文の完成,手紙文の内容把握,友人に伝えたい感動したできごとを3つの英文で表す。 |
| 3 | 対話文総合(約400語) 7問(記述式2問) 留学生を含む高校生4人の対話文。内容把握,書き換え,心情把握,内容に沿った英文の適語補充。 |
対話文総合(約440語) 7問(記述式2問) 留学生を含む高校生4人の対話文。内容把握,書き換え,心情把握,内容に沿った英文の適語補充。 |
対話文総合(約440語) 7問(記述式2問) 留学生を含む中学生3人の部活動に関する対話文。内容の読み取りと書き換え,内容に沿った英文の適語補充など。 |
| 4 | 長文総合(約600語) 7問(記述式3問) 適語補充による書き換え,文整序,内容合致の適文補充(3問),英問英答(2問・記述式)。 |
長文総合(約560語) 7問(記述式2問) 適文選択による書き換え,文整序,内容合致の適文補充(3問),英問英答(2問・記述式)。 |
長文総合(約640語) 7問(記述式2問) 適文選択による書き換え,文整序,内容合致の適文補充(3問),英問英答(2問・記述式)。 |
【傾向&アドバイス】
2014年も前年と同じく大問4題の構成となっている。基礎力を確認する設問が中心で,普段の授業や教科書レベルの単語や文法,構文,表現などができていれば十分に対応できる。長文の語数が多いので,速読速解力が必要となる。また,英作文も毎年出題されている。正確な表現力が求められるので,十分な練習を積んでおきたい。
1のリスニングの内容は基礎レベルで,放送内容の正確な理解を問う出題となっている。英文を書く問題 は答えがやや長めとなることもあるため,重要な点はメモしながら聞くことが必要である。また,ネイティブスピーカーの発音に慣れるため,普段からCDやラジオなどの英語講座を利用したい。
2は対話の流れから正確に内容を把握する力が必要となる。会話文の基本的な慣用表現はしっかり押さえておこう。スピーチ文の読解では文章全体の内容把握が設問の中心となっている。テーマ英作文は,簡潔でまとまりのある英文を書くように心がけたい。
3の対話文総合では文章の背景や登場人物の心情についての読み取りがポイントとなる。文脈を整理しながら読み進め,全体的な流れを把握しよう。書き換え,適語補充は単語力・文法力も試されるため,教科書レベルの単語・構文を確実に身につけておく必要がある。
4の長文総合は,英文を正確に素早く読みこなす力を養っておきたい。日ごろから,文章の情景やできごと,登場人物の心情に注意しながら読み進める練習をしておけば,解答するのはさほど難しくない。また,英文の書き換え,文整序,英問英答などの出題形式に慣れるため,問題集を活用した学習も大切にしたい。
【数学】
| 2014年 | 2013年 | 2012年 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 小問集(9問) 四則計算,文字式,無理数,一次方程式,連立方程式,二次方程式,中央値,角度,条件を満たす点の作図。 |
小問集(9問) 四則計算,文字式,無理数,一次方程式,連立方程式,二次方程式,割合,角度,条件を満たす点の作図。 |
小問集(9問) 四則計算,文字式,無理数,一次方程式,連立方程式,二次方程式,関数,確率,条件を満たす点の作図。 |
| 2 | 場合の数,数の性質(2問) 生徒が作った問題で4の倍数になる選び方,条件を満たす自然数についての証明。 |
立体図形(2問) 円すいの側面積を求める,正四角すいの側面積と2つの線分の積とが等しくなることの証明。 |
自然数(2問) 与えられた条件を満たす自然数の個数を求める,一定の条件を満たす自然数についての証明。 |
| 3 | 関数とグラフ(3問) 点のy座標がとる値の範囲,直線の式を求める,点の座標。 |
関数とグラフ(3問) 点のy座標が取る値の範囲,直線の式を求める,点の座標。 |
関数とグラフ(3問) 直線の式を求める,2つの線分の長さの比,点の座標。 |
| 4 | 平面図形(3問) 文字を使って角度を表す,三角形の相似の証明,一定の条件を満たす面積比を求める。 |
平面図形(3問) 文字を使って角度を表す,三角形の合同の証明,一定の条件を満たす線分の長さを求める。 |
平面図形(3問) 文字を使って角度を表す,三角形の相似の証明,一定の条件を満たす面積を求める。 |
| 5 | 立体図形(2問) 立方体の頂点を結んでできる角の大きさを求める,直方体の内部にできる立体の体積を求める。 |
立体図形(2問) 2つの三角形の面積比を求める,三角すいの内部にできる立体の体積を求める。 |
立体図形(2問) 正三角柱の展開図に線分を図示する,正三角柱の内部の立体の体積を求める。 |
【傾向&アドバイス】
2014年も前年と同様,大問5題の構成であった。作図と証明問題も例年どおり出題されている。出題傾向に大きな変化は見られないので,数年分の過去問を解いてどのような問題が出題されているか把握しておくとよい。教科書の各単元から幅広く出題されているが,全体的に基本的な設問で構成されている。確実に得点できる問題から処理していく習慣を身につけておきたい。また,作図や証明問題も基本事項を大切にして,苦手意識を持たずに,教科書レベルの問題で反復練習して解法パターンに慣れておこう。
1は例年どおり,基本的な計算問題中心の出題で,比較的得点しやすい。教科書の例題レベルの問題で,正確に計算する練習をしておこう。
2は,場合の数,数の性質の問題。与えられた条件を整理しながら,設問に答えていくことがポイント。証明問題も1問出題されているので,類題にあたって慣れておくとよい。
3は関数とグラフの問題で,例年出題されている。関数の基礎的な知識と理解に加え,グラフ上の点の座標を正確に把握できれば,解答はさほど難しくはない。与えられた座標の数値などをグラフに書き込んでから問題に取りかかろう。
4は平面図形。文字を使って角度を表す問題,三角形の相似を証明する問題は基礎的な内容である。また,2つの三角形の面積比を求める問題は数学的な思考力が問われるため,類題で演習を繰り返して慣れておくことが望ましい。
5の立体図形は直方体に関する問題。例年,立体の辺上にある点に関する問題が出題されており,与えられた条件をふまえたうえでの空間把握力や思考力が要求される。立体図形の問題を解くには,いろいろな方向から見て考え,辺上の点がつくる立体がどのような形になっているかを把握することが大切だ。
【国語】
| 2014年 | 2013年 | 2012年 |
|---|---|---|
| 1 2 漢字 1は漢字の読み,2は漢字の書き取りで,各5問。 |
1 2 漢字 1は漢字の読み,2は漢字の書き取りで,各5問。 |
1 2 漢字 1は漢字の読み,2は漢字の書き取りで,各5問。 |
| 3 小説文(5問) 出典は長野まゆみ『夏帽子』。主人公が期限つきで赴任した中学校の近くの海岸を散歩していたときの印象的なできごとと心情を描く。表現の解釈,心情把握,条件作文(「50字以内」での記述)。 |
3 小説文(5問) 出典は稲葉真弓『唇に小さな春を』。主人公が中学生の春休みに父方の祖母と過ごしたときの印象的なできごとと心情を描く。心情把握,表現の解釈,条件作文(「35字以内」での記述)。 |
3 小説文(5問) 出典は松樹剛史『熟してはじける果実のように』。弓道に打ち込む佐那子の苦悩と,試行錯誤するなかで変化する心情を描く。表現の解釈,心情理解,条件作文(「50字以内」での記述)。 |
| 4 論説文(5問) 出典は長谷川眞理子『生態学から見た持続可能な社会』。生態学の中で種が果たす機能などに関する文章。内容把握,文脈把握,200字論述。 |
4 論説文(5問) 出典は佐藤京子『居住の文化誌』。日本とヨーロッパの建築空間を比較したうえで,現代の居住のあり方を説く文章。内容把握,文脈把握,200字論述。 |
4 論説文(5問) 出典は宮原浩二郎『論力の時代』。深い社会性のある「自分の言葉」で個性的に話すこと・書くことについて説く文章。内容理解,文脈把握,200字論述。 |
| 5 評論文(5問) 出典は馬場あき子,水原紫苑『伝統を継ぐ,歌とつながる』ほか。内容把握,表現の解釈,条件作文(「25~35字での記述」)など。 |
5 評論文(5問) 出典は稲田利徳,千本英史,小林一彦,浅見和彦『「方丈記」800年』,堀田善衛『方丈記私記』ほか。内容把握,文脈把握など。 |
5 評論文(5問) 出典は石川忠久,中西進『石川忠久中西進の漢詩歓談』。条件作文(「25~35字」での記述),語句の意味,内容理解など。 |
【傾向&アドバイス】
2014年も前年と同様,大問5題の構成であった。また,200字の論述問題1問も例年に変わりなく,筆者の主張を踏まえたうえで,自分の具体的な体験を示して意見を述べることが求められた。記述式については,文章の要旨を正確に把握する力と,自分の主張したいことを簡潔にまとめる構成力,自分の考えを相手に伝える表現力が必要となる。課題作文などを書く場合も,まずは自分の考えを箇条書きにしてまとめ,それをもとに文章を構成していく練習が効果的である。記述問題は例年出題されているので,数年分の過去問を利用して練習しておくとよいだろう。全体の時間配分にも注意しなければならないため,日常の練習はしっかり行うようにしたい。全体としては,基礎から標準レベルまでの総合的な国語力を問われる問題が中心となっている。普段の学校の授業を大切にし,標準的な問題集で補強することで十分に対応できる。
1の漢字の読みは「鑑賞」「驚嘆」「銘菓」「鮮やか」「募る」が出題された。
2の漢字の書き取りは「初春」「逆さ」「富んで」「客室」「陸橋」が出題された。漢字の読み書きは,確実に得点できるよう練習を重ねておこう。
3の小説文は,内容理解と登場人物の心情の把握がポイントとなる。会話文や情景描写の中に織りこまれた心情の変化を把握し,理解するようにしたい。
4は論説文の出題。説明的文章の読解では,筆者の主張する内容を的確に把握することが不可欠となる。全体の文脈を把握するためには,段落ごとの要点を押さえながら読み進めることが大切である。普段から長文の読解に慣れておき,文章量に左右されずに速読できる力と,主題や要旨を的確に把握する力を身につけておきたい。
5は評論文の出題。2014年は,百人一首に関する対談の内容の記録などをもとに出題された。設問は抜き出し式と選択式で構成されている。和歌も引用されているが,現代語訳がついているので,解答はさほど難しくないだろう。
【理科】
| 2014年 | 2013年 | 2012年 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 第1・第2分野総合(6問) 炭酸水素ナトリウムの熱分解,2つの電熱線の抵抗,低気圧,食物連鎖,等加速度運動,化石を含む地層。 |
第1・第2分野総合(6問) 熱とエタノール粒子,2つの電熱線の抵抗と電圧,染色体の数,星の動きと方位,食物連鎖,化学変化のモデル。 |
第1・第2分野総合(6問) 気温と飽和水蒸気量,電熱線に流れる電流,ヒトの器官と有害な物質の変化,空気よりも重い単体の気体,地層,凸レンズ。 |
| 2 | 第1・第2分野総合(4問) 地震波の伝わる速さ,圧力,血液の成分のはたらき,有機物と融点。 |
第1・第2分野総合(4問) イネの特徴,海水の水分の蒸発と食塩のでき方,食塩水の濃度,熱の伝わり方とその名称。 |
第1・第2分野総合(4問) リサイクルに必要なエネルギー,蒸散,白熱電球とLED電球,生分解性プラスチックの分解。 |
| 3 | 天体の動き(3問) 地球の自転と日の出の時刻,地球・月・太陽の位置関係,秋分の日の太陽の道筋。 |
気象(3問) ある日時における天気と風向,ある日時における湿度,観測日の日本付近の天気図。 |
天体の動き(3問) 星座に対する太陽の位置の変化,恒星の南中時刻,観測地点と南中高度。 |
| 4 | 花のつくり,遺伝(3問) 双眼実体顕微鏡の使い方,有性生殖における染色体の数,遺伝子と遺伝。 |
消化酵素(3問) 沸騰石を入れる理由,ヒトの消化液と消化酵素,実験の条件の変え方と結果。 |
植物の観察(3問) 葉緑体,オオカナダモのはたらきと光合成,オオカナダモの呼吸の確認。 |
| 5 | 化学変化(3問) 気体の性質とその集め方,電池とイオン,電圧がより高くなる電池の作り方。 |
化学変化(3問) 気体の発生と方法,水溶液の色の変化とイオン,水溶液に含まれるイオンの数。 |
化学変化(3問) 実験上の注意点と適切な対応,化学変化と質量の変化,化学変化の種類。 |
| 6 | 電流と磁界,エネルギー(3問) コイルのまわりにできる磁界,電磁誘導と誘導電流,エネルギーの変換。 |
物体の運動(3問) ばねにはたらく力の大きさとばねの伸びの関係,斜面上の鉄球にはたらく力の向き,実験結果の考察。 |
物体の運動(3問) 向きが反対の2つの力の関係,台車を引く力の変化と台車の運動のようす,台車の速さを変化させている力。 |
【傾向&アドバイス】
2014年も例年同様,大問6題からの構成となっている。設問は選択式がほとんどだが,記述式も出題されている。12は第1・第2分野総合の小問集合,3~6はそれぞれ地学・生物・化学・物理の各分野から1題ずつという出題形式も例年と同様であった。出題内容は実験・観察による問題が中心で,基礎知識に加えて,観察力・科学的思考力が問われる構成となっている。また,記述式では実験・観察の過程や結果の正確な把握と理解力が求められている。出題の傾向を把握するために過去の問題をよく調べ,教科書レベルの基礎知識の定着と理解を充実させておきたい。
1は例年どおり6問出題された。内容は化学・物理・生物・地学の各分野の基本的な知識・理解を問う問題が中心。教科書レベルの知識があれば十分対応できる。
2も例年と同様,自由研究のレポートをもとに,各分野から出題する形式であった。レポートの内容をしっかり読み,落ち着いて問題の題意を読みとることが大切である。
3~6は,毎年,地学・生物・化学・物理の各分野から出題されている。どの単元も標準的な知識を問う内容が中心であるが,同時に,実験・観察の過程や結果を正確に把握する力も問われる。範囲が広くなるため,苦手分野をつくらないよう心がけたい。まずは,教科書の内容を中心にしっかりと復習しておこう。また,実験や観察に関する記述問題では,設問のポイントを的確にとらえ,簡潔にまとめられるようにしておきたい。数値の読み取りや計算問題への対応は,問題集での反復演習が効果的である。
【社会】
| 2014年 | 2013年 | 2012年 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 地理・歴史・公民総合(3問) 季節風,鉄砲の伝来,裁判員制度。 |
地理・歴史・公民総合(3問) 写真撮影の位置,奈良の東大寺,両院協議会。 |
地理・歴史・公民総合(3問) 地形図の読み取り,物価,延暦寺の位置。 |
| 2 | 世界地理(3問) 気温と降水量のグラフ,4か国の統計の読み取り,東南アジアの国々と日本との貿易。 |
世界地理(3問) 気温と降水量のグラフ,4か国の統計の読み取り,ヨーロッパの国々と日本との貿易。 |
世界地理(3問) 気温と降水量のグラフ,日本を含む5か国の産業や貿易の統計比較,東南アジアの経済。 |
| 3 | 日本地理(3問) 4県の自然環境とおもな特産物,製造品出荷額の統計資料の読み取り,日本の産業構造の変化について(記述)。 |
日本地理(3問) 4県の自然環境とおもな高速道路,4つの港湾に関する統計の読み取り,国際空港の整備を進める理由(記述)。 |
日本地理(3問) 4つの県の自然環境と産業,地形図の読み取り,国が農地法を改正した目的を農家数と耕作放棄地の面積に着目して記述。 |
| 4 | 歴史-古代~近・現代(4問) 治水の変遷,井原西鶴とその時代の水運の整備,玉川上水とその分水が作られた理由(記述),水に関連した技術。 |
歴史-古代~近・現代(4問) 各時代の統治制度,都市における経済活動,江戸時代から昭和時代にかけての土地開発,関東大震災後の復興計画(記述)。 |
歴史-古代~近・現代(4問) 新しい知識や技術の流入,狩野永徳とその時代,日本各地の学問の場,明治時代から昭和時代にかけての学校のようす。 |
| 5 | 公民(4問) 経済活動と憲法の条文,歳入・歳出の推移と経済状況,衆議院の優越,国民年金の課題(記述)。 |
公民(4問) 経済活動の自由と憲法の条文,レタスの販売量と小売価格,消費者庁,国の環境政策(記述)。 |
公民(4問) 議院内閣制と憲法,社会資本の整備,行政改革,市町村合併と新規事業における工夫(記述)。 |
| 6 | 地理・歴史・公民総合(3問) 地形図の読み取り,日本の環境保全に関する取り組み,世界遺産登録における課題(記述)。 |
地理・歴史・公民総合(3問) 4か国の歴史と技術開発,日本の製品開発,デジタルカメラの普及(記述)。 |
地理・公民総合(3問) 4か国の統計比較,バブル経済とその崩壊,東京都市圏の人口の特徴(記述)。 |
【傾向&アドバイス】
2014年も前年と同じく大問6題の出題で,全体の出題構成にも変化はない。地理・歴史・公民の各分野ともに基礎的な知識で対応できる問題が大半だが,地図・資料・グラフなどをもとにして考える総合問題で構成されているため,教科書のほかに地図帳や資料集を併用した学習が必要である。出題形式は選択式の設問が多いが,重要事項・資料の読み取りなどの記述式も増加傾向にあるため,記述対策の練習も十分に積み重ねておくことが必要である。
1は3分野から1問ずつの出題。基礎知識を問う設問が中心だが,略地図への書き込み形式の出題もある。確実に得点できるよう,重要事項を確認しておきたい。
2の世界地理は,世界の気候や日本との貿易などをテーマにした出題。統計資料をもとにした出題となっているため,グラフや表などから情報を正確に読み取る力を養っておきたい。
3の日本地理では,4県の自然環境の特色とおもな特産物,統計資料の読み取り,日本の産業構造の変化に関する記述問題が出題された。資料を的確に読み取る力が問われる。
4の歴史分野は,古代から近現代までの重要事項に関する知識や理解を問う問題が出題された。教科書や 資料集などで,各時代の特徴や前後関係を正確に把握しておくこと。
5の公民分野は,経済分野を中心に,法令や国の機関のはたらき,社会保障制度の今後の課題についての設問であった。資料を読み取って考察するタイプの問題演習も必要である。
6は,世界遺産に関するテーマから3分野の融合問題。資料を読み取って答える記述式も出題されている。題意を正確に把握し,要求されている条件を満たしながら文章で表現する力が求められる。
| 高校入試情報 市進受験情報ナビ | ■高校入試 偏差値・内申一覧 | ■高校入試 時期別ポイント | ■勉強方法と受験作戦 |
|---|---|---|---|
| 東京都立高校 偏差値 | 夏の学習法 | 先輩たちの合格体験 | |
| 東京都立高校 内申のめやす | 秋の学習法 | 併願作戦を立てよう | |
| ■2015年高校入試情報 | 神奈川県公立高校 | 冬の学習法 | 都県別 入試の実態 |
| 国立・私立高校 | 埼玉県公立高校 | 高校入試速報 | |
| 東京都立高校 | 千葉県公立高校 | 新年度特集 | |
| 神奈川県公立高校 | 茨城県立高校 | ||
| 埼玉県公立高校 | 国立・私立高校 | ■公立高校について詳しく知ろう | ■国立・私立高校について知ろう |
| 千葉県公立高校 | 偏差値ってなんだろう | 公立高校入試システム | 学校別入試結果分析 |
| 茨城県立高校 | 偏差値を上げるには | 公立高校入試問題分析 | 倍率や難易度が変わるしくみ |
| 学力検査の平均点 | 合格最低点 | ||
| 過去3年間の倍率推移 | 学費一覧と就学支援金・補助金 | ||
| ■学校説明会レポート | ■大学入試合格実績 | 高校別部活一覧 | 私立高校 面接内容一覧 |
| 国立・私立・公立高校 現役・浪人別大学合格実績 | 高校マップ | 高校別部活一覧 | |
| グラフで比較!大学合格実績 | 高校マップ |
Copyright c2013 Ichishin Kyouiku Group. All Rights Reserved.