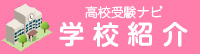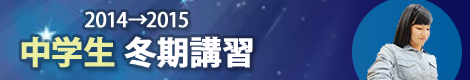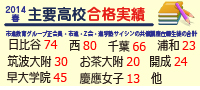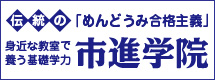神奈川県公立高校入試問題分析
【英語】※年度横の( )内は全県合格者平均点。2014・2013年からは100点満点,2012年は50点満点。
| 2014年(59.6点) | 2013年(54.8点) | 2012年(34.4点) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リスニング(8問) 対話文の受け答え選択,英問への英答選択,日本語での記述。 |
1 | リスニング(8問) 対話文の受け答え選択,英問への英答選択,日本語での記述。 |
1 | リスニング(10問) 絵にあう答えの選択,会話文の内容にあう答えの選択。 |
| 2 | 適語補充(2問) 頭文字が示された単語を補充して,文章を完成させる。 |
2 | 適語補充(2問) 頭文字が示された単語を補充して,文章を完成させる。 |
2 | 適語補充(4問) 頭文字が示された単語を補充して,文章を完成させる。 |
| 3 | 適語選択(3問) 前後の関係から文脈にあった単語を選択。 |
3 | 適語選択(3問) 前後の関係から文脈にあった単語を選択。 |
3 | 適語選択(4問) 前後の関係から文脈にあった単語を選択。 |
| 4 | 対話文完成(4問) 指定された6語のうち5語を並べ替え,英文を完成させる。 |
4 | 対話文完成(4問) 指定された6語のうち5語を並べ替え,英文を完成させる。 |
4 | 対話文完成(4問) 指定された5語から4語を選択して並べ替え,英文を完成させる。 |
| 5 | 条件作文(1問) 英文の空欄の適文補充。 |
5 | 条件作文(3問) 英文の空欄の適文補充,資料を読み取り日本語の質問に英語で答える。 |
5 | 適語適文選択(約340語・4問) 資料とともに示された対話文の空欄に入る適語や適文を選択。 |
| 6 | 条件作文(2問) 絵の場面を表す英文の作成。 |
6 | 長文総合(約500語,4問) 適文選択補充,内容把握の英問英答,文整序,内容合致。 |
6 | 英問英答・適文選択(5問) 英文・表・絵についての英問に対する英答選択と,短文の空欄に入る3つの英文の整序組み合せを選択。 |
| 7 | 対話文総合(約420語,4問) 適語補充,適文選択補充,内容把握,内容合致。 |
7 | 英問英答(4問) 表・絵・英文についての英問に対する英答選択。 |
||
| 8 | 適語選択・英問英答(4問) カード・グラフなどについての適語選択補充と英問に対する英答選択。 |
8 | 対話文総合(約690語,4問) 適文選択補充,内容把握の英問英答,適文補充,内容合致の英問英答。 |
7 | 長文総合(約560語,5問) 対話文をもとに,内容把握(3問),内容合致(1問),本文に沿ったスピーチ原稿の空欄に適語句を補充する(1問) |
| 9 | 長文総合(約440語,4問) 内容把握,適文補充,英文の整序組み合わせを選択,内容合致 |
【傾向&アドバイス】
2014年は前年より大問が1題増えて大問9題の出題となったが,小問数は前年同様32問であった。全般的に基礎的な出題が多く,普段の授業や教科書レベルの内容ができていれば十分に対応できる。
1のリスニングは,放送内容の正確な理解を問う出題となっている。内容把握の記述式も出題されており,重要な点をメモしながら聞くことが大切である。普段からCDやラジオの英語講座などを利用しよう。
2は最初のアルファベットが示されている英単語を空欄に補充する問題。英文と同じ内容の日本語の文章を参考にしながら解答すればよいため,平易な問題といえる。
3は基本的な文法問題。文の構造をしっかりととらえることがポイントとなる。
4は適語を選択・並べ替えて英文を完成させる問題。教科書の基本構文を理解しておけば容易に解ける。
5は条件作文の出題。空欄に適文を補充して英文を完成させる問題。基本構文を用いた英作文の練習をしておこう。
6は絵の内容を表す条件作文。平易な英文でよいので文法的な誤りがないように書くことが大切である。
7の対話文総合は,いずれも内容把握に関する設問であり,解答のポイントは文脈把握となる。長文になるべく多く接して慣れておきたい。
8は,カードやグラフの内容を正確に把握し,本文と照らし合わせて解答を導き出す力が求められている。
9の長文総合は文章量が比較的多いため,速読即解力が必要。記述式の空所補充もあるので,時間配分にも注意しよう。
【数学】※年度横の( )内は全県合格者平均点。2014・2013年からは100点満点,2012年は50点満点。
| 2014年(51.7点) | 2013年(65.5点) | 2012年(33.5点) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 小問集(4問) 正負の数,文字式,無理数。 |
小問集(4問) 正負の数,文字式,無理数。 |
小問集(7問) 正負の数,文字式,無理数。 |
| 2 | 小問集(8問) 文字式,因数分解,二次方程式,連立方程式,関数,角度など。 |
小問集(8問) 文字式,因数分解,二次方程式,連立方程式,関数,角度など。 |
小問集(5問) 因数分解,二次方程式,関数,平方根,平面図形。 |
| 3 | 一次・二次関数とグラフ(3問) 二次関数の比例定数,2点を通る直線の式,等積変形を利用して座標を求める。 |
一次・二次関数とグラフ(3問) 二次関数の比例定数,2点を通る直線の式,2つの図形の面積の比。 |
一次・二次関数とグラフ(3問) 二次関数の比例定数,2点を通る直線の式,2つの三角形の面積の比。 |
| 4 | 確率(3問) 2つのさいころの目の和や積が設問の条件どおりになる確率を求める問題。 |
規則と確率(3問) 規則に従い,2つのさいころの目によって座標平面上に特定の状態ができる確率を求める。 |
規則と確率(2問) 規則に従い,環状の鉄道路線に2人が同じ駅およびとなりの駅で降りる確率を求める。 |
| 5 | 連立方程式(1問) 条件にあわせて,連立方程式を使って道のりを求める問題。答えを導く手順を記述。 |
規則と二次方程式(1問) 規則に従い,連続する5つの自然数の特徴についての予測が正しいことを説明する。 |
規則と二次方程式(2問) 規則に従い,道路の交わるところに設置される信号機の数を求める。 |
| 6 | 立体図形(3問) 立体の体積,2点間の距離,特定の条件を満たす線分の長さ。 |
立体図形(3問) 立体の体積,2点間の距離,特定の条件を満たす線分の長さ。 |
立体図形(2問) 立体の2点間の距離,三角柱に巻きつけた紙テープの面積。 |
| 7 | 平面図形(1問) 基本的な定理を利用して2つの三角形の相似を証明する。 |
平面図形(1問) 基本的な定理を利用して2つの三角形の相似を証明する。 |
平面図形(2問) 円の性質を利用した2つの三角形の相似(穴埋め),角度。 |
【傾向&アドバイス】
2014年も前年と同様,大問7題の構成となっており,各分野から幅広く出題されているのが特徴である。また,規則性に関する問題が,確率・方程式とそれぞれ融合された形で出題されている。同様の傾向が続いているので,過去問で出題パターンを把握しておくことが必要である。
1は例年どおり,正負の数,文字式,無理数などの基本的な数・式の計算からの問題で,得点しやすくなっている。計算ミスがないよう,符号にも注意しながら正確に計算する練習をしておこう。
2の小問集は文字式,因数分解,二次方程式,連立方程式,関数,角度などからの出題。教科書の例題レベルの問題が中心。計算練習を繰り返して,確実に得点できるようにしておきたい。
3の関数とグラフは,毎年類似したパターンの出題となっており,今年も直線と放物線のグラフを組み合わせた問題。問題文をよく読み,与えられた座標数値などをグラフに書きこんでから問題に取りかかろう。
4は確率の問題で,毎年出題されている。数学的な思考力を必要とするが,与えられた条件を整理して考えていけば,比較的容易に解ける問題である。過去問や標準レベルの問題集で多くの類題で練習を重ね,思考力を養っておこう。
5は連立方程式を用いて速さ,道のりに関する問題の解法を記述する問題。規則性をもとに自分で連立方程式を作ることができれば,解答はさほど難しくない。
6の立体図形は三角すいに関する問題。立体の体積を求める問題,2点間の距離を求める問題のほか,特定の条件を満たしたときの線分の長さを求める問題で構成されており,いずれも空間把握力や思考力が要求される。問題集などで類題演習の量を増やし,パターンに慣れておきたい。
7の平面図形は,円の性質をもとに三角形の相似を証明する問題。教科書レベルの基本的な定理については十分に理解し活用できるようにしておくことが必要である。
【国語】※年度横の( )内は全県合格者平均点。2014・2013年からは100点満点,2012年は50点満点。
| 2014年(60.8点) | 2013年(67.8点) | 2012年(35.5点) |
|---|---|---|
| 1 漢字・語句 漢字の読み・書き取り(各4問),文法(1問),短歌(1問)。 |
1 漢字・語句 漢字の読み・書き取り(各4問),敬語(1問),俳句(1問)。 |
1 漢字・語句 漢字の読み・書き取り(各4問),敬語(1問),文章とグラフをもとにした内容把握(2問)。 |
| 2 古文(4問) 出典は『太平記』。寺に隠れた大塔宮を敵兵が探しにきたがうまく身を隠し生き延びた場面を描く。心情把握,内容把握,内容一致。 |
2 古文(4問) 出典は『義経記』。兄の源頼朝から逃げていく源義経の一行に起こったできごとを描く。心情把握,内容把握,内容一致。 |
2 小説文(7問) 出典ははらだみずき『ずっと忘れない』。高校3年生の「ぼく(松本)」を中心とする人間関係と登場人物の心情の変化を描く。適語補充,心情把握,内容把握など。 |
| 3 小説文(6問) 出典は平田オリザ『幕が上がる』。内容把握,心情把握,適語補充,内容一致など。 |
3 小説文(6問) 出典は坂井希久子『迷子の大人』。内容把握,心情把握,内容一致など。 |
3 論説文(8問) 出典は西江雅之『食べる』。食べ物を題材に取り上げて伝統とは何かということについて論ずる文章。適語補充,内容把握,記述式1問,内容一致。 |
| 4 論説文(7問) 出典は浜本隆志『「窓」の思想史』。 障子の文化とガラスの文化の対比を論ずる文章。適語選択補充,内容把握,記述式1問,内容一致。 |
4 論説文(7問) 出典は島田雅彦『いまを生きるための教室 死を想え 国語・外国語』。適語補充,内容把握,記述式1問,内容一致。 |
4 古文(5問) 出典は『駿台雑話』。江戸時代,庭で接ぎ木をする寺の老住職と,将軍との会話から,後世のために行動することの大切さを説く。主語,内容把握,内容一致など。 |
| 5 適文補充・条件作文(3問) 与えられた資料と会話文から,グラフを示すときと読み取るとき,それぞれの注意点をまとめる。(70~80字)。 |
5 条件作文(2問) 与えられた資料を読み取り,「メディアの効果的な利用について」というテーマで発表する原稿を完成させる(60字・80字)。 |
【傾向&アドバイス】
2014年は前年と同様,大問5題の構成であった。設問は選択式が中心であるが,記述式の問題が増加傾向にあるのが特徴である。ただし,文章読解を柱として基礎から標準レベルまでの総合的な国語力を問う構成に変わりはなく,普段の授業を大切にしながら,標準的な問題集で補強する学習を心がけたい。
1の漢字の読みは,「申告」「養蚕」「警鐘」「頂く」。漢字の書き取りは,「複写」「祝辞」「至難」「織る」が出題された。文法は基礎的な出題。短歌の内容を正しく説明した文章を選択する問題も出題された。
2の古文は内容を把握すること自体はさほど難しくはない。敬語に注意し,動作主を正確につかみながら読み進めていくことがポイントである。できるだけ多くの問題をこなして,古文に対する苦手意識を持たないようにしておきたい。
3の小説文は,内容理解と登場人物の心情の把握がポイントとなる。文章は比較的理解しやすいので,じっくり読み進めながら心理描写と心情の変化を把握し,理解するようにしたい。また,話の展開と登場人物どうしの関係にも注目することが大切である。
4の論説文は,内容把握を問う問題が中心である。文章は筆者の主張や考えが明確に述べられている内容でまとめられているので,内容の把握は比較的容易であろう。日ごろから,文章の主題や要旨を的確に把握する力を身につける読解練習を積み重ねておくことが大切である。
5の条件作文は,与えられた資料を参考にして,会話文を正確に読み取ったうえで,条件を満たす文章にまとめる力が必要となる。類題で十分に練習し,同様の設問に慣れておきたい。時間配分にも注意が必要である。
【理科】※年度横の( )内は全県合格者平均点。2014・2013年からは100点満点,2012年は50点満点。
| 2014年(38.6点) | 2013年(66.4点) | 2012年(31.3点) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 物理の小問集(3問) 電流と磁界,斜面を下る小球の持つエネルギー,電流回路。 |
物理の小問集(3問) 光の進み方,圧力を調べる実験,仕事の大きさと仕事率を調べる実験。 |
物理の小問集(3問) おもりにはたらく力,モノコードの弦をはじいたときの音の高さ,電流の大きさ。 |
| 2 | 化学の小問集(3問) 器具の使い方,炭酸水素ナトリウムの分解,水溶液の濃度。 |
化学の小問集(3問) エタノールの状態変化,金属の密度,アルカリ性の水溶液。 |
化学の小問集(3問) 炭酸水素ナトリウムの分解,ロウの状態変化,化学電池。 |
| 3 | 生物の小問集(3問) 顕微鏡の操作,遺伝,食物連鎖による個体数の変化。 |
生物の小問集(3問) 動物の分類,食物連鎖,細胞分裂の観察における留意事項。 |
生物の小問集(3問) 消化酵素によって消化されてできる物質,分解者,光合成。 |
| 4 | 地学の小問集(3問) 湿度の計算,星の日周運動,金星の見え方 |
地学の小問集(3問) 前線の通過,地層ができた過程,雲が発生するしくみ。 |
地学の小問集(3問) 月と地球の位置関係,地震,柱状図。 |
| 5 | 力と仕事(4問) フックの法則,仕事,手が糸を引いた距離とばねの伸びの関係をグラフに表す,浮力 |
回路と電流(4問) 回路図の完成,電圧系の読み取り,電流の大きさの計算,ヒーターと水の上昇温度。 |
物体とエネルギー(4問) レール上を進む小球にはたらく重力の大きさ,位置エネルギー,小球の衝突と木片の移動など。 |
| 6 | 化学変化とイオン(4問) 電池,イオン,イオン式,実験方法の考察(記述)。 |
化学変化(4問) 気体の発生,イオン式,実験結果の考察など。 |
化学変化(4問) 化学反応式,発生した気体の特徴,リトマス紙の色の変化など。 |
| 7 | だ液のはたらき(5問) 実験における条件の設定,だ液のはたらきなど。 |
植物のしくみ(4問) 受精と染色体の数の変化,主根と側根,維管束など。 |
遺伝(4問) 精細胞と胚,遺伝子の組合せ,優性の法則,染色体のようす。 |
| 8 | 地震(5問) 地震の原因,地震の発生時刻,震央の位置など。 |
太陽の動き(4問) 透明半球と観察者の位置,南中時刻,南中高度の変化など。 |
気象(4問) 春の天気図,小笠原気団,偏西風,海岸付近の風向き。 |
【傾向&アドバイス】
2014年は,例年と同じ大問8題の構成であった。出題傾向に目立った変更はなく,1~4がそれぞれ物理・化学・生物・地学の各分野の小問集,5~8は4分野から1題ずつの出題という形式であった。出題内容は例年どおり,実験・観察を中心とした観察力・思考力を問う設問となっている。大部分は選択式の設問であるが,一部で計算や化学反応式などの筆記問題も出題されている。記述式では,どのようにまとめるかがポイント。傾向を把握するために近年5年間の過去の入試問題をよく調べ,重要事項をしっかり定着させておきたい。
5の物理の問題では,ばねや定滑車を用いた実験から出題された。物理の問題では計算問題が出題されることが多いので,類題で繰り返し練習して慣れておきたい。設問は基本的な内容で構成されているので,教科書などの実験例を確認しておこう。
6の化学の問題では,化学変化に関係する設問が毎年出題されている。化学反応式やイオン式は例年出題されているので,教科書や問題集などでおもな化合や分解の化学反応式を確認しておくとよいだろう。設問内容は基礎力重視であるが,正確な知識が求められている。また,ある程度出題パターンが決まっているので,過去問などで傾向を確認しておきたい。
7の生物の問題では,だ液のはたらきを調べる実験からの出題であった。設問自体は基礎知識を問う構成となっており,確実に得点したい。重要な用語については,教科書や資料集でしっかりと復習しておくことが大切である。
8の地学の問題では,地震に関する設問が出題された。基礎知識を問うだけでなく,考察力や計算力もみる構成となっている。日ごろから問題集などで繰り返し練習をしておこう。
【社会】※年度横の( )内は全県合格者平均点。2014・2013年からは100点満点,2012年は50点満点。
| 2014年(49.5点) | 2013年(51.1点) | 2012年(32.1点) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 世界地理(5問) 世界の略地図,時差の計算,気温と降水量のグラフの読み取りなど。 |
世界地理(5問) 南半球の略地図,北方領土,時差の計算,気候の特徴,ASEANの課題と日本政府の対応。 |
世界地理(7問) 地図上の緯線,日本の東端と西端,タイの宗教,冷帯の住居,時差,統計の読み取りなど。 |
| 2 | 日本地理(7問) 日本地図,ハウス栽培の利点,写真撮影の位置と方向,地形図の読み取りなど。 |
日本地理(7問) 気温と降水量のグラフ,対馬海流とリマン海流,5県の輸出量の比較,地形図の読み取りなど。 |
日本地理(7問) 水力発電,気温と降水量のグラフ,統計の読み取り,縮尺と計算,地形図の読み取りなど。 |
| 3 | 歴史―古代~近世(5問) 明との貿易,江戸時代の出来事,長崎の歴史など |
歴史―古代~近世(7問) 風土記,江戸時代の対外関係,鉄道の利用と生糸の輸出など。 |
歴史―古代~近世(7問) 聖徳太子の政治,室町文化,江戸幕府の政治など。 |
| 4 | 歴史―近・現代(5問) 明治前半の出来事,東アジアへの侵略,戦後の経済民主化,減反政策など。 |
歴史―近・現代(6問) 日米安全保障条約の改定,戦費の審議,二・二六事件と議員の演説,日中国交正常化など。 |
歴史―近・現代(8問) 日露戦争の講和条約,昭和初期の日本,農地改革,大正デモクラシー,高度経済成長など。 |
| 5 | 公民(8問) 日本国憲法,精神の自由,労働三権,参議院の役割,最高裁判所,憲法改正など。 |
公民(7問) 自由権,天皇の国事行為,労働基準法,UNICEF,国際連合と平和維持活動など。 |
公民(7問) 自由権,解散請求,刑事裁判と裁判員制度,衆議院の選挙制度,日本銀行の役割,為替相場など。 |
| 6 | 公民(7問) バリアフリー,日本銀行の金融政策,企業と家計の関係など。 |
公民(7問) 円高不況とバブル景気,日本銀行の役割,デフレーションなど。 |
公民(5問) 少子高齢社会,日本の財政,グローバル化,国際連合など。 |
【傾向&アドバイス】
2014年は前年と同様,大問6題の構成で,各分野から大問が2題ずつ出題された。出題傾向に変更はなく,3分野ともに地図・グラフ・統計などの資料を参考にした問題が多く出題されている。選択式の設問が多いが,近年は記述式の設問が増加傾向にあるため,文章記述の対策もしておく必要がある。また,読み取る資料が多いため,時間配分にも注意が必要である。基本的な用語を暗記するだけでなく,日ごろから地図帳や資料集を活用して,内容を理解しながら進める学習を心がけたい。
1,2地理分野は,基礎的な知識を確認する問題のほか,地図や地形図,表・グラフなどから正確に情報を読み取る能力が要求される。知識事項を暗記するだけでなく,資料をもとにできごとや状況の意味を考えていく必要がある。ひとつのテーマに関してさまざまな角度から地理的な考察ができるように,日ごろから問題集などで練習しておこう。
3,4の歴史分野では,古代から近・現代までの幅広い出題となっている。資料とからめて出題される関連事項や時代背景,日本と諸外国とのかかわりなどを問う形式である。各年代の重要事項や歴史上の人物の業績については,しっかりと把握しておく必要があるが,このほかに資料を読み取って,考察し,論述する練習も必須である。
5,6の公民分野は,政治,経済,その他さまざまな現代社会の問題が取り上げられている。教科書で基礎レベルの知識事項を確認しておくほかに,日ごろから,国内や世界の時事的な問題に関心を持つようにしておきたい。教科書に出てくる用語などの基礎知識だけの暗記にとどまらず,時事問題対策としては,新聞やテレビのニュースを見て要点を整理しておくことが効果的である。
| 高校入試情報 市進受験情報ナビ | ■高校入試 偏差値・内申一覧 | ■高校入試 時期別ポイント | ■勉強方法と受験作戦 |
|---|---|---|---|
| 東京都立高校 偏差値 | 夏の学習法 | 先輩たちの合格体験 | |
| 東京都立高校 内申のめやす | 秋の学習法 | 併願作戦を立てよう | |
| ■2015年高校入試情報 | 神奈川県公立高校 | 冬の学習法 | 都県別 入試の実態 |
| 国立・私立高校 | 埼玉県公立高校 | 高校入試速報 | |
| 東京都立高校 | 千葉県公立高校 | 新年度特集 | |
| 神奈川県公立高校 | 茨城県立高校 | ||
| 埼玉県公立高校 | 国立・私立高校 | ■公立高校について詳しく知ろう | ■国立・私立高校について知ろう |
| 千葉県公立高校 | 偏差値ってなんだろう | 公立高校入試システム | 学校別入試結果分析 |
| 茨城県立高校 | 偏差値を上げるには | 公立高校入試問題分析 | 倍率や難易度が変わるしくみ |
| 学力検査の平均点 | 合格最低点 | ||
| 過去3年間の倍率推移 | 学費一覧と就学支援金・補助金 | ||
| ■学校説明会レポート | ■大学入試合格実績 | 高校別部活一覧 | 私立高校 面接内容一覧 |
| 国立・私立・公立高校 現役・浪人別大学合格実績 | 高校マップ | 高校別部活一覧 | |
| グラフで比較!大学合格実績 | 高校マップ |
Copyright c2013 Ichishin Kyouiku Group. All Rights Reserved.