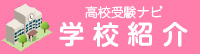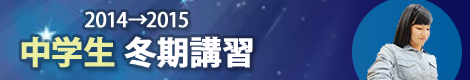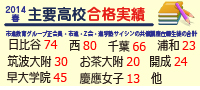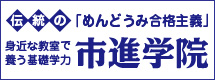千葉県公立高校入試問題分析(前期選抜)
【英語】
| 2014年 | 2013年 | 2012年 | |
|---|---|---|---|
| 1 | リスニング(2問) 対話文の受け答えを選択。 |
リスニング(2問) 対話文の受け答え選択。 |
リスニング(2問) 対話文の受け答え選択。 |
| 2 | リスニング(2問) 英文の内容にあてはまる英文や絵を選択。 |
リスニング(2問) 英文の内容にあてはまる絵を選択。 |
リスニング(2問) 英文の内容にあてはまる絵を選択。 |
| 3 | リスニング(3問) 英文に対する英問の英答選択。 |
リスニング(3問) 英文に対する英問の英答選択。 |
リスニング(3問) 英文に対する英問の英答選択。 |
| 4 | 英文に適語補充(4問) uncle,repeat,supportなど。 |
英文に適語補充(4問) March,bring,explainなど。 |
英文に適語補充(4問) summer,group,carry,alone。 |
| 5 | 語形変化・語順整序(5問) 複数形,過去形,分詞,関係代名詞など。 |
語形変化・語順整序(5問) 過去進行形,比較級,分詞,不定詞など。 |
語形変化・語順整序(5問) 序数,動詞の過去分詞形,分詞,疑問文など。 |
| 6 | 英作文(1問) テーマに対して20語程度の英作文。 |
英作文(1問) テーマに対して20語程度の英作文。 |
英作文(1問) テーマに対して20語程度の英作文。 |
| 7 | 長文総合(約260語,6問) 適語選択補充,英問への英答記述,内容合致選択,適語補充。 |
長文総合(約210語・6問) 適語選択補充,英問への英答記述,内容合致選択,適語補充。 |
長文総合(約230語・6問) 適語選択補充,英問への英答記述,内容合致選択,内容把握。 |
| 8 | 長文総合(約380語・4問) 内容把握,適語句選択補充,英問への英答記述,内容合致選択。 |
長文総合(約390語・4問) 内容把握,適語選択補充,英問への英答記述,内容合致選択。 |
長文総合(約340語・4問) 内容把握,内容合致選択,適語補充,英問への英答記述。 |
| 9 | 対話文総合(約130語・4問) 対話文の内容に合うように適文選択補充。 |
対話文総合(約160語・4問) 対話文の内容に合うように適文選択補充。 |
対話文総合(約160語・4問) 対話文の内容に合うように適文選択補充。 |
【傾向&アドバイス】
2014年は,前年と同じく大問9題の構成であった。長文は短めの文章をいくつかまとめた形式で出題されており,比較的短い文章をいかに正確に読めるかが問われている。全体的に基礎学力を見る内容になっているため,普段の授業や教科書を中心とした学習が大切である。重要単語や熟語,文法・基本構文,慣用表現をしっかりと覚えておけば十分に対応できる。日ごろから,より多くの英文にふれながら速読速解力を身につけておくことが大切である。また,英作文・英問英答では,英語による確かな表現力が求められるので,十分な練習を積んでおきたい。
1~3のリスニングは,全体の約2割の配点を占める。基礎レベルなので確実に得点したい。CDやラジオの英語講座などを利用して,ネイティブスピーカーの発音に慣れておくことが望ましい。
4の適語補充では,日常生活で使われる基礎的な単語が問われている。普段から単語練習はコツコツと積み重ねておくことが大切。正しいつづりをしっかり覚えておこう。
5は語形変化や整序英作文で対話を完成させる問題。基本的な文法事項を確認しておくこと。出題形式に慣れるために類題での練習も欠かせない。
6の英作文では,簡潔かつ正確にまとめる構成力が要求されるので,基本的な慣用表現と文法事項を理解したうえで,教科書の基本文型を暗記しておきたい。
7,8の長文総合は,適語補充や内容合致などが中心で,正確な内容把握が求められている。速読力を磨いておこう。また,英問英答では基本文型や慣用表現を押さえながら,繰り返し練習するのが効果的。
9の対話文は,会話の流れを把握することがポイント。慣用表現は正確に覚えておきたい。
【数学】
| 2014年 | 2013年 | 2012年 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 小問集(6問) 正負の数,四則計算,文字式,一次・二次方程式など。 |
小問集(6問) 正負の数,四則計算,文字式,比例式,無理数,因数分解。 |
小問集(6問) 正負の数,四則計算,文字式,一次関数,無理数,二次方程式。 |
| 2 | 小問集(5問) 数の性質,関数,確率,条件にあう円の作図など。 |
小問集(6問) 文字式,角度,一次方程式,立体図形,確率,条件にあう点Pの作図。 |
小問集(6問) 面積,角度,回転体,自然数の値,確率,条件にあう正三角形の作図。 |
| 3 | 関数とグラフ(3問) 座標を求める,条件をもとに三角形の面積や,回転移動したときの頂点の座標を求める。 |
関数とグラフ(2問) 条件をもとに三角形の面積を求める,条件にあったグラフ上の点の座標を求める。 |
方程式と関数(2問) 会話文と資料をもとに空欄に適切な数字を入れる,条件をもとに関数の交点を求める。 |
| 4 | 平面図形(2問) 三角形の相似の照明,線分の長さ。 |
規則性(4問) 点の移動と面積,条件にあった変数の変域など。 |
関数とグラフ(2問) 二次関数の比例定数,条件にあった点の座標を求める。 |
| 5 | 規則性(2問) 規則性の明確化,条件にあった図形の面積。 |
平面図形(3問) 三角形の合同の証明,線分の長さ。 |
平面図形(3問) 三角形の合同の証明,正方形の面積など。 |
【傾向&アドバイス】
2014年は前年と同様,大問5題の構成であった。具体的な事象と関数の融合問題の比重が高まっている。全体的には基本・標準レベルだが,数学的な思考力を問うやや難度の高い問題も出題されている。問題数はさほど多くないが,図形の作図問題や証明問題など解答に時間のかかる問題もあるので,時間配分には注意したい。小問集2題は例年と変わりなく,基本的な計算力を身につけておけば確実に得点できる問題なので,ケアレスミスに気をつけながらていねいに解いていきたい。そのほかの設問は,教科書や問題集を利用して補強しておくことが必要である。関数と図形に関する問題は,解法のパターンをしっかり身につけておくなど,十分に習熟して臨みたい。
1は例年どおり,正負の数,四則計算,文字式,一次・二次方程式,無理数などの基本的な計算問題中心の出題構成であった。いずれも教科書の例題レベルの問題で,計算ミスに注意して普段から正確に計算する練習をしておくことが大切である。
2は文字式,関数,確率,平面図形など幅広い分野からの出題。平面図形の作図問題は例年出題されているので,基本的な作図についてはよく理解しておく必要がある。類題演習を繰り返し解いておこう。
3は一次関数とグラフからの出題。問題文中に解法のヒントが示されているので,それをもとに条件を整理して解いていけば十分に対応できる。三角形の回転させたときの頂点の移動は難しいかもしれないが,問題文をしっかり読んで図で整理することで対応したい。関数の基礎的な知識と理解に加え,数学的な見方や考え方を養うことに力を注ぎ,万全の準備をしておくことが必要である。また,定理や法則を覚えるだけでなく,日ごろから考える筋道を重視した学習もしっかりと行っておきたい。
4の平面図形は,三角形の相似を証明する問題と,線分の長さを求める問題が出題された。証明の手順を理解し,必要なことがらを書きもらさないように注意しよう。証明問題に関しては,証明の一部だけではなくすべてを書く練習を繰り返し行っておくことが望ましい。
5の規則性は,規則的に並んだ整数の表を図形的に見て面積を求める問題が出題された。応用的な内容であるが,題意を正確に読み取り,与えられた条件を整理していけば,解答は導き出せる。そのためには,最初の設問が規則性の理解を手助けしてくれるので,多少時間をかけてでも落ち着いてしっかり取り組みたい。
【国語】
| 2014年 | 2013年 | 2012年 |
|---|---|---|
| 1 放送の聞き取り問題(4問) 四字熟語,敬語の使い方,内容一致,記述(20~30字) |
1 放送の聞き取り問題(4問) 内容一致,内容把握,四字熟語,記述(30字) |
1 放送の聞き取り問題(5問) 内容把握,内容一致,記述(30字・45字の2問)。 |
| 2 漢字の読み(4問) |
2 漢字の読み(4問) |
2 漢字の読み(4問) |
| 3 漢字の書き取り(5問) |
3 漢字の書き取り(5問) |
3 漢字の書き取り(4問) |
| 4 文法・語句(4問) 文法,漢文の返り点,慣用句など。 |
4 文法・語句(4問) 文法,慣用句,反対語,文章校正。 |
4 敬語・語句(4問) 手紙文,敬語の種類,四字熟語の意味。 |
| 5 論説文(6問) 出典は畑村洋太郎『組織を強くする技術の伝え方』ほか。内容・心情把握,記述(20~25字)など。 |
5 小説文(6問) 出典は岡崎ひでたか『鬼が瀬物語魔の海に炎たつ』。内容・心情把握,適語補充,記述(20字)など。 |
5 小説文(7問) 出典は鷺沢萠『ほおずきの花束』。内容・心情把握,適語補充,記述(35字)など。 |
| 6 小説文(6問) 出典は小納弘『五色の九谷』。内容把握,適語補充,記述(20字以内)など。 |
6 論説文(6問) 出典は野矢茂樹『新版 論理トレーニング』。文法,内容把握,適語補充,記述(25字)など。 |
6 論説文(6問) 出典は鷲田清一『〈想像〉のレッスン』。文法,適語補充,内容把握,記述(10字),作文。 |
| 7 古文・漢文(4問) 出典は『十訓抄』。現代仮名づかい,適語補充,内容把握など。 |
7 古文・漢文(5問) 出典は『浮世物語』。現代仮名づかい,適語補充,主語,内容把握。 |
7 古文・漢文(5問) 出典は『徒然草』。語句の意味,指示語,内容・心情把握,記述(30字)など。 |
| 8 作文(1問) 資料をもとに,自分の考えを書く。 |
8 作文(1問) 資料をもとに,自分の考えを書く。 |
【傾向&アドバイス】
2014年は前年と同じ大問8題の構成であった。記述や作文など,全体的に記述力を問う傾向に変わりはなく,日ごろから書く練習を重ねておきたい。全体的に,正確な知識や基本的な読解力を問う問題が中心となっている。
1は放送の聞き取り問題。放送は1回だけなので,メモをとり,確実に内容を把握できるようにしておこう。内容把握を問う記述も出題されている。聞き取り,記述のいずれにおいても,日ごろからの練習が大切。
2の漢字の読みは「澄んで」「悔しさ」「余裕」「慶弔」が出題された。
3の漢字の書き取りは「絶やす」「(途方に)暮れる」「綿密」「模様」「集大成」が出題された。
4は,助詞の「の」の用法,漢文の返り点,慣用句,話し方の工夫の出題。いずれも基本的な内容であるが,漢文に返り点を入れる問題が出された。貴重な得点源になるため,知識のもれがないようにしておきたい。知識問題は確実に得点できるように,教科書や問題集でしっかり確認しておこう。
5の論説文は,筆者の主張している内容を的確に把握することが不可欠である。適語補充,記述式とも,文章の内容を理解していないと解答できない。読解にあたっては,段落ごとの要点をつかみ,全体の文脈と要旨を把握することが求められる。
6の小説文は,内容理解と登場人物の心情の把握がポイント。文章をじっくり読めば,記述式もさほど難しいとはいえない。情景描写や会話の中に込められた心情の変化を把握し,理解するようにしたい。また,登場人物どうしの関係に注目するのもポイントである。
7の古文・漢文は,文章が短く,設問も比較的答えやすい。教科書や問題集で代表的な古典作品に数多くふれ,独特の文章に慣れておくことが大切である。
8の作文は,指定内の字数にまとめることはもちろん,原稿用紙の使い方を理解していることと,資料をしっかりと読み取ったうえで文章を構成することが前提となる。減点対象とならないように注意しよう。
【理科】
| 2014年 | 2013年 | 2012年 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4分野総合(4問) 熱放射,状態変化,中生代の生物,銀河系での太陽系の位置。 |
4分野総合(4問) プレート,種子植物,化石燃料,抵抗の計算。 |
4分野総合(4問) 減数分裂,浮力,台風,ガスバーナーの使い方。 |
| 2 | マツの花のつくり(3問) 裸子植物のつくり,顕微鏡の使い方など。 |
物体にはたらく力(3問) グラフ作成,浮力の大きさ,手が糸を引く力の大きさなど。 |
電解質の水溶液(3問) 水溶液のようす,電極に付着した物質と発生した気体など。 |
| 3 | 電池のしくみ(3問) 電極から発生する気体と化学変化,電流と電子の移動など。 |
月の観測(3問) 月が光って見える理由,地球・月・太陽の位置,観測時刻など。 |
セキツイ動物の分類(3問) 魚類,恒温動物の特徴,鳥類の特徴。 |
| 4 | 気象観測(4問) 天気記号,観測結果の読み取り,偏西風,天気図の読み取り。 |
化学変化(3問) 実験上の注意,化学反応式など。 |
岩石(3問) 火成岩,示準化石など。 |
| 5 | 電気回路と電力(3問) 直列回路と並列回路,消費電力の計算など。 |
遺伝の法則(3問) 分離の法則,染色体の模式図,遺伝子の組合せなど。 |
物体の運動(3問) 台車にはたらく重力の向き,等速直線運動,慣性の法則など。 |
| 6 | マグネシウムの燃焼(4問) 燃焼,化学反応式,質量比,中和など。 |
水溶液(4問) 溶質と溶媒,溶質の質量,質量パーセント濃度,結晶の質量。 |
植物の観察(4問) 顕微鏡の使い方,葉の断面図,気孔を出入りする気体など。 |
| 7 | 力のつり合い(4問) フックの法則,作用点と力のつり合いの図示など。 |
海陸風(4問) 砂と水の温度変化,海陸風の向き,海陸風の観測地点など。 |
回路と電熱線の発熱(4問) 電熱線の抵抗,グラフ作成,伝導と放射,水温の上昇。 |
| 8 | 土の中の生物のはたらき(4問) 微生物のはたらき,対照実験など。 |
光の反射(4問) 入射角と反射角の関係,反射した光の動き,実像の見え方など。 |
星の動き(4問) 星の日周運動と地球の自転,恒星と星座の動き,観察日時。 |
| 9 | 地震(4問) マグニチュード,震度,主要動,震源からの距離の計算。 |
動物の分類(4問) 軟体動物,解剖ばさみの使い方,イカの特徴,えらのはたらき。 |
化学変化(4問) 二酸化炭素の化学式,化学反応式,炭素粉末の質量,酸化銅。 |
【傾向&アドバイス】
2014年は,前年と同じく大問9題の構成であった。設問の構成も例年と同様で,物理・地学・化学・生物の各分野から均等の出題となっている。大部分の設問は,実験や観察に重点を置いた基本的な内容であるが,記述式とグラフの作成は前年同様に出題されている。教科書で取り上げられている実験・観察は,関連する図表・グラフなどとともによく確認しておきたい。また,実験は結果を得るまでの過程や流れに注意した学習がポイントである。
1は4分野総合で,各分野から1問ずつの基本的な出題。確実に得点したい。
2,8の生物は,マツの花のつくりと土の中の生物のはたらきについての出題。教科書で理科用語の確認をするなど,基礎事項は確実に理解しておきたい。
3,6の化学は,電池のしくみとマグネシウムの燃焼からの出題であった。化学変化に関する問題は毎年出題されているので,代表的な化学式や化学変化の例を覚えておきたい。典型的な問題を何回も解いて慣れておくとよい。計算問題も出題されている。
4,9の地学は,気象観測と地震に関する出題。目立った難問はなく,基礎事項を正確に確認しておけば,十分に対応できる。
5,7の物理は,電気回路と電力と力のつり合いに関する出題であった。物理は計算問題の対策が不可欠である。基礎的な事項を整理しておくほかに,類題の繰り返し演習で慣れておきたい。
【社会】
| 2014年 | 2013年 | 2012年 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 地理・歴史・公民総合(4問) 関東ローム層,輸送の歴史,多国籍企業,輸送に関する統計の読み取りと正誤問題。 |
地理・歴史・公民総合(4問) 黒潮,排他的経済水域,干鰯,魚介類に関する統計の読み取りと正誤問題。 |
地理・歴史・公民総合(4問) 東京湾と利根川,公共料金,1都3県の流通に関する統計,1府3県の産業に関する統計。 |
| 2 | 日本地理(5問) 日本の8地方の区分,やませ,冷害,地形図の読み取り(記述もあり)。 |
日本地理(5問) 宮城県の位置,4県の工業統計の読み取り,人口密度の計算と図示,地形図の読み取り。 |
日本地理(5問) 日本の国土,日本海側に雪が多い理由,都道府県の位置,包囲と縮尺,地形図の読み取り。 |
| 3 | 世界地理(5問) 大陸の位置関係,ロシアの属する州,標高,遊牧民の暮らす地域,産業別就業人口の割合統計。 |
世界地理(5問) 時差,ラクダのキャラバン,オーストラリア大陸を通る経線,原油の生産国,タイの貿易統計。 |
世界地理(5問) 本初子午線,正距方位図法の読み取り,インドの生活,5か国の統計と日本との比較。 |
| 4 | 歴史-古代~近世(5問) 縄文文化,奈良~鎌倉時代の出来事と文化,室町後期の国際関係,江戸時代の大阪に関する記述(20字以内)など。 |
歴史-古代~近世(5問) 戸籍と班田収授法,平清盛の業績,中国と朝鮮の王朝名,朱印状と日本町,鎖国と外国船の来航・開国。 |
歴史-原始~近世(5問) 弥生時代の生活,古事記,平安時代の地方の政治,柳生の徳政碑文の内容,元禄文化と松尾芭蕉。 |
| 5 | 歴史-近代~現代(5問) 開国後の貿易,自由民権運動,日清戦争~第二次世界大戦後の景気変動,犬養毅,満州事変頃の日本のようす。 |
歴史-近代~現代(5問) 伊藤博文の業績,不平等条約の締結と改正,普通選挙法の成立,国家総動員法と米の配給,中東戦争と石油価格の上昇。 |
歴史-近代~現代(5問) 幕末のできごとの流れ,西郷隆盛と西南戦争,二十一か条の要求の内容,国際連盟とアメリカ,GHQの指令と日本政府の政策。 |
| 6 | 公民-経済(3問) 消費者基本法,大企業に力が集中した市場,資料の読み取り。 |
公民-政治(3問) 日本国憲法で保障された権利,司法権の独立,三審制。 |
公民-経済(3問) 消費支出の費目構成,クーリングオフ,製造物責任法。 |
| 7 | 公民-政治(3問) 社会権,内閣総理大臣の決め方に関する記述(35字以内)など。 |
公民-国際社会(2問) ODA,GDPと二酸化炭素排出量。 |
公民-国際社会(2問) 国家の主権の及ぶ範囲,世界遺産。 |
| 8 | 公民-国際社会(2問) FTA,ASEANに関する資料の読み取り。 |
公民-経済(3問) 間接金融,企業の活動,日本銀行の金融政策。 |
公民-政治(3問) 地方自治の本旨,直接請求権,地方財政。 |
【傾向&アドバイス】
2014年は大問8題,小問32問で前年と同じ構成であった。地図・資料・グラフなどからの読み取りが大半を占める出題形式にも変わりはない。地理・歴史・公民の各分野ともに,基礎知識を充実させながら地図帳や資料集にもよく目を通しておくことが大切である。
地理分野では,統計資料や地形図の読み取りが出題されている。2014年は違ったが,日本地理では千葉県の産業をからめた設問が出題されることが多い。国勢と比較して整理をしておくと効果的である。
歴史分野では古代から現代まで幅広く出題されている。政治・経済・文化の各テーマ別に史実を整理するなどして理解を深めておきたい。世界との対外関係や歴史の年代把握にも注意しよう。
公民分野は,基礎知識を充実させるとともに,最近の日本や国内外で話題となっていることや身近なことがらに注意したい。ニュースや新聞は毎日確認するように心がけよう。
| 高校入試情報 市進受験情報ナビ | ■高校入試 偏差値・内申一覧 | ■高校入試 時期別ポイント | ■勉強方法と受験作戦 |
|---|---|---|---|
| 東京都立高校 偏差値 | 夏の学習法 | 先輩たちの合格体験 | |
| 東京都立高校 内申のめやす | 秋の学習法 | 併願作戦を立てよう | |
| ■2015年高校入試情報 | 神奈川県公立高校 | 冬の学習法 | 都県別 入試の実態 |
| 国立・私立高校 | 埼玉県公立高校 | 高校入試速報 | |
| 東京都立高校 | 千葉県公立高校 | 新年度特集 | |
| 神奈川県公立高校 | 茨城県立高校 | ||
| 埼玉県公立高校 | 国立・私立高校 | ■公立高校について詳しく知ろう | ■国立・私立高校について知ろう |
| 千葉県公立高校 | 偏差値ってなんだろう | 公立高校入試システム | 学校別入試結果分析 |
| 茨城県立高校 | 偏差値を上げるには | 公立高校入試問題分析 | 倍率や難易度が変わるしくみ |
| 学力検査の平均点 | 合格最低点 | ||
| 過去3年間の倍率推移 | 学費一覧と就学支援金・補助金 | ||
| ■学校説明会レポート | ■大学入試合格実績 | 高校別部活一覧 | 私立高校 面接内容一覧 |
| 国立・私立・公立高校 現役・浪人別大学合格実績 | 高校マップ | 高校別部活一覧 | |
| グラフで比較!大学合格実績 | 高校マップ |
Copyright c2013 Ichishin Kyouiku Group. All Rights Reserved.