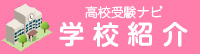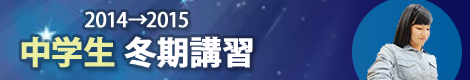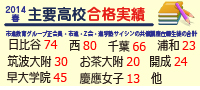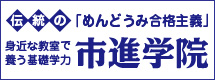埼玉県公立高校入試問題分析
【英語】
| 2014年 | 2013年 | 2012年 | |
|---|---|---|---|
| 1 | リスニング(11問) (選択式・記述式) |
リスニング(11問) (選択式・記述式) |
リスニング(11問) (選択式・記述式) |
| 2 | 長文総合(約160語・4問) 適文補充,書き換え,適語選択,英問英答(記述)。 |
基本構文(4問) 適文補充,適語選択,書き換え,短文の内容把握。 |
基本構文(4問) 適文補充,適語選択,所有格,短文の内容把握。 |
| 3 | 対話文(約440語・7問) 適語・適文補充,整序英作文,内容把握の日本語記述式,内容合致選択,条件英作文など。 |
リスニング(約430語・7問) 適語・適文補充,整序英作文,内容把握の日本語記述式,内容合致選択,条件英作文など。 |
リスニング(約440語・7問) 適語・適文補充,整序英作文,内容把握の日本語記述式,内容合致選択など。 |
| 4 | 長文総合(約510語・8問) 内容把握の選択式(2問),英問英答,日本語記述式,適語補充(4問)。 |
長文総合(約530語・8問) 内容把握の選択式(2問),日本語記述式,英問英答,適語補充(4問)。 |
長文総合(約550語・8問) 内容把握の選択式(2問),日本語記述式,英問英答,適語補充(4問)。 |
| 5 | 条件英作文 指定された2つの言葉を使用して,テーマに沿った内容を5文以上の英文で記述する。 |
条件英作文 指定された2つの語句を使用して,テーマに沿った内容を5文以上の英文で記述する。 |
条件英作文 指定された2つの単語を使用して,テーマに沿った内容を5文以上の英文で記述する。 |
【傾向&アドバイス】
2014年は,前年と同じく大問5題の出題で,リスニング,対話文,長文の総合問題,条件英作文という構成であった。出題内容もほぼ例年と同様である。時間内に余裕をもって解答できるようにするため,時間配分には十分に注意しよう。全体的に記述式の問題が目立ち,コミュニケーション能力をみる傾向が続いている。さらに,直接文法事項を問うのではなく,文脈の前後から考えさせる問題が多いのも特徴である。単語・文法・基本構文などの基礎学力を身につけておくだけでなく,記述式の問題にも対応できるように表現力を養成することが必要である。
1のリスニングは,対話文や英文の内容把握に関する問題が11問出題された。さまざまな場面における英文を聞いて,その状況を把握できる力が求められる。リスニング問題に登場する単語のほとんどは基礎的なものとなっているので,聞き取るときはポイントを絞り,必ずメモをとるようにしたい。
2の長文総合では,短めの英文を読んで,意味の通る英文を完成させる適語選択,形容詞を適切な形に直す問題などが出題された。基本的な文法・語法をよく確認しておこう。
3の対話文は,問題の形式はさまざまであるが,全体的には内容把握に関する設問が中心となっている。正確な文脈把握が要求されるため,会話の流れにも十分注意しながら読み進めるようにしたい。
4の長文も内容把握が中心となっているが,文脈の把握がしっかりできないと正解にたどり着くのが難しい問題が多い。さまざまな英文にふれて長文に慣れておくのはもちろんのこと,普段からていねいな読み取りを心がけ,文章の要点をつかむ訓練をしておくことが重要である。
5は,いくつかの条件に応じた自由記述式の英作文1問の出題。英作文は,簡潔かつ正確にまとめる構成力が要求される。基本的な慣用表現と文法事項を理解したうえで,教科書の基本構文などを用いた英作文の練習をしておくとよいだろう。
【数学】
| 2014年 | 2013年 | 2012年 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 小問集(12問) 文字式,式の値,無理数,二次方程式,連立方程式,二次関数,角度,立体図形など。 |
小問集(12問) 文字式,式の値,無理数,二次方程式,連立方程式,二次関数,整数の性質,立体図形など。 |
小問集(12問) 文字式,式の値,無理数,二次方程式,連立方程式,二次関数,立体図形,角度,方程式など。 |
| 2 | 小問集(4問) 平面図形の面積,作図で一定の条件を満たす点を示す,場合の数,球の体積を求める。 |
小問集(4問) 円の性質と角度,円の中心を作図する,確率,三角すいの体積を求める。 |
小問集(4問) 組合せ,直角二等辺三角形を作図する,平面図形,関数と図形の融合。 |
| 3 | 二次関数と直線(2問) 直線の式を求める,条件を満たす座標を求める。 |
二次関数と直線(2問) 三角形の面積,線分の長さを求める。 |
二次関数と直線(2問) 二次関数の係数,線分の長さを求める。 |
| 4 | 平面図形の応用(3問) 三角形の合同の証明,角度,三角形の面積を求める。 |
平面図形の応用(3問) 三角形の相似の証明,線分の長さ,長方形の面積を求める。 |
平面図形の応用(3問) 二等辺三角形であることの証明,線分の長さ,点の位置。 |
【傾向&アドバイス】
2014年も例年どおり,大問4題の構成となっている。論理的思考力が問われる設問もあり,注意が必要だが,大半は教科書レベルの基本的・標準的な内容からの出題である。図形の問題としてよく出題される三角形と四角形,合同と相似,円の性質などは,基本定理を自在に活用できるよう十分に練習を重ねておきたい。また,作図や証明など,考え方のプロセスを問う出題も定番である。このような傾向は今後も続き,大きな変動はないと考えられる。過去の問題をよく調べておくことはもちろん,よく出される問題や苦手な単元に関しては,問題集などで繰り返し練習をして,出題パターンに慣れておくことが大切である。また,時間配分もあらかじめよく考えておく必要がある。
1は例年どおり,文字式,式の値,無理数,二次方程式,連立方程式などの基本的な設問になっている。広範囲からの出題なので,各分野とも教科書の例題レベルの問題を解けるようにしておく必要がある。また,計算ミスがないように,普段から正確な計算力を養っておくことも不可欠である。
2は円の性質を利用した平面図形に関する問題,円すいからはみ出た球の体積を求める問題などが出題された。いずれも数学的な思考力を問う問題で,基礎知識をいかに使いこなせるかがポイントとなる。出題傾向をつかむため過去問を研究するとともに,多くの類題をこなして解法パターンを身につけておきたい。普段から,考えながら問題を解く姿勢で学習に臨むようにしよう。
3は二次関数と直線の応用問題。特別に難度が高いというわけではないが,条件を整理したうえで解答に臨み,多くの時間を費やさないように時間配分にも注意したい。問題の形式に慣れるために類題を数多くこなしておくとよいだろう。二次関数と直線の問題は例年出題されているので,苦手意識を持たないように十分な対策をしておきたい。
4は折り返し図形の応用問題が3問出題された。2つの三角形が合同であることを証明する問題,途中式や文章,図による説明を示しながら角度の大きさを求める問題,一定の条件を満たす三角形の面積を求める問題で構成されている。証明問題は毎年出題されているので,標準的な問題集や過去問を繰り返し解いて,証明問題に慣れておくとともに,基本的な定理は使いこなせるよう十分に練習しておこう。
【国語】
| 2014年 | 2013年 | 2012年 |
|---|---|---|
| 1 小説文(5問) 出典は堀米薫『林業少年』。家業の林業を継ぐと期待されている少年が初めて百年杉伐採に立ち会う場面の心情を描く。心情把握(2問),記述(2問),内容把握。 |
1 小説文(5問) 出典は水野次郎『ツバサの自由研究』。海女になりたいと思う中学2年生の女子生徒とその家族の心情の変化を描く。心情把握(2問),記述(2問),内容把握。 |
1 小説文(6問) 出典はまはら三桃『鉄のしぶきがはねる』。旋盤を使ってものづくりにはげむ工業高校の女子生徒の心情の変化を描く。内容把握(2問),記述(2問),内容一致。 |
| 2 漢字・語句・文法(9問) 漢字の読み・書き取り(5問),文法,熟語,語句。 |
2 漢字・語句(9問) 漢字の読み・書き取り(5問),熟語,文法,四字熟語。 |
2 漢字・語句(9問) 漢字の読み・書き取り(5問),四字熟語,敬語,文法など。 |
| 3 説明文(5問) 出典は藤田正勝『哲学のヒント』。言葉と経験の隔たりやそれを越える「ふくらみ」の考察。内容把握(2問),記述(2問),内容一致。 |
3 説明文(5問) 出典は福岡伸一『動的平衡2』。ゼロテクノロジーの意味と課題について説明する。内容把握(2問),記述(2問),内容一致。 |
3 説明文(5問) 出典は岸田一隆『科学コミュニケーション』。人間の脳とコンピュータの違いを説明する。内容把握(2問),記述(2問),内容一致。 |
| 4 古文(4問) 出典は『俊頼髄脳』。和歌の効用を記述。主語把握,現代かなづかい,内容把握。 |
4 古文(4問) 出典は『十訓抄』。平清盛の人柄を考察する。現代かなづかい,記述,指示語,内容把握。 |
4 古文(4問) 出典は『平家物語』。内容把握(2問),漢文の返り点,現代かなづかい。 |
| 5 課題作文 「働く理由」についての調査結果と自分の体験をもとに「働くこと」について自分なりの考えをまとめる。 |
5 課題作文 3種類の中から自分が参加しようと考えるボランティア活動を1つ選び,自分の体験をふまえて意見や考えをまとめる。 |
5 課題作文 日常生活の中で言葉の使い方はどうあるべきかという質問に対する4つの意見を見て,自分の意見や考えをまとめる。 |
【傾向&アドバイス】
2014年は前年と同様に大問5題の構成で,出題傾向にも目立った変更はなかった。読解問題は例年同様に比較的読みやすい文章であるため,普段から学校の授業を大切にしていれば十分に対応できる内容になっている。課題作文をはじめとする記述問題の時間配分にも注意しながら,得意分野から取りかかるようにする とよい。
1の小説文は,登場人物の心情理解と内容把握を問う設問が中心となっている。文章自体は読みやすいので,場面・情景を正確にとらえ,主人公の気持ちを考えながら読み進めていこう。
2は知識問題の出題。漢字は,「厳密」「管轄」「潜む」の読み,「評論」「額」の書き取りが出題された。ほかに,文法,熟語,語句などの構成となっている。いずれも基本事項が中心なので,確実に得点したい。教科書レベルの学習をしっかりしておくことが大切である。
3の説明文は,文章はさほど難しくないが,長文に慣れるため普段から読書を習慣づけておくことが望ましい。読解問題の文章の内容と設問との関係についても,十分考えながら読み進めていくことがポイントとなる。
4の古文は引用文が短く,重要部分には口語訳がついているので,難度はそれほど高くない。古文と口語訳を照らしあわせて読み進めていけば,全体の内容は比較的容易に把握できるだろう。なお,年度によっては一部に漢文の問題も出題されることがあるため,注意が必要である。教科書や問題集などを活用して,古文・漢文の読解に慣れておくとよい。
5の課題作文は配点が高いので十分な対策が必要である。2014年は,「働く理由」についての調査結果と自分の経験をふまえて「働くこと」について自分なりの考えをまとめるという出題であった。指定内の字数にまとめることはもちろん,原稿用紙の使い方を理解していることが前提となるので,減点対象とならないように注意が必要である。
【理科】
| 2014年 | 2013年 | 2012年 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 小問集(8問) 地震,太陽の黒点,光合成,細胞分裂,融点と沸点,質量保存の法則,弦の長さが同じ場合の波長,陰極線と電子。 |
小問集(8問) 新生代の示準化石,乾湿計と湿度,受粉と精細胞,生産者,電離,化学反応式のモデル,静電気,屈折角。 |
小問集(8問) しゅう曲,星の動き,植物細胞のつくり,アミノ酸,単体の物質と原子記号,蒸留,凸レンズを通した見え方,対流。 |
| 2 | 地層(6問) 堆積岩の特徴と区別のしかた,柱状図の読み取りと作成,地層の傾き,火山の噴火を示す地層。 |
天体の運動(6問) 新月,水星,太陽系の惑星,金星の見える時間帯と方角,金星の満ち欠け。 |
気象(5問) 天気図記号,露点と水蒸気量,小笠原気団とその性質,天気図と気象衛星による雲画像。 |
| 3 | 消化と吸収(7問) だ液のはたらき,消化酵素,小腸のしくみとはたらき,肝臓,胆汁のはたらき。 |
生物の観察(6問) 軟体動物,外骨格,卵の表面のつくり,前あしの特徴,イヌの前あしの骨格,進化。 |
植物の観察(7問) 顕微鏡の使い方,胞子,ゼニゴケのからだのつくり,コケ植物の特徴,植物の分類と特徴など。 |
| 4 | 化学変化とイオン(6問) 化学式とイオン式,塩化銅水溶液の電気分解,酸の性質とリトマス紙の変化など。 |
化学変化と密度(7問) 二酸化炭素の発生,プラスチックの種類と密度,メスシリンダーの目盛りの読み取りなど。 |
水溶液(6問) 砂糖の溶ける様子,水溶液の質量パーセント濃度,溶け残った物質,結晶の質量。 |
| 5 | 運動とエネルギー(6問) 台車の斜面上の運動,位置エネルギーと運動エネルギー,台車を引く力,台車の速さなど。 |
仕事と力(6問) 2つの力の関係,フックの法則,合力の大きさ,仕事の大きさ,ひもを引く力の大きさなど。 |
回路と電流(6問) グラフ作成,電圧と電流の大きさの関係,電熱線の抵抗の大きさ,直列回路と並列回路など。 |
【傾向&アドバイス】
2014年も例年どおり大問5題の構成で,小問集・地学・生物・化学・物理各1題の構成であった。基礎・基本を問うものが多いため,教科書の内容を理解していれば対応できる。ただし,実験・観察とからめた記述式の問題が多いため,単に知識をつめこむだけの学習では,納得のいく解答ができないだろう。実験・観察を体系的に理解し,結果をもとに考察する思考力を養っておくことが必要である。解法パターンを身につけるために,標準レベルの問題を数多くこなしておこう。
1の小問集は,各分野からの出題で基礎知識を問う。各設問とも教科書レベルの内容なので,確実に得点したい。
2の地学の問題では,地層に関する設問が出題された。基礎知識を問うだけでなく,考察力や理解力も見る構成となっている。柱状図の作図が出題されたが,正確に図を読み取って作成することが必要である。
3の生物の問題では,食物の消化や消化器官のはたらきに関する設問が出題された。設問自体は基礎知識を問う構成となっているので,確実に得点したい。重要な用語については,教科書や資料集でしっかりと復習しておくことが大切である。
4の化学の問題では,化学変化とイオンに関係する設問が出題された。教科書や問題集などでおもな化合や分解の化学反応式を確認しておくとよいだろう。設問内容は基礎力重視であるが,正確な知識が求められている。また,記述問題については,要点をおさえて的確に解答する練習を積ねておきたい。
5の物理の問題では,運動とエネルギーについての実験から出題された。重要事項の確認はもちろんのこと,例年出題されている計算問題の対策も不可欠である。また,実験の手順が多いので,題意を正確に把握する力も必要とされる。類題で繰り返し練習して慣れておこう。
【社会】
| 2014年 | 2013年 | 2012年 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 地理総合(4問) 大西洋,小麦の自給率や輸出量の読み取り,日本とニュージーランドの農業の比較など。 |
地理総合(4問) 大西洋,札幌と比較したロンドンの冬の気候,中国との貿易,4か国の統計の読み取り。 |
地理総合(4問) ユーラシア大陸,正距方位図法の読み取り,乾燥帯の特色と住居,4か国の統計の読み取り。 |
| 2 | 日本地理(5問) 3都市の気温と降水量,リアス式海岸,輸出・入の資料の読み取り,地形図の読み取りなど。 |
日本地理(5問) 岐阜県の位置,気温と降水量のグラフ,4県の統計の読み取り,地形図の読み取りなど。 |
日本地理(5問) 3都市の日の入りの時刻,佐賀県の位置,5県の統計の読み取り,地形図の読み取りなど。 |
| 3 | 歴史―古代~近世(5問) 大陸の位置関係,ロシアの属する州,標高,遊牧民の暮らす地域,産業別就業人口の割合統計。 |
歴史―古代~近世(5問) 時差,ラクダのキャラバン,オーストラリア大陸を通る経線,原油の生産国,タイの貿易統計。 |
歴史―古代~近世(5問) 口分田,天平文化,平清盛と日宋貿易,鎌倉幕府の特色,参勤交代と大名への影響。 |
| 4 | 歴史―近・現代(5問) 日米修好通商条約,選挙権の歴史,産業の発展,明治終盤~太平洋戦争前までの社会や経済,アメリカに関連する日本の外交について。 |
歴史―近・現代(5問) 幕末における貿易の状況,明治時代前半の社会や文学,憲政の常道,サンフランシスコ平和条約と日米安全保障条約,近現代のできごと。 |
歴史―近・現代(4問) 地租改正反対一揆による制度変更,日清戦争と立憲政友会の結成,明治後半~大正期の対外関係,農地改革と地主・小作関係の変化。 |
| 5 | 公民―政治経済(7問) 基本的人権,内閣が成立するまで,三権分立,地方自治のしくみ,消費者の権利,企業の海外進出,南南問題。 |
公民―政治経済(8問) 国会の権限,連立政権と与党,議院内閣制,裁判員制度,日本銀行の公開市場操作,UNESCO,京都議定書など。 |
公民―政治経済(7問) 統計の読み取り,日本の政治制度,為替相場と貿易,寡占化と消費者の不利益,公共料金,国連の総会,拒否権。 |
| 6 | 地理・歴史・公民総合(5問) 日本の都道府県,国務大臣,承久の乱,空海,埼玉県の伝統的工芸品と文化財の保護。 |
地理・歴史・公民総合(5問) 豊臣秀吉,廃藩置県,国庫支出金,高速道路のインターチェンジ開設と産業への影響,条例。 |
地理・歴史・公民総合(5問) 化政文化,ペリーとアメリカ,高度経済成長期の日本,地方自治,近郊農業の特色。 |
【傾向&アドバイス】
2014年も例年どおり大問6題の構成であった。3分野とも,基本的な知識や理解力をみる問題であるが,図やグラフ・統計などの資料をからめた設問が多く,用語と年代の暗記だけでは対応できない。普段から地図帳や資料集などを活用した学習を心がけよう。また,記述式の設問がかなり多く出題されている。資料を読み取り,時間内に適切に解答をまとめる練習もしておきたい。
12の地理分野では,統計や地図を正確に読み取って答えさせる問題が多く出題されている。総合的な理解力が要求されるので,教科書の基本事項の確認はもとより,地図帳や資料集にも目を通しておきたい。
34の歴史分野は,出題範囲が古代から現代までと幅広くなっている。教科書や年表などで,各時代の特徴やできごとの前後関係を把握しながら,歴史の流れを理解しておこう。
5の公民分野は,政治・経済分野からの幅広い出題だが,基礎的な内容を問うものが中心である。教科書などで重要な用語をよく確認しておきたい。
6の3分野総合では,与えられた文章や統計をもとに,基礎知識と結びつけて解答する能力が必要となる。政治に関する時事問題が出題されることもあるので,普段からテレビや新聞でニュースをチェックし,社会のさまざまなできごとに問題意識をもって考えていく習慣をつけておきたい。
| 高校入試情報 市進受験情報ナビ | ■高校入試 偏差値・内申一覧 | ■高校入試 時期別ポイント | ■勉強方法と受験作戦 |
|---|---|---|---|
| 東京都立高校 偏差値 | 夏の学習法 | 先輩たちの合格体験 | |
| 東京都立高校 内申のめやす | 秋の学習法 | 併願作戦を立てよう | |
| ■2015年高校入試情報 | 神奈川県公立高校 | 冬の学習法 | 都県別 入試の実態 |
| 国立・私立高校 | 埼玉県公立高校 | 高校入試速報 | |
| 東京都立高校 | 千葉県公立高校 | 新年度特集 | |
| 神奈川県公立高校 | 茨城県立高校 | ||
| 埼玉県公立高校 | 国立・私立高校 | ■公立高校について詳しく知ろう | ■国立・私立高校について知ろう |
| 千葉県公立高校 | 偏差値ってなんだろう | 公立高校入試システム | 学校別入試結果分析 |
| 茨城県立高校 | 偏差値を上げるには | 公立高校入試問題分析 | 倍率や難易度が変わるしくみ |
| 学力検査の平均点 | 合格最低点 | ||
| 過去3年間の倍率推移 | 学費一覧と就学支援金・補助金 | ||
| ■学校説明会レポート | ■大学入試合格実績 | 高校別部活一覧 | 私立高校 面接内容一覧 |
| 国立・私立・公立高校 現役・浪人別大学合格実績 | 高校マップ | 高校別部活一覧 | |
| グラフで比較!大学合格実績 | 高校マップ |
Copyright c2013 Ichishin Kyouiku Group. All Rights Reserved.