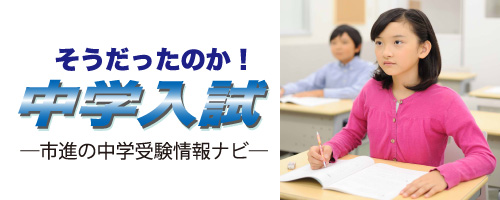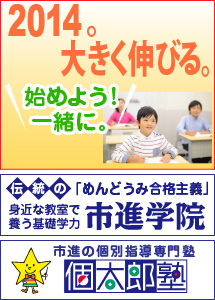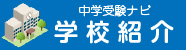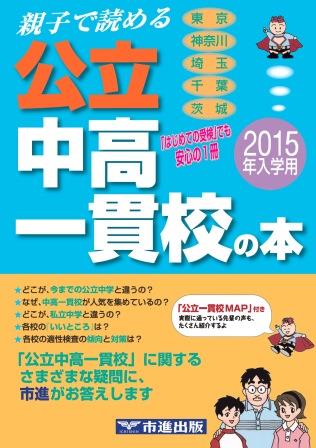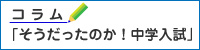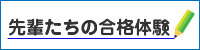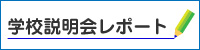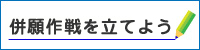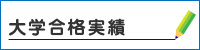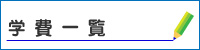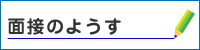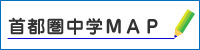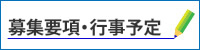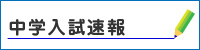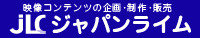トップページ > コラム「そうだったのか!中学入試」第31~40話 > 第39話「2013年中学入試予想第3弾 ――10月公開模試から入試動向を読む――(つづき)」
第39話「2013年中学入試予想第3弾 ――10月公開模試から入試動向を読む――(つづき)」
2012年12月3日
(5)注目される中堅校の志望動向
① 男子校

攻玉社 攻玉社(目黒区)は7月模試から10月模試にかけて志望者数が増えてきています。定員を80→100名と増員する1回が13%減→1%増、定員を90→70に減員する2回も9%減→5%減と増加しています。定員増の1回がようやく前年並みになってきたのは、後述の世田谷学園との競合によるものと思われます。
その世田谷学園(世田谷区)は第一志望者が多い1回が16%増で上位層が激増して受験者層がワンランク上の層と入れ替わっています。駒場東邦や芝などの上位校併願者中心の2回は2%減、3回は5%増です。1回の入試レベルの上昇は確実で厳しい入試になりそうです。
城北(板橋区)は1回が3%増ですが、2回は14%減、3回は2%減と志望者数では前年と大きく変わってはいませんが、学校に対する評価が上がっているのか、第一志望者が多い1回で上位層が厚くなってきていますから、ボーダーラインが上昇する可能性が高いでしょう。
高輪(港区)は中堅上位の受験生が世田谷学園1回、城北1回に回っているのか2月1日のAが19%減で上位層も大きく減っています。逆に2日のBは世田谷学園、城北の併願校になっているようで13%増で上位層も増えています。
都内の全私立中で2年連続応募者総数が最多だった東京都市大付(世田谷区)は1回の志望者が7%増ですが、さすがに急激な応募者増の反動か2回は4%減です。コース制の導入によって午後入試の1回は上位校との併願者を広範囲に集めているようです。

芝浦工大 東大合格者1名を出した芝浦工大(板橋区)は3回の入試中2回で志望者が増えています。1回が26%増、3回は14%増で、2回のみ3%減です。理工系大学の付属校のため理系のイメージが強かった学校ですが、理数系教育はもちろんのこと、英語を中心とする言語教育にも力を入れていて、他大学進学にも成果を挙げてきているのが評価されているのでしょうか。前年に続き倍率アップの可能性が高そうです。
② 女子校

大妻多摩 大妻多摩(多摩市)は2月1日に新設の午後入試で模試の志望者が500名を超えています。午前の1回も50→40名と定員減にもかかわらず2%増、2回も8%増です。これは午後入試の導入が起爆剤になっていることは間違いありませんが、今春の国公立大の実績が伸びて学校の評価が上がっていることが背景にあると思われます。ここ数年入試状況が緩和してきていましたが、このままいけばボーダーが上昇する可能性大です。
東京女学館(渋谷区)も国際学級に加え、一般クラスでも午後入試を新設します。10月模試の午後入試(2回)の志望者数は600名に近く予想をはるかに超える規模になりそうです。しかし70→60名と定員減の1回は志望者が25%減、60→40名と減員の3回は35%の大幅な減少となっていて、志望者が午後入試の2回に集中していることが見て取れます。
都心の伝統校山脇学園(港区)は「山脇ルネサンス」と称する学校改革が進行中で、新校舎の建設も始まり大きく学校が変わろうとしています。すでに大学進学で難関国公立大の実績が出始めていて注目を集めているようで、10月模試ではAが39%増、Bは29%増、Cは15%増と都内の中堅女子校では例外的にすべての回で志望者が大幅に増えています。

三輪田学園 都心の中堅女子校としては山脇学園とならんで増加傾向が顕著なのが三輪田学園(千代田区)です。85→80名と定員減の1回が4%増、55→60名に定員増の2回は9%増、3回は6%増です。地味ながら教育内容の充実ぶりがしっかりと伝わってきて、学校の評価が上がっているものと思われます。
麹町学園女子(千代田区)はこのレベルでは数少ない完全中高一貫校です。学校所在地周辺の受験生がほとんどいない都心部の中堅女子校は、生徒募集で苦戦していますが、この学校は5回の入試のうち3回で志望者が増えています。特に1回の午前は45→50名と定員増もあってか10%増、2回午後の特待入試は6%増です。
捜真女学校(横浜市神奈川区)は今春入試から第一志望層を対象に基本的な出題のS入試を新設しましたが、このS入試がさらに人気を集めているようで、なんと志望者数が78%増です。ただしAは17%減、Bは13%減となっています。
今春入試で大きく受験者数を回復した横浜女学院(横浜市中区)は30→40名と定員増のAが35%増、55→45名と定員減のBも20%増などすべての回で増えていて、一時共学校に押されていましたが、完全に勢いが戻っています。
今春午後入試を導入した聖園女学院(藤沢市)は午後入試の3次を30→35名と定員増しますが志望者数も20%増、さらに入試日を4日から3日に変更の4次も30%増です。
新校舎が完成し、東大や早慶上智大の実績を伸ばした千葉の国府台女子学院(市川市)の1回は1%増ですが、2回は9%増と県内の多くの学校が志望者を減らしている中での増加基調で注目されます。
③ 共学校
穎明館(八王子市)は新制服を採用したためか、今春の入試で急上昇した女子の人気がまだ続いています。志望状況には7月から9月、10月にかけて相当な変化が見られ、1回は男子が15%減→13%減→1%減と増えてきていますが、女子は19%増→47%増→13%増と大きく上下。2回は男子が9%減→20%増→11%増ですが、女子は40%増→15%増→71%増と1回とは逆パターンで上下。以上から女子の志望者が1回と2回のあいだで揺れ動いている状況が見て取れます。1回~3回の合計では男子が2%の微増ですが、女子は32%の大幅増です。
桜美林(町田市)は今春難関大学合格実績が伸びて人気が上がっていますが、男女で志望動向に違いが見られます。男子は1回午後が6%減ですが、上位校との併願者が増えて、下位層は大きく減っています。女子は第一志望者中心の1回午前が2%減ですが、上位層が厚くなっています。上位校との併願者が多い1回午後は大妻多摩の午後入試導入の影響を受けているものと思われ、16%減となっています。
国学院久我山(杉並区)は早慶上智大の実績を伸ばし、午後入試のSTの男子1回が23%増、2回が14%増、午前入試の一般2回が17%増と相当な増加で、特にSTの2回は上位層が大幅に増加しています。しかし女子の志望者数はSTの1回が4%増、2回は13%増ですが、一般では1回が6%減、2回は10%減で上位層も大きく減っています。

淑徳 淑徳(板橋区)は5回の入試すべてで志望者が増加しています。スーパー特進は1回が23%増、2回は25%増、3回は7%増、東大選抜の1回は6%増ですが、2回は43%の大幅増です。特に女子はスーパー特進2回が42%増、3回は32%増、東大2回が51%増と増加幅が大きくなっています。
2014年に新校舎が完成する青稜(品川区)は国公立大や早慶上智大の合格実績が伸びたためか人気を回復しているようです。7月から10月にかけて志望状況が大きく変わっていて、午後入試の男子1回Bが16%減→9%増に、2回Bは22%増→37%増に、女子の1回Bは15%減→4%減で、2回Bが12%減→29%増と大幅に増加し上位層も増えています。結局5回の入試の男女合計で減っているのは2回Aの5%減だけで、1回Aが13%増、1回Bは6%増、2回Bは34%の大幅増、3回は10%増です。増えているのは、主に競合している広尾学園の中下位層や東京都市大等々力から回ってきているものと思われます。特に東京都市大等々力は青稜と入試レベルも近い上に受験生のエリアもほとんど重なっていますから、今後も両校の綱引きは注視していく必要がありそうです。
帝京大学(八王子市)の注目される初の午後入試導入(3回)は午前入試だった前年に比べ男子が50%増で、女子はさらに大きく72%の増加です。ただし1回女子を除く他の回はむしろ減り気味で、上位校との併願層が3回の午後入試に集中しているようです。
東京都市大等々力(世田谷区)は共学化以来の右肩上がりの応募者増とレベルアップで敬遠されて志望者増加に歯止めがかかってきました。特進1回は男子が2%減、女子は1%減、2回は男子が50%増、女子は17%増で、午後入試の特選は1回の男子が8%増、女子は15%増、2回は男子が14%減、女子は28%減です。しかし減っているのは中位以下の層で受験者層の学力レベルは上がっていますからボーダーラインの低下は望めません。倍率が下がっても難易度アップの可能性もあり注意が必要です。
東京農大一(世田谷区)は今春卒業した一貫2期生が難関国公立大や早慶上智大の合格実績を大きく伸ばしました。そのためか男子の志望者増が目立ちます。午後入試の1回は男子が13%増、女子は27%減、2回は男子が6%増で女子は3%増、3回は男子が18%増、女子は12%減です。男子は3回とも受験者層が大きく上昇しています。
広尾学園(港区)の志望者増加は続いていますが7月、9月、10月と模試の回を追うごとに減ってきています。1回は男子が30%増ですが、女子は5%減、午後入試の2回は男子が20%増、女子は10%増、同じく午後の医進・サイエンスは男子が8%増、女子は40%増、3回は男子が18%増、女子は80%増です。しかし7月以降に減っているのはあきらかに中下位層で、志望者の学力レベルは男女ともすべての回で大きく上昇しています。難易度はむしろ上昇する可能性を考えておいた方が良さそうです。
大学合格実績が飛躍的に伸びて大人気の湘南学園は第35話でも触れたように男女ともすべての入試回で志望者数が増えていますが、10月模試ではさらに増えて、男女合わせてAが56%増、Bは60%増、Cが58%増、Dは50%増で、なんと4回の入試ともに50%以上の増加となっています。
早慶上智大の合格実績を大きく伸ばしたにもかかわらず7月模試では志望者が大きく減っていた桐光学園(川崎市麻生区)は、10月になってだいぶ志望者数を回復してきています。1回の男子は23%減→11%減、2回は28%減→9%減、3回は10%減→20%減、女子は1回が大幅増で12%減→37%増、逆に2回は大幅減で10%増→25%減、3回のみ16%減のままで変わっていません。男子は3回が減っていますが1回・2回は減少幅を縮め、女子は2回から1回に志望者が移動しています。
東大など難関国公立大の実績が上がっている神奈川大附(横浜市緑区)は、中大横浜が市営地下鉄グリーンライン沿線のセンター北に移転してきて受験生のエリアがもろに競合しますが、男女合わせた10月の志望者数で、2月6日と遅い入試日のCは12%減ですが、Aが4%増、Bは2%増とわずかながらも増えています。中大横浜との併願者は当然多くなると思われますが、神奈川大付の方が志望順位の高い受験生がほとんどと思われます。

西武学園文理 西武学園文理(狭山市)は県内西部では共学の進学校として人気の高い学校です。中学を開校して20年目の新しい学校ですがここ数年は後発の栄東と開智の勢いに押されていました。しかし10月模試では2回以降の志望者数で盛り返していて、1月10日の1回は栄東Aと入試日が重複するため18%減、特選は25%減ですが、13日の2回は51%増、特選も4%増、18日の3回は23%増、特選は94%増です。
(6)国立大附属中学校・公立中高一貫校の志望動向
まず国立大附属中学校から見ていきます。以下は模試志望者の前年比(%)で、Mは男子、Fは女子です。(模試データのある学校のみ)
東京学芸大小金井(小金井市)の志望者増は今春入試で緩和した入試だった反動でしょう。なお同校は2015年より4科目入試になります。
東京学芸大世田谷(世田谷区)の男子は志望者微減ですが、ボーダーのあたりが厚くなっていて難易度がアップする可能性があり要注意です。
横浜国立大附横浜(横浜市南区)と横浜国立大附鎌倉(鎌倉市)の両校は10月に入って2月2日から2月3日への入試日の変更を発表しました。10月までの模試の志望者数はこの変更をまったく反映していないため上記のデータには入れていません。前年までは2日に横浜国大附横浜か鎌倉を受験し3日は東京学芸大世田谷や県立相模原、横浜市立南などを併願する受験生が多かったのでこの影響がどうなるか、11月以降の模試の志望動向を注視する必要があります。
最後に公立中高一貫校です。

桜修館 東京ではなんといっても1期生がすばらしい大学合格実績を出した桜修館(目黒区)の志望者増が注目されます。同じく1期生が卒業した両国(墨田区)もやや志望者増ですが、入学レベルが最も高いわりには1期生の実績がいまひとつだった小石川(文京区)はやや志望者が減っています。九段(千代田区)は今までの卒業生は設立時に母体校(都立九段高校、区立九段中学)から編入学した生徒でした。適性検査を受検して入学した生徒は今春の卒業生が最初の学年です。いろいろ途中で問題があった学年で進路結果は必ずしも良かったとは言えませんが、問題は大きく改善されており現在は受検生から高い評価を受けているようで特に男子は21%増で、小石川からの流れもありそうです。
神奈川では横浜市立南(横浜市南区)の志望者増、とりわけ女子の志望者が90%増と激増しているのが注目の的です。前述のように横浜国大附の2校との入試日重複は模試実施日との関係で志望者数に反映されていませんが、これによる減少はわずかと予想されます。大変な勢いがあり学力上位の受検生も大幅に増えていて、フェリス女学院や慶応湘南藤沢などの私立上位校への影響もありそうです。
なお埼玉県立伊奈学園(北足立郡伊奈町)は全国の公立中高一貫校の入学者決定で唯一実施されていた1次の抽選を廃止します。模試データが不完全なため具体的な数字で示すことはできませんが、応募者の増加とともに受検準備をしっかりしてきた層が増えてボーダーラインの上昇が予想されます。
① 男子校

攻玉社 攻玉社(目黒区)は7月模試から10月模試にかけて志望者数が増えてきています。定員を80→100名と増員する1回が13%減→1%増、定員を90→70に減員する2回も9%減→5%減と増加しています。定員増の1回がようやく前年並みになってきたのは、後述の世田谷学園との競合によるものと思われます。
その世田谷学園(世田谷区)は第一志望者が多い1回が16%増で上位層が激増して受験者層がワンランク上の層と入れ替わっています。駒場東邦や芝などの上位校併願者中心の2回は2%減、3回は5%増です。1回の入試レベルの上昇は確実で厳しい入試になりそうです。
城北(板橋区)は1回が3%増ですが、2回は14%減、3回は2%減と志望者数では前年と大きく変わってはいませんが、学校に対する評価が上がっているのか、第一志望者が多い1回で上位層が厚くなってきていますから、ボーダーラインが上昇する可能性が高いでしょう。
高輪(港区)は中堅上位の受験生が世田谷学園1回、城北1回に回っているのか2月1日のAが19%減で上位層も大きく減っています。逆に2日のBは世田谷学園、城北の併願校になっているようで13%増で上位層も増えています。
都内の全私立中で2年連続応募者総数が最多だった東京都市大付(世田谷区)は1回の志望者が7%増ですが、さすがに急激な応募者増の反動か2回は4%減です。コース制の導入によって午後入試の1回は上位校との併願者を広範囲に集めているようです。

芝浦工大 東大合格者1名を出した芝浦工大(板橋区)は3回の入試中2回で志望者が増えています。1回が26%増、3回は14%増で、2回のみ3%減です。理工系大学の付属校のため理系のイメージが強かった学校ですが、理数系教育はもちろんのこと、英語を中心とする言語教育にも力を入れていて、他大学進学にも成果を挙げてきているのが評価されているのでしょうか。前年に続き倍率アップの可能性が高そうです。
② 女子校

大妻多摩 大妻多摩(多摩市)は2月1日に新設の午後入試で模試の志望者が500名を超えています。午前の1回も50→40名と定員減にもかかわらず2%増、2回も8%増です。これは午後入試の導入が起爆剤になっていることは間違いありませんが、今春の国公立大の実績が伸びて学校の評価が上がっていることが背景にあると思われます。ここ数年入試状況が緩和してきていましたが、このままいけばボーダーが上昇する可能性大です。
東京女学館(渋谷区)も国際学級に加え、一般クラスでも午後入試を新設します。10月模試の午後入試(2回)の志望者数は600名に近く予想をはるかに超える規模になりそうです。しかし70→60名と定員減の1回は志望者が25%減、60→40名と減員の3回は35%の大幅な減少となっていて、志望者が午後入試の2回に集中していることが見て取れます。
都心の伝統校山脇学園(港区)は「山脇ルネサンス」と称する学校改革が進行中で、新校舎の建設も始まり大きく学校が変わろうとしています。すでに大学進学で難関国公立大の実績が出始めていて注目を集めているようで、10月模試ではAが39%増、Bは29%増、Cは15%増と都内の中堅女子校では例外的にすべての回で志望者が大幅に増えています。

三輪田学園 都心の中堅女子校としては山脇学園とならんで増加傾向が顕著なのが三輪田学園(千代田区)です。85→80名と定員減の1回が4%増、55→60名に定員増の2回は9%増、3回は6%増です。地味ながら教育内容の充実ぶりがしっかりと伝わってきて、学校の評価が上がっているものと思われます。
麹町学園女子(千代田区)はこのレベルでは数少ない完全中高一貫校です。学校所在地周辺の受験生がほとんどいない都心部の中堅女子校は、生徒募集で苦戦していますが、この学校は5回の入試のうち3回で志望者が増えています。特に1回の午前は45→50名と定員増もあってか10%増、2回午後の特待入試は6%増です。
捜真女学校(横浜市神奈川区)は今春入試から第一志望層を対象に基本的な出題のS入試を新設しましたが、このS入試がさらに人気を集めているようで、なんと志望者数が78%増です。ただしAは17%減、Bは13%減となっています。
今春入試で大きく受験者数を回復した横浜女学院(横浜市中区)は30→40名と定員増のAが35%増、55→45名と定員減のBも20%増などすべての回で増えていて、一時共学校に押されていましたが、完全に勢いが戻っています。
今春午後入試を導入した聖園女学院(藤沢市)は午後入試の3次を30→35名と定員増しますが志望者数も20%増、さらに入試日を4日から3日に変更の4次も30%増です。
新校舎が完成し、東大や早慶上智大の実績を伸ばした千葉の国府台女子学院(市川市)の1回は1%増ですが、2回は9%増と県内の多くの学校が志望者を減らしている中での増加基調で注目されます。
③ 共学校
穎明館(八王子市)は新制服を採用したためか、今春の入試で急上昇した女子の人気がまだ続いています。志望状況には7月から9月、10月にかけて相当な変化が見られ、1回は男子が15%減→13%減→1%減と増えてきていますが、女子は19%増→47%増→13%増と大きく上下。2回は男子が9%減→20%増→11%増ですが、女子は40%増→15%増→71%増と1回とは逆パターンで上下。以上から女子の志望者が1回と2回のあいだで揺れ動いている状況が見て取れます。1回~3回の合計では男子が2%の微増ですが、女子は32%の大幅増です。
桜美林(町田市)は今春難関大学合格実績が伸びて人気が上がっていますが、男女で志望動向に違いが見られます。男子は1回午後が6%減ですが、上位校との併願者が増えて、下位層は大きく減っています。女子は第一志望者中心の1回午前が2%減ですが、上位層が厚くなっています。上位校との併願者が多い1回午後は大妻多摩の午後入試導入の影響を受けているものと思われ、16%減となっています。
国学院久我山(杉並区)は早慶上智大の実績を伸ばし、午後入試のSTの男子1回が23%増、2回が14%増、午前入試の一般2回が17%増と相当な増加で、特にSTの2回は上位層が大幅に増加しています。しかし女子の志望者数はSTの1回が4%増、2回は13%増ですが、一般では1回が6%減、2回は10%減で上位層も大きく減っています。

淑徳 淑徳(板橋区)は5回の入試すべてで志望者が増加しています。スーパー特進は1回が23%増、2回は25%増、3回は7%増、東大選抜の1回は6%増ですが、2回は43%の大幅増です。特に女子はスーパー特進2回が42%増、3回は32%増、東大2回が51%増と増加幅が大きくなっています。
2014年に新校舎が完成する青稜(品川区)は国公立大や早慶上智大の合格実績が伸びたためか人気を回復しているようです。7月から10月にかけて志望状況が大きく変わっていて、午後入試の男子1回Bが16%減→9%増に、2回Bは22%増→37%増に、女子の1回Bは15%減→4%減で、2回Bが12%減→29%増と大幅に増加し上位層も増えています。結局5回の入試の男女合計で減っているのは2回Aの5%減だけで、1回Aが13%増、1回Bは6%増、2回Bは34%の大幅増、3回は10%増です。増えているのは、主に競合している広尾学園の中下位層や東京都市大等々力から回ってきているものと思われます。特に東京都市大等々力は青稜と入試レベルも近い上に受験生のエリアもほとんど重なっていますから、今後も両校の綱引きは注視していく必要がありそうです。
帝京大学(八王子市)の注目される初の午後入試導入(3回)は午前入試だった前年に比べ男子が50%増で、女子はさらに大きく72%の増加です。ただし1回女子を除く他の回はむしろ減り気味で、上位校との併願層が3回の午後入試に集中しているようです。
東京都市大等々力(世田谷区)は共学化以来の右肩上がりの応募者増とレベルアップで敬遠されて志望者増加に歯止めがかかってきました。特進1回は男子が2%減、女子は1%減、2回は男子が50%増、女子は17%増で、午後入試の特選は1回の男子が8%増、女子は15%増、2回は男子が14%減、女子は28%減です。しかし減っているのは中位以下の層で受験者層の学力レベルは上がっていますからボーダーラインの低下は望めません。倍率が下がっても難易度アップの可能性もあり注意が必要です。
東京農大一(世田谷区)は今春卒業した一貫2期生が難関国公立大や早慶上智大の合格実績を大きく伸ばしました。そのためか男子の志望者増が目立ちます。午後入試の1回は男子が13%増、女子は27%減、2回は男子が6%増で女子は3%増、3回は男子が18%増、女子は12%減です。男子は3回とも受験者層が大きく上昇しています。
広尾学園(港区)の志望者増加は続いていますが7月、9月、10月と模試の回を追うごとに減ってきています。1回は男子が30%増ですが、女子は5%減、午後入試の2回は男子が20%増、女子は10%増、同じく午後の医進・サイエンスは男子が8%増、女子は40%増、3回は男子が18%増、女子は80%増です。しかし7月以降に減っているのはあきらかに中下位層で、志望者の学力レベルは男女ともすべての回で大きく上昇しています。難易度はむしろ上昇する可能性を考えておいた方が良さそうです。
大学合格実績が飛躍的に伸びて大人気の湘南学園は第35話でも触れたように男女ともすべての入試回で志望者数が増えていますが、10月模試ではさらに増えて、男女合わせてAが56%増、Bは60%増、Cが58%増、Dは50%増で、なんと4回の入試ともに50%以上の増加となっています。
早慶上智大の合格実績を大きく伸ばしたにもかかわらず7月模試では志望者が大きく減っていた桐光学園(川崎市麻生区)は、10月になってだいぶ志望者数を回復してきています。1回の男子は23%減→11%減、2回は28%減→9%減、3回は10%減→20%減、女子は1回が大幅増で12%減→37%増、逆に2回は大幅減で10%増→25%減、3回のみ16%減のままで変わっていません。男子は3回が減っていますが1回・2回は減少幅を縮め、女子は2回から1回に志望者が移動しています。
東大など難関国公立大の実績が上がっている神奈川大附(横浜市緑区)は、中大横浜が市営地下鉄グリーンライン沿線のセンター北に移転してきて受験生のエリアがもろに競合しますが、男女合わせた10月の志望者数で、2月6日と遅い入試日のCは12%減ですが、Aが4%増、Bは2%増とわずかながらも増えています。中大横浜との併願者は当然多くなると思われますが、神奈川大付の方が志望順位の高い受験生がほとんどと思われます。

西武学園文理 西武学園文理(狭山市)は県内西部では共学の進学校として人気の高い学校です。中学を開校して20年目の新しい学校ですがここ数年は後発の栄東と開智の勢いに押されていました。しかし10月模試では2回以降の志望者数で盛り返していて、1月10日の1回は栄東Aと入試日が重複するため18%減、特選は25%減ですが、13日の2回は51%増、特選も4%増、18日の3回は23%増、特選は94%増です。
(6)国立大附属中学校・公立中高一貫校の志望動向
まず国立大附属中学校から見ていきます。以下は模試志望者の前年比(%)で、Mは男子、Fは女子です。(模試データのある学校のみ)
| ・お茶の水女子大附 | F 95% | |
| ・筑波大附駒場 | M 97% | |
| ・筑波大附 | M 87% | F 83% |
| ・東京学芸大小金井 | M 116% | F 152% |
| ・東京学芸大竹早 | M 97% | F 104% |
| ・東京学芸大世田谷 | M 98% | F 100% |
| ・千葉大附 | M 75% | F 114% |
| ・埼玉大附 | M 72% | F 91% |
東京学芸大小金井(小金井市)の志望者増は今春入試で緩和した入試だった反動でしょう。なお同校は2015年より4科目入試になります。
東京学芸大世田谷(世田谷区)の男子は志望者微減ですが、ボーダーのあたりが厚くなっていて難易度がアップする可能性があり要注意です。
横浜国立大附横浜(横浜市南区)と横浜国立大附鎌倉(鎌倉市)の両校は10月に入って2月2日から2月3日への入試日の変更を発表しました。10月までの模試の志望者数はこの変更をまったく反映していないため上記のデータには入れていません。前年までは2日に横浜国大附横浜か鎌倉を受験し3日は東京学芸大世田谷や県立相模原、横浜市立南などを併願する受験生が多かったのでこの影響がどうなるか、11月以降の模試の志望動向を注視する必要があります。
最後に公立中高一貫校です。
| ・都立桜修館 | M 153% | F 158% |
| ・都立小石川 | M 86% | F 94% |
| ・都立白鴎 | M 84% | F 93% |
| ・都立三鷹 | M 87% | F 101% |
| ・都立南多摩 | M 82% | F 81% |
| ・都立武蔵 | M 82% | F 101% |
| ・都立両国 | M 102% | F 104% |
| ・区立九段 | M 121% | F 107% |

桜修館 東京ではなんといっても1期生がすばらしい大学合格実績を出した桜修館(目黒区)の志望者増が注目されます。同じく1期生が卒業した両国(墨田区)もやや志望者増ですが、入学レベルが最も高いわりには1期生の実績がいまひとつだった小石川(文京区)はやや志望者が減っています。九段(千代田区)は今までの卒業生は設立時に母体校(都立九段高校、区立九段中学)から編入学した生徒でした。適性検査を受検して入学した生徒は今春の卒業生が最初の学年です。いろいろ途中で問題があった学年で進路結果は必ずしも良かったとは言えませんが、問題は大きく改善されており現在は受検生から高い評価を受けているようで特に男子は21%増で、小石川からの流れもありそうです。
| ・県立相模原 | M 91% | F 85% |
| ・市立南高 | M 123% | F 190% |
神奈川では横浜市立南(横浜市南区)の志望者増、とりわけ女子の志望者が90%増と激増しているのが注目の的です。前述のように横浜国大附の2校との入試日重複は模試実施日との関係で志望者数に反映されていませんが、これによる減少はわずかと予想されます。大変な勢いがあり学力上位の受検生も大幅に増えていて、フェリス女学院や慶応湘南藤沢などの私立上位校への影響もありそうです。
| ・県立千葉 | M 95% | F 86% |
| ・市立稲毛 | M 110% | F 93% |
| ・市立浦和 | M 82% | F 96% |
なお埼玉県立伊奈学園(北足立郡伊奈町)は全国の公立中高一貫校の入学者決定で唯一実施されていた1次の抽選を廃止します。模試データが不完全なため具体的な数字で示すことはできませんが、応募者の増加とともに受検準備をしっかりしてきた層が増えてボーダーラインの上昇が予想されます。