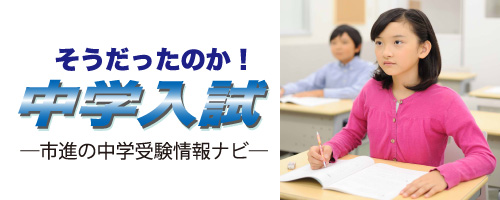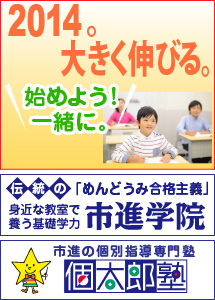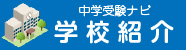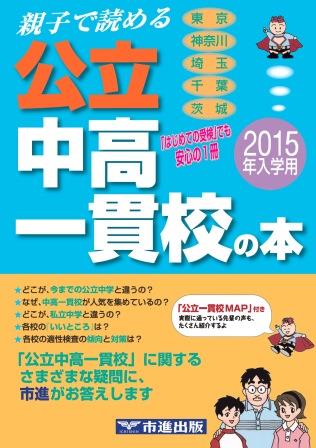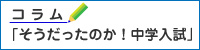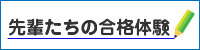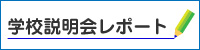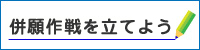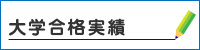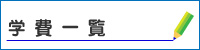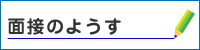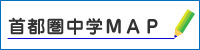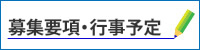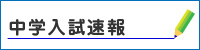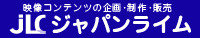トップページ > コラム「そうだったのか!中学入試」第41~50話 > 第42話「2013年首都圏中学入試(2) ――千葉・埼玉中学入試状況――」
第42話「2013年首都圏中学入試(2) ――千葉・埼玉中学入試状況――」
2013年2月12日
千葉と埼玉の一般入試の解禁日がそれぞれ1月10日と1月20日で東京・神奈川の解禁日2月1日より早いため、千葉と埼玉の学校には東京・神奈川の受験生が大量に「試し受験」をします。特に東京寄りの地域の学校では応募者の7~8割が東京・神奈川の受験生というのも珍しくありません。つまり千葉・埼玉の学校で先に合格をもらってから本命の東京・神奈川の学校を受験するわけです。そのため入試の在り方が東京・神奈川の学校とかなり異なっていることに注意して見ていく必要があります。
1. 千葉の中学入試
ここではすでに入試データを公表している学校のうち主要校および注目される学校について見ていきます。
(1)共学校

渋谷教育学園幕張 渋谷教育学園幕張(千葉市美浜区)は昨年1次・2次ともに応募者を11%減と相当に減らしましたが、今年の1次は11%増と大きく回復しほぼ2011年の水準に戻っています。この3年間の1次の応募者数は、1,947→1,737→1,923名、また受験者数では1,893→1,689→1,820名です。欠席者が54→48→103名と増えたため実質倍率は2.2→2.2→2.3倍とわずかな上昇にとどまりました。2月2日の2次の応募者は546名で18%増、合格者は51名で実質倍率は10.2倍と例年の水準を回復しています。
市川(市川市)は昨年大きく応募者を減らしましたが、今年の1回もまた2,565→2,495名と3%の減少です。特に男子の減少幅が大きく、この3年間の男子の応募者数の推移は、1,952→1,626→1,552名と400名も減っています。女子はむしろ今年は939→943名とわずか4名ですが、増えていて、男女で志望動向に大きな差が見られます。昨年大きく入試状況が緩和しましたが、今年も男子はその状況が続いて、実質倍率は男子が1.9→1.9倍、女子は2.1→2.2倍とわずかに上昇、また合否判定は男女別で昨年まで1回は男女の合格点は同じでしたが、今年は男子が258点、女子は262点と女子が4点高くなっています。
東大合格者が2→7→10名と躍進した東邦大東邦(習志野市)は前期の応募者が2,410→2,503名と4%増で実質倍率も2.0→2.1倍とわずかに上昇しています。昨年は県内の多くの学校が応募者を大きく減らす中で前年並みを維持し、さらに今年は100名近く応募者をふやすなど安定して好調な入試状況が続いているほとんど唯一の学校といえます。なお応募者数を男女別に見ると市川とは逆に男子が1,532→1,633名と101名増、女子は878→870名と微減で対照的な志望動向となっています。
上記3校につぐ位置にあるのが昭和学院秀英(千葉市美浜区)です。昨春の大学合格実績は悪くなかったのですが、第41話でお伝えしたように第一志望入試の1回で応募者が12%減でした。一般入試の2回も1,161→1,010名と13%減です。合格者を15名増やしたため実質倍率は3.4→2.8倍とかなり低下し難易度も下がっているようです。

芝浦工大柏 県内で最も好調な入試を展開しているのは事前の予想通り芝浦工大柏(柏市)です。昨年の東大2名、早慶上智129名など大学合格実績の躍進で評価を上げ、1回の応募者が833→961名と15%増、2回は705→797名と13%増です。1回、2回とも合格者を減らしたため実質倍率は1回が2.1→2.7倍、2回は2.9→4.4倍と上昇、難易度も上がっているでしょう。男女別に見る1回、2回とも男子の増加が著しく女子はほとんど前年並みです。もとより理工系大学の系列校で男子の方の人気が高かったのですが、大学合格実績の伸長はより男子の受験生と保護者にアピールしているのでしょう。
専修大松戸(松戸市)の1回の応募者は昨年1,372→1,109名と19%の大幅減でしたが、今年は1,109→1,065名と4%の小幅減です。しかしこの3年間で実質倍率は2.5→2.0→1.9倍で今年は2倍を切ってしまいました。2回の応募者も昨年は1,052→842名と20%の大幅減でしたが、今年は11名減の831名でした。実際に受験したのは1回で合格した292名と欠席者99名を除く440名で、合格者を120→144名と増やしたため実質倍率は3.8→3.1倍とかなり下がっています。
昨年入試では前年並みの応募者数を維持した成田高校附(成田市)の前期は331→278名と16%減で、実質倍率も2.4→2.0倍とやや低下しました。後期(1/31)は定員が15名と少なくなりますが応募者は127→111名と13%減、欠席者が増えたため受験者数では122→98名と20%減。合格者を15→19名と増やしたため実質倍率が8.1→5.2倍と大きく低下しました。
麗澤(柏市)は2011年春の国公立大実績が伸びて昨年は男子の応募者を増やしましたが、2012年春の難関大学合格実績が今一つで、1回の応募者が491→442名と10%減、2回は410→359名と12%減です。合格者を増やしたため実質倍率も1回が2.1→1.7倍、2回は3.1→1.9倍とかなり低下しています。
日出学園(市川市)は推薦入試の応募者が45→46名と前年並みでしたが、一般入試では Ⅰ期が186→153名と18%減、Ⅱ期は81→83名と微増です。実質倍率はⅠ期が1.3→1.3倍で前年並み、Ⅱ期は1.3→1.4倍とわずかにアップですが難易度の変動はなさそうです。なお一般入試にも第一志望者には優遇制度があり、合格点が併願受験者よりⅠ期で24点、Ⅱ期は15点下でした(300点満点)。
千葉日大第一(船橋市)は1期の応募者が6%減、2期は3%減でしたが、今年はさらに減少幅が大きくなり、1期が609→532名と13%減、2期は717→638名で11%減です。昨年は女子の応募者がやや増えていましたが、今年の女子は1期が24%減、2期は15%減と大きく減っています。実質倍率も1期が1.6→1.5倍、Ⅱ期は1.9→1.5倍と低下しています。
中堅私大の付属校で進学校化する学校が増える中、東海大浦安(浦安市)は東海大学への進学を前提とする中高大10年一貫教育を教育目標としていますが、将来の進路が東海大学に限定されるために受験者層が絞られてきているようです(他の東海大系列校も同じ)。推薦入試の応募者が145→114名と21%の大幅減となったのに続き、A試験の応募者も703→582名と17%減、B試験は145→114名と21%減です。実質倍率もAが1.4→1.1倍とかなり低下。(Bは1.3→1.3倍と前年並み)
開校3年目を迎える二松学舎大附柏(柏市)は昨年応募者総数を16%も減らしましたが、新年度から特選クラスを新設し、入試回を3回から4回に増やすなどの入試改革を行い、やや復調しているようです。1回特選の応募者は前年の1回に相当するとすれば206→212名と微増、2回特選は163→216名と33%の大幅増、新設の3回の応募者は226名です。受験者数、合格者数などの基本データが未公表なのでこれ以上のことはわかりませんが、昨年の落ち込みをかなり回復していることは間違いないでしょう。
(2)女子校
新校舎が完成し大学合格実績も好調な国府台女子学院(市川市)は推薦入試の応募者は222→240名と8%増でしたが、一般入試の1回の応募者は966→924名で4%減でした。現在のところ応募者数以外のデータが未公表なためこれ以上のことはわかりません。

聖徳大附女子 聖徳大附女子(松戸市)は選抜クラス、進学クラスにくわえ高い学力を身に着けて国公立大や難関私大を目指すS選抜クラスを新設しました。第一志望入試の応募者が前年同数の65名でした。一般入試は1回の午前が181→65名で64%の大幅減、午後は逆に72→155名で115%の大幅増ですが、午前・午後の合計では253→220名と13%減、2回は161→160名でほぼ前年と同数です。注目のS選抜の実質倍率は1回午前が3.1倍、1回午後は2.4倍となりました。特待選抜は応募者が136→111名で18%減、また特待合格者は29名でした。
和洋国府台女子(市川市)は昨年の入試で大きく応募者を減らし、今年の入試でも推薦入試の応募者が79→89名とやや増加しましたが、一般入試では1回が691→646名と7%減、2回も406→398名で2%減と減少傾向が続いています。1回、2回とも合格者数を絞っているので実質倍率は1回が1.1倍、2回は1.2倍と前年と変わっていません。
2.埼玉の中学入試
埼玉の中学入試ではここ数年一部の学校に受験生が集中する傾向が続いていますが、今年もさらにその傾向が強まっています。また県内で一気に4校も新規開校があり、周辺の学校への影響も小さくはないようです。
(1)男子校

立教新座 立教新座(新座市)の1次の応募者は1,962→1,579名と20%の大幅減です。同じ立教大系列の男子校である立教池袋の1次が243→266名と9%増なのと志望動向が大きく異なるのは、埼玉の1月入試を「試し受験」する東京・神奈川の受験生がターゲットを栄東などの共学進学校に変えてきているからでしょう。立教池袋の動向からみて立教系を第一志望とするコアな層が20%も減っているわけではないと思われます。
城西川越(川越市)の応募者は1回が429→364名と15%減、2回は349→276名で21%減、新設の3回SAの受験者が20名で、合格者は11名でした。ただし1回の合格者減で2回の欠席者が大幅に減ったため2回の実受験者は135→139名とわずかに増えています。
城北埼玉(川越市)の応募者は1回1,026→825名と20%減、2回は897→675名で25%減、3回は353→381と8%増ですが、実際に受験した人数では1回が20%減、2回は33%減、3回は25%減とすべての回で20%以上の大きな減少です。実質倍率も1回は1.7→1.7倍と変わっていませんが、2回は 2.0→1.4倍、3回は3.3→1.5倍と下がって緩和した入試となっています。
(2)女子校
女子校トップの浦和明の星女子(さいたま市緑区)は1回の応募者が1,940→1,804名と7%減です。やはり栄東などの共学進学校に一部が回っていると思われますが、県内唯一のカトリックのブランド女子校として都内の最難関女子校との併願者が多く、難易度の変動はほとんどないものと思われます。
淑徳与野(さいたま市中央区)も1回の応募者も1,067→937名と12%の減です。減り方が浦和明の星女子より大きいのは受験者の学力層が栄東や開智に近いためより直接的な影響を受けるからでしょう。
大妻嵐山(比企郡)は県内西部で新規開校の狭山ヶ丘、東京成徳大深谷の影響もあるのか、6回の入試のうち新設のアドバンス2回以外の5回の入試で応募者が大きく減っています。1回が21%減、2回は28%減、アドバンス1回は9%減ですが、セレクトが20%減、理数アドバンスは37%減です。
(3)共学校
なんといっても注目の的は栄東(さいたま市見沼区)です。昨年は応募総数が8,172名で今年は東大クラスの増員でさらに人気を呼び応募総数が10,000名を超えそうな勢いとお伝えしてきましたが、結局応募総数は9,703名で19%増でした。この4年間の応募総数の推移は3,539→7,089→8,172→9,703名で、増えているのは主に東京や神奈川の受験生です。定員を60から80名に増員した東大Ⅰは応募者が1,703→2,622名で54%増、20名から40名に増員した東大Ⅱは783→1,234名で58%増と定員増の効果がはっきり見て取れます。
県西部のトップ校西武学園文理(狭山市)の応募者は特選クラスの1回が439→382名と13%減ですが2回は345→394名と14%増、3回は173→307名と77%の大幅増です。しかし一貫クラスは1回7%減、2回9%減、3回22%減,4回は16%減とすべての回で応募者減です。

本庄東高附 中堅レベルで最も好調な入試だったのは本庄東高附(本庄市)です。昨年中高一貫1期生58名が卒業し東大1名、東北大4名、山形大医学部など国公立大23名の実績を出して評価が上がっているものと思われ、立地的には県中心部から外れていますが3回の入試とも応募者数を相当に増やしています。1回が109→135名で24%増、2回は118→145名で23%増、3回は118→141名で19%増です。さらに実受験者数では1回が25%増、2回は47%増、3回は100%増となっていることから志望順位が上がっていることをうかがわせます。
埼玉栄(さいたま市西区)の応募者は進学クラスが5回中1回のみが微増で他の回は減っていますが、東大合格者が2年連続出たのが好感されてか、難関大クラスはⅠが146→279名と91%増、Ⅱは143→149名で4%増と好調です。
浦和実業学園(さいたま市南区)の応募者は1回午後が微増で他の4回は微減で、入試状況も前年並みでした。昨春の大学合格実績が下がっているように見えますが、中高一貫生(2期生)のみで見ると、国公立大16名、早慶上理大7名、GMARCH大25名など悪くありません。栄東があれだけ集め、近くに武南が新規開校したことを考えれば前年より37名減とはいえ延べ3,049名の応募者はなかなかのものです。
開校3年目を迎える開智の姉妹校の開智未来(加須市)は4回の入試すべてで応募者が若干減っていますが、男女で志望動向がはっきり異なり、男子は1回が13%減、2回は9%減、3回未来選抜は11%減、4回は15%減で、これに対して女子は1回が5%増、2回は7%増、3回未来選抜は9%増、4回のみ減っていますが1%減です。
昨年開校して2年目を迎える西武台新座(新座市)は1回特進が248→221名、特選は191→145名、2回特進は164→140名、特選は238→152名、3回特進は新設で93名、特選は109→102名とかなりの応募者減になっています。
最後に新規開校の4校の状況を見てみます。

武南 東京に近く高校のレベルからも最も応募者を集めるだろうと予想されていた武南(蕨市)は予想通り4校中最多の延べ820名を集めました。実受験者も延べ588名で、ダブリを除いた実人数は364名です。各回の応募者と実質倍率は1回午前が236名で1.5倍、1回午後は258名で1.5倍、2回が144名で1.4倍、3回が110名で1.3倍、4回は72名で1.3倍です。説明会などで女子のほうが多かったのに、実際の入試では男子の方が多かったこと、都内の受験生が、三分の一だったこと、併願校は地元周辺の浦和実業、大宮開成.埼玉栄などは当然としてかなりレベル的には上の栄東、また都内では北区の順天、桜ヶ丘などの他、広尾学園や東京都市大等々力などが、目立ちました。

狭山ヶ丘 武南につぐ応募者を集めているのが狭山ヶ丘(入間市)で1回が176名、2回は189名,3回は141名、4回は102名で総計608名、実受験者の総数は385名です。実質倍率は1回が1.5倍、2回が1.6倍,3回は1.5倍,4回は3.4倍でした。受験生の学力レベルはかなり幅があったとのことです。都内生は1回・2回は少なかったのですが、3回・4回で増えて全体の4割弱、あとは県内西部中心で県内東部はほとんどいなかったそうです。併願校は西武学園文理、星野学園など地元周辺の学校以外では中央大附や立教新座、立教池袋などの大学付属校が目立ったとのこと。
県北部の東京成徳大深谷(深谷市)は地元中心の入試になりました。5回の応募者の合計は194名です。受験生は地元の深谷の他、熊谷、本庄が多く、南側は鴻巣、桶川が多少、高崎方面はわずかだったようです。併願校では本庄東高附は近いだけに2桁以上だったようですが、東京農業大第三、大妻嵐山は予想したより少なく1桁だったようです。その他では栄東、開智未来、また都内では帝京、日大豊山、芝浦工業大などでした。
国際学院(北足立郡)も7回の入試の応募者の合計は211名、受験者総数が90名、合格者総数は79名です。入学者は15名前後になりそうです。受験生のエリアは北が上尾、鴻巣あたり、西は越谷、三郷あたり、都内は北区、江戸川区、品川区とかなり広く、併願校はバラバラで県内では県立伊奈学園、浦和実業、大宮開成、武南など、都内では上野学園、郁文館、京華などでした。
1. 千葉の中学入試
ここではすでに入試データを公表している学校のうち主要校および注目される学校について見ていきます。
(1)共学校

渋谷教育学園幕張 渋谷教育学園幕張(千葉市美浜区)は昨年1次・2次ともに応募者を11%減と相当に減らしましたが、今年の1次は11%増と大きく回復しほぼ2011年の水準に戻っています。この3年間の1次の応募者数は、1,947→1,737→1,923名、また受験者数では1,893→1,689→1,820名です。欠席者が54→48→103名と増えたため実質倍率は2.2→2.2→2.3倍とわずかな上昇にとどまりました。2月2日の2次の応募者は546名で18%増、合格者は51名で実質倍率は10.2倍と例年の水準を回復しています。
市川(市川市)は昨年大きく応募者を減らしましたが、今年の1回もまた2,565→2,495名と3%の減少です。特に男子の減少幅が大きく、この3年間の男子の応募者数の推移は、1,952→1,626→1,552名と400名も減っています。女子はむしろ今年は939→943名とわずか4名ですが、増えていて、男女で志望動向に大きな差が見られます。昨年大きく入試状況が緩和しましたが、今年も男子はその状況が続いて、実質倍率は男子が1.9→1.9倍、女子は2.1→2.2倍とわずかに上昇、また合否判定は男女別で昨年まで1回は男女の合格点は同じでしたが、今年は男子が258点、女子は262点と女子が4点高くなっています。
東大合格者が2→7→10名と躍進した東邦大東邦(習志野市)は前期の応募者が2,410→2,503名と4%増で実質倍率も2.0→2.1倍とわずかに上昇しています。昨年は県内の多くの学校が応募者を大きく減らす中で前年並みを維持し、さらに今年は100名近く応募者をふやすなど安定して好調な入試状況が続いているほとんど唯一の学校といえます。なお応募者数を男女別に見ると市川とは逆に男子が1,532→1,633名と101名増、女子は878→870名と微減で対照的な志望動向となっています。
上記3校につぐ位置にあるのが昭和学院秀英(千葉市美浜区)です。昨春の大学合格実績は悪くなかったのですが、第41話でお伝えしたように第一志望入試の1回で応募者が12%減でした。一般入試の2回も1,161→1,010名と13%減です。合格者を15名増やしたため実質倍率は3.4→2.8倍とかなり低下し難易度も下がっているようです。

芝浦工大柏 県内で最も好調な入試を展開しているのは事前の予想通り芝浦工大柏(柏市)です。昨年の東大2名、早慶上智129名など大学合格実績の躍進で評価を上げ、1回の応募者が833→961名と15%増、2回は705→797名と13%増です。1回、2回とも合格者を減らしたため実質倍率は1回が2.1→2.7倍、2回は2.9→4.4倍と上昇、難易度も上がっているでしょう。男女別に見る1回、2回とも男子の増加が著しく女子はほとんど前年並みです。もとより理工系大学の系列校で男子の方の人気が高かったのですが、大学合格実績の伸長はより男子の受験生と保護者にアピールしているのでしょう。
専修大松戸(松戸市)の1回の応募者は昨年1,372→1,109名と19%の大幅減でしたが、今年は1,109→1,065名と4%の小幅減です。しかしこの3年間で実質倍率は2.5→2.0→1.9倍で今年は2倍を切ってしまいました。2回の応募者も昨年は1,052→842名と20%の大幅減でしたが、今年は11名減の831名でした。実際に受験したのは1回で合格した292名と欠席者99名を除く440名で、合格者を120→144名と増やしたため実質倍率は3.8→3.1倍とかなり下がっています。
昨年入試では前年並みの応募者数を維持した成田高校附(成田市)の前期は331→278名と16%減で、実質倍率も2.4→2.0倍とやや低下しました。後期(1/31)は定員が15名と少なくなりますが応募者は127→111名と13%減、欠席者が増えたため受験者数では122→98名と20%減。合格者を15→19名と増やしたため実質倍率が8.1→5.2倍と大きく低下しました。
麗澤(柏市)は2011年春の国公立大実績が伸びて昨年は男子の応募者を増やしましたが、2012年春の難関大学合格実績が今一つで、1回の応募者が491→442名と10%減、2回は410→359名と12%減です。合格者を増やしたため実質倍率も1回が2.1→1.7倍、2回は3.1→1.9倍とかなり低下しています。
日出学園(市川市)は推薦入試の応募者が45→46名と前年並みでしたが、一般入試では Ⅰ期が186→153名と18%減、Ⅱ期は81→83名と微増です。実質倍率はⅠ期が1.3→1.3倍で前年並み、Ⅱ期は1.3→1.4倍とわずかにアップですが難易度の変動はなさそうです。なお一般入試にも第一志望者には優遇制度があり、合格点が併願受験者よりⅠ期で24点、Ⅱ期は15点下でした(300点満点)。
千葉日大第一(船橋市)は1期の応募者が6%減、2期は3%減でしたが、今年はさらに減少幅が大きくなり、1期が609→532名と13%減、2期は717→638名で11%減です。昨年は女子の応募者がやや増えていましたが、今年の女子は1期が24%減、2期は15%減と大きく減っています。実質倍率も1期が1.6→1.5倍、Ⅱ期は1.9→1.5倍と低下しています。
中堅私大の付属校で進学校化する学校が増える中、東海大浦安(浦安市)は東海大学への進学を前提とする中高大10年一貫教育を教育目標としていますが、将来の進路が東海大学に限定されるために受験者層が絞られてきているようです(他の東海大系列校も同じ)。推薦入試の応募者が145→114名と21%の大幅減となったのに続き、A試験の応募者も703→582名と17%減、B試験は145→114名と21%減です。実質倍率もAが1.4→1.1倍とかなり低下。(Bは1.3→1.3倍と前年並み)
開校3年目を迎える二松学舎大附柏(柏市)は昨年応募者総数を16%も減らしましたが、新年度から特選クラスを新設し、入試回を3回から4回に増やすなどの入試改革を行い、やや復調しているようです。1回特選の応募者は前年の1回に相当するとすれば206→212名と微増、2回特選は163→216名と33%の大幅増、新設の3回の応募者は226名です。受験者数、合格者数などの基本データが未公表なのでこれ以上のことはわかりませんが、昨年の落ち込みをかなり回復していることは間違いないでしょう。
(2)女子校
新校舎が完成し大学合格実績も好調な国府台女子学院(市川市)は推薦入試の応募者は222→240名と8%増でしたが、一般入試の1回の応募者は966→924名で4%減でした。現在のところ応募者数以外のデータが未公表なためこれ以上のことはわかりません。

聖徳大附女子 聖徳大附女子(松戸市)は選抜クラス、進学クラスにくわえ高い学力を身に着けて国公立大や難関私大を目指すS選抜クラスを新設しました。第一志望入試の応募者が前年同数の65名でした。一般入試は1回の午前が181→65名で64%の大幅減、午後は逆に72→155名で115%の大幅増ですが、午前・午後の合計では253→220名と13%減、2回は161→160名でほぼ前年と同数です。注目のS選抜の実質倍率は1回午前が3.1倍、1回午後は2.4倍となりました。特待選抜は応募者が136→111名で18%減、また特待合格者は29名でした。
和洋国府台女子(市川市)は昨年の入試で大きく応募者を減らし、今年の入試でも推薦入試の応募者が79→89名とやや増加しましたが、一般入試では1回が691→646名と7%減、2回も406→398名で2%減と減少傾向が続いています。1回、2回とも合格者数を絞っているので実質倍率は1回が1.1倍、2回は1.2倍と前年と変わっていません。
2.埼玉の中学入試
埼玉の中学入試ではここ数年一部の学校に受験生が集中する傾向が続いていますが、今年もさらにその傾向が強まっています。また県内で一気に4校も新規開校があり、周辺の学校への影響も小さくはないようです。
(1)男子校

立教新座 立教新座(新座市)の1次の応募者は1,962→1,579名と20%の大幅減です。同じ立教大系列の男子校である立教池袋の1次が243→266名と9%増なのと志望動向が大きく異なるのは、埼玉の1月入試を「試し受験」する東京・神奈川の受験生がターゲットを栄東などの共学進学校に変えてきているからでしょう。立教池袋の動向からみて立教系を第一志望とするコアな層が20%も減っているわけではないと思われます。
城西川越(川越市)の応募者は1回が429→364名と15%減、2回は349→276名で21%減、新設の3回SAの受験者が20名で、合格者は11名でした。ただし1回の合格者減で2回の欠席者が大幅に減ったため2回の実受験者は135→139名とわずかに増えています。
城北埼玉(川越市)の応募者は1回1,026→825名と20%減、2回は897→675名で25%減、3回は353→381と8%増ですが、実際に受験した人数では1回が20%減、2回は33%減、3回は25%減とすべての回で20%以上の大きな減少です。実質倍率も1回は1.7→1.7倍と変わっていませんが、2回は 2.0→1.4倍、3回は3.3→1.5倍と下がって緩和した入試となっています。
(2)女子校
女子校トップの浦和明の星女子(さいたま市緑区)は1回の応募者が1,940→1,804名と7%減です。やはり栄東などの共学進学校に一部が回っていると思われますが、県内唯一のカトリックのブランド女子校として都内の最難関女子校との併願者が多く、難易度の変動はほとんどないものと思われます。
淑徳与野(さいたま市中央区)も1回の応募者も1,067→937名と12%の減です。減り方が浦和明の星女子より大きいのは受験者の学力層が栄東や開智に近いためより直接的な影響を受けるからでしょう。
大妻嵐山(比企郡)は県内西部で新規開校の狭山ヶ丘、東京成徳大深谷の影響もあるのか、6回の入試のうち新設のアドバンス2回以外の5回の入試で応募者が大きく減っています。1回が21%減、2回は28%減、アドバンス1回は9%減ですが、セレクトが20%減、理数アドバンスは37%減です。
(3)共学校
なんといっても注目の的は栄東(さいたま市見沼区)です。昨年は応募総数が8,172名で今年は東大クラスの増員でさらに人気を呼び応募総数が10,000名を超えそうな勢いとお伝えしてきましたが、結局応募総数は9,703名で19%増でした。この4年間の応募総数の推移は3,539→7,089→8,172→9,703名で、増えているのは主に東京や神奈川の受験生です。定員を60から80名に増員した東大Ⅰは応募者が1,703→2,622名で54%増、20名から40名に増員した東大Ⅱは783→1,234名で58%増と定員増の効果がはっきり見て取れます。
県西部のトップ校西武学園文理(狭山市)の応募者は特選クラスの1回が439→382名と13%減ですが2回は345→394名と14%増、3回は173→307名と77%の大幅増です。しかし一貫クラスは1回7%減、2回9%減、3回22%減,4回は16%減とすべての回で応募者減です。

本庄東高附 中堅レベルで最も好調な入試だったのは本庄東高附(本庄市)です。昨年中高一貫1期生58名が卒業し東大1名、東北大4名、山形大医学部など国公立大23名の実績を出して評価が上がっているものと思われ、立地的には県中心部から外れていますが3回の入試とも応募者数を相当に増やしています。1回が109→135名で24%増、2回は118→145名で23%増、3回は118→141名で19%増です。さらに実受験者数では1回が25%増、2回は47%増、3回は100%増となっていることから志望順位が上がっていることをうかがわせます。
埼玉栄(さいたま市西区)の応募者は進学クラスが5回中1回のみが微増で他の回は減っていますが、東大合格者が2年連続出たのが好感されてか、難関大クラスはⅠが146→279名と91%増、Ⅱは143→149名で4%増と好調です。
浦和実業学園(さいたま市南区)の応募者は1回午後が微増で他の4回は微減で、入試状況も前年並みでした。昨春の大学合格実績が下がっているように見えますが、中高一貫生(2期生)のみで見ると、国公立大16名、早慶上理大7名、GMARCH大25名など悪くありません。栄東があれだけ集め、近くに武南が新規開校したことを考えれば前年より37名減とはいえ延べ3,049名の応募者はなかなかのものです。
開校3年目を迎える開智の姉妹校の開智未来(加須市)は4回の入試すべてで応募者が若干減っていますが、男女で志望動向がはっきり異なり、男子は1回が13%減、2回は9%減、3回未来選抜は11%減、4回は15%減で、これに対して女子は1回が5%増、2回は7%増、3回未来選抜は9%増、4回のみ減っていますが1%減です。
昨年開校して2年目を迎える西武台新座(新座市)は1回特進が248→221名、特選は191→145名、2回特進は164→140名、特選は238→152名、3回特進は新設で93名、特選は109→102名とかなりの応募者減になっています。
最後に新規開校の4校の状況を見てみます。

武南 東京に近く高校のレベルからも最も応募者を集めるだろうと予想されていた武南(蕨市)は予想通り4校中最多の延べ820名を集めました。実受験者も延べ588名で、ダブリを除いた実人数は364名です。各回の応募者と実質倍率は1回午前が236名で1.5倍、1回午後は258名で1.5倍、2回が144名で1.4倍、3回が110名で1.3倍、4回は72名で1.3倍です。説明会などで女子のほうが多かったのに、実際の入試では男子の方が多かったこと、都内の受験生が、三分の一だったこと、併願校は地元周辺の浦和実業、大宮開成.埼玉栄などは当然としてかなりレベル的には上の栄東、また都内では北区の順天、桜ヶ丘などの他、広尾学園や東京都市大等々力などが、目立ちました。

狭山ヶ丘 武南につぐ応募者を集めているのが狭山ヶ丘(入間市)で1回が176名、2回は189名,3回は141名、4回は102名で総計608名、実受験者の総数は385名です。実質倍率は1回が1.5倍、2回が1.6倍,3回は1.5倍,4回は3.4倍でした。受験生の学力レベルはかなり幅があったとのことです。都内生は1回・2回は少なかったのですが、3回・4回で増えて全体の4割弱、あとは県内西部中心で県内東部はほとんどいなかったそうです。併願校は西武学園文理、星野学園など地元周辺の学校以外では中央大附や立教新座、立教池袋などの大学付属校が目立ったとのこと。
県北部の東京成徳大深谷(深谷市)は地元中心の入試になりました。5回の応募者の合計は194名です。受験生は地元の深谷の他、熊谷、本庄が多く、南側は鴻巣、桶川が多少、高崎方面はわずかだったようです。併願校では本庄東高附は近いだけに2桁以上だったようですが、東京農業大第三、大妻嵐山は予想したより少なく1桁だったようです。その他では栄東、開智未来、また都内では帝京、日大豊山、芝浦工業大などでした。
国際学院(北足立郡)も7回の入試の応募者の合計は211名、受験者総数が90名、合格者総数は79名です。入学者は15名前後になりそうです。受験生のエリアは北が上尾、鴻巣あたり、西は越谷、三郷あたり、都内は北区、江戸川区、品川区とかなり広く、併願校はバラバラで県内では県立伊奈学園、浦和実業、大宮開成、武南など、都内では上野学園、郁文館、京華などでした。