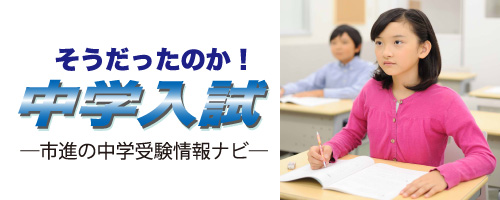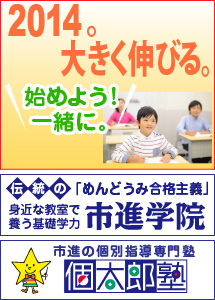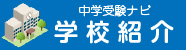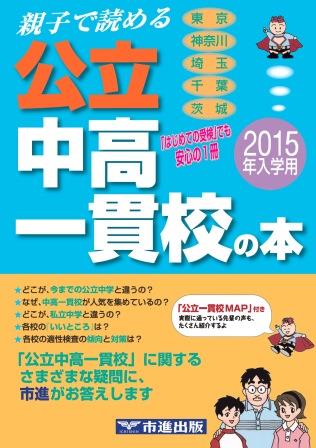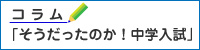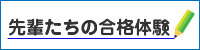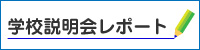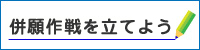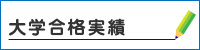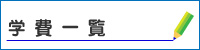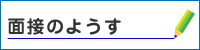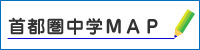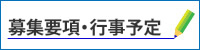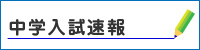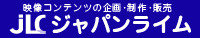トップページ > コラム「そうだったのか!中学入試」第41~50話 > 第43話「2013年首都圏中学入試(3) ――東京・神奈川の中学入試(その1)――」
第43話「2013年首都圏中学入試(3) ――東京・神奈川の中学入試(その1)――」
2013年5月8日
東京と神奈川の私立中学入試は2月1日に始まり6日ないし7日あたりまで続きます。10日前後でほぼすべての入試そのものは終了しますが、その後も上位校から順に玉突きに補欠の繰り上げが断続的に続いて2月末には最終段階を迎えます。 また東京と神奈川にある国立大学付属中学と公立中高一貫校はすべて2月3日に入試が行われています。
1. 東京の中学入試
(1)男子校
最上位4校の応募状況は以下の通りです。
開成(荒川区)は2012年春に東大合格者数が14年ぶりに200名を超えて好感度を上げての増加でしょう。関西や九州など地方からの受験生も多いため繰り上げ合格も60名前後出ているようですが、難易度はやや上昇しています。
麻布(港区)は2012年入試で応募者が12%減となった反動で5%増ですが、難易度は変わっていません。11月~12月以降に競合する駒場東邦からの流入がかなりあったようです。
駒場東邦(世田谷区)は前述のように麻布と競合しています。入試レベルが接近し、受験生のエリアもともに都内城南地区と神奈川を中心としています。前年応募者が15%増で今年は3%減です。高倍率となりそうな予測があった駒場東邦を避けて、比較的緩やかになると予想された麻布に回った受験生が相当数いたものと思われます。
武蔵(練馬区)は前年の応募者9%減に続き2013年も16%減で500名台を割り込み減少傾向に歯止めがかかりません。難易度も低下したようです。
海城(新宿区)の応募者は1回が566→577名、2回は1,214→1,244名とともに微増ですが、1月の帰国は132→149名と13%増でした。
巣鴨(豊島区)は新校舎建設のため、中学が北区浮間の仮校舎に移転していて、Ⅰ期が393→322名、Ⅱ期は702→682名と減っています。2014年中には新校舎が完成し豊島区に戻ってきますから、来年の入試では応募者数を回復する可能性が高いでしょう。
城北(板橋区)は1回の応募者が微増ですが、2・3回はやや減少です。
本郷(豊島区)は数年前に急速に人気が上がった学校ですが、このところは落ち着いてきていて3回の入試すべてで応募者が減っています。大学合格実績が下がっているわけではありませんが、やや足踏み状態が続き、かつての勢いが見られないためでしょうか。
武蔵(練馬区)は前年の応募者9%減に続き2013年も16%減で500名台を割り込み減少傾向に歯止めがかかりません。難易度も低下したようです。

芝 芝(港区)の応募者は1回が前年並みでした。御三家などとの併願者が多い2回は減少傾向が2年続いていましたが、今年は1,127→1,383名と23%の増加に転じています。やや停滞感のあった大学合格実績が東大14名など大きく回復したのが評価された結果でしょう。2013年春も東大16名など前年を上回る実績を上げていて2014年入試でもまだこの勢いが続きそうです。
攻玉社(目黒区)は回による増減がありますがおおむね好調な入試状況を維持しています。1回が前年並みで、2回はやや減り、6日の特別選抜は431→360名と16%の減少です。
世田谷学園(世田谷区)は難関国公立大の現役合格実績が大きく伸びて注目を集め、応募者は予想通りすべての回で増加しています。1次が275→357名、2次は853→909名、3次は752→797名です。1次の大幅増や3回同時出願者の増加などから第一志望者の増加が見てとれます。また地元世田谷区の受験生が増えているのも注目されます。
東京都市大付(世田谷区)は付属校から進学校への転換で評価が上がり、Ⅰ類・Ⅱ類のコース制導入でさらに人気が上がりました。4年連続応募者増で、都内私立中の応募数最多記録を3年連続で更新しています。この4年間の応募総数は3,328→3,692→4,479→4,809名です。また駒場東邦、桐朋、栄光学園、聖光学院、芝などとの併願者が増えていて、最上位の受験生が増加しているのがはっきりわかります。

高輪 今年の中堅レベルの男子校で最も注目された学校のひとつが高輪(港区)です。帰国生の入試2回を除いて一般生の入試は4回ありますが、応募者総数で1,511→1,974名と31%の大幅な増加です。これだけ増えた主な要因は大学合格が2011年からの3年間で、東大が0→1→3名、早慶上智が65→73→100名と着実に伸びているためでしょう。
日本学園(世田谷区)も注目校の1つです。まだ入学しやすいレベルの学校ですが、2012年より明治大学との高大連携がはじまり、2013年入試では「明大&SS特待入試」が人気を呼び、昨年から導入された公立一貫校受検者向けの「SS適性検査入試」も応募者がほぼ倍増し、応募総数では291→504名と73%の大幅増です。この4月から明大中野八王子の元教頭の小岩利夫先生が校長に就任しています。
(2)女子校
最上位3校の応募状況は以下の通りです。
女子校最難関の桜蔭(文京区)は2012年春の東大合格実績が75→58名と減少したのに加え、女子最上位受験生の桜蔭シフトで難化が進んだ反動もあってか応募者が11%減です。もちろん減っているのは主にチャレンジ層で難易度は変わっていません。
女子学院(千代田区)も2012年春の東大合格実績が32→23名と減った影響があるのか応募者が3%減ですが難易度には変化なし。
雙葉(千代田区)も応募者が5%減ですがやはり難易度には変化ありません。
以上3校の応募状況から2013年入試で女子最上位受験生が手堅い受験校選択をしたように見えますが、この背景には次の2つの動きがあったようです。
1つは東京の女子御三家を受験していた神奈川の最上位生の地元回帰で、フェリス女学院の応募者増はその結果でしょう。特に女子学院とフェリス女学院はともに創立143年目の日本最古のプロテスタント・ミッション校で自由な校風など共通する部分も多いので、受験生は両校の間で揺れ動いたものと思われます。また千葉や埼玉の上位受験生のあいだにも地元志向が強まっているようで、これには共学志向という要素もあるようです。
もうひとつは2月1日に女子御三家ではなく吉祥女子、鴎友学園女子、晃華学園などで手堅く押さえて、2日(3日、4日)に第一志望として豊島岡女子を受験する受験生の増加です。豊島岡女子は女子学院や雙葉とほとんど入試レベルは変わらず、進路では理系に強く国公立大や医学部で実績を上げているのは周知のとおりです。いわばブランドで選ぶか、実績で選ぶかということでしょうか。
その豊島岡女子(豊島区)は1回が微増で2・3回は微減でした。御三家の併願校として定着し難易度の上昇が続いた結果、受験者層が御三家3校とほぼ同レベルになり、多少の応募者の増減があっても難易度の変動はわずかな上下にとどまり安定してきています。
頌栄女子学院(港区)は1回の応募者数にはっきりと隔年現象が見られます。この4年間の1回の応募者の推移は帰国生を除き263→324→286→301名です。前年より帰国入試をやめた2回は2月5日と遅い日程のためか2年続いて応募者が減っていましたが、今年は552→592名と回復しています。

吉祥女子 吉祥女子(武蔵野市)は今年の入試で最も注目される学校の1つです。1回が380→461名、2回は641→702名、3回は431→571名と3回とも応募者増で、総計では1,452→1,734名で19%増です。
鴎友学園女子(世田谷区)はここ3年間応募者増で難化し続けて敬遠されたのか、1次が409→363名、2次は630→502名、3次は593→459名と3回とも減っています。総計では19%減です。ただし減っているのは主にチャレンジ層で、第一志望の上位層はむしろ厚くなっています。2013年春の大学合格実績が、東大4→11名(全員現役)と大きく伸び、国公立大合計でも88→99名と確実に伸びています。早慶上智大は191→201名とわずかな伸びにとどまっているようですが、国立大医学部や私大医学部合格者の増加から理系へシフトしつつある様子が見てとれ、文系学部中心の早慶上智大の実績に反映しないのは当然かもしれません。
カトリック・ミッション校の晃華学園(調布市)も大いに注目される学校です。前年入試で2月1日に参入しましたが応募者総計43%の大幅減となりました。しかし2013年入試では定員増の1回が87→114名と31%増、難関校との併願者が多い2回は定員減ですが160→232名と大幅増、3回も189→237名とすべての入試回で応募者が増えていて、応募総数では34%増です。
さてこのへんで中堅レベルの女子校のうち今春入試で注目された学校の動向を見ておきましょう。

山脇学園 最も注目を集めたのは予想通り山脇学園(港区)です。やや保守的なイメージのあった都心の伝統校ですが、カリキュラムの改定、新制服の採用、新校舎建設など「山脇ルネサンス」と称する全面的な学校改革によって、進学校への転換を図る改革が進路実績でも成果を出してきています。応募者はAが289→427名、Bは595→804名、Cは506→681名と3回とも増加、3回計では1,390→1,912名と38%の大幅増です。今春の大学合格実績も早慶上智大が31→57名、GMARCH大が155→211名と大きく伸びていますから来年もますます人気が上がりそうです。
これに次いで注目されるのが、創立110年を超える伝統校ながら地味なイメージが強かった実践女子学園(渋谷区)です。一時落ち込んでいた時期もありますが大胆な学校改革によって女子大付属から進学校へ転換しいよいよ結果が出始めています。2012年春は一橋大1名をはじめ国公立大11名、早慶上智大が9→26名、GMARCH大は74→146名と大きく大学合格実績を伸ばし、2013年入試の応募者は一般学級1回が208→253名、2回は468→545名、3回は464→494名と3回とも増加し、3回計では13%増です。国際学級も37→50名と増えています。この春も早慶上智大が26→47名、GMARCH大は146→164名と実績が伸びていますから、さらに人気が上がりそうです。
東京女学館(渋谷区)も創立125年目の都内でも有数の伝統校ですが、国際学級の設置などの学校改革によって進学校として実績を上げてきています。今年は以前から午後入試を行っていた国際学級と同じ2日午後に一般学級が午後入試を新設し大きな注目を集めました。その2回午後は611名、3回も443→476名の応募者を集めましたが、反面で第一志望の多い1回が200→152名と大きく減ってしまいました。午後入試の合格者を抑えた結果、手続き者数が見込みより少なくなり一般学級だけで繰り上げを34名出しています。なお2013年春は東大、一橋大、東工大、東京医科歯科大が各1名のほか、早慶上智大76→86名や医学部などで実績を伸ばしています。

大妻多摩 多摩地区で注目校はなんといっても大妻多摩(多摩市)です。2012年春に東大1名、一橋大2名など難関国立大の実績を出し、さらに2013年入試では午後入試の導入で一気に人気に火が付いたのか、1回は150→152名と前年並みですが、1回午後が339名、2回は310→372名、3回は281→311名で、総計では741→1174名と58%の大幅増です。新設の午後入試は吉祥女子、友学園女子、洗足学園、立教女学院など相当数の上位校併願者が受験していたようです。
さらに中堅校でも入学しやすいレベルの学校の多くは応募者を減らしていますが、その中で創立110周年を迎えた東京女子学園(港区)は大きく応募者を増やしています。2012年春の大学合格実績が、早慶上智大1→7名、GMARCH大11→24名、東京女子大・日本女子大・学習院女子大は0→23名など大きく伸びたためか、一般入試の応募総数は293→410名と40%の大幅増です。特別入試から名称変更され2回に増えた特奨入試も79→91名と増えています。2013年春も北大医学部、大分大医学部、防衛医大などにも合格者を出していますからさらに人気が上がりそうです。
2012年に大きく応募者を減らし、今年午後入試を新設したプロテスタント・ミッション校の玉川聖学院(世田谷区)は予想通り応募者数を大きく増やしています。午後入試が呼び水になったのか従来からの午前入試も増えて、応募総数が415→1,173名と183%増とまさに激増です。特に午後入試では上位層も多く受験しましたが、手続き率が低下し入学者数では141→121名と減ってしまいました。
カトリック・ミッションの女子校目黒星美学園(世田谷区)は1学年が80名前後の小規模校で入試も小規模ですが、昨年発想力入試というユニークな入試を導入、今年は午後入試を新設して、応募総数が136→244名と79%の大幅増です。2013年春の大学合格実績も東大1名、お茶大1名、北大1名などの難関国公立大や、早慶上智大8→19名、GMARCH大19→34名など大きく伸びていますから、2014年入試でもさらに応募者が増える可能性大です。
和洋九段女子(千代田区)は創立116年目の伝統校ですが、ここ数年応募者の減少が続き、特に前年は手続き日を早めたため大きく応募者が減りました。今年は手続き日をすべての回で2月8日まで延ばし、4回の入試のうち3回で応募者が増え、総計では758→853名で13%増とやや回復しました。
(3)共学校
ここでは共学校(別学を含む)のうち進学校系の学校を中心に見ていきます。東京と神奈川の共学の上位校はほとんどが有名大学の付属校ですが、これは次回に東京・神奈川の学校をまとめて見ていきます。
大学付属校を除けば共学のトップ校は渋谷教育学園渋谷(渋谷区)です。2012年は2回・3回の応募者が増えていましたが、今年は1回が461→455名と前年並みですが、2回は673→600名、3回は694→637名と前年の反動かかなり減って総計では7%減となっています。
国学院久我山(杉並区)は正確にいえば別学校です。国学院大学の併設校ですが90%以上が東大などの国公立大や早慶などの難関私大などに進学しています。最難関国公立大の現役合格を目指すSTクラスは人気を持続し、ST1回では男子が366→423名と増え、女子は232→237名とわずかですが増えています。ST2回は男子が前年並みで女子は157→136名と若干の減少でした。ただし一般の方は1回~3回まですべて応募者が男女とも減っています。これは男子が東京都市大付、女子は晃華学園や大妻多摩などとの競合が厳しくなっているためと思われます。
ここ数年進学校としての評価を高めている淑徳(板橋区)は毎年のように応募者の増加が続いていましたが、今年も好調な入試状況です。2年目の入試になるスーパー特進東大セレクトは、男子がチャレンジ層に敬遠されやや減っていて、逆に女子の増加が目立ちます。スーパー特進は1回から3回まですべて応募者が男女ともやや増加。東大セレクトは、御三家や巣鴨、城北など併願校のレベルも上がっているようです。

東京農大一 東京農大一(世田谷区)は周辺に世田谷学園、東京都市大付、東京都市大等々力、鴎友学園女子などの強力な競合校があるにもかかわらず、前年の一貫2期生の大学合格実績の伸びで進学校としての評価が上がり、応募者は1回が596→619名、2回は497→583名、3回は401→425名とすべての回で増え、総数では1,494→1,627名と9%増です。特に男子の増加が18%増と大きくなっています。上位の併願校では駒場東邦や女子学院、また都立桜修館、県立相模原などの公立一貫校も増えているようです。
共学化以来受験者層が上昇し続けている広尾学園(港区)は難化のため前年は受験者が絞られ応募者が減りましたが、今年は特待制度を廃止したのにもかかわらず帰国を除く応募総数は2,297→2,346名と2%増です。本科は5%減ですが、本科へのスライド合格のあるインターSGの応募者は50%増で相当に難化しています。なお8年間の在職期間に共学化、校名変更、新校舎建設などの大改革を行なった大橋清貴校長がこの3月に退任し、4月からは東大名誉教授の田邊裕先生が新校長に就任しました。
東京都市大等々力(世田谷区)は共学化から4年目になりますがいまだに勢いが衰えず、応募者は特選が5%増、特進は17%増です。ただし実受験者では特選が9%減、特進は1%減でした。男子は攻玉社、世田谷学園、高輪、女子は中大横浜との競合が激しくなってきています。併願者が最も多いのは姉妹校の東京都市大付ですが、今年は都立桜修館が急増しています。
宝仙学園理数インター(中野区)は共学部一貫1期生が卒業して早慶上智大1→21名、GMARCH大0→36名と大躍進しました。今年の入試でも好調を維持していて、応募総数は帰国生入試を除いて1,384→1,396名と微増ですが、1回の倍率は合格者が絞られたため午前が1.8→4.9倍、午後は4.8→6.8倍と上昇して難化しています。また公立一貫対応入試もこの3年間で応募者が123→183→216名と毎年増加しており、公立一貫校受検生にも定着しているようです。

かえつ有明 かえつ有明(江東区)は2006年に校地を有明に移転、女子校から共学化して校名を変更、2012年には共学1期生が卒業して早慶上智大8→26名、GMARCH大8→56名と大学合格実績が急上昇、そして今年2013年には全国初の共学校から別学校への転換で注目を集めました。これは男女の性差をふまえて中1から高1まで授業のみ男女別クラス編成を行うものです。応募者は予想通り大幅増で、総数で1,533→2,377名と55%増で、ほとんどの回で倍率が大きく上昇しています。
青稜(品川区)は2012年の大学合格実績が京大1名、一橋大1名、東工大1名などの他、早慶上智大40→88名、GMARCH大86→245名と大躍進し、やや停滞していた応募者数が総数で1,695→2,061名と22%増で大きく回復しています。併願校もまだ少数ですが浅野などの上位校や、公立一貫校では都立桜修館、区立九段、横浜市立南などレベルが上がっています。2013年も大学合格実績が東大2名など好調ですからさらに応募者増の可能性があります。
文教大付(品川区)は一貫1期生が東大合格者5名を出して話題になった都立白鴎高・中の前校長の星野喜代美先生が2012年4月に校長に就任し学校改革が加速しています。 「進学の強豪校へ!」をスローガンに掲げ、着任して早々に「放課後学内塾」「文教ステーション」「寺子屋クラブ」など学習・進学指導強化のための施策を矢つぎばやに立ち上げて、進学校としての認知度が急速に上がっているようです。2013年入試では応募総数は991→1,103名と11%増ですが、特に男子の受験者数は4科受験を中心に18%増で2回の午後入試では上位校との併願者が増えているようです。なお現在新校舎を建設中ですが、主に中学生が使う校舎は2014年2月完成予定です。(すべてが完成するのは2016年6月予定)

東京電機大 順天(北区)は城北地区の中堅校で最も伸びた学校ですが、前年の大学合格実績の停滞、ここ数年続いた難化傾向に対するチャレンジ層の敬遠、淑徳との上位層での競合などの要因が重なったためか、試験回数が1回増えているにもかかわらず、応募総数が1,013→632名と38%の大幅減で新設回を除きすべての回で倍率が低下しました。しかし前年落ち込んだ大学合格実績が早慶上智大42→23→52名、GMARCH大158→102→166名など大きくV字回復していますから、2014年入試では応募者数の増加が予想されます。 多摩地区は男女御三家のような伝統的な別学校がなく、戦後に創立された共学校と都心から移転してきた学校(付属校が多い)が主流です。そのなかで今年の入試で一番元気がよかったのは東京電機大(小金井市)です。1992年に都心から現在地に移転し、1996年に中学校を開校、1999年には中高を同時に共学化し、2012年春は東工大2名、阪大1名、早慶43名など好調な大学合格実績で、2013年入試の応募者は総計で1,128→1,306名と16%増でした。受験者数では686→907名で32%増です。1回は合格者を絞ったため倍率が大きく上昇し難易度もアップしています。近年理系志向の上昇傾向も見られるなかで目の離せない学校です。
東京は学校数が非常に多くまだまだ触れておきたい学校もありますが、ひとまず東京の2013年私立中入試の状況についてのレポートを終えます。なお国立大付属校と公立中高一貫校については、あらためて別の機会にお伝えする予定です。次回は神奈川の入試状況のレポートです。
1. 東京の中学入試
(1)男子校
最上位4校の応募状況は以下の通りです。
| ・開成 | 1,179→1,257名(+6%) |
| ・麻布 | 834→874名(+5%) |
| ・武蔵 | 525→443名(-16%) |
| ・駒場東邦 | 724→701名(-3%) |
開成(荒川区)は2012年春に東大合格者数が14年ぶりに200名を超えて好感度を上げての増加でしょう。関西や九州など地方からの受験生も多いため繰り上げ合格も60名前後出ているようですが、難易度はやや上昇しています。
麻布(港区)は2012年入試で応募者が12%減となった反動で5%増ですが、難易度は変わっていません。11月~12月以降に競合する駒場東邦からの流入がかなりあったようです。
駒場東邦(世田谷区)は前述のように麻布と競合しています。入試レベルが接近し、受験生のエリアもともに都内城南地区と神奈川を中心としています。前年応募者が15%増で今年は3%減です。高倍率となりそうな予測があった駒場東邦を避けて、比較的緩やかになると予想された麻布に回った受験生が相当数いたものと思われます。
武蔵(練馬区)は前年の応募者9%減に続き2013年も16%減で500名台を割り込み減少傾向に歯止めがかかりません。難易度も低下したようです。
海城(新宿区)の応募者は1回が566→577名、2回は1,214→1,244名とともに微増ですが、1月の帰国は132→149名と13%増でした。
巣鴨(豊島区)は新校舎建設のため、中学が北区浮間の仮校舎に移転していて、Ⅰ期が393→322名、Ⅱ期は702→682名と減っています。2014年中には新校舎が完成し豊島区に戻ってきますから、来年の入試では応募者数を回復する可能性が高いでしょう。
城北(板橋区)は1回の応募者が微増ですが、2・3回はやや減少です。
本郷(豊島区)は数年前に急速に人気が上がった学校ですが、このところは落ち着いてきていて3回の入試すべてで応募者が減っています。大学合格実績が下がっているわけではありませんが、やや足踏み状態が続き、かつての勢いが見られないためでしょうか。
武蔵(練馬区)は前年の応募者9%減に続き2013年も16%減で500名台を割り込み減少傾向に歯止めがかかりません。難易度も低下したようです。

芝 芝(港区)の応募者は1回が前年並みでした。御三家などとの併願者が多い2回は減少傾向が2年続いていましたが、今年は1,127→1,383名と23%の増加に転じています。やや停滞感のあった大学合格実績が東大14名など大きく回復したのが評価された結果でしょう。2013年春も東大16名など前年を上回る実績を上げていて2014年入試でもまだこの勢いが続きそうです。
攻玉社(目黒区)は回による増減がありますがおおむね好調な入試状況を維持しています。1回が前年並みで、2回はやや減り、6日の特別選抜は431→360名と16%の減少です。
世田谷学園(世田谷区)は難関国公立大の現役合格実績が大きく伸びて注目を集め、応募者は予想通りすべての回で増加しています。1次が275→357名、2次は853→909名、3次は752→797名です。1次の大幅増や3回同時出願者の増加などから第一志望者の増加が見てとれます。また地元世田谷区の受験生が増えているのも注目されます。
東京都市大付(世田谷区)は付属校から進学校への転換で評価が上がり、Ⅰ類・Ⅱ類のコース制導入でさらに人気が上がりました。4年連続応募者増で、都内私立中の応募数最多記録を3年連続で更新しています。この4年間の応募総数は3,328→3,692→4,479→4,809名です。また駒場東邦、桐朋、栄光学園、聖光学院、芝などとの併願者が増えていて、最上位の受験生が増加しているのがはっきりわかります。

高輪 今年の中堅レベルの男子校で最も注目された学校のひとつが高輪(港区)です。帰国生の入試2回を除いて一般生の入試は4回ありますが、応募者総数で1,511→1,974名と31%の大幅な増加です。これだけ増えた主な要因は大学合格が2011年からの3年間で、東大が0→1→3名、早慶上智が65→73→100名と着実に伸びているためでしょう。
日本学園(世田谷区)も注目校の1つです。まだ入学しやすいレベルの学校ですが、2012年より明治大学との高大連携がはじまり、2013年入試では「明大&SS特待入試」が人気を呼び、昨年から導入された公立一貫校受検者向けの「SS適性検査入試」も応募者がほぼ倍増し、応募総数では291→504名と73%の大幅増です。この4月から明大中野八王子の元教頭の小岩利夫先生が校長に就任しています。
(2)女子校
最上位3校の応募状況は以下の通りです。
| ・桜蔭 | 588→523名(-11%) |
| ・女子学院 | 728→707名(-3%) |
| ・雙葉 | 432→411名(-5%) |
女子校最難関の桜蔭(文京区)は2012年春の東大合格実績が75→58名と減少したのに加え、女子最上位受験生の桜蔭シフトで難化が進んだ反動もあってか応募者が11%減です。もちろん減っているのは主にチャレンジ層で難易度は変わっていません。
女子学院(千代田区)も2012年春の東大合格実績が32→23名と減った影響があるのか応募者が3%減ですが難易度には変化なし。
雙葉(千代田区)も応募者が5%減ですがやはり難易度には変化ありません。
以上3校の応募状況から2013年入試で女子最上位受験生が手堅い受験校選択をしたように見えますが、この背景には次の2つの動きがあったようです。
1つは東京の女子御三家を受験していた神奈川の最上位生の地元回帰で、フェリス女学院の応募者増はその結果でしょう。特に女子学院とフェリス女学院はともに創立143年目の日本最古のプロテスタント・ミッション校で自由な校風など共通する部分も多いので、受験生は両校の間で揺れ動いたものと思われます。また千葉や埼玉の上位受験生のあいだにも地元志向が強まっているようで、これには共学志向という要素もあるようです。
もうひとつは2月1日に女子御三家ではなく吉祥女子、鴎友学園女子、晃華学園などで手堅く押さえて、2日(3日、4日)に第一志望として豊島岡女子を受験する受験生の増加です。豊島岡女子は女子学院や雙葉とほとんど入試レベルは変わらず、進路では理系に強く国公立大や医学部で実績を上げているのは周知のとおりです。いわばブランドで選ぶか、実績で選ぶかということでしょうか。
その豊島岡女子(豊島区)は1回が微増で2・3回は微減でした。御三家の併願校として定着し難易度の上昇が続いた結果、受験者層が御三家3校とほぼ同レベルになり、多少の応募者の増減があっても難易度の変動はわずかな上下にとどまり安定してきています。
頌栄女子学院(港区)は1回の応募者数にはっきりと隔年現象が見られます。この4年間の1回の応募者の推移は帰国生を除き263→324→286→301名です。前年より帰国入試をやめた2回は2月5日と遅い日程のためか2年続いて応募者が減っていましたが、今年は552→592名と回復しています。

吉祥女子 吉祥女子(武蔵野市)は今年の入試で最も注目される学校の1つです。1回が380→461名、2回は641→702名、3回は431→571名と3回とも応募者増で、総計では1,452→1,734名で19%増です。
鴎友学園女子(世田谷区)はここ3年間応募者増で難化し続けて敬遠されたのか、1次が409→363名、2次は630→502名、3次は593→459名と3回とも減っています。総計では19%減です。ただし減っているのは主にチャレンジ層で、第一志望の上位層はむしろ厚くなっています。2013年春の大学合格実績が、東大4→11名(全員現役)と大きく伸び、国公立大合計でも88→99名と確実に伸びています。早慶上智大は191→201名とわずかな伸びにとどまっているようですが、国立大医学部や私大医学部合格者の増加から理系へシフトしつつある様子が見てとれ、文系学部中心の早慶上智大の実績に反映しないのは当然かもしれません。
カトリック・ミッション校の晃華学園(調布市)も大いに注目される学校です。前年入試で2月1日に参入しましたが応募者総計43%の大幅減となりました。しかし2013年入試では定員増の1回が87→114名と31%増、難関校との併願者が多い2回は定員減ですが160→232名と大幅増、3回も189→237名とすべての入試回で応募者が増えていて、応募総数では34%増です。
さてこのへんで中堅レベルの女子校のうち今春入試で注目された学校の動向を見ておきましょう。

山脇学園 最も注目を集めたのは予想通り山脇学園(港区)です。やや保守的なイメージのあった都心の伝統校ですが、カリキュラムの改定、新制服の採用、新校舎建設など「山脇ルネサンス」と称する全面的な学校改革によって、進学校への転換を図る改革が進路実績でも成果を出してきています。応募者はAが289→427名、Bは595→804名、Cは506→681名と3回とも増加、3回計では1,390→1,912名と38%の大幅増です。今春の大学合格実績も早慶上智大が31→57名、GMARCH大が155→211名と大きく伸びていますから来年もますます人気が上がりそうです。
これに次いで注目されるのが、創立110年を超える伝統校ながら地味なイメージが強かった実践女子学園(渋谷区)です。一時落ち込んでいた時期もありますが大胆な学校改革によって女子大付属から進学校へ転換しいよいよ結果が出始めています。2012年春は一橋大1名をはじめ国公立大11名、早慶上智大が9→26名、GMARCH大は74→146名と大きく大学合格実績を伸ばし、2013年入試の応募者は一般学級1回が208→253名、2回は468→545名、3回は464→494名と3回とも増加し、3回計では13%増です。国際学級も37→50名と増えています。この春も早慶上智大が26→47名、GMARCH大は146→164名と実績が伸びていますから、さらに人気が上がりそうです。
東京女学館(渋谷区)も創立125年目の都内でも有数の伝統校ですが、国際学級の設置などの学校改革によって進学校として実績を上げてきています。今年は以前から午後入試を行っていた国際学級と同じ2日午後に一般学級が午後入試を新設し大きな注目を集めました。その2回午後は611名、3回も443→476名の応募者を集めましたが、反面で第一志望の多い1回が200→152名と大きく減ってしまいました。午後入試の合格者を抑えた結果、手続き者数が見込みより少なくなり一般学級だけで繰り上げを34名出しています。なお2013年春は東大、一橋大、東工大、東京医科歯科大が各1名のほか、早慶上智大76→86名や医学部などで実績を伸ばしています。

大妻多摩 多摩地区で注目校はなんといっても大妻多摩(多摩市)です。2012年春に東大1名、一橋大2名など難関国立大の実績を出し、さらに2013年入試では午後入試の導入で一気に人気に火が付いたのか、1回は150→152名と前年並みですが、1回午後が339名、2回は310→372名、3回は281→311名で、総計では741→1174名と58%の大幅増です。新設の午後入試は吉祥女子、友学園女子、洗足学園、立教女学院など相当数の上位校併願者が受験していたようです。
さらに中堅校でも入学しやすいレベルの学校の多くは応募者を減らしていますが、その中で創立110周年を迎えた東京女子学園(港区)は大きく応募者を増やしています。2012年春の大学合格実績が、早慶上智大1→7名、GMARCH大11→24名、東京女子大・日本女子大・学習院女子大は0→23名など大きく伸びたためか、一般入試の応募総数は293→410名と40%の大幅増です。特別入試から名称変更され2回に増えた特奨入試も79→91名と増えています。2013年春も北大医学部、大分大医学部、防衛医大などにも合格者を出していますからさらに人気が上がりそうです。
2012年に大きく応募者を減らし、今年午後入試を新設したプロテスタント・ミッション校の玉川聖学院(世田谷区)は予想通り応募者数を大きく増やしています。午後入試が呼び水になったのか従来からの午前入試も増えて、応募総数が415→1,173名と183%増とまさに激増です。特に午後入試では上位層も多く受験しましたが、手続き率が低下し入学者数では141→121名と減ってしまいました。
カトリック・ミッションの女子校目黒星美学園(世田谷区)は1学年が80名前後の小規模校で入試も小規模ですが、昨年発想力入試というユニークな入試を導入、今年は午後入試を新設して、応募総数が136→244名と79%の大幅増です。2013年春の大学合格実績も東大1名、お茶大1名、北大1名などの難関国公立大や、早慶上智大8→19名、GMARCH大19→34名など大きく伸びていますから、2014年入試でもさらに応募者が増える可能性大です。
和洋九段女子(千代田区)は創立116年目の伝統校ですが、ここ数年応募者の減少が続き、特に前年は手続き日を早めたため大きく応募者が減りました。今年は手続き日をすべての回で2月8日まで延ばし、4回の入試のうち3回で応募者が増え、総計では758→853名で13%増とやや回復しました。
(3)共学校
ここでは共学校(別学を含む)のうち進学校系の学校を中心に見ていきます。東京と神奈川の共学の上位校はほとんどが有名大学の付属校ですが、これは次回に東京・神奈川の学校をまとめて見ていきます。
大学付属校を除けば共学のトップ校は渋谷教育学園渋谷(渋谷区)です。2012年は2回・3回の応募者が増えていましたが、今年は1回が461→455名と前年並みですが、2回は673→600名、3回は694→637名と前年の反動かかなり減って総計では7%減となっています。
国学院久我山(杉並区)は正確にいえば別学校です。国学院大学の併設校ですが90%以上が東大などの国公立大や早慶などの難関私大などに進学しています。最難関国公立大の現役合格を目指すSTクラスは人気を持続し、ST1回では男子が366→423名と増え、女子は232→237名とわずかですが増えています。ST2回は男子が前年並みで女子は157→136名と若干の減少でした。ただし一般の方は1回~3回まですべて応募者が男女とも減っています。これは男子が東京都市大付、女子は晃華学園や大妻多摩などとの競合が厳しくなっているためと思われます。
ここ数年進学校としての評価を高めている淑徳(板橋区)は毎年のように応募者の増加が続いていましたが、今年も好調な入試状況です。2年目の入試になるスーパー特進東大セレクトは、男子がチャレンジ層に敬遠されやや減っていて、逆に女子の増加が目立ちます。スーパー特進は1回から3回まですべて応募者が男女ともやや増加。東大セレクトは、御三家や巣鴨、城北など併願校のレベルも上がっているようです。

東京農大一 東京農大一(世田谷区)は周辺に世田谷学園、東京都市大付、東京都市大等々力、鴎友学園女子などの強力な競合校があるにもかかわらず、前年の一貫2期生の大学合格実績の伸びで進学校としての評価が上がり、応募者は1回が596→619名、2回は497→583名、3回は401→425名とすべての回で増え、総数では1,494→1,627名と9%増です。特に男子の増加が18%増と大きくなっています。上位の併願校では駒場東邦や女子学院、また都立桜修館、県立相模原などの公立一貫校も増えているようです。
共学化以来受験者層が上昇し続けている広尾学園(港区)は難化のため前年は受験者が絞られ応募者が減りましたが、今年は特待制度を廃止したのにもかかわらず帰国を除く応募総数は2,297→2,346名と2%増です。本科は5%減ですが、本科へのスライド合格のあるインターSGの応募者は50%増で相当に難化しています。なお8年間の在職期間に共学化、校名変更、新校舎建設などの大改革を行なった大橋清貴校長がこの3月に退任し、4月からは東大名誉教授の田邊裕先生が新校長に就任しました。
東京都市大等々力(世田谷区)は共学化から4年目になりますがいまだに勢いが衰えず、応募者は特選が5%増、特進は17%増です。ただし実受験者では特選が9%減、特進は1%減でした。男子は攻玉社、世田谷学園、高輪、女子は中大横浜との競合が激しくなってきています。併願者が最も多いのは姉妹校の東京都市大付ですが、今年は都立桜修館が急増しています。
宝仙学園理数インター(中野区)は共学部一貫1期生が卒業して早慶上智大1→21名、GMARCH大0→36名と大躍進しました。今年の入試でも好調を維持していて、応募総数は帰国生入試を除いて1,384→1,396名と微増ですが、1回の倍率は合格者が絞られたため午前が1.8→4.9倍、午後は4.8→6.8倍と上昇して難化しています。また公立一貫対応入試もこの3年間で応募者が123→183→216名と毎年増加しており、公立一貫校受検生にも定着しているようです。

かえつ有明 かえつ有明(江東区)は2006年に校地を有明に移転、女子校から共学化して校名を変更、2012年には共学1期生が卒業して早慶上智大8→26名、GMARCH大8→56名と大学合格実績が急上昇、そして今年2013年には全国初の共学校から別学校への転換で注目を集めました。これは男女の性差をふまえて中1から高1まで授業のみ男女別クラス編成を行うものです。応募者は予想通り大幅増で、総数で1,533→2,377名と55%増で、ほとんどの回で倍率が大きく上昇しています。
青稜(品川区)は2012年の大学合格実績が京大1名、一橋大1名、東工大1名などの他、早慶上智大40→88名、GMARCH大86→245名と大躍進し、やや停滞していた応募者数が総数で1,695→2,061名と22%増で大きく回復しています。併願校もまだ少数ですが浅野などの上位校や、公立一貫校では都立桜修館、区立九段、横浜市立南などレベルが上がっています。2013年も大学合格実績が東大2名など好調ですからさらに応募者増の可能性があります。
文教大付(品川区)は一貫1期生が東大合格者5名を出して話題になった都立白鴎高・中の前校長の星野喜代美先生が2012年4月に校長に就任し学校改革が加速しています。 「進学の強豪校へ!」をスローガンに掲げ、着任して早々に「放課後学内塾」「文教ステーション」「寺子屋クラブ」など学習・進学指導強化のための施策を矢つぎばやに立ち上げて、進学校としての認知度が急速に上がっているようです。2013年入試では応募総数は991→1,103名と11%増ですが、特に男子の受験者数は4科受験を中心に18%増で2回の午後入試では上位校との併願者が増えているようです。なお現在新校舎を建設中ですが、主に中学生が使う校舎は2014年2月完成予定です。(すべてが完成するのは2016年6月予定)

東京電機大 順天(北区)は城北地区の中堅校で最も伸びた学校ですが、前年の大学合格実績の停滞、ここ数年続いた難化傾向に対するチャレンジ層の敬遠、淑徳との上位層での競合などの要因が重なったためか、試験回数が1回増えているにもかかわらず、応募総数が1,013→632名と38%の大幅減で新設回を除きすべての回で倍率が低下しました。しかし前年落ち込んだ大学合格実績が早慶上智大42→23→52名、GMARCH大158→102→166名など大きくV字回復していますから、2014年入試では応募者数の増加が予想されます。 多摩地区は男女御三家のような伝統的な別学校がなく、戦後に創立された共学校と都心から移転してきた学校(付属校が多い)が主流です。そのなかで今年の入試で一番元気がよかったのは東京電機大(小金井市)です。1992年に都心から現在地に移転し、1996年に中学校を開校、1999年には中高を同時に共学化し、2012年春は東工大2名、阪大1名、早慶43名など好調な大学合格実績で、2013年入試の応募者は総計で1,128→1,306名と16%増でした。受験者数では686→907名で32%増です。1回は合格者を絞ったため倍率が大きく上昇し難易度もアップしています。近年理系志向の上昇傾向も見られるなかで目の離せない学校です。
東京は学校数が非常に多くまだまだ触れておきたい学校もありますが、ひとまず東京の2013年私立中入試の状況についてのレポートを終えます。なお国立大付属校と公立中高一貫校については、あらためて別の機会にお伝えする予定です。次回は神奈川の入試状況のレポートです。