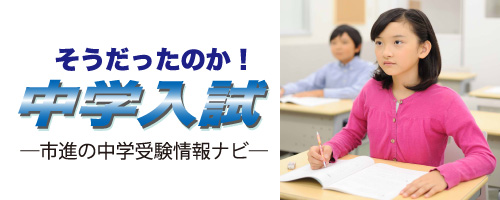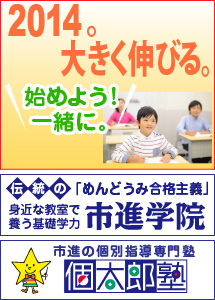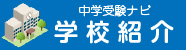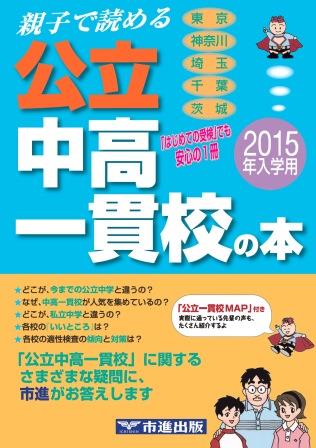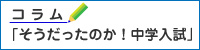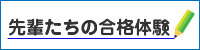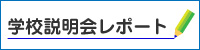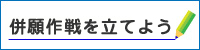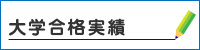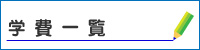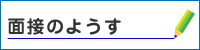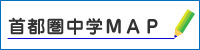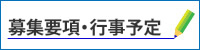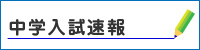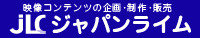トップページ > コラム「そうだったのか!中学入試」第41~50話 > 第46話「2013年 首都圏公立中高一貫校の入試状況(2)」
第46話「2013年 首都圏公立中高一貫校の入試状況(2)」
2013年7月29日
今回は前回の東京に続き、神奈川、千葉、埼玉、茨城の公立中高一貫校の2013年入試状況についてお伝えしていきます。なお中高一貫校は①中等教育学校、②併設型、③連携型の3種類がありますが、ここでは①と②のみを扱います。また応募状況の数字は2012年応募者数→2013年応募者数および増減率(%)で、Mが男子、Fは女子です。
(1)神奈川の公立中高一貫校
神奈川の公立中高一貫校は県立が2校、横浜市立が1校で計3校です。神奈川県には人口370万人で東京23区につぎ全国2位の横浜市と人口143万人で全国8位の川崎市があり、県は県立中高一貫校を当初より市立高校を設置している横浜市、川崎市、横須賀市の3市を除く地域に設置しました。言い換えれば県立の2校は県の中心部をはずして開校したわけです。そして上記の3市については一貫教育校の設置そのものがそれぞれの市に任されていました。それではまず3校の応募状況をまとめておきます。

県立相模原 2009年に開校した県立相模原(相模原市南区)は1期生が5年生になりました。(なお紛らわしいのですが、県立相模原中等教育学校と県立相模原高校は別の学校です)昨年は横浜市立南高附中学校の開校の影響か県立相模原の応募者は女子が若干減りましたが、男子は16%増でした。2013年は前年増えた男子の応募者が754→703名と7%減、女子は前年の2%減に続いて811→791名と2%減ですが、難易度は男女ともにむしろ上昇気味です。
県立平塚(平塚市)も県立相模原と同時開校ですから1期生が5年生になっています。県の中心部からかなり外れているため応募者は県立相模原や横浜市立南高附の半分強ですが、応募者は3年連続で増えています。また私立中が少ない地域で公立志向が強い地域性もあり、他の2校に比べて試験当日の欠席者が少なく第一志望者中心の安定した選抜になっています。母体校の県立大原高校は部活動が盛んな中堅レベルの学校でしたが、中等教育学校としてスタートして5年目となり、高いレベルの学習活動、進路指導やキャリア教育の取り組みなどの教育内容が徐々に理解されてきているのが3年連続応募者増加の要因でしょう。

横浜市立南高附 3校の中で最も注目を集めているのが昨年開校した横浜市立南高附(横浜市港南区)です。横浜市で初の公立中高一貫校として、開校初年度の前年は1,700名近い応募者を集めましたが、2年目の今年は多くの公立一貫校の2年目と同様に応募者がかなり減っています。しかし減っているのは、初年度入試の高倍率を見て敬遠した層だったようで、むしろしっかり適性検査対策をしてきた受検生による厳しい競争になっています。多くの私立中学があり私立中受験率が高い地域であることを踏まえ、私立中受験者を意識した適性検査の出題や、明確に大学進学を目標としたカリキュラムなど私立中高一貫校との親和性も高く、予想通り私立中併願者が増えています。併願先は栄光学園、フェリス女学院、慶應湘南などの最難関レベルから、これらに次ぐ横浜共立や鎌倉女学院、あるいは神奈川大付、山手学院や中央大横浜などの中堅上位の共学校などと幅広く、県内の多くの私立中に影響を与えています。特に女子は上位層の厚みが増して上位校との併願者が多く、そのため難関私学に合格した受検生の辞退者も相当な人数が出ています。しかし逆に男子でも栄光学園、女子ではフェリス女学院などに合格しても本校を選んだ受検生もいました。男女各80名の定員ですが、合格者の決定にあたり、まず男女それぞれ70名を決めて、残りの20名と繰り上げ合格者は男女の区別なく成績順に決める選考方法のため、最初の正規合格者は男子70名、女子90名と女子が20名も多くなっています。繰り上げ後の最終的な入学者は男子75名、女子85名です。急速に入学者のレベルも上昇していて、間違いなく来年もさらに人気が上がっていきそうです。
なお来春2014年4月に川崎市立川崎高校に附属中学校が開校し、県内の公立一貫校は4校になります。7月に募集要項が発表されましたので、以下に概要を記しておきます。
また横須賀市教育委員会は横須賀市立横須賀総合高校を一貫教育校に改編する方向で検討を進めていて、早ければ2017年に開校する可能性があります。
(2)千葉の公立中高一貫校
千葉の公立中高一貫校は県立が1校、千葉市立が1校で計2校です。まず2007年4月に千葉市立稲毛高校に附属中学校が設置され、翌2008年4月に千葉県のみならず全国的にも公立でトップレベルの県立千葉高校に附属中学校が設置されました。
まず2校の応募状況をまとめておきます。

市立稲毛高附中 市立稲毛高附中(千葉市美浜区)はここ数年男子が300名台、女子が400名台で推移しています。2013年入試の応募者は男子が371→374名と前年並みでしたが、女子は2011年に446→483と大きく増え12倍近い高倍率で敬遠されたのか、その後は483→462→454名と少しずつ減っています。とはいえ開校7年目でも応募倍率で男子9.1倍、女子10.9倍は首都圏の公立一貫校では非常に高い水準の倍率です。本校が開校して2年目に千葉市内に県立千葉中が開校し、上位層は県立千葉中に集中し棲み分けができているようで、今年の入試の難易度もほぼ例年並みでした。しかし今春一貫1期生が卒業し大学合格実績が出たことによって入試状況にも変化が出てくる可能性があります。本校の母体となった市立稲毛高校は県内公立高校のなかでは中堅上位の学校で、高校募集だけだった最後の学年が卒業した2012年春は、卒業生317名で現役では国公立大が19名、早慶上智大が8名、MARCH大が97名でした。国公立大19名のうち旧帝大は0名で千葉大9名、電通大2名などが主なところです。それに対してこの春卒業した一貫1期生80名の実績(当然全員現役です)は京大2名、東北大2名、名古屋大1名と旧帝大に5名を含め国公立大14(18)名、早慶上智大は11(16)名、MARCH大が32(106)名と明らかに難関大合格実績が上がっているのがわかります。(( )内は高入生の現役合格者数。学年8クラスのうち一貫生が2クラス分、高入生は6クラス分です)
千葉市内の受検生のうち上位層は県立千葉中を受検するでしょうが、その次のレベルの受検生の中にはこの大学合格実績を見て県立千葉中ではなく市立稲毛高附中を選ぶ受検生も増える可能性があります。県立千葉中から回ってくる受検生は従来の本校の受検生からすれば上位層になると思われ、難易度が上昇する可能性があり要注意です。

県立千葉中 県立千葉中(千葉市中央区)は前述のように母体の県立千葉高校が公立では全国的にもトップレベルの学校で、今春の大学合格実績は卒業生325名に対し現浪合わせて、東大25名を含め国公立大が167名、早慶上智大は328名でした。附属中学は間違いなく全国の公立中高一貫校で最も難易度の高い学校です。開校して6年目、1期生が高3になり来春の進路結果が注目されるところです。
開校初年度の2008年入試では2,165名という大変な数の応募者がありましたが、他の公立一貫校同様に2年目は1,348名と38%の大幅減となり、その後は少しずつ減って今春の入試では1,159→1,077名と7%減でした。一次で定員のほぼ4倍(2010年までは約6倍)まで絞り、二次で男女各40名の合格者を決定する2段階選抜方式ですが、応募者が減少傾向とはいえ一次の応募者から二次合格者までの形式倍率は男子14.7倍、女子12.2倍と男女ともに10倍を超える高倍率で、これは首都圏のみならず全国の公立一貫校で最も高い倍率です。また応募者の減少傾向が続いていますが、明らかに減っているのはチャレンジ層で、上位層はむしろ増加傾向にあるようです。
二次の合格発表は2月1日で、昨年から入学確約書の提出期限が2月4日と遅くなったため2012年入試では難関私立中との併願者が増えて、追加合格も増えましたが難易度はやや上昇しました。今年も難易度は男女ともに前年並みでしたが、特に男子で難関私立中との併願者が増えているようです。これは入試日程から予想できるだけでなく、一次合格者のうち二次を棄権している人数の増加からも見てとることができます。
開校以来6年間の二次検査欠席者数の推移を男女別に見ると、
男子 4→4→1→3→10→19名
女子 3→3→3→4→10→9名
と昨年から大きく増加しており、特に男子は今年さらに2倍近く増えていることがわかります。体調不良などのケースを除き二次を棄権するのは、二次検査日の1月23日までに合格発表のあった私立中に合格し、そちらを進学先として選ぶ(優先順位が高い)場合に限られ、入試日程や入試レベルから見てこれに該当する学校は、県内では1月22日に合格発表を行った市川中の1回、県外では合格発表が1月12日の栄東の東大Ⅰ、開智の先端Aあたりでしょう。なお渋谷教育学園幕張の1次と東邦大付東邦の前期は合格発表が1月24日と23日でしたから上記には該当しません。
また入学確約書の提出期限の2月4日までには、1都3県の主要な難関私立中が合格発表を終えていえるため、二次を受検して合格しても、入学手続きを取らない受検生も増えているようで、人数は非公表ですが相当数の追加合格が出ています。
(3)埼玉の公立中高一貫校
埼玉の公立中高一貫校は県立が1校、さいたま市立が1校で計2校、いずれも併設型一貫校です。2003年に首都圏初の公立一貫校として県立伊奈学園総合高校に県立伊奈学園中学校が設置され、2007年にさいたま市立浦和高校に中学校が設置されました。
まず2校の応募状況をまとめておきます。
県立伊奈学園中(伊奈町)の母体となった県立伊奈学園総合高校は全国初の総合選択制の普通科高校(総合学科ではありません)で、県内の公立高校では中堅レベルの学校です。東京ドーム3個分以上の広大な敷地に6棟の校舎および管理棟、芸術棟、また4つの体育館、野球場、サッカー場、ラグビー場、ソフトボール場、テニスコートなどのほか、自動車教習棟まであり、1学年が18クラスで800名と公立高校では全国最大の高校です。全体を縦割りの6ブロックに分けたハウス制をとっていて、各ハウスはハウス長(教頭)と約30名の教員のもとそれぞれの棟で生活します。伊奈学園中学校は第1ハウスに入っています。高校2年次からは人文系、理数系、語学系、芸術系、スポーツ科学系、生活科学系、情報経営系の7学系から選択するという独特のシステムをとっている学校です。
中学の入試では男女別の定員がなく、他の都県と異なり、さいたま市在住の受検生は伊奈学園中と市立浦和中を併願することが可能です。昨年までは一次選考が抽選で200名(2010年までは180名)まで絞り、二次選考は作文と面接で80名の合格者を決定していました。しかし抽選については受検生に不満が多いこともあり2013年入試から廃止され、一次選考が作文、二次選考は面接になりました。なお「作文」と称していますが、実質的には他の公立一貫校の適性検査とほぼ同じものと考えてよいでしょう。
抽選廃止によって応募者が950→712名と25%の大幅減となりましたが、これは都内の国立大学付属中各校が抽選を廃止した時に例外なく見られたのと同じ現象です。ようするに抽選で倍率が絞られることに期待していた受検生―その多くは作文に自信がない受検生でしょう―が受検を取りやめた結果です。したがって減っているのは主にチャレンジ層で、作文対策をしっかりやってきた受検生は抽選で予選落ちになることがなくなっため、逆に増えているものと思われます。応募者数が大幅減で倍率も下がっていますが、受検生のレベルが上がり、特に中上位層が厚くなっているため難易度もやや上昇しています。

さいたま市立浦和中 さいたま市立浦和中(さいたま市浦和区)は開校7年目を迎えました。母体となった市立浦和高校は県内の公立高校ではトップ校につぐ位置にある学校です。県立浦和、浦和一女、川越、川越女子など県立トップの伝統校の多くが別学のため、学力最上位層でも共学志向の受検生は本校を選ぶこともあるようです。中学校の入試は1次選抜が適性検査、2次選抜が作文と個人面接、グループ討論による2段階選抜です。開校初年度は2,018名の応募者を集めましたが、2年目には1,191名と激減し、その後少しずつ減って、前年の応募者は723名でした。2013年入試では伊奈学園中の抽選廃止の影響が注目されましたが、723→582名と20%減となり両校ともに応募者減となっています。ランク的にはかなり市立浦和中のほうが上ですから、直接的な影響はほとんどなかったようです。難易度は男子が前年並みで、女子はわずかに下がっているようです。
今春一貫1期生が卒業し、東大1名、東北大1名、一橋大1名、東京外語大1名、自治医大1名、筑波大3名、埼玉大6名など国公立大計28名、早慶上智大38名、MARCH大68名と素晴らしい実績をあげました。中学は2クラスで80名規模の学校ですから相当に良い実績といえるでしょう。2014年入試ではこの大学合格実績により人気が上がって、応募者が急増する可能性があり要注意です。
(4)茨城の公立中高一貫校
茨城の公立中高一貫校は県立が3校で、そのうち2校が中等教育型で1校が併設型です。まず2008年に筑波研究学園都市にある県立並木高校を母体校として県立並木中等教育学校が開校し、少し間が空いて昨年2012年に県北の日立第一高校を母体校として日立第一高校附属中学校が開校、そして今年2013年に県立総和高校を母体校として古河中等教育学校が開校しました。
まず3校の応募状況をまとめておきます。
茨城の公立一貫校3校は県南地区のつくば市、県北地区の日立市、県西地区の古河市に設置され、立地や交通事情からそれぞれのエリアで完結した入試になっていているため、複数の公立一貫校の中から受検校を選ぶことはほとんどありません。また県南地区以外は私立中学校が少なく、ほとんどが公立1本の受検生のようです。

県立並木中等教育学校 県内初の公立一貫校の県立並木中等教育学校(つくば市)は開校6年目をむかえ1年から6年までそろいました。学校がある筑波研究学園都市には大学の他、産業技術総合研究所や筑波宇宙センターなどの多くの研究機関があり、教育熱心な家庭が多く県内のみならず千葉や東京の私立中も受験している県内ではやや特殊な地域です。本校の生徒は地元のつくば市のほか、牛久市、土浦市を中心に県南地区全域および県西地区の一部から通学しています。地域性もあってか科学教育と国際理解教育が重視され、昨年には文科省からSSH(スーパー・サイエンス・ハイスクール)の指定を受けています。
定員は最初の2年間は男女各60名でしたが、3年目から増員され男女各80名の計160名です。選抜は適性検査と面接によって行われ、適性検査の問題は3校統一問題です。開校初年度は852名の受検生を集め、2年目以降は年によって多少の増減はありますが、600名台後半から700名台で推移。前年は男子が9%増で、女子は11%減と男女で志望動向が異なりました。2013年入試では検査日が1月7日から12日に変わり、近隣の私立中の入試日とずれたこともあって、男子は369→370名と1名増でしたが、女子は前年の減少の反動もあり355→418名と18%と相当に増加。その結果男女とも応募者数は開校初年度に次ぐ人数となりました。なお前年まで公表していた追加合格数を今年は公表していませんが、過去の例から見て15名前後と思われます。
2014年3月には1期生が卒業しますから、その大学合格実績が注目されますが、期待感が高くなって応募者がさらに増える可能性もありそうです。
昨年開校した県立日立第一高校附中(日立市)の母体になった県立日立第一高校は県北地区の名門校で、県内トップの県立水戸第一高校、土浦第一高校に次ぐ「進学重視型単位制高校」で本校も文科省からSSHの指定を受けています。今春の卒業生は317名で国公立大学現役合格者は125名でした(現浪計では163名)。
中学校開校2年目の2013年入試では他の公立一貫校に見られるように応募者が428→390名と9%減となりました。これは気軽に受検してもとても合格できるものではないことがわかって敬遠されたためでしょう。前年に比べて市内からの受検生が減り、周辺からの受検生が増えていますが、市内が減ったのは、近所なのでとりあえず受けてみようという受検生が減ったということで、周辺部が増えたのは本気の受検生が増えたということでしょう。したがって応募者が減って倍率も若干下がっていますが、難易度は変わっていません。
なお日立市には私立中学はミッション系大学の付属校の1校だけですが、JR常磐線で30~40分の水戸には国立の茨城大付属中や私立では水戸英宏中など3校があり、特に茨城大付属中との併願者はかなりいるようです。
県内3校目の公立一貫校として今春開校した県西地区の県立古河中等教育学校(古河市)は、他の2校に比べて立地や母体校の知名度などの条件に恵まれていませんが、地元古河市や古河市医師会などの強い要望があり開校にいたりました。茨城県には県立高校受検について隣接する5県との隣接県協定があり、埼玉県と栃木県に隣接する古河市からは埼玉県、栃木県、および群馬県、千葉県の県立高校を受検することができます。そのため以前から市内中学校卒業生がかなり県外に流出していました。なんとか流出を抑えたい古河市、また地域医療に携わる医師の養成が期待できる進学校の設置を求める古河市医師会、さらに日野自動車の進出にともない従業員の子供たちの教育環境の整備をもとめる声が強力に六年制の一貫校の開校を推進したようです。
母体校の県立総和高校は県内公立高校の中では比較的入学しやすいレベルの中堅校です。 しかし上記のような開校に至る事情もあり、新校は開設準備段階から母体校のイメージを払しょくし、先行する一貫教育校の最先端のプログラムを導入し、進学校として学校づくりに取り組んでいました。
2013年入試ではもともと中学受検の土壌がない地域性(古河市とその周辺には私立中学はなく、一番近いのは埼玉の開智未来中)もあるのか、開校初年度の応募者数は、前年開校の県立日立第一高校附中の428名に比してもかなり少ない326名となっています。倍率も県立並木中等教育学校と県立日立第一高校附中の4.8倍に対し2.8倍と緩やかになっています。市内および周辺に4方面5コースのスクールバス(有料)が運行されているため、受検生は古河市のほか、結城市、坂東市、桜川市、下妻市、筑西市、堺町、八千代町、五霞町などから来ています。なおほとんどの受検生は私立中学との併願はせず古河中等教育学校1本だったようです。
(1)神奈川の公立中高一貫校
神奈川の公立中高一貫校は県立が2校、横浜市立が1校で計3校です。神奈川県には人口370万人で東京23区につぎ全国2位の横浜市と人口143万人で全国8位の川崎市があり、県は県立中高一貫校を当初より市立高校を設置している横浜市、川崎市、横須賀市の3市を除く地域に設置しました。言い換えれば県立の2校は県の中心部をはずして開校したわけです。そして上記の3市については一貫教育校の設置そのものがそれぞれの市に任されていました。それではまず3校の応募状況をまとめておきます。
| ・県立相模原中等教育学校 |
M 754→703(-7%) F 811→791(-2%) 計 1,567→1,494(-5%) |
| ・県立平塚中等教育学校 | M 400→407(+2%) F 481→488(+1%) 計 881→895(+2%) |
| ・横浜市立南高附中学校 | M 815→686(-16%) F 952→907(-5%) 計 1,697→1,520(-10%) |

県立相模原 2009年に開校した県立相模原(相模原市南区)は1期生が5年生になりました。(なお紛らわしいのですが、県立相模原中等教育学校と県立相模原高校は別の学校です)昨年は横浜市立南高附中学校の開校の影響か県立相模原の応募者は女子が若干減りましたが、男子は16%増でした。2013年は前年増えた男子の応募者が754→703名と7%減、女子は前年の2%減に続いて811→791名と2%減ですが、難易度は男女ともにむしろ上昇気味です。
県立平塚(平塚市)も県立相模原と同時開校ですから1期生が5年生になっています。県の中心部からかなり外れているため応募者は県立相模原や横浜市立南高附の半分強ですが、応募者は3年連続で増えています。また私立中が少ない地域で公立志向が強い地域性もあり、他の2校に比べて試験当日の欠席者が少なく第一志望者中心の安定した選抜になっています。母体校の県立大原高校は部活動が盛んな中堅レベルの学校でしたが、中等教育学校としてスタートして5年目となり、高いレベルの学習活動、進路指導やキャリア教育の取り組みなどの教育内容が徐々に理解されてきているのが3年連続応募者増加の要因でしょう。

横浜市立南高附 3校の中で最も注目を集めているのが昨年開校した横浜市立南高附(横浜市港南区)です。横浜市で初の公立中高一貫校として、開校初年度の前年は1,700名近い応募者を集めましたが、2年目の今年は多くの公立一貫校の2年目と同様に応募者がかなり減っています。しかし減っているのは、初年度入試の高倍率を見て敬遠した層だったようで、むしろしっかり適性検査対策をしてきた受検生による厳しい競争になっています。多くの私立中学があり私立中受験率が高い地域であることを踏まえ、私立中受験者を意識した適性検査の出題や、明確に大学進学を目標としたカリキュラムなど私立中高一貫校との親和性も高く、予想通り私立中併願者が増えています。併願先は栄光学園、フェリス女学院、慶應湘南などの最難関レベルから、これらに次ぐ横浜共立や鎌倉女学院、あるいは神奈川大付、山手学院や中央大横浜などの中堅上位の共学校などと幅広く、県内の多くの私立中に影響を与えています。特に女子は上位層の厚みが増して上位校との併願者が多く、そのため難関私学に合格した受検生の辞退者も相当な人数が出ています。しかし逆に男子でも栄光学園、女子ではフェリス女学院などに合格しても本校を選んだ受検生もいました。男女各80名の定員ですが、合格者の決定にあたり、まず男女それぞれ70名を決めて、残りの20名と繰り上げ合格者は男女の区別なく成績順に決める選考方法のため、最初の正規合格者は男子70名、女子90名と女子が20名も多くなっています。繰り上げ後の最終的な入学者は男子75名、女子85名です。急速に入学者のレベルも上昇していて、間違いなく来年もさらに人気が上がっていきそうです。
なお来春2014年4月に川崎市立川崎高校に附属中学校が開校し、県内の公立一貫校は4校になります。7月に募集要項が発表されましたので、以下に概要を記しておきます。
| ・募集定員 | 120名(男女別の定員はありません) |
| ・通学区域 | 川崎市全域(市外枠はありません) |
| ・受付期間 | 1月8日~1月10日までに簡易書留で郵送 (消印可) |
| ・検査方法 | 作文を含む適性検査及び面接 |
| ・検査期日 | 2月3日 |
| ・合格発表 | 2月10日 |
また横須賀市教育委員会は横須賀市立横須賀総合高校を一貫教育校に改編する方向で検討を進めていて、早ければ2017年に開校する可能性があります。
(2)千葉の公立中高一貫校
千葉の公立中高一貫校は県立が1校、千葉市立が1校で計2校です。まず2007年4月に千葉市立稲毛高校に附属中学校が設置され、翌2008年4月に千葉県のみならず全国的にも公立でトップレベルの県立千葉高校に附属中学校が設置されました。
まず2校の応募状況をまとめておきます。
| ・千葉市立稲毛高附中 | M 371→374(+1%) F 462→454(-2%) 計 833→828(-1%) |
| ・県立千葉中1次 | M 635→589(+2%) F 524→488(-7%) 計 1,159→1,077 (-7%) |

市立稲毛高附中 市立稲毛高附中(千葉市美浜区)はここ数年男子が300名台、女子が400名台で推移しています。2013年入試の応募者は男子が371→374名と前年並みでしたが、女子は2011年に446→483と大きく増え12倍近い高倍率で敬遠されたのか、その後は483→462→454名と少しずつ減っています。とはいえ開校7年目でも応募倍率で男子9.1倍、女子10.9倍は首都圏の公立一貫校では非常に高い水準の倍率です。本校が開校して2年目に千葉市内に県立千葉中が開校し、上位層は県立千葉中に集中し棲み分けができているようで、今年の入試の難易度もほぼ例年並みでした。しかし今春一貫1期生が卒業し大学合格実績が出たことによって入試状況にも変化が出てくる可能性があります。本校の母体となった市立稲毛高校は県内公立高校のなかでは中堅上位の学校で、高校募集だけだった最後の学年が卒業した2012年春は、卒業生317名で現役では国公立大が19名、早慶上智大が8名、MARCH大が97名でした。国公立大19名のうち旧帝大は0名で千葉大9名、電通大2名などが主なところです。それに対してこの春卒業した一貫1期生80名の実績(当然全員現役です)は京大2名、東北大2名、名古屋大1名と旧帝大に5名を含め国公立大14(18)名、早慶上智大は11(16)名、MARCH大が32(106)名と明らかに難関大合格実績が上がっているのがわかります。(( )内は高入生の現役合格者数。学年8クラスのうち一貫生が2クラス分、高入生は6クラス分です)
千葉市内の受検生のうち上位層は県立千葉中を受検するでしょうが、その次のレベルの受検生の中にはこの大学合格実績を見て県立千葉中ではなく市立稲毛高附中を選ぶ受検生も増える可能性があります。県立千葉中から回ってくる受検生は従来の本校の受検生からすれば上位層になると思われ、難易度が上昇する可能性があり要注意です。

県立千葉中 県立千葉中(千葉市中央区)は前述のように母体の県立千葉高校が公立では全国的にもトップレベルの学校で、今春の大学合格実績は卒業生325名に対し現浪合わせて、東大25名を含め国公立大が167名、早慶上智大は328名でした。附属中学は間違いなく全国の公立中高一貫校で最も難易度の高い学校です。開校して6年目、1期生が高3になり来春の進路結果が注目されるところです。
開校初年度の2008年入試では2,165名という大変な数の応募者がありましたが、他の公立一貫校同様に2年目は1,348名と38%の大幅減となり、その後は少しずつ減って今春の入試では1,159→1,077名と7%減でした。一次で定員のほぼ4倍(2010年までは約6倍)まで絞り、二次で男女各40名の合格者を決定する2段階選抜方式ですが、応募者が減少傾向とはいえ一次の応募者から二次合格者までの形式倍率は男子14.7倍、女子12.2倍と男女ともに10倍を超える高倍率で、これは首都圏のみならず全国の公立一貫校で最も高い倍率です。また応募者の減少傾向が続いていますが、明らかに減っているのはチャレンジ層で、上位層はむしろ増加傾向にあるようです。
二次の合格発表は2月1日で、昨年から入学確約書の提出期限が2月4日と遅くなったため2012年入試では難関私立中との併願者が増えて、追加合格も増えましたが難易度はやや上昇しました。今年も難易度は男女ともに前年並みでしたが、特に男子で難関私立中との併願者が増えているようです。これは入試日程から予想できるだけでなく、一次合格者のうち二次を棄権している人数の増加からも見てとることができます。
開校以来6年間の二次検査欠席者数の推移を男女別に見ると、
男子 4→4→1→3→10→19名
女子 3→3→3→4→10→9名
と昨年から大きく増加しており、特に男子は今年さらに2倍近く増えていることがわかります。体調不良などのケースを除き二次を棄権するのは、二次検査日の1月23日までに合格発表のあった私立中に合格し、そちらを進学先として選ぶ(優先順位が高い)場合に限られ、入試日程や入試レベルから見てこれに該当する学校は、県内では1月22日に合格発表を行った市川中の1回、県外では合格発表が1月12日の栄東の東大Ⅰ、開智の先端Aあたりでしょう。なお渋谷教育学園幕張の1次と東邦大付東邦の前期は合格発表が1月24日と23日でしたから上記には該当しません。
また入学確約書の提出期限の2月4日までには、1都3県の主要な難関私立中が合格発表を終えていえるため、二次を受検して合格しても、入学手続きを取らない受検生も増えているようで、人数は非公表ですが相当数の追加合格が出ています。
(3)埼玉の公立中高一貫校
埼玉の公立中高一貫校は県立が1校、さいたま市立が1校で計2校、いずれも併設型一貫校です。2003年に首都圏初の公立一貫校として県立伊奈学園総合高校に県立伊奈学園中学校が設置され、2007年にさいたま市立浦和高校に中学校が設置されました。
まず2校の応募状況をまとめておきます。
| ・県立伊奈学園中 | M ?→374(――) F ?→454(――) 計 950→712(-25%) *2012年入試までは男女別人数非公表 |
| ・さいたま市立浦和中 | M 344→282(-18%) F 379→305(-20%) 計 723→582(-20%) |
県立伊奈学園中(伊奈町)の母体となった県立伊奈学園総合高校は全国初の総合選択制の普通科高校(総合学科ではありません)で、県内の公立高校では中堅レベルの学校です。東京ドーム3個分以上の広大な敷地に6棟の校舎および管理棟、芸術棟、また4つの体育館、野球場、サッカー場、ラグビー場、ソフトボール場、テニスコートなどのほか、自動車教習棟まであり、1学年が18クラスで800名と公立高校では全国最大の高校です。全体を縦割りの6ブロックに分けたハウス制をとっていて、各ハウスはハウス長(教頭)と約30名の教員のもとそれぞれの棟で生活します。伊奈学園中学校は第1ハウスに入っています。高校2年次からは人文系、理数系、語学系、芸術系、スポーツ科学系、生活科学系、情報経営系の7学系から選択するという独特のシステムをとっている学校です。
中学の入試では男女別の定員がなく、他の都県と異なり、さいたま市在住の受検生は伊奈学園中と市立浦和中を併願することが可能です。昨年までは一次選考が抽選で200名(2010年までは180名)まで絞り、二次選考は作文と面接で80名の合格者を決定していました。しかし抽選については受検生に不満が多いこともあり2013年入試から廃止され、一次選考が作文、二次選考は面接になりました。なお「作文」と称していますが、実質的には他の公立一貫校の適性検査とほぼ同じものと考えてよいでしょう。
抽選廃止によって応募者が950→712名と25%の大幅減となりましたが、これは都内の国立大学付属中各校が抽選を廃止した時に例外なく見られたのと同じ現象です。ようするに抽選で倍率が絞られることに期待していた受検生―その多くは作文に自信がない受検生でしょう―が受検を取りやめた結果です。したがって減っているのは主にチャレンジ層で、作文対策をしっかりやってきた受検生は抽選で予選落ちになることがなくなっため、逆に増えているものと思われます。応募者数が大幅減で倍率も下がっていますが、受検生のレベルが上がり、特に中上位層が厚くなっているため難易度もやや上昇しています。

さいたま市立浦和中 さいたま市立浦和中(さいたま市浦和区)は開校7年目を迎えました。母体となった市立浦和高校は県内の公立高校ではトップ校につぐ位置にある学校です。県立浦和、浦和一女、川越、川越女子など県立トップの伝統校の多くが別学のため、学力最上位層でも共学志向の受検生は本校を選ぶこともあるようです。中学校の入試は1次選抜が適性検査、2次選抜が作文と個人面接、グループ討論による2段階選抜です。開校初年度は2,018名の応募者を集めましたが、2年目には1,191名と激減し、その後少しずつ減って、前年の応募者は723名でした。2013年入試では伊奈学園中の抽選廃止の影響が注目されましたが、723→582名と20%減となり両校ともに応募者減となっています。ランク的にはかなり市立浦和中のほうが上ですから、直接的な影響はほとんどなかったようです。難易度は男子が前年並みで、女子はわずかに下がっているようです。
今春一貫1期生が卒業し、東大1名、東北大1名、一橋大1名、東京外語大1名、自治医大1名、筑波大3名、埼玉大6名など国公立大計28名、早慶上智大38名、MARCH大68名と素晴らしい実績をあげました。中学は2クラスで80名規模の学校ですから相当に良い実績といえるでしょう。2014年入試ではこの大学合格実績により人気が上がって、応募者が急増する可能性があり要注意です。
(4)茨城の公立中高一貫校
茨城の公立中高一貫校は県立が3校で、そのうち2校が中等教育型で1校が併設型です。まず2008年に筑波研究学園都市にある県立並木高校を母体校として県立並木中等教育学校が開校し、少し間が空いて昨年2012年に県北の日立第一高校を母体校として日立第一高校附属中学校が開校、そして今年2013年に県立総和高校を母体校として古河中等教育学校が開校しました。
まず3校の応募状況をまとめておきます。
| ・県立並木中等教育学校 | M 369→370(±0%) F 355→418(+18%) 計 724→788(+9%) |
| ・県立日立第一高校附中 | M 223→205(-8%) F 205→185(-10%) 計 428→390(-9%) |
| ・県立古河中等教育学校 | M 149(――) F 177(――) 計 326(――) *古河中等教育学校は今春開校 |
茨城の公立一貫校3校は県南地区のつくば市、県北地区の日立市、県西地区の古河市に設置され、立地や交通事情からそれぞれのエリアで完結した入試になっていているため、複数の公立一貫校の中から受検校を選ぶことはほとんどありません。また県南地区以外は私立中学校が少なく、ほとんどが公立1本の受検生のようです。

県立並木中等教育学校 県内初の公立一貫校の県立並木中等教育学校(つくば市)は開校6年目をむかえ1年から6年までそろいました。学校がある筑波研究学園都市には大学の他、産業技術総合研究所や筑波宇宙センターなどの多くの研究機関があり、教育熱心な家庭が多く県内のみならず千葉や東京の私立中も受験している県内ではやや特殊な地域です。本校の生徒は地元のつくば市のほか、牛久市、土浦市を中心に県南地区全域および県西地区の一部から通学しています。地域性もあってか科学教育と国際理解教育が重視され、昨年には文科省からSSH(スーパー・サイエンス・ハイスクール)の指定を受けています。
定員は最初の2年間は男女各60名でしたが、3年目から増員され男女各80名の計160名です。選抜は適性検査と面接によって行われ、適性検査の問題は3校統一問題です。開校初年度は852名の受検生を集め、2年目以降は年によって多少の増減はありますが、600名台後半から700名台で推移。前年は男子が9%増で、女子は11%減と男女で志望動向が異なりました。2013年入試では検査日が1月7日から12日に変わり、近隣の私立中の入試日とずれたこともあって、男子は369→370名と1名増でしたが、女子は前年の減少の反動もあり355→418名と18%と相当に増加。その結果男女とも応募者数は開校初年度に次ぐ人数となりました。なお前年まで公表していた追加合格数を今年は公表していませんが、過去の例から見て15名前後と思われます。
2014年3月には1期生が卒業しますから、その大学合格実績が注目されますが、期待感が高くなって応募者がさらに増える可能性もありそうです。
昨年開校した県立日立第一高校附中(日立市)の母体になった県立日立第一高校は県北地区の名門校で、県内トップの県立水戸第一高校、土浦第一高校に次ぐ「進学重視型単位制高校」で本校も文科省からSSHの指定を受けています。今春の卒業生は317名で国公立大学現役合格者は125名でした(現浪計では163名)。
中学校開校2年目の2013年入試では他の公立一貫校に見られるように応募者が428→390名と9%減となりました。これは気軽に受検してもとても合格できるものではないことがわかって敬遠されたためでしょう。前年に比べて市内からの受検生が減り、周辺からの受検生が増えていますが、市内が減ったのは、近所なのでとりあえず受けてみようという受検生が減ったということで、周辺部が増えたのは本気の受検生が増えたということでしょう。したがって応募者が減って倍率も若干下がっていますが、難易度は変わっていません。
なお日立市には私立中学はミッション系大学の付属校の1校だけですが、JR常磐線で30~40分の水戸には国立の茨城大付属中や私立では水戸英宏中など3校があり、特に茨城大付属中との併願者はかなりいるようです。
県内3校目の公立一貫校として今春開校した県西地区の県立古河中等教育学校(古河市)は、他の2校に比べて立地や母体校の知名度などの条件に恵まれていませんが、地元古河市や古河市医師会などの強い要望があり開校にいたりました。茨城県には県立高校受検について隣接する5県との隣接県協定があり、埼玉県と栃木県に隣接する古河市からは埼玉県、栃木県、および群馬県、千葉県の県立高校を受検することができます。そのため以前から市内中学校卒業生がかなり県外に流出していました。なんとか流出を抑えたい古河市、また地域医療に携わる医師の養成が期待できる進学校の設置を求める古河市医師会、さらに日野自動車の進出にともない従業員の子供たちの教育環境の整備をもとめる声が強力に六年制の一貫校の開校を推進したようです。
母体校の県立総和高校は県内公立高校の中では比較的入学しやすいレベルの中堅校です。 しかし上記のような開校に至る事情もあり、新校は開設準備段階から母体校のイメージを払しょくし、先行する一貫教育校の最先端のプログラムを導入し、進学校として学校づくりに取り組んでいました。
2013年入試ではもともと中学受検の土壌がない地域性(古河市とその周辺には私立中学はなく、一番近いのは埼玉の開智未来中)もあるのか、開校初年度の応募者数は、前年開校の県立日立第一高校附中の428名に比してもかなり少ない326名となっています。倍率も県立並木中等教育学校と県立日立第一高校附中の4.8倍に対し2.8倍と緩やかになっています。市内および周辺に4方面5コースのスクールバス(有料)が運行されているため、受検生は古河市のほか、結城市、坂東市、桜川市、下妻市、筑西市、堺町、八千代町、五霞町などから来ています。なおほとんどの受検生は私立中学との併願はせず古河中等教育学校1本だったようです。