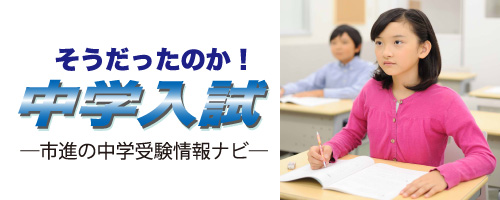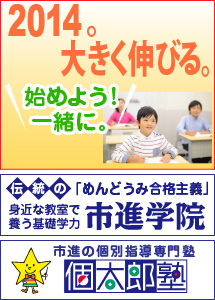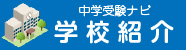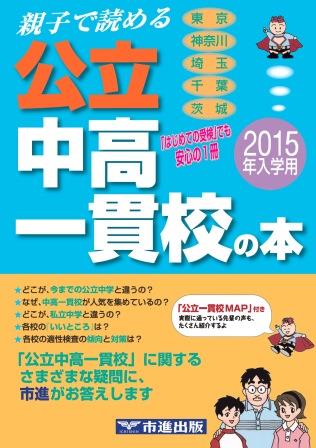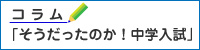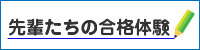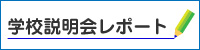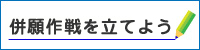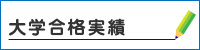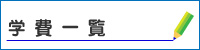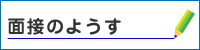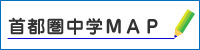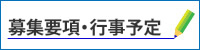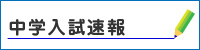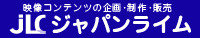トップページ > コラム「そうだったのか!中学入試」第41~50話 > 第50話 「2014年中学入試予想 第1弾 ――9月公開模試から入試動向を読む――」
第50話 「2014年中学入試予想 第1弾 ――9月公開模試から入試動向を読む――」
2013年11月8日
1.男子校・・・2013年11月1日更新
2.女子校・・・2013年11月5・8日更新
3.共学校・・・2013年11月12・15日・19日更新
いよいよ中学入試も秋の陣。入試にむけて勉強はもとより志望校の選択も正念場を迎える時期に入ってきているものと思います。多くの受験生が参加する公開模試も9月から本格的になってきました。本稿では9月以降の注目すべき動きから2014年入試を予測します。もちろんまだ最終的な段階ではありませんので、流動的な要素もあることを留意しながら見ていきます。
今回の9月の大手公開模試の受験者総数は前年9月からみて5%前後の減少です。ここから2014年度首都圏中学入試の全体の規模は若干の減少が予想されます。しかし以前のように秋の大手公開模試の受験者数の増減が、実際の受験者数の増減をストレートに反映しなくなっています。
いくつかの要因が考えられますが、一つは一人あたりの模試受験回数が減っている可能性です。以前は9月にA模試とB模試を受け、10月はB模試とC模試を受けてみるといった受験生も多かったのですが、1回5,000円はかかる受験料のこともあり、各月1回ずつしか受けない受験生が増えているのかもしれません。
また二つ目は主な大手公開模試が国・私立中入試をターゲットとしているのに対し、近年の傾向として適性検査による入学者選抜をおこなう公立中高一貫校を併願する受験生が増えていて、模試の規模は小さいながら公立中高一貫校の適性検査対策模試を受験するようになっていることが考えられます。ここ数年の例から見て本番入試の受験者数は模試受験者の減少ほど減らない可能性が高いと思われます。
1.男子校
今回は男子校の志望動向を見ていきます。なお各学校の志望者の増減の数値は前年同月実施模試の志望者との対前年比(%)です。
(1)東京の男子校
最初に都内最上位進学校の志望動向を見ていきます。なお大学付属校は後でまとめて見ます。

武蔵 この4校の志望者の合計は4,406→4,359名で1%減とほとんど前年並みですから、男子の最上位の受験生数は前年と変わっていないと思われます。そのことから見てこの4校の志望者数の増減は4校の中で志望動向が変動している可能性が高く、開成・駒場東邦から麻布・武蔵という流れが想定されます。この中では麻布と駒場東邦の志望者に地域的にも学力レベル的にも重なりが多く、昨年は早い段階では駒場東邦に向いていた流れが徐々に麻布に向いていったという経過をたどりましたが、今年は逆のパターンになるのでしょうか。開成・駒場東邦とも上位層は増えていて、減っているのはチャレンジ層ですから、難易度が低下することはないでしょう。また両校とも今後減少幅を縮める可能性があります。武蔵の大幅な志望者増はここ数年応募者減が続き緩和傾向が進んでいた反動と思われますが、大学合格実績の改善にくわえ、積極的な広報活動によりアカデミックな校風があらためて見直されたこともあるでしょう。また早稲田や海城からの流れも考えられます。
上記4校に続く上位校の志望状況は以下の通りです。
この中で最も注目される学校は2月1日に参入した本郷です。試験回は3回で昨年と同じで、上記の数字は同じ試験回での前年比です。しかし1回と2回の日程が変わって、1回 2/2→2/1、2回 2/3→2/2となり、同じ1回でも2月2日だった2013年までの入試と、2月1日になる2014年入試では全く別の入試になりますから、試験回ではなく同じ日程どうしで比べると、
となり3回の合計では1,955→1,981名と微増です。併願受験者中心から第一志望者中心になる1日の451名は強豪校がひしめく1日に参入した初年度としては健闘しているものと思われます。また新たに出現した2月1日の本郷志望者451名は、当然2月1日の周辺の城北や巣鴨あるいは攻玉社などに影響を与えているものと思われます。
芝は2回の入試回とも志望者が増えています。のびのびとした校風にくわえて、東大合格者が5→14→16名と好調なのも高い支持を集めている要因でしょう。
東京都市大付は4年連続で応募者を増やしていて勢いのある学校です。特にこの3年間は都内最多の応募者数でした。1回は2月1日午後入試ですがいまだに増加基調が続いています。今春の大学合格実績が過去最高だったのも好調の要因でしょう。
また早稲田1回と巣鴨Ⅰ期の志望者の減少が20%を超えているのも気になるところです。
早稲田は早稲田実業や早大高等学院とならぶ早稲田大の系列校ですが、早稲田大へ進学しているのは約半数で、残りは東大や慶応大など他大学進学です。今春の東大合格者が23→13名と減ったのが志望者減の一因でしょうか。また武蔵の人気上昇の影響もあるようです。
巣鴨は来年9月に新校舎が完成し現在の北区浮間の仮校舎から戻る予定です。一般的に生徒募集にとって、仮校舎は不利な条件で、新校舎は有利な条件ですが、完成時期が2014年9月というのが微妙なところです。さらに東大合格者が41→24名と大きく減った影響もあるでしょう。また上記の本郷1日参入の影響もあるでしょう。

高輪 中堅レベルの男子進学校では高輪(港区)の勢いが続いています。昨年春に東大3名などで注目を集め東大は3→2名と1名減りましたが、京大、阪大、東北大、一橋大、東工大、福島医大に各1名など国公立大計36名、また早慶上智大も73→100→106名、GMARCH大は144→224→217名と前年に続き好調な実績を維持しています。この大学合格実績の伸長が人気の原動力であることは間違いないでしょう。また少数ながら続いていた高校募集を2014年より停止して完全中高一貫校となるのも好感されていると思われます。
9月模試の志望者数は以下のように4回の入試すべてで志望者数が増えています。
伝統校ながら地味な存在だった成城(新宿区)は大学合格実績がここ数年徐々に伸びてきて、今春は東大1名、東工大3名、北大2名など国公立大の合計で28→41名、早慶上智大も73→80名と伸び、さらに新校舎が一部完成(残りは2014年7月に完成予定)、この4月には前都立小石川中等教育学校校長の栗原卯田子先生が新校長に就任(男子校の女性校長は全国初?)、また入試では3回を2月5日に増設し注目を集めています。9月模試では1回が90%ですが、140→110名と定員減の2回の志望者は逆に117%と増えています。今後さらに増加してくる可能性がありそうです。
(2)神奈川の男子校
神奈川の男子校のツートップ、栄光学園(鎌倉市)、聖光学院(横浜市中区)はともにカトリック・ミッション校ですが、毎年入口の入試でも出口の大学合格実績でも抜きつ抜かれつのデッドヒートを演じています。9月の模試の志望者数では以下のように明暗を分けています。
栄光学園の説明会参加者数は前年並みとのことですが、9月模試では大幅な志望者減となっています。今春の東大が70→52名と大きく減った影響が大きいものと思われます。ただし京大1→7名、一橋大9→17名、東工大8→10名など東大以外の最難関国公立大の増加を見ると全体的にはさほど実績が下がっているわけではありません。また工事方法が近日中に決まるとのことですが、2017年完成予定で新校舎建設計画が進んでいて年明けから着工予定です。数年間は仮説校舎になる可能性があり敬遠されているという事情もあるかもしれません。
一方の聖光学院も東大は65→62名と微減ですが、やはり東大合格者52名と62名の差が大きく聖光学院を選ぶ受験生が増えたということでしょうか。今後両校の間の綱引きで揺り戻しの可能性もあり、受験生がどのように動くか注目されます。
この2校に次ぐのが浅野(横浜市神奈川区)です。入試日が2月3日のため東京・神奈川の上位受験生が集中し例年2,000名前後の応募者を集めます。今春の大学合格実績は東大が32→29→27名と少しずつ減ってはいますが、国公立大、難関私大を全体としてみれば前年並みと言ってよいでしょう。しかし9月模試の志望者数は前年比88%でかなり大きな減少です。神奈川の男子上位層が12%も減るというのは考えにくく、何か今までになかった競合などの要因があるのでしょうか。2月3日に入試を行う県内の学校で浅野に匹敵する有力校はありませんが、競合する可能性がある横浜市立南高附は志望者が減少していますし、逗子開成2次もわずかしか増えておらず、結局判然としませんが東京の学校も含めて分散しているのかもしれません。いずれにせよ12%減は減りすぎの感が強く、10月以降の模試では徐々に志望者数を回復する可能性もあるのではないでしょうか。

サレジオ学院 カトリック・ミッション男子校のサレジオ学院(横浜市都筑区)は同じカトリックの栄光学園や聖光学院との併願者が多い学校です。今春は東大・京大・一橋大・東工大の4大学の計で36→19名、早慶上智大も203→187名とダウン。大学合格実績が振るわなかったためか、9月模試の志望者は2月1日のAが81%、Aとの連続受験者が多い4日のBも当然減っていて78%です。ここ数年第一志望者が増えていたAの志望者減は前述の逗子開成1次との競合もあるでしょうが、おそらくはほとんど入試レベルが同じ芝1回との競合が主因ではないでしょうか。
さて逗子開成(逗子市)は今年東大が4→14名など大学合格実績が大躍進して大注目校となっています。予想通り志望者数が以下のように3回の入試とも増えています。
特に2月1日の1回は志望者数が増えているだけではなく、上位層も厚くなっていて、もとから多かった2日の栄光学園、聖光学院1回を本命とするトップ層の併願者が増えているのがはっきり見て取れます。

鎌倉学園 臨済宗の古刹建長寺に隣接する鎌倉学園(鎌倉市)は同寺によって設立された仏教主義教育の男子校で、湘南地区の進学校として定評があります。逗子開成の躍進で影が薄くなったように見えますが、大学合格実績は少しずつですが伸びています。今春は東大2名、一橋大2名、東工大4名など国公立大計で60名、そのうちで医学部が北大など7名、早慶上智大は144名、GMARCH大が299名です。9月模試の志望者は
と第一志望の多い2月2日の1回は微増、4日の2回は微減でほぼ前年並みです。
逗子開成の3回と入試日が重複する5日の3回は相当な減となっています。両校の3回の入試日重複は今に始まったことではありませんが、今年は逗子開成の躍進が大きかったのでやむを得ない結果でしょう。
藤嶺学園藤沢(藤沢市)も臨済宗と同じ鎌倉新仏教の時宗の教えに基づく仏教主義教育の男子校です。ここ数年は大学合格実績がやや停滞していて、2013年入試では応募者も大きく減りましたが、今春の大学合格実績は大きく躍進しています。東大こそ出ませんでしたが、一橋大2名、東北大2名など国公立大計で11→27名(全員一貫生)、早慶上理大は27→41名、GMARCH大は58→101名と大きく伸びています。9月模試の志望者は2月1日の1回が87%でやや減っていますが、2日午後の2回が102%、3日の3回は100%、6日の4回は98%と微減です。
2.女子校
今回は前回の男子校に引き続き女子校の志望動向を見ていきます。なお各学校の志望者の増減の数値は前年同月実施模試の志望者との対前年比(%)です。
(1)東京の女子校
最初に都内最上位進学校の志望動向を見ていきます。なお大学付属校は後でまとめて見ます。

女子学院 この3校の志望者の合計は、2,155→2,180名で1%増とほとんど前年並みですから、女子の最上位の受験者数は前年と変わっていないようです。このなかでは、女子学院の増加が目につきます。入試では応募者の微減が2年間続いていましたが、昨年下がった東大合格実績が32→23→37名と大きく回復したのが好感されて、志望者増につながったものと思われます。このままいけばボーダーあたりで厳しくなるかもしれません。カトリック・ミッション校の雙葉は堅い支持層のある学校ですが、浮動層の上位の一部が女子学院、中位以下の一部が鴎友学園女子に回っている可能性があります。
上記3校に続く上位校の志望状況は以下の通りです。
このなかで注目されるのは、1次の定員増で2月1日シフトを強めている鴎友学園女子で(詳細は第47話を参照)、東大が3→4→11名のほか難関国立大の実績躍進(詳細は第49話(2)を参照)を背景として、定員増の1次だけでなく、減員の2次も含めて3回とも志望者増で勢いのあるところを見せています。
また2日の白百合学園が5%増で、鴎友学園女子2次とともに豊島岡女子1回から中位層が回っている可能性もありそうです。
晃華学園はこの春の大学合格実績が好調だった(東大・京大。一橋大。東工大の合計で3→8名、早慶上智大は70→101名など)にもかかわらず3回とも志望者が大きく減っています。2013年入試で各回とも応募者が増えた反動とも考えられますが、鴎友学園女子や吉祥女子、あるいは大妻多摩や恵泉女学園との競合もあるかもしれません。ただし減少幅が大きすぎる感もあり、今後いくらか増えてくる可能性もあるのではないでしょうか。
次に中堅レベルで主な学校の状況は以下の通りです。
この中で注目されるいくつかの学校について見てみましょう。
大妻多摩は昨春難関国公立大の実績を伸ばし、さらに午後入試の導入によって多摩地区の女子の受験で台風の目となりました。今春も1日午後と2回の志望者は前年に続いて増加していますが、1日午前が減少していることから見ると、レベルの上昇に伴い鴎友学園女子や吉祥女子との競合があるかもしれません。

恵泉女学園 プロテスタント系の恵泉女学園は来春2月2日が日曜日になるため2014年入試に限り午後入試のS方式を実施します(詳細は本シリーズ47話を参照)。予想通りS方式の志望者は午前入試だった今春2回の志望者の171%と大幅増となっています。
実践女子学園は難関大実績が伸びて、今春入試では上位層が増えすべての回で応募者増となり、難易度もアップしました。そのためチャレンジ層に敬遠されているのか1回・2回の志望者は1割以上の減少ですが、国際人の育成を目指す先端的な取り組みで知られるGSC(グローバル・スタンダード・クラス)の午後入試は前年に続き人気が上がって志望者が2割以上の増加です。
品川女子学院は2回・3回の入試日を前倒ししますが、今のところ2回・3回ともに志望者が減っています。
昭和女子大は2014年から少人数クラスへの移行のため定員減となり、A・Bともに70→60名と減員されます。ここ数年応募者数に隔年現象が見られ、今春応募者が大きく減った反動か定員減にもかかわらずA、Bの志望者が大幅に増加していて、入試状況が厳しくなることが予想されます。
東京女学館は1回の志望者が18%増ですが、これは今春導入された一般学級の午後入試に受験生が集中して、1回の応募者数が200→152名と大きく減った反動です。2回午後入試は倍率が高かったので敬遠されたのか志望者が15%減です。今後1回の志望者はまだ増える可能性があります。
山脇学園は都内の中堅女子校では最も勢いのある学校です。保守的なイメージが強い伝統校でしたが、「山脇ルネサンス」と称する学校改革が軌道に乗って、進路においても結果を出しつつあり(本シリーズ49話(2)参照)、一部完成している新校舎人気もあり今春の入試では応募総数が37%増、実受験者では56%増と多くの受験生を集め、都心の中堅女子校ではほとんど一人勝ちの状況でした。その人気ぶりはまだ続いていて、A・B・Cの3回の入試すべてで志望者数を伸ばしています。
(2)神奈川の女子校
神奈川の最上位の女子校は、いずれも横浜山手の丘(横浜市中区)の上にある創立100年を超えるミッション校です。

フェリス女学院 横浜共立Bが30%の大幅減となっていますが、これは今年の2月3日が日曜日だったため入試日を4日に移動して応募者が急増していたのが、2014年は例年通り3日に戻るためです。さてご覧のとおり最上位の3校すべて志望者が相当に減っています。特にトップのフェリス女学院の減少が20%以上と大きいのも気になるところです。2月1日のこの3校の志望者の合計(3日の横浜共立Bを除く)は1,481→1,273名で14%減です。この最上位層の減少は、3校とも減っているところから、3校の中での志望者の移動ではなく他の要因と思われます。10月以降の状況を見ないとはっきりしたことはわかりませんが、いくつか考えられる減少の要因は、
①安全志向でチャレンジ層が減っている
②共学系の学校に回っている
③東京の有力校に回っている
④今年の神奈川女子受験生は上位層が薄い
⑤今年の神奈川女子受験生自体が減っている
などですが、①については、この3校につぐ県内の2月1日入試校と言えば洗足学園1回、日本女子大1回ですが両校とも志望者は微減です。
②も県内にこの3校と同レベルの2月1日入試の共学校はなく該当しないようです。
②は神奈川寄りの都内の学校で増えているのは、女子学院、鴎友学園女子1次、東洋英和女学院Aで、減少した208名のうちいくらかはこの3校に回った受験生もいるかもしれません。なお模試データからの検証は不可能ですが、都内からの受験生が減っている可能性もあります。
④については検証が難しいのですが、地域的に学力上位層の割合が年によって大きく変動するというのは考えにくく、実際にはあり得ないのではないかと思われます。
一番ありそうなのは⑤ですが、都県別の受験生数を推計するための網羅的なデータがないため、現時点では判断を保留するしかありません。それにしても首都圏全域の受験者数は9月模試からは前年比4%前後の減少と思われ、さすがに14%減は大きすぎるので、③と⑤などの複合的な要因によるものと思われます。
以上の最上位3校に次ぐのは、
見ての通りほとんどの学校が志望者数を少しずつ減らしていています。トップ3校からの流れがあるようには見えないのは前述したところです。
洗足学園の2回の減少が大きくなっていますが、ここ数年で桜蔭、女子学院、フェリス女学院などとの併願者が増えて難易度が上がって、通学圏が重なる鴎友学園女子と受験者層が重なるようになったため鴎友学園女子2次に回っている受験生もいる者と思われます。
その他の中堅校では、

神奈川学園 神奈川の中堅女子校はここ数年応募者の減少に見舞われた学校が多かったのですが、今年は9月模試の志望動向を見る限り志望者数を回復している学校が増えています。
神奈川の私立女子校では数少ない非宗教系の学校の神奈川学園は学校改革の成果が順調に大学合格実績の伸長に表れていて、国公立大は7名とまだ少ないのですが、その中身は一橋大、北大、東京外語大などを含み、難関私大では早慶上智大が7→8→33名、GMARCH大は45→52→70名と躍進しています。すべての入試回の志望者が増えていますが、併願者が多い午後入試のA2より午前入試のA1、B、Cの増加の方が大きいところから見て受験生の志望順位が上がっていることが予想されます。
横浜女学院は2011年に一時的な応募者減がありましたが、その後は県内の中堅女子校でもっとも安定した応募者数で、実受験者数は2年連続の増加です。今春は今までほとんどいなかった東工大や北大など難関国公立大にも合格者を出し、難関私大では早慶上智大が7→16→27名、GMARCH大は33→41→59名と躍進しています。9月模試の志望者は神奈川学園と同様に午前入試のA、D、Eの増加が大きく受験生の志望順位が上がっていることが予想されます。
清泉女学院はこのところ隔年現象があり来年は増加が予想される年で、9月模試の動向でもそうなる可能性が高そうです。
カリタス女子、聖園女学院、横浜英和女学院の3校はこの2~3年応募者の減少が続いていましたが、ようやく回復の兆しが見えてきました。
3.共学校
今回の(3)は前回の女子校に引き続き共学校の志望動向を見ていきます。大学付属校については最後にまとめて見ていきます。なおMは男子、Fは女子で、各学校の志望者の増減の数値は前年同月実施模試の志望者との対前年比(%)です。
(1)東京の共学校
都内の主な共学進学校の9月模試における志望状況は以下の通りです。
都内の共学校で大学付属校を除けば上位校(市進偏差値で60以上)といえるのは渋谷教育学園渋谷(渋谷区)だけです。この2年ほどの大学合格実績が、国公立大では東大が15→16→12名、東大、京大、一橋大、東工大の4大学計では29→27→24名とわずかの減ですが、難関私大は海外大へ30名以上の合格者を出している影響もあるのか、早慶上智大は211→194→155名と大きく減っています。9月模試の志望者は男子の1・2回は前年並みですが、女子は3回とも大きく減っています。今春入試でも女子の2回以外は応募者数が減っていましたから、減少が続いていることになります。特に女子は3回とも減少幅が大きいのが気になりますが、鴎友学園女子や吉祥女子などの勢いのある女子校に押されている可能性もありそうです。

広尾学園 広尾学園は2007年に共学化・校名変更し、先端的な取り組みによって人気が急上昇し応募者が毎年のように増え続け、入試レベルもこの6年間で偏差値15は上がっています。中学の共学1期生が今春卒業し、国公立大は東工大、東京外語大、北大、東北大、旭川医大などを含めて13→20名、早慶上智大は17→62名、アメリカ・カナダの大学に8名と大躍進しています。1期生は入学時の偏差値が40程度でしたから卒業までの6年間で大きく伸びたことがうかがえます。その後の入学レベルの上昇を考えると、今後さらに大学合格実績が伸びていくものと思われます。応募者数は昨年、今年と落ち着いてきていますが、試験回数を減らしたり特待制度を廃止したりして、「量から質へ」の転換を図っているように見えます。9月模試の志望者は医進・サイエンスの男子、3回の女子以外は減っていますが、入試レベルが緩和することは期待できないでしょう。
穎明館は小規模校ながら大学進学実績が高い学校です(本シリーズ第49話を参照)。志望者は男子が増加、女子が減少と男女で対照的ですが、女子の減少は新制服の導入で人気が急上昇し、この2年続いて応募者が急増した反動でしょう。
桜美林は2回午前の女子以外で志望者数が大きく落ち込んでいます。ここ数年の入試で上位校との併願者が増えて難易度が上がってきたことへの敬遠もありそうですが、それ以上にこの春の卒業生の大学合格実績が低下したのが主因でしょう。国公立大の総数は前年同数ながら、昨年は合格者を出した東大、一橋大、東工大、東京外語大などの難関レベルの大学の合格者がいなくなり、早慶上智大も41→19名と激減。これは今年の卒業生数自体が397→266名と大きく減り、またその他の事情が重なったためのこの学年固有の現象で、来年以降は実績を回復していくものと思われます。とはいえこの実績低下によって2014年入試は応募者が相当に減少するのは確実で難易度が緩和する可能性が高いでしょう。
共学化4年目の東京都市大等々力はこの3年間応募者が増え続けていましたが、9月模試の結果を見る限りそろそろブレーキがかかってきているようです。女子はまだ6回の入試のうち4回で増えていますが、男子は6回のうち5回で減少に転じています。おそらく男子は減少幅の大きさから見て、芝や高輪などの勢いのある男子校や巻き返しに転じてきている青稜などとの競合と、難易度の上昇によりチャレンジ層に敬遠されているという2つの要因がありそうです。
淑徳は今春、東大0→1名、一橋大0→1名、東京外語大0→2名、東北大1→2名など最難関国公立大の実績を伸ばしています。ところが女子は5回の入試すべて志望者が増えていますが、男子の志望者は東大1回が微増以外の他の4回は大きく減っています。これだけ難関大の合格実績を伸ばすと男子受験生が増えるのが通例ですから、これは明らかに外部的な要因です。結論的にいえばこれは人気の高い本郷の1日参入の影響でしょう。ただし合否判定は男女合同で、女子は増えていますから難易度が大きく下がることはないでしょう。
青稜は2012年春に国公立大27→51名、早慶上智大40→88名など大きく大学合格実績が伸びて、今春の入試では応募総数が22%増となりました。さらにこの3月の大学合格実績も東大が0→2名、東工大は1→2名など最難関レベルで結果を出し、人気が上がっています。特に2月1日午前の1回Aの女子が相当な増加で第一志望者が増えていることをうかがわせます。女子校から共学化した学校にもかかわらず、一時は女子の応募者が減っていましたが、今年は女子の方の人気が高くなっています。2014年9月には新校舎が完成予定なのも追い風になっているようです。
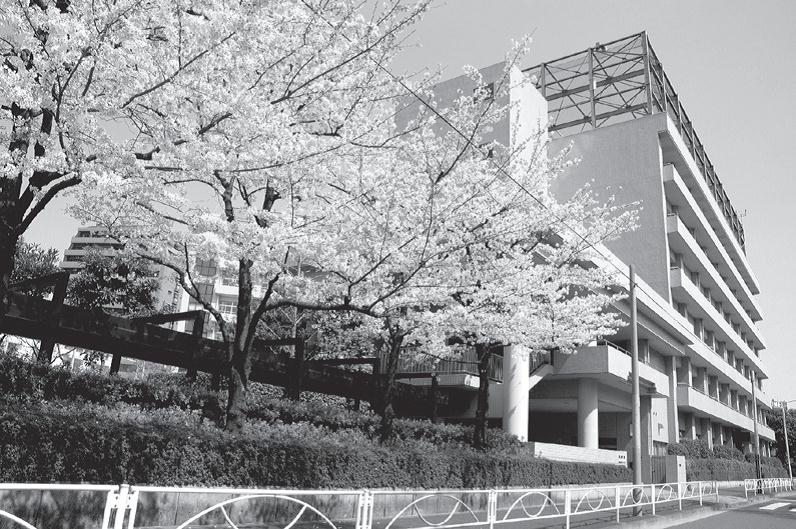
安田学園 なお2014年から共学化される男子校の安田学園(墨田区)の志望者は、9月模試のデータでは6回の入試の志望者合計で男子が250名、女子が100名ほどですが、説明会参加者などでは男女比が3:2とのことですから、女子の志望者は今後まだまだ増えていくものと思われます。また先進コース第1回の合格者20名は入学金・施設設備費、6年間の授業料全額免除ですから、公立一貫校との併願受験者が相当に集まる可能性があります。学校側の狙いもそこにあり、公立一貫型入試の適性検査はすぐ近くの都立両国高附中の出題傾向を意識した作問にするとのことです。またカフェテラスやコンビニを新設した校舎のリニューアル工事が終わり、この8月には中学棟(新南館)も完成しました。
(2)神奈川の共学校
神奈川の主な共学進学校の9月模試における志望状況は以下の通りです。なお神奈川大附と関東学院は併設大への進学者がほとんどいないため、実態に合わせて進学校として考えます、
神奈川大附はここ数年勢いがありましたが、9月模試の志望者数は男子が前年並み、女子はやや減で、一息ついた感があります。
三春台の丘の上のプロテスタント系ミッション校の関東学院は、全体的に見れば大学合格実績が下がってはいませんが、今年は東大、一橋大、東工大などの目立つような実績がなく、逗子開成、湘南学園、神奈川学園などの勢いに押されているのか1期Bの女子以外は各回とも相当に志望者数を減らしています。特に1期Aは定員増にもかかわらず志望者減で緩和した入試になりそうです。2月6日の2期の減少幅が大きいのは、多くの学校が入試日程を早める中で6日という遅い日程のためかもしれません。

湘南学園 湘南の高級住宅地として知られる鵠沼の湘南学園は、保護者と教職員によって共同運営という全国的にも珍しい学校です。前年春の大学合格実績が大躍進して、今春入試の応募総数がなんと70%増と大人気になりました。今年の大学実績は下がっていますが、あいかわらず人気が続いていて、Bの女子を除いてすべての回で男女とも志望者が相当に増加。上位校との併願者も増えていて今春に続いて難易度が上昇する可能性が高く要注意です。
桐蔭学園は別学の中学校と男子校の中等教育学校は別の学校ですが、入試は一体的に行われているため、ここでまとめて見ておきます。(表中のM、Fは中学校の男子部、女子部、理数は中学女子部の理数コースです。)中等教育学校は東大13名(うち理Ⅲ2名)など大学合格実績を回復。また2014年入試から今まで2次A,Bで出していた特別奨学生合格を1次~3次すべての回で出すことになりました。さらに1次、2次A,Bの入学手続きの締め切りを3次と同じ2月7日まで延長するなどの入試改革を行います。これだけの好条件にもかかわらず9月模試では志望者が増えずむしろ減り気味で、今のところ減少傾向に歯止めがかかっていません。
桐光学園はここ数年応募者の減少が続いていましたが、9月模試では3回の入試で男女とも志望者数が増加に転じています。特に女子は減少が目立ちましたが、今回大きく回復しています。
森村学園は過去最高の大学合格実績を出しましたが、前述の桐光学園、神奈川大附や中大横浜あるいは東京都市大等々力との競合があるのか、2回の男子以外の志望者が減っています。女子に人気が高い学校でしたが、9月模試では女子の志望者の減少が目立っています。
山手学院は国際色豊かな共学の中堅進学校として人気の高い学校です。中高一貫教育へのシフトを強め、午後入試の導入などでしばらくは応募者増が続いていましたが、中大横浜や湘南学園との競合が厳しくなっているのか、この2年間は応募者減が続いていました。しかし9月模試では2月2日午後入試のBは男女とも増加に転じています。Cは4日→3日へ入試日を前倒しして定員を20→10名と減員したため大きく志望者が減っています。
(3)埼玉の共学校
埼玉の主な共学進学校の9月模試における志望状況は以下の通りです。
東京・神奈川の私立中入試が2月1日から始まるのに対し、埼玉は1月10日、千葉の一般入試は1月20日が入試解禁日となっています。そのため埼玉・千葉の1月入試の、特に東京からのアクセスの良い学校には東京・神奈川の受験生が大量に「試し受験」していることはよく知られています。東京・神奈川の「試し受験生」はほとんどが合格しても入学しないため、「試し受験生」が増えても入学者の確保のために合格者も増やしますから、難易度がかえって低下することもあり、模試の志望動向から入試状況、特に難易度を予測するのがなかなか難しいことをご理解ください。
さて開智と栄東の2校は上位から中位まで県内・県外から大量の受験生を集める学校です。ここ数年の埼玉の中学入試はこの2校を軸に動いていると言っても過言ではありません。この2校は激しい競合関係にあり、2014年入試では両校ともお互いを意識した大きな入試変更を行います。(詳細は本シリーズ47話を参照)
開智は先端Aの入試日を入試解禁初日の1月10日に前倒しして栄東のAにぶつけ、定員も30→85名と大幅に増員、一貫1回は130→85名と大幅減員、残りの2回は5名ずつの減員です。9月模試の志望者は定員増の先端Aの男子がやや減、女子は微増ですから今のところ学校の狙いは成功していません。一貫1回は男女とも減っていますがこれは定員減ですから当然です。一貫2回は前年並み、先端Bは50→45名と減員ながら内訳では先端30→35名・一貫20→15名と先端の実質増が好感されたのか男女とも10%以上の増です。

栄東 栄東も難関Aを110→140名に増員すると同時に難関Aの定員140名の中に東大クラス20名の定員を設けます。しかも標準的レベルの出題で合格者を多く出すとアナウンスして栄東への誘導をはかっています。これが功を奏しているのか、難関Aは男女とも志望者増、80→50名と定員減の東大Ⅰも志望者増、20→40名と定員増の難関Bは大幅に志望者増です。以上から見て、開智と栄東の攻防は9月段階では明らかに栄東に軍配が上がるようです。
西武学園文理は県西部の最有力校ですが、上記の2校の勢いに押されているのか今春の入試では応募総数が5%減で、この傾向は今年も続いていますが、特選は特待生選抜を兼ねていて2回の男子以外は増えています。
春日部共栄はこの2年間で大きく応募者が減っていますが、2014年入試では大きな入試改革を行います。総定員を120→160名と増員し、試験回を3回→4回に増やし、グローバル・エリート・クラス(GE)を新設。GEの1回~3回の入試は午後入試になります。また一般クラスの名称もグローバル・スタンダード・クラス(GS)と変わります。しかしこの大きな入試改革も発表が遅かったためか、まだ十分に周知されていないようで、9月模試にはまだ入試改革は反映されていないようです。
*栄東の東大Ⅲ、西武学園文理の4回、春日部共栄の4回は模試データが少ないため割愛しました。
(4)千葉・茨城の共学校
千葉・茨城の主な共学進学校の9月模試における志望状況は以下の通りです。
*芝浦工大柏の3回はデータ件数が少なく、昭和学院秀英 の1回は第一志望入試でデータがないため割愛しました。
以上の7校の最後の回の入試はすべて2月入試で東京の入試日程と重なるため、模試の志望動向と本番入試の応募者数に大きな乖離が生じます。そのため入試動向というより人気度を測る資料としてみてください。

東邦大東邦 千葉御三家ともいわれる、渋谷教育学園幕張、市川、東邦大東邦の3校では東邦大東邦の増加、特に女子の増加が目につきます。渋谷教育学園幕張は男子が前年並みで女子が5%減ですから、女子受験生の一部が安全志向から東邦大東邦に回っているのかもしれません。
昭和学院秀英はここ2年ほど応募者の減少が続いていましたが、一橋大1→4名、東工大2→3名、阪大0→1名、東北大1→2名、北大1→2名、千葉大21→38名など難関国公立大の実績を伸ばして、9月模試では男女とも志望者数を伸ばしています。特に男子の2回は2012年並みの応募者に回復しそうな勢いです。
江戸川学園取手は茨城のトップ進学校ですが、受験生の出身地は地元の茨城が3割、千葉が6割、その他が1割と千葉からの受験生が非常に多い学校です。東大が11→13名、一橋大1→2名、東工大2→4名、東北大4→10名、北大3→5名、千葉大6→16名、筑波大17→19名と難関国公立大の実績を伸ばし、男子の志望者は相当に増えていますが、女子は逆に減っています。
(5)大学付属校
ここで主要な大学付属校(大学系列校)について別学校を含め、まとめて見てみます。なお主要な大学付属校は、卒業生の大半が併設大学に進学する早慶大、GMARCH大に限定します。これ以外は東海大系を除くと、卒業生の進路状況から見て進学校化している学校が多く、実態として「付属校」というカテゴリーではくくりきれないからです。
慶應普通部は2012年に応募者が大幅に減りましたが今春入試では微減で、9月模試でも志望者は微減です。
慶應中等部の男子は前年並みの志望者数ですが、女子は2010年から3年連続で応募者を減らし、今春入試ではわずかながら回復しましたが、9月模試データから見ると再び大きく減少に転じそうです。その要因としては、青山学院が2月2日の日曜日を避けて3日への入試日移動、また東洋英和女学院Bが4日から3日に戻り、併願受験者が多い両校の入試日と重複するという事情があります。とはいえこの2校に回るのは主にチャレンジ層で、女子の定員は少ないため難易度への影響はほとんどないでしょう。
慶応湘南藤沢は女子の志望者数がやや減っています。男子は2012年に大きく減りましたが、今春は微減で9月の志望者数は前年並みです。

早大高等学院 早大高等学院は中学部を開設して4年目となり、1期生が高校に進学しました。開校初年度の応募者数が442名と超有名大学の附属校にしては少なく、2年目に大きく増えましたが、その後2年間で536→472→352名大きく減っています。さすがにここまで減ると反動があるのか、9月模試の志望者は13%増で前年並みに応募者数を回復しそうです。
早稲田実業の男子は応募者数に隔年現象があり、今春入試では7%増でしたから来春は減る年にあたりますが、16%減はやや大きいように思えます。女子は19%減で、男子より大きく減っています。
GMARCH大の系列校で目につく志望者増は、明大明治の女子、明中八王子の1回の男子、法政大学第二、学習院の4校です。
学習院の併設大学への推薦率は46%で、半数以上は他大学進学です。主な他大学は東大5名、京大1名、一橋大4名、東工大3名、早慶上智大110名などでこれが人気の主要因でしょう。
青山学院は今年の入試で日曜日を避けて3日入試となりました。3日入試だった10年前の2003年は応募者が2割増となりましたが、この春は男女ともに応募者が大きく減っています。結局この3年間で、男子は513→452→275名、女子は641→629→427名と大幅な減少です。9月模試で男子は前年並みとしていますが、女子はさらに大きく減りそうです。このままいけば女子の難易度は緩和する可能性大です。
中央大学横浜は2012年の共学化で大人気になりましたが、今春入試ではだいぶん落ち着いてきました。9月模試では志望者が男女各回の入試とも減少に転じています。上位校併願者が急激に増えて倍率・難易度が上がりすぎていた反動とともに、共学化当初は強調されていた他大学進学のトーンが下がり附属色を強めているために、志望順位の高い受験生に絞られてきているのではないでしょうか。
今回の9月の大手公開模試の受験者総数は前年9月からみて5%前後の減少です。ここから2014年度首都圏中学入試の全体の規模は若干の減少が予想されます。しかし以前のように秋の大手公開模試の受験者数の増減が、実際の受験者数の増減をストレートに反映しなくなっています。
いくつかの要因が考えられますが、一つは一人あたりの模試受験回数が減っている可能性です。以前は9月にA模試とB模試を受け、10月はB模試とC模試を受けてみるといった受験生も多かったのですが、1回5,000円はかかる受験料のこともあり、各月1回ずつしか受けない受験生が増えているのかもしれません。
また二つ目は主な大手公開模試が国・私立中入試をターゲットとしているのに対し、近年の傾向として適性検査による入学者選抜をおこなう公立中高一貫校を併願する受験生が増えていて、模試の規模は小さいながら公立中高一貫校の適性検査対策模試を受験するようになっていることが考えられます。ここ数年の例から見て本番入試の受験者数は模試受験者の減少ほど減らない可能性が高いと思われます。
1.男子校
今回は男子校の志望動向を見ていきます。なお各学校の志望者の増減の数値は前年同月実施模試の志望者との対前年比(%)です。
(1)東京の男子校
最初に都内最上位進学校の志望動向を見ていきます。なお大学付属校は後でまとめて見ます。
| 麻布(港区) | 111% |
| 開成(荒川区) | 93% |
| 駒場東邦(世田谷区) | 88% |
| 武蔵(練馬区) | 120% |

武蔵 この4校の志望者の合計は4,406→4,359名で1%減とほとんど前年並みですから、男子の最上位の受験生数は前年と変わっていないと思われます。そのことから見てこの4校の志望者数の増減は4校の中で志望動向が変動している可能性が高く、開成・駒場東邦から麻布・武蔵という流れが想定されます。この中では麻布と駒場東邦の志望者に地域的にも学力レベル的にも重なりが多く、昨年は早い段階では駒場東邦に向いていた流れが徐々に麻布に向いていったという経過をたどりましたが、今年は逆のパターンになるのでしょうか。開成・駒場東邦とも上位層は増えていて、減っているのはチャレンジ層ですから、難易度が低下することはないでしょう。また両校とも今後減少幅を縮める可能性があります。武蔵の大幅な志望者増はここ数年応募者減が続き緩和傾向が進んでいた反動と思われますが、大学合格実績の改善にくわえ、積極的な広報活動によりアカデミックな校風があらためて見直されたこともあるでしょう。また早稲田や海城からの流れも考えられます。
上記4校に続く上位校の志望状況は以下の通りです。
| 早稲田(新宿区) | 1回 | 78% | 2回 | 89% |
| 海城(新宿区) | 1回 | 86% |
| 2回 | 102% | |
| 芝(港区) | 1回 | 111% |
| 2回 | 107% | |
| 城北(板橋区) | 1回 | 96% |
| 2回 | 109% | |
| 3回 | 84% | |
| 巣鴨(豊島区) | Ⅰ期 | 79% |
| Ⅱ期 | 85% | |
| 攻玉社(目黒区) | 1回 | 84% |
| 2回 | 90% | |
| 特選 | 101% | |
| 世田谷学園(世田谷区) | 1回 | 85% |
| 2回 | 90% | |
| 3回 | 73% | |
| 本郷(豊島区) | 1回 | 61% |
| 2回 | 163% | |
| 3回 | 106% | |
| 東京都市大付(世田谷区) | 1回 | 112% |
| 2回 | 89% | |
| 3回 | 123% | |
| 4回 | 87% | |
| 桐朋(国立市) | 97% | |
この中で最も注目される学校は2月1日に参入した本郷です。試験回は3回で昨年と同じで、上記の数字は同じ試験回での前年比です。しかし1回と2回の日程が変わって、1回 2/2→2/1、2回 2/3→2/2となり、同じ1回でも2月2日だった2013年までの入試と、2月1日になる2014年入試では全く別の入試になりますから、試験回ではなく同じ日程どうしで比べると、
| 2/1(新設1回) | 0→451名 |
| 2/2(1回→2回) | 740→600名 |
| 2/3(2回→廃止) | 339→0名 |
| 2/5(3回→3回) | 876→930名 |
となり3回の合計では1,955→1,981名と微増です。併願受験者中心から第一志望者中心になる1日の451名は強豪校がひしめく1日に参入した初年度としては健闘しているものと思われます。また新たに出現した2月1日の本郷志望者451名は、当然2月1日の周辺の城北や巣鴨あるいは攻玉社などに影響を与えているものと思われます。
芝は2回の入試回とも志望者が増えています。のびのびとした校風にくわえて、東大合格者が5→14→16名と好調なのも高い支持を集めている要因でしょう。
東京都市大付は4年連続で応募者を増やしていて勢いのある学校です。特にこの3年間は都内最多の応募者数でした。1回は2月1日午後入試ですがいまだに増加基調が続いています。今春の大学合格実績が過去最高だったのも好調の要因でしょう。
また早稲田1回と巣鴨Ⅰ期の志望者の減少が20%を超えているのも気になるところです。
早稲田は早稲田実業や早大高等学院とならぶ早稲田大の系列校ですが、早稲田大へ進学しているのは約半数で、残りは東大や慶応大など他大学進学です。今春の東大合格者が23→13名と減ったのが志望者減の一因でしょうか。また武蔵の人気上昇の影響もあるようです。
巣鴨は来年9月に新校舎が完成し現在の北区浮間の仮校舎から戻る予定です。一般的に生徒募集にとって、仮校舎は不利な条件で、新校舎は有利な条件ですが、完成時期が2014年9月というのが微妙なところです。さらに東大合格者が41→24名と大きく減った影響もあるでしょう。また上記の本郷1日参入の影響もあるでしょう。

高輪 中堅レベルの男子進学校では高輪(港区)の勢いが続いています。昨年春に東大3名などで注目を集め東大は3→2名と1名減りましたが、京大、阪大、東北大、一橋大、東工大、福島医大に各1名など国公立大計36名、また早慶上智大も73→100→106名、GMARCH大は144→224→217名と前年に続き好調な実績を維持しています。この大学合格実績の伸長が人気の原動力であることは間違いないでしょう。また少数ながら続いていた高校募集を2014年より停止して完全中高一貫校となるのも好感されていると思われます。
9月模試の志望者数は以下のように4回の入試すべてで志望者数が増えています。
| A | 114% |
| B | 126% |
| 算数午後 | 105% |
| C | 113% |
伝統校ながら地味な存在だった成城(新宿区)は大学合格実績がここ数年徐々に伸びてきて、今春は東大1名、東工大3名、北大2名など国公立大の合計で28→41名、早慶上智大も73→80名と伸び、さらに新校舎が一部完成(残りは2014年7月に完成予定)、この4月には前都立小石川中等教育学校校長の栗原卯田子先生が新校長に就任(男子校の女性校長は全国初?)、また入試では3回を2月5日に増設し注目を集めています。9月模試では1回が90%ですが、140→110名と定員減の2回の志望者は逆に117%と増えています。今後さらに増加してくる可能性がありそうです。
(2)神奈川の男子校
神奈川の男子校のツートップ、栄光学園(鎌倉市)、聖光学院(横浜市中区)はともにカトリック・ミッション校ですが、毎年入口の入試でも出口の大学合格実績でも抜きつ抜かれつのデッドヒートを演じています。9月の模試の志望者数では以下のように明暗を分けています。
| 栄光学園 | 88% |
| 聖光学院1回 | 105% |
栄光学園の説明会参加者数は前年並みとのことですが、9月模試では大幅な志望者減となっています。今春の東大が70→52名と大きく減った影響が大きいものと思われます。ただし京大1→7名、一橋大9→17名、東工大8→10名など東大以外の最難関国公立大の増加を見ると全体的にはさほど実績が下がっているわけではありません。また工事方法が近日中に決まるとのことですが、2017年完成予定で新校舎建設計画が進んでいて年明けから着工予定です。数年間は仮説校舎になる可能性があり敬遠されているという事情もあるかもしれません。
一方の聖光学院も東大は65→62名と微減ですが、やはり東大合格者52名と62名の差が大きく聖光学院を選ぶ受験生が増えたということでしょうか。今後両校の間の綱引きで揺り戻しの可能性もあり、受験生がどのように動くか注目されます。
この2校に次ぐのが浅野(横浜市神奈川区)です。入試日が2月3日のため東京・神奈川の上位受験生が集中し例年2,000名前後の応募者を集めます。今春の大学合格実績は東大が32→29→27名と少しずつ減ってはいますが、国公立大、難関私大を全体としてみれば前年並みと言ってよいでしょう。しかし9月模試の志望者数は前年比88%でかなり大きな減少です。神奈川の男子上位層が12%も減るというのは考えにくく、何か今までになかった競合などの要因があるのでしょうか。2月3日に入試を行う県内の学校で浅野に匹敵する有力校はありませんが、競合する可能性がある横浜市立南高附は志望者が減少していますし、逗子開成2次もわずかしか増えておらず、結局判然としませんが東京の学校も含めて分散しているのかもしれません。いずれにせよ12%減は減りすぎの感が強く、10月以降の模試では徐々に志望者数を回復する可能性もあるのではないでしょうか。

サレジオ学院 カトリック・ミッション男子校のサレジオ学院(横浜市都筑区)は同じカトリックの栄光学園や聖光学院との併願者が多い学校です。今春は東大・京大・一橋大・東工大の4大学の計で36→19名、早慶上智大も203→187名とダウン。大学合格実績が振るわなかったためか、9月模試の志望者は2月1日のAが81%、Aとの連続受験者が多い4日のBも当然減っていて78%です。ここ数年第一志望者が増えていたAの志望者減は前述の逗子開成1次との競合もあるでしょうが、おそらくはほとんど入試レベルが同じ芝1回との競合が主因ではないでしょうか。
さて逗子開成(逗子市)は今年東大が4→14名など大学合格実績が大躍進して大注目校となっています。予想通り志望者数が以下のように3回の入試とも増えています。
| 1回 | 110% |
| 2回 | 101% |
| 3回 | 109% |
特に2月1日の1回は志望者数が増えているだけではなく、上位層も厚くなっていて、もとから多かった2日の栄光学園、聖光学院1回を本命とするトップ層の併願者が増えているのがはっきり見て取れます。

鎌倉学園 臨済宗の古刹建長寺に隣接する鎌倉学園(鎌倉市)は同寺によって設立された仏教主義教育の男子校で、湘南地区の進学校として定評があります。逗子開成の躍進で影が薄くなったように見えますが、大学合格実績は少しずつですが伸びています。今春は東大2名、一橋大2名、東工大4名など国公立大計で60名、そのうちで医学部が北大など7名、早慶上智大は144名、GMARCH大が299名です。9月模試の志望者は
| 1回 | 101% |
| 2回 | 98% |
| 3回 | 72% |
と第一志望の多い2月2日の1回は微増、4日の2回は微減でほぼ前年並みです。
逗子開成の3回と入試日が重複する5日の3回は相当な減となっています。両校の3回の入試日重複は今に始まったことではありませんが、今年は逗子開成の躍進が大きかったのでやむを得ない結果でしょう。
藤嶺学園藤沢(藤沢市)も臨済宗と同じ鎌倉新仏教の時宗の教えに基づく仏教主義教育の男子校です。ここ数年は大学合格実績がやや停滞していて、2013年入試では応募者も大きく減りましたが、今春の大学合格実績は大きく躍進しています。東大こそ出ませんでしたが、一橋大2名、東北大2名など国公立大計で11→27名(全員一貫生)、早慶上理大は27→41名、GMARCH大は58→101名と大きく伸びています。9月模試の志望者は2月1日の1回が87%でやや減っていますが、2日午後の2回が102%、3日の3回は100%、6日の4回は98%と微減です。
2.女子校
今回は前回の男子校に引き続き女子校の志望動向を見ていきます。なお各学校の志望者の増減の数値は前年同月実施模試の志望者との対前年比(%)です。
(1)東京の女子校
最初に都内最上位進学校の志望動向を見ていきます。なお大学付属校は後でまとめて見ます。
| 桜蔭(文京区) | 101% |
| 女子学院(千代田区) | 109% |
| 雙葉(千代田区) | 88% |

女子学院 この3校の志望者の合計は、2,155→2,180名で1%増とほとんど前年並みですから、女子の最上位の受験者数は前年と変わっていないようです。このなかでは、女子学院の増加が目につきます。入試では応募者の微減が2年間続いていましたが、昨年下がった東大合格実績が32→23→37名と大きく回復したのが好感されて、志望者増につながったものと思われます。このままいけばボーダーあたりで厳しくなるかもしれません。カトリック・ミッション校の雙葉は堅い支持層のある学校ですが、浮動層の上位の一部が女子学院、中位以下の一部が鴎友学園女子に回っている可能性があります。
上記3校に続く上位校の志望状況は以下の通りです。
| 豊島岡女子(豊島区) | 1回 | 93% |
| 2回 | 82% | |
| 3回 | 93% | |
| 白百合学園(千代田区) | 105% | |
| 鴎友学園女子(世田谷区) | 1次 | 106% |
| 2次 | 109% | |
| 3次 | 114% | |
| 吉祥女子(武蔵野市) | 1回 | 103% |
| 2回 | 99% | |
| 3回 | 97% | |
| 東洋英和女学院(港区) | A | 108% |
| B | 53% | |
| 頌栄女子学院(港区) | 1回 | 102% |
| 2回 | 97% | |
| 晃華学園(調布市) | 1回 | 73% |
| 2回 | 65% | |
| 3回 | 85% | |
| 光塩女子学院(杉並区) | 1回 | 93% |
| 2回 | 108% | |
このなかで注目されるのは、1次の定員増で2月1日シフトを強めている鴎友学園女子で(詳細は第47話を参照)、東大が3→4→11名のほか難関国立大の実績躍進(詳細は第49話(2)を参照)を背景として、定員増の1次だけでなく、減員の2次も含めて3回とも志望者増で勢いのあるところを見せています。
また2日の白百合学園が5%増で、鴎友学園女子2次とともに豊島岡女子1回から中位層が回っている可能性もありそうです。
晃華学園はこの春の大学合格実績が好調だった(東大・京大。一橋大。東工大の合計で3→8名、早慶上智大は70→101名など)にもかかわらず3回とも志望者が大きく減っています。2013年入試で各回とも応募者が増えた反動とも考えられますが、鴎友学園女子や吉祥女子、あるいは大妻多摩や恵泉女学園との競合もあるかもしれません。ただし減少幅が大きすぎる感もあり、今後いくらか増えてくる可能性もあるのではないでしょうか。
次に中堅レベルで主な学校の状況は以下の通りです。
| 跡見学園(文京区) | 1回 | 93% |
| 2回 | 97% | |
| 3回 | 82% | |
| 江戸川女子(江戸川区) | 1回 | 77% |
| AO | 95% | |
| 2回 | 97% | |
| 3回 | 100% | |
| 大妻(千代田区) | 1回 | 96% |
| 2回 | 110% | |
| 3回 | 88% | |
| 大妻多摩(多摩市) | 1回 | 90% |
| 午後 | 111% | |
| 2回 | 119% | |
| 3回 | 85% | |
| 共立女子(千代田区) | A | 95% |
| B | 95% | |
| C | 92% | |
| 恵泉女学園(世田谷区) | A1回 | 97% |
| S | 171% | |
| A2回 | 106% | |
| 香蘭女学校(品川区) | 105% | |
| 実践女子学園(渋谷区) | 1回 | 89% |
| GSC | 121% | |
| 2回 | 83% | |
| 3回 | 104% | |
| 品川女子学院 | 1回 | 97% |
| 2回 | 89% | |
| 3回 | 69% | |
| 昭和女子大(世田谷区) | A | 129% |
| B | 122% | |
| C | 89% | |
| 田園調布学園(世田谷区) | 1回 | 64% |
| 2回 | 82% | |
| 3回 | 80% | |
| 東京女学館(渋谷区) | 1回 | 118% |
| 2回 | 85% | |
| 国際 | 92% | |
| 3回 | 77% | |
| 富士見(練馬区) | 1回 | 82% |
| 2回 | 93% | |
| 3回 | 95% | |
| 三輪田学園(千代田区) | 1回 | 89% |
| 2回 | 93% | |
| 3回 | 95% | |
| 八雲学園(目黒区) | 1回 | 96% |
| 2回 | 98% | |
| 3回 | 94% | |
| 4回 | 104% | |
| 山脇学園(港区) | A | 127% |
| B | 115% | |
| C | 132% | |
この中で注目されるいくつかの学校について見てみましょう。
大妻多摩は昨春難関国公立大の実績を伸ばし、さらに午後入試の導入によって多摩地区の女子の受験で台風の目となりました。今春も1日午後と2回の志望者は前年に続いて増加していますが、1日午前が減少していることから見ると、レベルの上昇に伴い鴎友学園女子や吉祥女子との競合があるかもしれません。

恵泉女学園 プロテスタント系の恵泉女学園は来春2月2日が日曜日になるため2014年入試に限り午後入試のS方式を実施します(詳細は本シリーズ47話を参照)。予想通りS方式の志望者は午前入試だった今春2回の志望者の171%と大幅増となっています。
実践女子学園は難関大実績が伸びて、今春入試では上位層が増えすべての回で応募者増となり、難易度もアップしました。そのためチャレンジ層に敬遠されているのか1回・2回の志望者は1割以上の減少ですが、国際人の育成を目指す先端的な取り組みで知られるGSC(グローバル・スタンダード・クラス)の午後入試は前年に続き人気が上がって志望者が2割以上の増加です。
品川女子学院は2回・3回の入試日を前倒ししますが、今のところ2回・3回ともに志望者が減っています。
昭和女子大は2014年から少人数クラスへの移行のため定員減となり、A・Bともに70→60名と減員されます。ここ数年応募者数に隔年現象が見られ、今春応募者が大きく減った反動か定員減にもかかわらずA、Bの志望者が大幅に増加していて、入試状況が厳しくなることが予想されます。
東京女学館は1回の志望者が18%増ですが、これは今春導入された一般学級の午後入試に受験生が集中して、1回の応募者数が200→152名と大きく減った反動です。2回午後入試は倍率が高かったので敬遠されたのか志望者が15%減です。今後1回の志望者はまだ増える可能性があります。
山脇学園は都内の中堅女子校では最も勢いのある学校です。保守的なイメージが強い伝統校でしたが、「山脇ルネサンス」と称する学校改革が軌道に乗って、進路においても結果を出しつつあり(本シリーズ49話(2)参照)、一部完成している新校舎人気もあり今春の入試では応募総数が37%増、実受験者では56%増と多くの受験生を集め、都心の中堅女子校ではほとんど一人勝ちの状況でした。その人気ぶりはまだ続いていて、A・B・Cの3回の入試すべてで志望者数を伸ばしています。
(2)神奈川の女子校
神奈川の最上位の女子校は、いずれも横浜山手の丘(横浜市中区)の上にある創立100年を超えるミッション校です。
| フェリス女学院 | 79% | |
| 横浜雙葉 | 86% | |
| 横浜共立 | A | 94% |
| B | 70% | |

フェリス女学院 横浜共立Bが30%の大幅減となっていますが、これは今年の2月3日が日曜日だったため入試日を4日に移動して応募者が急増していたのが、2014年は例年通り3日に戻るためです。さてご覧のとおり最上位の3校すべて志望者が相当に減っています。特にトップのフェリス女学院の減少が20%以上と大きいのも気になるところです。2月1日のこの3校の志望者の合計(3日の横浜共立Bを除く)は1,481→1,273名で14%減です。この最上位層の減少は、3校とも減っているところから、3校の中での志望者の移動ではなく他の要因と思われます。10月以降の状況を見ないとはっきりしたことはわかりませんが、いくつか考えられる減少の要因は、
①安全志向でチャレンジ層が減っている
②共学系の学校に回っている
③東京の有力校に回っている
④今年の神奈川女子受験生は上位層が薄い
⑤今年の神奈川女子受験生自体が減っている
などですが、①については、この3校につぐ県内の2月1日入試校と言えば洗足学園1回、日本女子大1回ですが両校とも志望者は微減です。
②も県内にこの3校と同レベルの2月1日入試の共学校はなく該当しないようです。
②は神奈川寄りの都内の学校で増えているのは、女子学院、鴎友学園女子1次、東洋英和女学院Aで、減少した208名のうちいくらかはこの3校に回った受験生もいるかもしれません。なお模試データからの検証は不可能ですが、都内からの受験生が減っている可能性もあります。
④については検証が難しいのですが、地域的に学力上位層の割合が年によって大きく変動するというのは考えにくく、実際にはあり得ないのではないかと思われます。
一番ありそうなのは⑤ですが、都県別の受験生数を推計するための網羅的なデータがないため、現時点では判断を保留するしかありません。それにしても首都圏全域の受験者数は9月模試からは前年比4%前後の減少と思われ、さすがに14%減は大きすぎるので、③と⑤などの複合的な要因によるものと思われます。
以上の最上位3校に次ぐのは、
| 鎌倉女学院(鎌倉市) | 1回 | 90% |
| 2回 | 92% | |
| 湘南白百合(藤沢市) | 93% | |
| 洗足学園(川崎市高津区) | 1回 | 94% |
| 2回 | 79% | |
| 3回 | 96% | |
| 日本女子大附(川崎市多摩区) | 1回 | 98% |
| 2回 | 106% | |
見ての通りほとんどの学校が志望者数を少しずつ減らしていています。トップ3校からの流れがあるようには見えないのは前述したところです。
洗足学園の2回の減少が大きくなっていますが、ここ数年で桜蔭、女子学院、フェリス女学院などとの併願者が増えて難易度が上がって、通学圏が重なる鴎友学園女子と受験者層が重なるようになったため鴎友学園女子2次に回っている受験生もいる者と思われます。
その他の中堅校では、
| 神奈川学園(横浜市神奈川区) | A1 | 113% |
| A2 | 108% | |
| B | 141% | |
| C | 117% | |
| カリタス女子(川崎市多摩区) | 1回 | 94% |
| 2回 | 104% | |
| 3回 | 103% | |
| 聖セシリア女子(大和市) | 1回 | 99% |
| 2回 | 97% | |
| 3回 | 97% | |
| 清泉女学院(鎌倉市) | 1回 | 104% |
| 2回 | 119% | |
| 聖園女学院(藤沢市) | 1次 | 104% |
| 2次 | 103% | |
| 3次 | 92% | |
| 4次 | 104% | |
| 横浜英和女学院(横浜市南区) | A1 | 66% |
| A2 | 108% | |
| B | 76% | |
| C | 126% | |
| 横浜女学院(横浜市中区) | A | 121% |
| B | 82% | |
| C | 112% | |
| D | 136% | |
| E | 124% |

神奈川学園 神奈川の中堅女子校はここ数年応募者の減少に見舞われた学校が多かったのですが、今年は9月模試の志望動向を見る限り志望者数を回復している学校が増えています。
神奈川の私立女子校では数少ない非宗教系の学校の神奈川学園は学校改革の成果が順調に大学合格実績の伸長に表れていて、国公立大は7名とまだ少ないのですが、その中身は一橋大、北大、東京外語大などを含み、難関私大では早慶上智大が7→8→33名、GMARCH大は45→52→70名と躍進しています。すべての入試回の志望者が増えていますが、併願者が多い午後入試のA2より午前入試のA1、B、Cの増加の方が大きいところから見て受験生の志望順位が上がっていることが予想されます。
横浜女学院は2011年に一時的な応募者減がありましたが、その後は県内の中堅女子校でもっとも安定した応募者数で、実受験者数は2年連続の増加です。今春は今までほとんどいなかった東工大や北大など難関国公立大にも合格者を出し、難関私大では早慶上智大が7→16→27名、GMARCH大は33→41→59名と躍進しています。9月模試の志望者は神奈川学園と同様に午前入試のA、D、Eの増加が大きく受験生の志望順位が上がっていることが予想されます。
清泉女学院はこのところ隔年現象があり来年は増加が予想される年で、9月模試の動向でもそうなる可能性が高そうです。
カリタス女子、聖園女学院、横浜英和女学院の3校はこの2~3年応募者の減少が続いていましたが、ようやく回復の兆しが見えてきました。
3.共学校
今回の(3)は前回の女子校に引き続き共学校の志望動向を見ていきます。大学付属校については最後にまとめて見ていきます。なおMは男子、Fは女子で、各学校の志望者の増減の数値は前年同月実施模試の志望者との対前年比(%)です。
(1)東京の共学校
都内の主な共学進学校の9月模試における志望状況は以下の通りです。
| 穎明館(八王子市) | 1回 | M | 108% |
| F | 77% | ||
| 2回 | M | 106% | |
| F | 100% | ||
| 3回 | M | 100% | |
| F | 95% | ||
| 桜美林(町田市) | 1回AM | M | 56% |
| F | 79% | ||
| 1回PM | M | 71% | |
| F | 75% | ||
| 2回AM | M | 41% | |
| F | 103% | ||
| 2回PM | M | 77% | |
| F | 85% | ||
| 3回 | M | 61% | |
| F | 80% | ||
| 国学院久我山(杉並区) | 1回 | M | 81% |
| F | 92% | ||
| 1回ST | M | 88% | |
| F | 78% | ||
| 2回 | M | 88% | |
| F | 117% | ||
| 2回ST | M | 96% | |
| F | 112% | ||
| 3回 | M | 81% | |
| F | 92% | ||
| 渋谷教育学園渋谷(渋谷区) | 1回 | M | 102% |
| F | 72% | ||
| 2回 | M | 98% | |
| F | 89% | ||
| 3回 | M | 85% | |
| F | 77% | ||
| 淑徳(板橋区) | 1回 | M | 55% |
| F | 106% | ||
| 東大1回 | M | 105% | |
| F | 148% | ||
| 2回 | M | 83% | |
| F | 102% | ||
| 3回 | M | 87% | |
| F | 116% | ||
| 東大2回 | M | 68% | |
| F | 162% | ||
| 順天(北区) | 1回A | M | 90% |
| F | 78% | ||
| 1回B | M | 80% | |
| F | 105% | ||
| 2回A | M | 126% | |
| F | 75% | ||
| 2回B | M | 74% | |
| F | 64% | ||
| 3回 | M | 94% | |
| F | 113% | ||
| 青稜(品川区) | 1回A | M | 112% |
| F | 145% | ||
| 1回B | M | 113% | |
| F | 119% | ||
| 2回A | M | 93% | |
| F | 84% | ||
| 2回B | M | 84% | |
| F | 101% | ||
| 3回 | M | 66% | |
| F | 100% | ||
| 帝京大学(八王子市) | 1回 | M | 115% |
| F | 66% | ||
| 2回 | M | 103% | |
| F | 103% | ||
| 3回 | M | 109% | |
| F | 87% | ||
| 東京都市大等々力(世田谷区) | 特進1回 | M | 110% |
| F | 91% | ||
| 特進2回 | M | 60% | |
| F | 103% | ||
| 特進3回 | M | 61% | |
| F | 119% | ||
| 特選1回 | M | 65% | |
| F | 81% | ||
| 特選2回 | M | 97% | |
| F | 103% | ||
| 特選3回 | M | 73% | |
| F | 161% | ||
| 東京農大一(世田谷区) | 1回 | M | 91% |
| F | 117% | ||
| 2回 | M | 112% | |
| F | 100% | ||
| 3回 | M | 86% | |
| F | 109% | ||
| 広尾学園(港区) | 1回 | M | 96% |
| F | 95% | ||
| 2回 | M | 76% | |
| F | 96% | ||
| 医進 | M | 102% | |
| F | 97% | ||
| 3回 | M | 90% | |
| F | 118% |
都内の共学校で大学付属校を除けば上位校(市進偏差値で60以上)といえるのは渋谷教育学園渋谷(渋谷区)だけです。この2年ほどの大学合格実績が、国公立大では東大が15→16→12名、東大、京大、一橋大、東工大の4大学計では29→27→24名とわずかの減ですが、難関私大は海外大へ30名以上の合格者を出している影響もあるのか、早慶上智大は211→194→155名と大きく減っています。9月模試の志望者は男子の1・2回は前年並みですが、女子は3回とも大きく減っています。今春入試でも女子の2回以外は応募者数が減っていましたから、減少が続いていることになります。特に女子は3回とも減少幅が大きいのが気になりますが、鴎友学園女子や吉祥女子などの勢いのある女子校に押されている可能性もありそうです。

広尾学園 広尾学園は2007年に共学化・校名変更し、先端的な取り組みによって人気が急上昇し応募者が毎年のように増え続け、入試レベルもこの6年間で偏差値15は上がっています。中学の共学1期生が今春卒業し、国公立大は東工大、東京外語大、北大、東北大、旭川医大などを含めて13→20名、早慶上智大は17→62名、アメリカ・カナダの大学に8名と大躍進しています。1期生は入学時の偏差値が40程度でしたから卒業までの6年間で大きく伸びたことがうかがえます。その後の入学レベルの上昇を考えると、今後さらに大学合格実績が伸びていくものと思われます。応募者数は昨年、今年と落ち着いてきていますが、試験回数を減らしたり特待制度を廃止したりして、「量から質へ」の転換を図っているように見えます。9月模試の志望者は医進・サイエンスの男子、3回の女子以外は減っていますが、入試レベルが緩和することは期待できないでしょう。
穎明館は小規模校ながら大学進学実績が高い学校です(本シリーズ第49話を参照)。志望者は男子が増加、女子が減少と男女で対照的ですが、女子の減少は新制服の導入で人気が急上昇し、この2年続いて応募者が急増した反動でしょう。
桜美林は2回午前の女子以外で志望者数が大きく落ち込んでいます。ここ数年の入試で上位校との併願者が増えて難易度が上がってきたことへの敬遠もありそうですが、それ以上にこの春の卒業生の大学合格実績が低下したのが主因でしょう。国公立大の総数は前年同数ながら、昨年は合格者を出した東大、一橋大、東工大、東京外語大などの難関レベルの大学の合格者がいなくなり、早慶上智大も41→19名と激減。これは今年の卒業生数自体が397→266名と大きく減り、またその他の事情が重なったためのこの学年固有の現象で、来年以降は実績を回復していくものと思われます。とはいえこの実績低下によって2014年入試は応募者が相当に減少するのは確実で難易度が緩和する可能性が高いでしょう。
共学化4年目の東京都市大等々力はこの3年間応募者が増え続けていましたが、9月模試の結果を見る限りそろそろブレーキがかかってきているようです。女子はまだ6回の入試のうち4回で増えていますが、男子は6回のうち5回で減少に転じています。おそらく男子は減少幅の大きさから見て、芝や高輪などの勢いのある男子校や巻き返しに転じてきている青稜などとの競合と、難易度の上昇によりチャレンジ層に敬遠されているという2つの要因がありそうです。
淑徳は今春、東大0→1名、一橋大0→1名、東京外語大0→2名、東北大1→2名など最難関国公立大の実績を伸ばしています。ところが女子は5回の入試すべて志望者が増えていますが、男子の志望者は東大1回が微増以外の他の4回は大きく減っています。これだけ難関大の合格実績を伸ばすと男子受験生が増えるのが通例ですから、これは明らかに外部的な要因です。結論的にいえばこれは人気の高い本郷の1日参入の影響でしょう。ただし合否判定は男女合同で、女子は増えていますから難易度が大きく下がることはないでしょう。
青稜は2012年春に国公立大27→51名、早慶上智大40→88名など大きく大学合格実績が伸びて、今春の入試では応募総数が22%増となりました。さらにこの3月の大学合格実績も東大が0→2名、東工大は1→2名など最難関レベルで結果を出し、人気が上がっています。特に2月1日午前の1回Aの女子が相当な増加で第一志望者が増えていることをうかがわせます。女子校から共学化した学校にもかかわらず、一時は女子の応募者が減っていましたが、今年は女子の方の人気が高くなっています。2014年9月には新校舎が完成予定なのも追い風になっているようです。
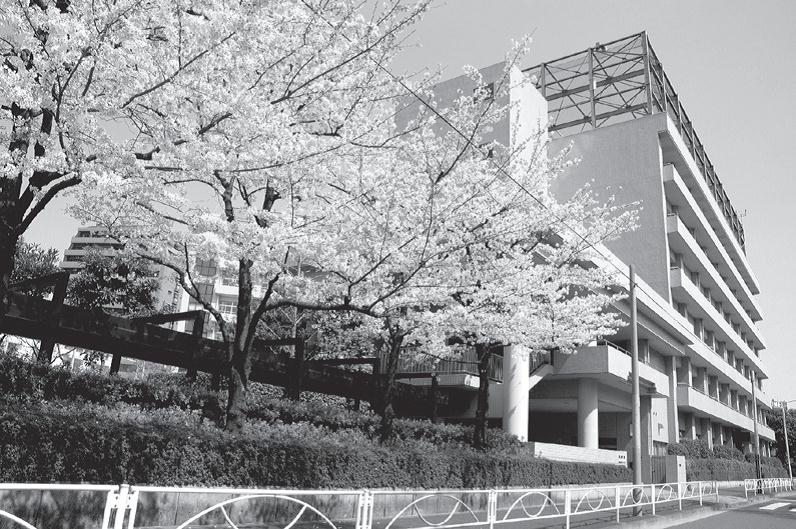
安田学園 なお2014年から共学化される男子校の安田学園(墨田区)の志望者は、9月模試のデータでは6回の入試の志望者合計で男子が250名、女子が100名ほどですが、説明会参加者などでは男女比が3:2とのことですから、女子の志望者は今後まだまだ増えていくものと思われます。また先進コース第1回の合格者20名は入学金・施設設備費、6年間の授業料全額免除ですから、公立一貫校との併願受験者が相当に集まる可能性があります。学校側の狙いもそこにあり、公立一貫型入試の適性検査はすぐ近くの都立両国高附中の出題傾向を意識した作問にするとのことです。またカフェテラスやコンビニを新設した校舎のリニューアル工事が終わり、この8月には中学棟(新南館)も完成しました。
(2)神奈川の共学校
神奈川の主な共学進学校の9月模試における志望状況は以下の通りです。なお神奈川大附と関東学院は併設大への進学者がほとんどいないため、実態に合わせて進学校として考えます、
| 神奈川大附(横浜市緑区) | A | M | 109% |
| F | 95% | ||
| B | M | 100% | |
| F | 90% | ||
| C | M | 73% | |
| F | 90% | ||
| 関東学院(横浜市南区) | 1期A | M | 88% |
| F | 87% | ||
| 1期B | M | 86% | |
| F | 107% | ||
| 1期C | M | 80% | |
| F | 96% | ||
| 2期 | M | 73% | |
| F | 71% | ||
| 湘南学園(藤沢市) | A | M | 125% |
| F | 119% | ||
| B | M | 137% | |
| F | 78% | ||
| C | M | 117% | |
| F | 105% | ||
| D | M | 139% | |
| F | 114% | ||
| 桐蔭学園(横浜市緑区) | 1次 | M | 85% |
| F | 85% | ||
| 中等 | 79% | ||
| 理数 | 89% | ||
| 2次A | M | 139% | |
| F | 57% | ||
| 中等 | 92% | ||
| 理数 | 118% | ||
| 2次B | M | 91% | |
| F | 76% | ||
| 中等 | 75% | ||
| 理数 | 46% | ||
| 3次 | M | 109% | |
| F | 96% | ||
| 中等 | 75% | ||
| 理数 | 97% | ||
| 桐光学園(川崎市麻生区) | 1回 | M | 102% |
| F | 111% | ||
| 2回 | M | 119% | |
| F | 107% | ||
| 3回 | M | 102% | |
| F | 118% | ||
| 森村学園(横浜市緑区) | 1回 | M | 92% |
| F | 85% | ||
| 2回 | M | 127% | |
| F | 94% | ||
| 3回 | M | 97% | |
| F | 90% | ||
| 山手学院(横浜市栄区) | A | M | 91% |
| F | 92% | ||
| B | M | 119% | |
| F | 104% | ||
| C | M | 64% | |
| F | 56% | ||
| 後期 | M | 123% | |
| F | 97% |
神奈川大附はここ数年勢いがありましたが、9月模試の志望者数は男子が前年並み、女子はやや減で、一息ついた感があります。
三春台の丘の上のプロテスタント系ミッション校の関東学院は、全体的に見れば大学合格実績が下がってはいませんが、今年は東大、一橋大、東工大などの目立つような実績がなく、逗子開成、湘南学園、神奈川学園などの勢いに押されているのか1期Bの女子以外は各回とも相当に志望者数を減らしています。特に1期Aは定員増にもかかわらず志望者減で緩和した入試になりそうです。2月6日の2期の減少幅が大きいのは、多くの学校が入試日程を早める中で6日という遅い日程のためかもしれません。

湘南学園 湘南の高級住宅地として知られる鵠沼の湘南学園は、保護者と教職員によって共同運営という全国的にも珍しい学校です。前年春の大学合格実績が大躍進して、今春入試の応募総数がなんと70%増と大人気になりました。今年の大学実績は下がっていますが、あいかわらず人気が続いていて、Bの女子を除いてすべての回で男女とも志望者が相当に増加。上位校との併願者も増えていて今春に続いて難易度が上昇する可能性が高く要注意です。
桐蔭学園は別学の中学校と男子校の中等教育学校は別の学校ですが、入試は一体的に行われているため、ここでまとめて見ておきます。(表中のM、Fは中学校の男子部、女子部、理数は中学女子部の理数コースです。)中等教育学校は東大13名(うち理Ⅲ2名)など大学合格実績を回復。また2014年入試から今まで2次A,Bで出していた特別奨学生合格を1次~3次すべての回で出すことになりました。さらに1次、2次A,Bの入学手続きの締め切りを3次と同じ2月7日まで延長するなどの入試改革を行います。これだけの好条件にもかかわらず9月模試では志望者が増えずむしろ減り気味で、今のところ減少傾向に歯止めがかかっていません。
桐光学園はここ数年応募者の減少が続いていましたが、9月模試では3回の入試で男女とも志望者数が増加に転じています。特に女子は減少が目立ちましたが、今回大きく回復しています。
森村学園は過去最高の大学合格実績を出しましたが、前述の桐光学園、神奈川大附や中大横浜あるいは東京都市大等々力との競合があるのか、2回の男子以外の志望者が減っています。女子に人気が高い学校でしたが、9月模試では女子の志望者の減少が目立っています。
山手学院は国際色豊かな共学の中堅進学校として人気の高い学校です。中高一貫教育へのシフトを強め、午後入試の導入などでしばらくは応募者増が続いていましたが、中大横浜や湘南学園との競合が厳しくなっているのか、この2年間は応募者減が続いていました。しかし9月模試では2月2日午後入試のBは男女とも増加に転じています。Cは4日→3日へ入試日を前倒しして定員を20→10名と減員したため大きく志望者が減っています。
(3)埼玉の共学校
埼玉の主な共学進学校の9月模試における志望状況は以下の通りです。
| 開智(さいたま市岩槻区) | 先端A | M | 93% |
| F | 101% | ||
| 1回 | M | 82% | |
| F | 90% | ||
| 2回 | M | 100% | |
| F | 99% | ||
| 先端B | M | 114% | |
| F | 118% | ||
| 栄東(さいたま市見沼区) | A | M | 105% |
| F | 123% | ||
| 東大Ⅰ | M | 107% | |
| F | 108% | ||
| B | M | 127% | |
| F | 140% | ||
| 東大Ⅱ | M | 87% | |
| F | 138% | ||
| 西武学園文理(狭山市) | 1回 | M | 91% |
| F | 74% | ||
| 1回特選 | M | 101% | |
| F | 110% | ||
| 2回 | M | 65% | |
| F | 65% | ||
| 2回特選 | M | 49% | |
| F | 109% | ||
| 3回 | M | 92% | |
| F | 55% | ||
| 3回特選 | M | 191% | |
| F | 142% | ||
| 春日部共栄(春日部市) | 1回 | M | 76% |
| F | 82% | ||
| 2回 | M | 103% | |
| F | 109% | ||
| 3回 | M | 85% | |
| F | 103% |
東京・神奈川の私立中入試が2月1日から始まるのに対し、埼玉は1月10日、千葉の一般入試は1月20日が入試解禁日となっています。そのため埼玉・千葉の1月入試の、特に東京からのアクセスの良い学校には東京・神奈川の受験生が大量に「試し受験」していることはよく知られています。東京・神奈川の「試し受験生」はほとんどが合格しても入学しないため、「試し受験生」が増えても入学者の確保のために合格者も増やしますから、難易度がかえって低下することもあり、模試の志望動向から入試状況、特に難易度を予測するのがなかなか難しいことをご理解ください。
さて開智と栄東の2校は上位から中位まで県内・県外から大量の受験生を集める学校です。ここ数年の埼玉の中学入試はこの2校を軸に動いていると言っても過言ではありません。この2校は激しい競合関係にあり、2014年入試では両校ともお互いを意識した大きな入試変更を行います。(詳細は本シリーズ47話を参照)
開智は先端Aの入試日を入試解禁初日の1月10日に前倒しして栄東のAにぶつけ、定員も30→85名と大幅に増員、一貫1回は130→85名と大幅減員、残りの2回は5名ずつの減員です。9月模試の志望者は定員増の先端Aの男子がやや減、女子は微増ですから今のところ学校の狙いは成功していません。一貫1回は男女とも減っていますがこれは定員減ですから当然です。一貫2回は前年並み、先端Bは50→45名と減員ながら内訳では先端30→35名・一貫20→15名と先端の実質増が好感されたのか男女とも10%以上の増です。

栄東 栄東も難関Aを110→140名に増員すると同時に難関Aの定員140名の中に東大クラス20名の定員を設けます。しかも標準的レベルの出題で合格者を多く出すとアナウンスして栄東への誘導をはかっています。これが功を奏しているのか、難関Aは男女とも志望者増、80→50名と定員減の東大Ⅰも志望者増、20→40名と定員増の難関Bは大幅に志望者増です。以上から見て、開智と栄東の攻防は9月段階では明らかに栄東に軍配が上がるようです。
西武学園文理は県西部の最有力校ですが、上記の2校の勢いに押されているのか今春の入試では応募総数が5%減で、この傾向は今年も続いていますが、特選は特待生選抜を兼ねていて2回の男子以外は増えています。
春日部共栄はこの2年間で大きく応募者が減っていますが、2014年入試では大きな入試改革を行います。総定員を120→160名と増員し、試験回を3回→4回に増やし、グローバル・エリート・クラス(GE)を新設。GEの1回~3回の入試は午後入試になります。また一般クラスの名称もグローバル・スタンダード・クラス(GS)と変わります。しかしこの大きな入試改革も発表が遅かったためか、まだ十分に周知されていないようで、9月模試にはまだ入試改革は反映されていないようです。
*栄東の東大Ⅲ、西武学園文理の4回、春日部共栄の4回は模試データが少ないため割愛しました。
(4)千葉・茨城の共学校
千葉・茨城の主な共学進学校の9月模試における志望状況は以下の通りです。
| 渋谷教育学園幕張(千葉市美浜区) | 1回 | M | 99% |
| F | 95% | ||
| 2回 | M | 110% | |
| F | 110% | ||
| 市川(市川市) | 1回 | M | 99% |
| F | 102% | ||
| 2回 | M | 94% | |
| F | 92% | ||
| 東邦大東邦(習志野市) | 前期 | M | 104% |
| F | 112% | ||
| 後期 | M | 87% | |
| F | 117% | ||
| 芝浦工大柏(柏市) | 1回 | M | 100% |
| F | 94% | ||
| 2回 | M | 136% | |
| F | 94% | ||
| 昭和学院秀英(千葉市美浜区) | 2回 | M | 113% |
| F | 103% | ||
| 3回 | M | 103% | |
| F | 109% | ||
| 専修大松戸(松戸市) | 1回 | M | 97% |
| F | 107% | ||
| 2回 | M | 101% | |
| F | 101% | ||
| 3回 | M | 150% | |
| F | 113% | ||
| 江戸川学園取手(取手市) | 1回 | M | 114% |
| F | 94% | ||
| 2回 | M | 112% | |
| F | 94% | ||
| 3回 | M | 229% | |
| F | 130% |
*芝浦工大柏の3回はデータ件数が少なく、昭和学院秀英 の1回は第一志望入試でデータがないため割愛しました。
以上の7校の最後の回の入試はすべて2月入試で東京の入試日程と重なるため、模試の志望動向と本番入試の応募者数に大きな乖離が生じます。そのため入試動向というより人気度を測る資料としてみてください。

東邦大東邦 千葉御三家ともいわれる、渋谷教育学園幕張、市川、東邦大東邦の3校では東邦大東邦の増加、特に女子の増加が目につきます。渋谷教育学園幕張は男子が前年並みで女子が5%減ですから、女子受験生の一部が安全志向から東邦大東邦に回っているのかもしれません。
昭和学院秀英はここ2年ほど応募者の減少が続いていましたが、一橋大1→4名、東工大2→3名、阪大0→1名、東北大1→2名、北大1→2名、千葉大21→38名など難関国公立大の実績を伸ばして、9月模試では男女とも志望者数を伸ばしています。特に男子の2回は2012年並みの応募者に回復しそうな勢いです。
江戸川学園取手は茨城のトップ進学校ですが、受験生の出身地は地元の茨城が3割、千葉が6割、その他が1割と千葉からの受験生が非常に多い学校です。東大が11→13名、一橋大1→2名、東工大2→4名、東北大4→10名、北大3→5名、千葉大6→16名、筑波大17→19名と難関国公立大の実績を伸ばし、男子の志望者は相当に増えていますが、女子は逆に減っています。
(5)大学付属校
ここで主要な大学付属校(大学系列校)について別学校を含め、まとめて見てみます。なお主要な大学付属校は、卒業生の大半が併設大学に進学する早慶大、GMARCH大に限定します。これ以外は東海大系を除くと、卒業生の進路状況から見て進学校化している学校が多く、実態として「付属校」というカテゴリーではくくりきれないからです。
| 慶應普通部(横浜市港北区) | M | 98% | |
| 慶應中等部(港区) | M | 98% | |
| F | 84% | ||
| 慶應湘南藤沢(藤沢市) | M | 100% | |
| F | 96% | ||
| 早大高等学院(練馬区) | M | 113% | |
| 早稲田実業(国分寺市) | M | 84% | |
| F | 81% | ||
| 明大明治(調布市) | 1回 | M | 86% |
| F | 119% | ||
| 2回 | M | 77% | |
| F | 119% | ||
| 明大中野(中野区) | 1回 | M | 95% |
| 2回 | M | 92% | |
| 明中八王子(八王子市) | 1回 | M | 109% |
| F | 85% | ||
| 2回 | M | 94% | |
| F | 98% | ||
| 青山学院(渋谷区) | M | 100% | |
| F | 77% | ||
| 立教池袋(豊島区) | 1回 | M | 98% |
| 2回 | M | 110% | |
| 立教新座(新座市) | 1回 | M | 91% |
| 2回 | M | 98% | |
| 立教女学院(杉並区) | F | 91% | |
| 中央大附(小金井市) | 1回 | M | 82% |
| F | 85% | ||
| 2回 | M | 78% | |
| F | 91% | ||
| 中央大横浜(横浜市都筑区) | 1回 | M | 80% |
| F | 87% | ||
| 2回 | M | 91% | |
| F | 78% | ||
| 3回 | M | 81% | |
| F | 83% | ||
| 法政大学(三鷹市) | 1回 | M | 82% |
| F | 85% | ||
| 2回 | M | 78% | |
| F | 91% | ||
| 法政大学第二(川崎市中原区) | 1回 | M | 112% |
| 2回 | M | 103% | |
| 学習院(豊島区) | 1回 | M | 109% |
| 2回 | M | 118% | |
| 学習院女子(新宿区) | A | F | 89% |
| B | F | 68% | |
慶應普通部は2012年に応募者が大幅に減りましたが今春入試では微減で、9月模試でも志望者は微減です。
慶應中等部の男子は前年並みの志望者数ですが、女子は2010年から3年連続で応募者を減らし、今春入試ではわずかながら回復しましたが、9月模試データから見ると再び大きく減少に転じそうです。その要因としては、青山学院が2月2日の日曜日を避けて3日への入試日移動、また東洋英和女学院Bが4日から3日に戻り、併願受験者が多い両校の入試日と重複するという事情があります。とはいえこの2校に回るのは主にチャレンジ層で、女子の定員は少ないため難易度への影響はほとんどないでしょう。
慶応湘南藤沢は女子の志望者数がやや減っています。男子は2012年に大きく減りましたが、今春は微減で9月の志望者数は前年並みです。

早大高等学院 早大高等学院は中学部を開設して4年目となり、1期生が高校に進学しました。開校初年度の応募者数が442名と超有名大学の附属校にしては少なく、2年目に大きく増えましたが、その後2年間で536→472→352名大きく減っています。さすがにここまで減ると反動があるのか、9月模試の志望者は13%増で前年並みに応募者数を回復しそうです。
早稲田実業の男子は応募者数に隔年現象があり、今春入試では7%増でしたから来春は減る年にあたりますが、16%減はやや大きいように思えます。女子は19%減で、男子より大きく減っています。
GMARCH大の系列校で目につく志望者増は、明大明治の女子、明中八王子の1回の男子、法政大学第二、学習院の4校です。
学習院の併設大学への推薦率は46%で、半数以上は他大学進学です。主な他大学は東大5名、京大1名、一橋大4名、東工大3名、早慶上智大110名などでこれが人気の主要因でしょう。
青山学院は今年の入試で日曜日を避けて3日入試となりました。3日入試だった10年前の2003年は応募者が2割増となりましたが、この春は男女ともに応募者が大きく減っています。結局この3年間で、男子は513→452→275名、女子は641→629→427名と大幅な減少です。9月模試で男子は前年並みとしていますが、女子はさらに大きく減りそうです。このままいけば女子の難易度は緩和する可能性大です。
中央大学横浜は2012年の共学化で大人気になりましたが、今春入試ではだいぶん落ち着いてきました。9月模試では志望者が男女各回の入試とも減少に転じています。上位校併願者が急激に増えて倍率・難易度が上がりすぎていた反動とともに、共学化当初は強調されていた他大学進学のトーンが下がり附属色を強めているために、志望順位の高い受験生に絞られてきているのではないでしょうか。
[次回予告] 「2014年中学入試予想 第2弾――10月公開模試から入試動向を読む――」
次回51話は今回につづき10月の大手公開模試データから2014年中学入試を予測します。9月からの変化が見られる学校および注目される中堅校(男子校・女子校・共学校)を中心に見ていきます。