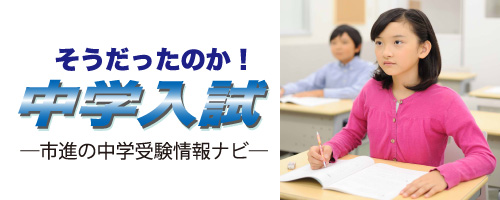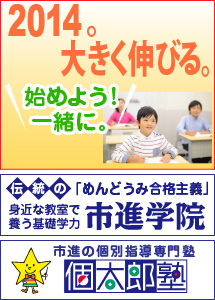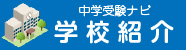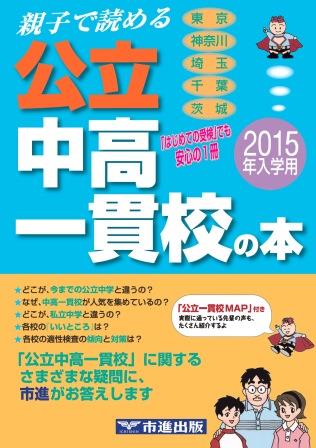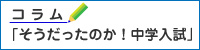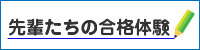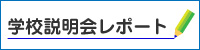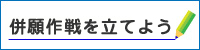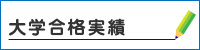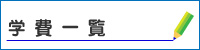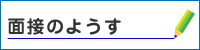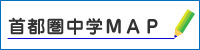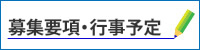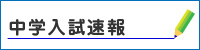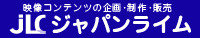トップページ > コラム「そうだったのか!中学入試」第41~50話 > 第48話 「2013年大学入試で伸びた中高一貫校を考える(1)」
第48話 「2013年大学入試で伸びた中高一貫校を考える(1)」
2013年10月3日
今回は、いろいろな学校の大学合格実績を見ていくにあたり、まず基本的な視点、あるいは切り口について考えてみます。次回は本題の2013年の大学入試で大きく伸びたいくつかの学校について見てみます。
1.大学合格(進学)実績の見方について
様々な大学受験に関する資料を見ていると、「進学実績」と称するものの多くは「合格実績」で、両者が混同、混用されていることが多いのに気づきます。国公立大学の合格者は1人1校ですが、私立大学は1人で複数の大学・学部を受験し、数校に合格することが多いので、「合格者数」と「進学者数」に大きな乖離が生ずることも珍しくありません。特に一般入試で何校も併願受験する生徒が多い上位校ほどその乖離は大きいのが普通です。進路状況の実態は現浪別・大学別の「進学者数」を見なければ正確なところがわかりませんが、大学別の「進学者数」を公表していない学校も多いため、今回は「合格者数」のデータを使って見ていきます。なおこの問題については本シリーズ第16話を参照してください。それではいくつかの切り口から大学合格実績の見方について考えてみます。
(1)大学進学状況の推移を見る
当然のことながら、どの学校でも大学進学状況が毎年同じということはあり得ません。私たちはしばしば大学進学実績が「伸びている」、「停滞している」、「低下している」などと評価しますが、実績を去年と今年の2年間だけの比較で判断するのはあまりに短絡的です。せめて3年間、できれば5年間ぐらいの実績の推移を見ておきたいものです。 さてここでは一気に10年前までさかのぼって実績の推移を見てみます。1例としてデータがとりやすい東大合格者数の10年間の推移によって大学進学状況の変化を考えてみます。ここでは「東大合格者数」の方ではなく「10年間の推移」の方に注目して見てください。取り上げるのは首都圏の国私立中高一貫校です。したがって灘やラ・サールのような地方の学校や都立日比谷高校や県立浦和高校のような公立高校は除いてあります。なお首都圏の公立一貫校は一貫教育校に改編されて以降に東大合格者が2桁以上になった学校はまだありません(最高は今年の都立桜修館の6名)。以下は2013年の東大合格者数(現浪計)が10名以上の学校34校の10年間(2004→2013)の合格者数推移で、2013年春の合格者数の順に並べたものです。
こうして10年間の推移を見ると、3年間、5年間の推移では気がつかなかったいろいろなことが見えてきます。いくつかのポイントを指摘しておくと、

開成 ①トップの開成は合格者の絶対数が多いから当然とも思えますが、年によって上下に起伏が大きく、最高203名から最少138名と落差が大きくなっています。2006年から2007年にかけて50名増え、2008年から2009年にかけては50名減っています。しかしその後の推移を見ていくと、2008年~2009年の2年間だけを見て「開成の凋落」などと言うのはとんだ見当違いということになります。10年間を通してみると、少々大きいですが「誤差の範囲」と言ってよさそうです。10年間の平均は171名ですから、170±30名の範囲と言えるでしょう。 2位の筑波大駒場は80名台から100名台を上下していますが、どういうわけかこの10年間では90名台になった年がありません。 このようなトップクラスの学校で、大きく東大合格者が減っている年は、その学年の医学部志向が高い場合や、前の学年の現役合格が多かったので、浪人受験生が少なかったといった場合が多いようです。もちろんこれの逆の場合もあります。
② 10年間を通して増加傾向も減少傾向もなく、増減はありますがその幅が小さい、つまり比較的安定している学校があります。 3位の麻布、5位の桜蔭、8位の駒場東邦、9位の栄光学園、10位の海城、11位の筑波大、12位の女子学院、23位の江戸川学園取手、30位の雙葉、33位のフェリス女学院などです。例外的に増減が大きい年もありますが、他の年は比較的小幅な変動で安定しています。

豊島岡女子学園 ③この10年間で増加傾向が見てとれる学校
6位の聖光学院は2005年から2009年までが40名台で、その後の4年間は60名台で定着しています。
14位の豊島岡女子学園も前半の10名台からこの4年間はほぼ20名台に定着。
21位の攻玉社は前半の1桁からこの4年間は10名台で定着。
26位の渋谷教育学園渋谷と栄東はここ3年間10名台をキープ。
同じく25位の世田谷学園と31位の東邦大東邦はこの2年間10名台をキープ。
7位の渋谷教育学園幕張はこの2年間大きく伸びて初の全国ベスト10にランクイン。
20位の芝は2000年、2001年と振るわなかったが、この2年間は着実に伸びているように見えます。
21位の逗子開成、23位の市川、29位の鴎友学園女子は今春大きく伸びています。
④ この10年間で減少傾向が見てとれる学校 16位の巣鴨と18位の桐蔭学園はこの10年であきらかに減ってきています。さらにさかのぼれば、両校ともかつては東大合格者全国ベスト10の常連だった時期があり、過去最高はともに1992年で、巣鴨が78名、桐蔭学園は114名でした。 この10年間では大きな変化は見えないけれど、さらに10年ほどさかのぼってみると、13位の武蔵は特に多かった1992年で85名、その前後は60名台の年が多かったので、やはり20年単位で見ると相当な減少といえます。4位の東京学芸大附もここ数年は50名台の年が多いのですが、90年代は90名前後の年が多く、1993年は103名でした。17位の桐朋もここ数年は20名台ですが、90年代では40~50名台が多かったので、やはり両校ともこの20年の推移を見ると相当に減少しています。
この10年間では大きな変化は見えないけれど、さらに10年ほどさかのぼってみると、13位の武蔵は特に多かった1992年で85名、その前後は60名台の年が多かったので、やはり20年単位で見ると相当な減少といえます。4位の東京学芸大附もここ数年は50名台の年が多いのですが、90年代は90名前後の年が多く、1993年は103名でした。17位の桐朋もここ数年は20名台ですが、90年代では40~50名台が多かったので、やはり両校ともこの20年の推移を見ると相当に減少しています。
(2)学校規模を考慮する
例えば東大合格者が20名のA校と30名のB校ならB校の方が10名多いから実績が良いかというと、必ずしもそうは言いきれません。学校規模つまり卒業生数を考慮する必要があるのは今や常識でしょう。上記でA校の卒業生数が200名なら10%で、B校が500名なら4%ですから断然A校の実績の方が良いということになるでしょう。次に先ほど10年間の推移を見た首都圏中高一貫校34校を、合格者数順ではなく、2013年の卒業生数に占める東大合格者(現浪計)の割合の高い順に並べてみました(学校名の右の数字は今春卒業生数、学校名の左の数字は、左が合格者数の順位、右は割合の順位)。

栄光学園 合格者数では圧倒的に開成が多いのですが、合格者の割合では1学年4クラス約160名と生徒数が少ない筑波大駒場が圧倒的に高くなることがわかります。
また学校規模が小さい栄光学園は9位→3位、武蔵は13位→10位、暁星は19位→15位、そのほか渋谷教育渋谷は25位→20位、世田谷学園は25→22位、鴎友学園女子は29位→25位とかなり順位を上げます。
逆に学校規模が大きい東京学芸大附は4位→8位、また海城は10位→13位、豊島岡女子は14位→17位、市川は23位→28位、城北と栄東は25→29位、開智は30→33位、また桐蔭学園は18位→31位と大きく順位が下がります。
なお合格者数が10名未満なので上記には入っていませんが、合格者の割合で桐蔭学園の1.4%より高い首都圏の中高一貫校として以下の11校があります。
(3)現役合格率について考える
「現役合格率」という言葉の使い方はいくつかあって、
① 1学年中の現役合格した割合を表す場合。たとえば、A高校の卒業生200名中、現役合格した人数(少なくとも1校には合格した、延べ人数ではない実人数)が120名であれば、A高校の現役合格率は60%。
② 1学年中の特定の大学に現役合格した割合を表す場合。たとえば卒業生が200名だったB高校の東大現役合格者が12名なら、B高校の東大現役合格率は6%。
③ 特定の大学の合格者のうち現役合格者の割合を表す場合。たとえば、C高校から東大合格者が現浪あわせて20名合格したが、そのうち現役は12名ならC高校の東大現役合格率は60%。
④ 特定の大学を受験した現役受験生のうち合格した割合を表す場合。たとえば、D高校の現役生が40-名東大を受験し12名が合格したら、D高校の東大現役合格率は30%。
ほとんどの場合は①、②か③の意味で使われています。④は「○○人受験して△△人合格」という「合格率」の本来の意味に即した使い方なのですが、受験者数を公表している学校はほとんどないため④の意味の合格率が外部に出ることはまずありません。(とはいえ内部的には非常に重要な数字です。)
さて多くの人は①の意味の「現役合格率」や「現役進学率」は高ければ高いほどよいと考えているでしょう。確かに「現役で合格(進学)する方がよいに決まっている」というわけです。ところがこれはそう簡単な話ではないのです。
以下は2年前のデータによるものですが、本シリーズ第17話で首都圏の主要な私立中高一貫校の「現役進学率」を、学校の入学レベル別、男子校、女子校、共学校別に集計したものです。詳細は第17話を読んでいただくしかありませんが、ここに総括的な結論を再掲します。
まず学校の入学レベルを以下のようにA~Cの3グループにわける。
Aグループ (市進偏差値で65~70, 最難関レベルの学校)
Bグループ (市進偏差値で55~64, 上位レベルの学校)
Cグループ (市進偏差値で40~54, 中堅レベルの学校)
入学レベル別に男子校,女子校,共学校の「現役進学率」の平均をまとめると、
ご覧のとおり「現役進学率」は男子校、女子校、共学校のいずれにおいても学力上位のグループになるほど低く、またすべてのグループで「現役進学率」は男子校、共学校、女子校の順に高くなっていきます。どうしてこのような状況になるのでしょうか。
まず男女で現役進学に対する志向、執着度にかなりの差があります。男子に比べて、女子は浪人を避ける受験生が多いのはよく知られていることです。
また現役進学率が高い学校はB、Cグループの学校に多く、とりわけ中堅レベルのCグループの学校の実態としては
・推薦入試やAO入試を利用した受験生が多い
・難関大学をチャレンジするのはごく少数
・第一志望が不合格でも受かった大学で進学を決める
といった場合が多いようです。
逆に上位校では現役進学率の低い学校が増えてきます。実態としては、
・推薦入試やAO入試を利用した受験生は少ない
・難関大学をチャレンジする受験生が多い
・第一志望が不合格なら浪人しても初志貫徹の受験生がかなりいる
特に東大などの難関国公立大や医学部志向が強いAグループの最難関レベルの学校ほどこの傾向が強く、そもそも東大や国立大医学部しか受験しない受験生がかなりいる、さらに早慶上智大も1学部しか受験しないし、合格しても浪人して東大や国公立大医学部などにリベンジする受験生がかなりいる、というわけで必然的に「現役進学率」は低くなります。
ただし上記の集計はあくまで各グループの平均であり、実際には同じAグループの男子校でも「現役進学率」にはかなりの差があり、たとえば今春卒業した学年の場合、開成55%、筑波大駒場63%、駒場東邦54%、栄光学園59%、聖光学院78%、(麻布は2013年データがないが例年40%前後)と50%台から70%台までとまちまちです。この差は何に起因するのでしょうか。これは現役での進学への志向性の強弱、あるいは東大(や国公立大医学部)合格への志向性の強弱によるものと思われます。
「現役進学率」が78%と非常に高い聖光学院は、1990年ごろまでは早慶上智大をメインターゲットにする学校でした。ここ20数年で急速に難関国公立大受験にシフトしていますが、東大受験者も早慶大のバックアップをとって受験しており、東大不合格なら、多くは浪人せずに早慶大に進学します。
これに対し、東大合格者全国1位を30年以上続ける開成では、そもそも東大しか受けていない受験生や、早慶大は合格しても東大がだめなら浪人してリベンジという受験生が多く、「現役進学率」は54%と低くなっています。
これは早慶大の「現役合格率」の差からも裏付けられます。聖光学院の早慶大現役合格率115%に対し、開成は45%と大きく下回ります。この差が生じる理由は、もちろん開成の生徒の学力が聖光学院より低いためではなく、開成の早慶大現役受験者が少ないためです。ただし浪人の場合は逆に開成が45%、聖光学院は35%となります。
都内の最上位男子校、開成、麻布、駒場東邦の3校は東大や国公立大医学部などの最難関レベルの国公立大志向が非常に強く、浪人することも辞さない生徒が多いようです。これに対し神奈川の男子トップ2校、栄光学園、聖光学院は現役進学率が60~70%で都内の3校より高目なのは、生徒の志向性あるいは受験への取り組み方などの違いでしょう。

女子学院 女子のAグループの学校の「現役進学率」は男子校ほどの差がなくほとんど80%弱ですが、東大など国公立大や医学部志向が強い桜蔭が75%、豊島岡女子が71%、またここ数年国公立大志向が高くなってきている女子学院は73%とやや低くなっているのは、男子校と程度の差はあれども同様な事情でしょう。
(4)文系進学と理系進学
今回は部分的に触れるにとどめますが、文系・理系の比率(の推移)や学部・系統別の進路状況も重要なファクターであることは論を待ちません。ここでは「理系志向」と「国公立大志向」の関係について指摘しておきます。
個々の生徒の適性という問題はありますが、一般的にいって学校(生徒)の学力レベルが上昇すると理系志望者が増えていく傾向があります。上の学年になるほど増えていた理系→文系への進路変更(いわゆる文転)が減ってきているということもありそうです。近年の理系志向、医学部志向の高まり、あるいは女子の場合、伝統的に文系の進路選択していた高学力層が理系の進路選択をするようになってきた(理系女子、リケジョの増加)ことに後押しされている要素もあるでしょう。
さて芝浦工大や北里大のような理工系、医学・医療系大学を除いて、ほとんどの私大は文系学部が中心です。全国の私立大学の募集定員は、教員養成系、芸術系、体育系、生活系などを除くと文系学部と理系学部が2:1です。
逆に国公立大は一橋大や東京芸術大など一部を除き理系学部の定員の方が多く、研究の実績でも圧倒的に優位にあります。全国の国立大学の募集定員は、教員養成系、芸術系、体育系、生活系などを除くと文系学部と理系学部がちょうど私大と逆に1:2なります。ちなみに東大の前期日程の募集定員は文系が41%、理系が59%です。(後期日程は理Ⅲを除く一括募集)
したがってこの日本の大学の構造的なあり方に規定されて、「学力レベル上昇」→「理系志望者増加」→「国公立志望者増加」という「進化」の定式がほとんどの学校に当てはまります。ただし学校の個性や男子校、女子校、共学校の違いによって「進化」のしかたに差がありますから、そのあたりもしっかり見ていく必要があるでしょう。
(5)大学のグレード別グルーピングについて
大学進学について語るとき、大学を入学レベル別に、「早慶上智」、「MARCH」、「日東駒專」、「大東亜帝国」あるいは「女子大御三家」などの語呂の良いグループ名をつけて呼ぶことがあります。関西圏では「関関同立」[産近甲龍]などが使われています。これにはいろいろなバリエーションがあり、たとえば「早慶上智」に東京理科大を加えて「早慶上理」、あるいは「MARCH」に学習院を加えて「GMARCH」といったところはすでに市民権を得ているようです。大変便利で現在では一般化しているため、本シリーズでもしばしば使っていますが次のような問題もあります。
これらのくくりは入学レベルが近い大学のグループを表わしていると考えられていますが、実際には同じ大学でも学部・学科による差があり、またほぼ同レベルの大学がグループに入っていないようなこともあります。たとえば武蔵、成蹊、成城などの大学の入学レベルは学部・学科によってはGMARCHと同レベルなのに、このグルーピングではこれらの大学(の合格者)はカウントされません。また男女による進路志向の違いもこのグルーピングではうまくとらえることができません。たとえば女子ではGMARCHや日東駒專のかわりに女子大や医療系大学を受験する受験生も多いのです。さらに個性を重視し、美術系、音楽系、国際系、教養系など多彩な進路を特色としている学校は、このくくり方では全く進路傾向をとらえることができません。というわけで上記のくくり方は大学進学状況のおおざっぱな傾向は見ることができても、細かく見ていくといろいろ問題があることを承知しておいた方が良いでしょう。
なお国立大にはあまり語呂のよいグループ名はなく、あえて言えば旧制の帝国大学だった東大、京大、東北大、北大、阪大、名大、九大を指す「旧7帝大」や昔の入試制度による「旧一期校」「旧二期校」という呼称が現在でも一定の有効性を持つものとして使われることがあります。また首都圏の学校の場合は「東大・京大・一橋大・東工大」あるいは「旧7帝大プラス一橋大・東工大」さらにこれに「国公立大医学部(医学科)」を加えたくくりで最難関国立大学とすることがあります。ちなみに一橋大・東工大をほとんど受験しない関西圏での難関国公立大のグループ名は「京大・阪大・神戸大」が一般的です。
1.大学合格(進学)実績の見方について
様々な大学受験に関する資料を見ていると、「進学実績」と称するものの多くは「合格実績」で、両者が混同、混用されていることが多いのに気づきます。国公立大学の合格者は1人1校ですが、私立大学は1人で複数の大学・学部を受験し、数校に合格することが多いので、「合格者数」と「進学者数」に大きな乖離が生ずることも珍しくありません。特に一般入試で何校も併願受験する生徒が多い上位校ほどその乖離は大きいのが普通です。進路状況の実態は現浪別・大学別の「進学者数」を見なければ正確なところがわかりませんが、大学別の「進学者数」を公表していない学校も多いため、今回は「合格者数」のデータを使って見ていきます。なおこの問題については本シリーズ第16話を参照してください。それではいくつかの切り口から大学合格実績の見方について考えてみます。
(1)大学進学状況の推移を見る
当然のことながら、どの学校でも大学進学状況が毎年同じということはあり得ません。私たちはしばしば大学進学実績が「伸びている」、「停滞している」、「低下している」などと評価しますが、実績を去年と今年の2年間だけの比較で判断するのはあまりに短絡的です。せめて3年間、できれば5年間ぐらいの実績の推移を見ておきたいものです。 さてここでは一気に10年前までさかのぼって実績の推移を見てみます。1例としてデータがとりやすい東大合格者数の10年間の推移によって大学進学状況の変化を考えてみます。ここでは「東大合格者数」の方ではなく「10年間の推移」の方に注目して見てください。取り上げるのは首都圏の国私立中高一貫校です。したがって灘やラ・サールのような地方の学校や都立日比谷高校や県立浦和高校のような公立高校は除いてあります。なお首都圏の公立一貫校は一貫教育校に改編されて以降に東大合格者が2桁以上になった学校はまだありません(最高は今年の都立桜修館の6名)。以下は2013年の東大合格者数(現浪計)が10名以上の学校34校の10年間(2004→2013)の合格者数推移で、2013年春の合格者数の順に並べたものです。
| 1. | 開成 | 177→166→140→190→188→138→168→172→203→170 |
| 2. | 筑波大駒場 | 83→105→86→84→75→106→100→103→83→103 |
| 3. | 麻布 | 69→84→89→97→76→77→91→79→90→82 |
| 4. | 東京学芸大附 | 93→78→77→72→77→74→54→58→55→68 |
| 5. | 桜蔭 | 80→64→68→68→59→69→67→75→58→66 |
| 6. | 聖光学院 | 32→49→44→48→44→49→65→60→65→62 |
| 7. | 渋谷教育学園幕張 | 16→38→26→30→35→28→47→34→49→61 |
| 8. | 駒場東邦 | 57→64→46→42→38→39→61→64→69→59 |
| 9. | 栄光学園 | 49→56→70→44→42→59→57→63→70→52 |
| 10. | 海城 | 40→60→52→51→44→34→49→34→47→40 |
| 11. | 筑波大附 | 38→31→44→40→25→43→40→36→31→38 |
| 12. | 女子学院 | 30→37→28→19→26→23→26→32→23→37 |
| 13. | 武蔵 | 26→34→30→26→17→20→24→28→20→29 |
| 14. | 浅野 | 22→25→14→42→29→25→36→32→29→27 |
| 14. | 豊島岡女子学園 | 9→10→14→14→12→17→24→13→25→27 |
| 16. | 巣鴨 | 48→40→29→26→22→22→16→30→41→24 |
| 17. | 桐朋 | 43→29→32→24→32→22→21→32→25→23 |
| 18. | 桐蔭学園 | 42→42→23→33→28→20→15→24→15→18 |
| 19. | 暁星 | 16→10→13→10→13→7→8→14→9→17 |
| 20. | 芝 | 2→12→8→7→10→12→6→5→14→16 |
| 21. | 攻玉社 | 7→13→7→7→9→6→18→14→19→14 |
| 21. | 逗子開成 | 1→2→7→6→6→4→4→4→4→14 |
| 23. | 市川 | 3→3→6→4→6→4→5→4→6→13 |
| 23. | 江戸川学園取手 | 12→16→18→14→20→5→11→8→11→13 |
| 23. | 早稲田 | 7→5→11→11→14→14→16→14→23→13 |
| 26. | 世田谷学園 | 4→5→2→2→3→4→4→7→12→12 |
| 26. | 城北 | 29→14→16→17→12→15→20→25→16→12 |
| 26. | 栄東 | 4→3→5→1→4→11→6→12→11→12 |
| 26. | 渋谷教育学園渋谷 | 2→4→9→23→14→4→2→15→16→12 |
| 30. | 雙葉 | 8→11→10→9→13→9→15→16→10→11 |
| 30. | 開智 | 2→6→6→3→9→7→4→17→9→11 |
| 30. | 鴎友学園女子 | 5→4→3→6→1→3→1→3→4→11 |
| 33. | フェリス女学院 | 10→12→9→6→7→10→6→11→12→10 |
| 33. | 東邦大東邦 | 4→4→7→5→4→4→2→7→10→10 |
| *桐蔭学園は男子部・女子部、および2007年以降は中等教育学校も含めた合計 | ||
|
*全国順位ベスト10には上記で9位の栄光学園までが入っている。 10位内に入っている地方の学校は合格者105名の灘(神戸市灘区)のみ。 |
||
こうして10年間の推移を見ると、3年間、5年間の推移では気がつかなかったいろいろなことが見えてきます。いくつかのポイントを指摘しておくと、

開成 ①トップの開成は合格者の絶対数が多いから当然とも思えますが、年によって上下に起伏が大きく、最高203名から最少138名と落差が大きくなっています。2006年から2007年にかけて50名増え、2008年から2009年にかけては50名減っています。しかしその後の推移を見ていくと、2008年~2009年の2年間だけを見て「開成の凋落」などと言うのはとんだ見当違いということになります。10年間を通してみると、少々大きいですが「誤差の範囲」と言ってよさそうです。10年間の平均は171名ですから、170±30名の範囲と言えるでしょう。 2位の筑波大駒場は80名台から100名台を上下していますが、どういうわけかこの10年間では90名台になった年がありません。 このようなトップクラスの学校で、大きく東大合格者が減っている年は、その学年の医学部志向が高い場合や、前の学年の現役合格が多かったので、浪人受験生が少なかったといった場合が多いようです。もちろんこれの逆の場合もあります。
② 10年間を通して増加傾向も減少傾向もなく、増減はありますがその幅が小さい、つまり比較的安定している学校があります。 3位の麻布、5位の桜蔭、8位の駒場東邦、9位の栄光学園、10位の海城、11位の筑波大、12位の女子学院、23位の江戸川学園取手、30位の雙葉、33位のフェリス女学院などです。例外的に増減が大きい年もありますが、他の年は比較的小幅な変動で安定しています。

豊島岡女子学園 ③この10年間で増加傾向が見てとれる学校
6位の聖光学院は2005年から2009年までが40名台で、その後の4年間は60名台で定着しています。
14位の豊島岡女子学園も前半の10名台からこの4年間はほぼ20名台に定着。
21位の攻玉社は前半の1桁からこの4年間は10名台で定着。
26位の渋谷教育学園渋谷と栄東はここ3年間10名台をキープ。
同じく25位の世田谷学園と31位の東邦大東邦はこの2年間10名台をキープ。
7位の渋谷教育学園幕張はこの2年間大きく伸びて初の全国ベスト10にランクイン。
20位の芝は2000年、2001年と振るわなかったが、この2年間は着実に伸びているように見えます。
21位の逗子開成、23位の市川、29位の鴎友学園女子は今春大きく伸びています。
④ この10年間で減少傾向が見てとれる学校 16位の巣鴨と18位の桐蔭学園はこの10年であきらかに減ってきています。さらにさかのぼれば、両校ともかつては東大合格者全国ベスト10の常連だった時期があり、過去最高はともに1992年で、巣鴨が78名、桐蔭学園は114名でした。 この10年間では大きな変化は見えないけれど、さらに10年ほどさかのぼってみると、13位の武蔵は特に多かった1992年で85名、その前後は60名台の年が多かったので、やはり20年単位で見ると相当な減少といえます。4位の東京学芸大附もここ数年は50名台の年が多いのですが、90年代は90名前後の年が多く、1993年は103名でした。17位の桐朋もここ数年は20名台ですが、90年代では40~50名台が多かったので、やはり両校ともこの20年の推移を見ると相当に減少しています。
この10年間では大きな変化は見えないけれど、さらに10年ほどさかのぼってみると、13位の武蔵は特に多かった1992年で85名、その前後は60名台の年が多かったので、やはり20年単位で見ると相当な減少といえます。4位の東京学芸大附もここ数年は50名台の年が多いのですが、90年代は90名前後の年が多く、1993年は103名でした。17位の桐朋もここ数年は20名台ですが、90年代では40~50名台が多かったので、やはり両校ともこの20年の推移を見ると相当に減少しています。
(2)学校規模を考慮する
例えば東大合格者が20名のA校と30名のB校ならB校の方が10名多いから実績が良いかというと、必ずしもそうは言いきれません。学校規模つまり卒業生数を考慮する必要があるのは今や常識でしょう。上記でA校の卒業生数が200名なら10%で、B校が500名なら4%ですから断然A校の実績の方が良いということになるでしょう。次に先ほど10年間の推移を見た首都圏中高一貫校34校を、合格者数順ではなく、2013年の卒業生数に占める東大合格者(現浪計)の割合の高い順に並べてみました(学校名の右の数字は今春卒業生数、学校名の左の数字は、左が合格者数の順位、右は割合の順位)。
| 2→1 | 筑波大駒場(163) | 63.2% |
| 1→2 | 開成(399) | 42.6% |
| 9→3 | 栄光学園(164) | 31.7% |
| 5→4 | 桜蔭(232) | 28.3% |
| 6→5 | 聖光学院(226) | 27.4% |
| 3→6 | 麻布(309) | 26.5% |
| 8→7 | 駒場東邦(238) | 24.8% |
| 4→8 | 東京学芸大附(340) | 20.0% |
| 7→9 | 渋谷教育幕張(336) | 18.2% |
| 13→10 | 武蔵(168) | 17.3% |
| 12→11 | 女子学院(222) | 16.7% |
| 11→12 | 筑波大附(239) | 15.9% |
| 10→13 | 海城(375) | 10.7% |
| 14→14 | 浅野(270) | 10.0% |
| 16→15 | 巣鴨(258) | 9.3% |
| 19→15 | 暁星(183) | 9.3% |
| 14→17 | 豊島岡女子(358) | 7.5% |
| 17→18 | 桐朋(326) | 7.1% |
| 30→19 | 雙葉(181) | 6.1% |
| 21→19 | 攻玉社(231) | 6.1% |
| 25→21 | 渋谷教育渋谷(200) | 6.0% |
| 20→22 | 芝(273) | 5.9% |
| 25→23 | 世田谷学園(210) | 5.7% |
| 33→24 | フェリス女学院(181) | 5.5% |
| 21→25 | 逗子開成(261) | 5.4% |
| 23→26 | 早稲田(299) | 4.3% |
| 29→27 | 鴎友学園女子(264) | 4.2% |
| 23→28 | 江戸川学園取手(342) | 3.8% |
| 25→29 | 城北(349) | 3.4% |
| 25→29 | 栄東(357) | 3.4% |
| 23→31 | 市川(482) | 2.7% |
| 33→32 | 東邦大東邦(443) | 2.3% |
| 30→33 | 開智(605) | 1.8% |
| 18→34 | 桐蔭学園(1289) | 1.4% |

栄光学園 合格者数では圧倒的に開成が多いのですが、合格者の割合では1学年4クラス約160名と生徒数が少ない筑波大駒場が圧倒的に高くなることがわかります。
また学校規模が小さい栄光学園は9位→3位、武蔵は13位→10位、暁星は19位→15位、そのほか渋谷教育渋谷は25位→20位、世田谷学園は25→22位、鴎友学園女子は29位→25位とかなり順位を上げます。
逆に学校規模が大きい東京学芸大附は4位→8位、また海城は10位→13位、豊島岡女子は14位→17位、市川は23位→28位、城北と栄東は25→29位、開智は30→33位、また桐蔭学園は18位→31位と大きく順位が下がります。
なお合格者数が10名未満なので上記には入っていませんが、合格者の割合で桐蔭学園の1.4%より高い首都圏の中高一貫校として以下の11校があります。
| 都立桜修館 | 3.9% |
| 浦和明の星女子 | 3.5% |
| 都立小石川 | 3.2% |
| 光塩女子学院 | 2.9% |
| 都立両国 | 2.6% |
| 公文国際学園 | 2.4% |
| 穎明館 | 2.3% |
| 都立白鴎 | 2.1% |
| 吉祥女子 | 1.8% |
| 横浜雙葉 | 1.6% |
| 洗足学園 | 1.5% |
(3)現役合格率について考える
「現役合格率」という言葉の使い方はいくつかあって、
① 1学年中の現役合格した割合を表す場合。たとえば、A高校の卒業生200名中、現役合格した人数(少なくとも1校には合格した、延べ人数ではない実人数)が120名であれば、A高校の現役合格率は60%。
② 1学年中の特定の大学に現役合格した割合を表す場合。たとえば卒業生が200名だったB高校の東大現役合格者が12名なら、B高校の東大現役合格率は6%。
③ 特定の大学の合格者のうち現役合格者の割合を表す場合。たとえば、C高校から東大合格者が現浪あわせて20名合格したが、そのうち現役は12名ならC高校の東大現役合格率は60%。
④ 特定の大学を受験した現役受験生のうち合格した割合を表す場合。たとえば、D高校の現役生が40-名東大を受験し12名が合格したら、D高校の東大現役合格率は30%。
ほとんどの場合は①、②か③の意味で使われています。④は「○○人受験して△△人合格」という「合格率」の本来の意味に即した使い方なのですが、受験者数を公表している学校はほとんどないため④の意味の合格率が外部に出ることはまずありません。(とはいえ内部的には非常に重要な数字です。)
さて多くの人は①の意味の「現役合格率」や「現役進学率」は高ければ高いほどよいと考えているでしょう。確かに「現役で合格(進学)する方がよいに決まっている」というわけです。ところがこれはそう簡単な話ではないのです。
以下は2年前のデータによるものですが、本シリーズ第17話で首都圏の主要な私立中高一貫校の「現役進学率」を、学校の入学レベル別、男子校、女子校、共学校別に集計したものです。詳細は第17話を読んでいただくしかありませんが、ここに総括的な結論を再掲します。
まず学校の入学レベルを以下のようにA~Cの3グループにわける。
Aグループ (市進偏差値で65~70, 最難関レベルの学校)
Bグループ (市進偏差値で55~64, 上位レベルの学校)
Cグループ (市進偏差値で40~54, 中堅レベルの学校)
入学レベル別に男子校,女子校,共学校の「現役進学率」の平均をまとめると、
| 男子校 | 女子校 | 共学校 | |
| Aグループ | 53% | 73% | 62% |
| Bグループ | 59% | 85% | 75% |
| Cグループ | 68% | 83% | 75% |
ご覧のとおり「現役進学率」は男子校、女子校、共学校のいずれにおいても学力上位のグループになるほど低く、またすべてのグループで「現役進学率」は男子校、共学校、女子校の順に高くなっていきます。どうしてこのような状況になるのでしょうか。
まず男女で現役進学に対する志向、執着度にかなりの差があります。男子に比べて、女子は浪人を避ける受験生が多いのはよく知られていることです。
また現役進学率が高い学校はB、Cグループの学校に多く、とりわけ中堅レベルのCグループの学校の実態としては
・推薦入試やAO入試を利用した受験生が多い
・難関大学をチャレンジするのはごく少数
・第一志望が不合格でも受かった大学で進学を決める
といった場合が多いようです。
逆に上位校では現役進学率の低い学校が増えてきます。実態としては、
・推薦入試やAO入試を利用した受験生は少ない
・難関大学をチャレンジする受験生が多い
・第一志望が不合格なら浪人しても初志貫徹の受験生がかなりいる
特に東大などの難関国公立大や医学部志向が強いAグループの最難関レベルの学校ほどこの傾向が強く、そもそも東大や国立大医学部しか受験しない受験生がかなりいる、さらに早慶上智大も1学部しか受験しないし、合格しても浪人して東大や国公立大医学部などにリベンジする受験生がかなりいる、というわけで必然的に「現役進学率」は低くなります。
ただし上記の集計はあくまで各グループの平均であり、実際には同じAグループの男子校でも「現役進学率」にはかなりの差があり、たとえば今春卒業した学年の場合、開成55%、筑波大駒場63%、駒場東邦54%、栄光学園59%、聖光学院78%、(麻布は2013年データがないが例年40%前後)と50%台から70%台までとまちまちです。この差は何に起因するのでしょうか。これは現役での進学への志向性の強弱、あるいは東大(や国公立大医学部)合格への志向性の強弱によるものと思われます。
「現役進学率」が78%と非常に高い聖光学院は、1990年ごろまでは早慶上智大をメインターゲットにする学校でした。ここ20数年で急速に難関国公立大受験にシフトしていますが、東大受験者も早慶大のバックアップをとって受験しており、東大不合格なら、多くは浪人せずに早慶大に進学します。
これに対し、東大合格者全国1位を30年以上続ける開成では、そもそも東大しか受けていない受験生や、早慶大は合格しても東大がだめなら浪人してリベンジという受験生が多く、「現役進学率」は54%と低くなっています。
これは早慶大の「現役合格率」の差からも裏付けられます。聖光学院の早慶大現役合格率115%に対し、開成は45%と大きく下回ります。この差が生じる理由は、もちろん開成の生徒の学力が聖光学院より低いためではなく、開成の早慶大現役受験者が少ないためです。ただし浪人の場合は逆に開成が45%、聖光学院は35%となります。
都内の最上位男子校、開成、麻布、駒場東邦の3校は東大や国公立大医学部などの最難関レベルの国公立大志向が非常に強く、浪人することも辞さない生徒が多いようです。これに対し神奈川の男子トップ2校、栄光学園、聖光学院は現役進学率が60~70%で都内の3校より高目なのは、生徒の志向性あるいは受験への取り組み方などの違いでしょう。

女子学院 女子のAグループの学校の「現役進学率」は男子校ほどの差がなくほとんど80%弱ですが、東大など国公立大や医学部志向が強い桜蔭が75%、豊島岡女子が71%、またここ数年国公立大志向が高くなってきている女子学院は73%とやや低くなっているのは、男子校と程度の差はあれども同様な事情でしょう。
(4)文系進学と理系進学
今回は部分的に触れるにとどめますが、文系・理系の比率(の推移)や学部・系統別の進路状況も重要なファクターであることは論を待ちません。ここでは「理系志向」と「国公立大志向」の関係について指摘しておきます。
個々の生徒の適性という問題はありますが、一般的にいって学校(生徒)の学力レベルが上昇すると理系志望者が増えていく傾向があります。上の学年になるほど増えていた理系→文系への進路変更(いわゆる文転)が減ってきているということもありそうです。近年の理系志向、医学部志向の高まり、あるいは女子の場合、伝統的に文系の進路選択していた高学力層が理系の進路選択をするようになってきた(理系女子、リケジョの増加)ことに後押しされている要素もあるでしょう。
さて芝浦工大や北里大のような理工系、医学・医療系大学を除いて、ほとんどの私大は文系学部が中心です。全国の私立大学の募集定員は、教員養成系、芸術系、体育系、生活系などを除くと文系学部と理系学部が2:1です。
逆に国公立大は一橋大や東京芸術大など一部を除き理系学部の定員の方が多く、研究の実績でも圧倒的に優位にあります。全国の国立大学の募集定員は、教員養成系、芸術系、体育系、生活系などを除くと文系学部と理系学部がちょうど私大と逆に1:2なります。ちなみに東大の前期日程の募集定員は文系が41%、理系が59%です。(後期日程は理Ⅲを除く一括募集)
したがってこの日本の大学の構造的なあり方に規定されて、「学力レベル上昇」→「理系志望者増加」→「国公立志望者増加」という「進化」の定式がほとんどの学校に当てはまります。ただし学校の個性や男子校、女子校、共学校の違いによって「進化」のしかたに差がありますから、そのあたりもしっかり見ていく必要があるでしょう。
(5)大学のグレード別グルーピングについて
大学進学について語るとき、大学を入学レベル別に、「早慶上智」、「MARCH」、「日東駒專」、「大東亜帝国」あるいは「女子大御三家」などの語呂の良いグループ名をつけて呼ぶことがあります。関西圏では「関関同立」[産近甲龍]などが使われています。これにはいろいろなバリエーションがあり、たとえば「早慶上智」に東京理科大を加えて「早慶上理」、あるいは「MARCH」に学習院を加えて「GMARCH」といったところはすでに市民権を得ているようです。大変便利で現在では一般化しているため、本シリーズでもしばしば使っていますが次のような問題もあります。
これらのくくりは入学レベルが近い大学のグループを表わしていると考えられていますが、実際には同じ大学でも学部・学科による差があり、またほぼ同レベルの大学がグループに入っていないようなこともあります。たとえば武蔵、成蹊、成城などの大学の入学レベルは学部・学科によってはGMARCHと同レベルなのに、このグルーピングではこれらの大学(の合格者)はカウントされません。また男女による進路志向の違いもこのグルーピングではうまくとらえることができません。たとえば女子ではGMARCHや日東駒專のかわりに女子大や医療系大学を受験する受験生も多いのです。さらに個性を重視し、美術系、音楽系、国際系、教養系など多彩な進路を特色としている学校は、このくくり方では全く進路傾向をとらえることができません。というわけで上記のくくり方は大学進学状況のおおざっぱな傾向は見ることができても、細かく見ていくといろいろ問題があることを承知しておいた方が良いでしょう。
なお国立大にはあまり語呂のよいグループ名はなく、あえて言えば旧制の帝国大学だった東大、京大、東北大、北大、阪大、名大、九大を指す「旧7帝大」や昔の入試制度による「旧一期校」「旧二期校」という呼称が現在でも一定の有効性を持つものとして使われることがあります。また首都圏の学校の場合は「東大・京大・一橋大・東工大」あるいは「旧7帝大プラス一橋大・東工大」さらにこれに「国公立大医学部(医学科)」を加えたくくりで最難関国立大学とすることがあります。ちなみに一橋大・東工大をほとんど受験しない関西圏での難関国公立大のグループ名は「京大・阪大・神戸大」が一般的です。