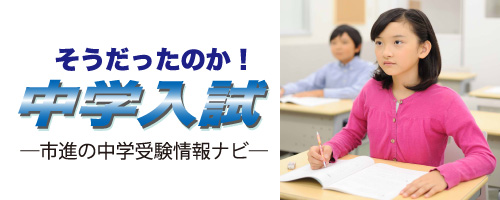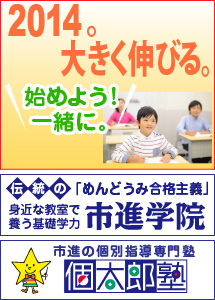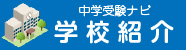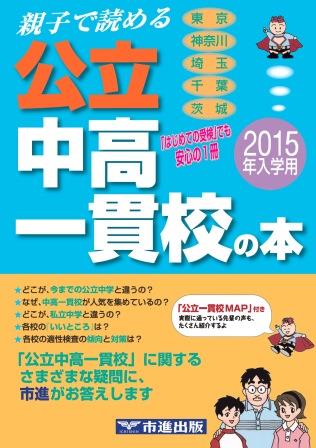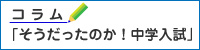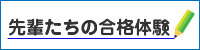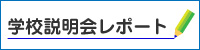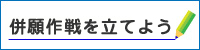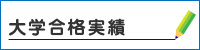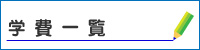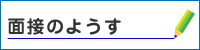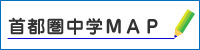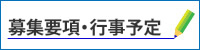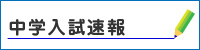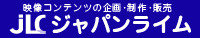第60話 2014年中学入試レポート ― 2月 神奈川の私立中入試(2)―
2014年8月8日
なお学校名の右の数字は2013年→2014年の応募者(前年比)と倍率、倍率は合格者/受験者による実質倍率で合格者は正規合格者で繰り上げ合格者を含めずに算出しています。またMは男子、Fは女子です。
(2)女子校(つづき)
女子中堅レベル校の入試では応募者を減らした学校が多い中で、いくつか注目される学校があります。またここへ来て有力大学と絡む動きが出てきているのであわせてお伝えします。
| 日本女子大附 | 1回 | 215→230名(107%) | 2.1→2.2倍 |
| 2回 | 364→364名(100%) | 3.3→3.3倍 | |
| 神奈川学園 | A1 | 184→234名(127%) | 1.7→1.8倍 |
| A2 | 351→470名(134%) | 1.8→1.4倍 | |
| B | 379→468名(123%) | 1.7→1.8倍 | |
| C | 263→366名(139%) | 2.2→2.6倍 | |
| 横浜女学院 | A | 112→116名(104%) | 1.5→1.5倍 |
| B | 365→460名(79%) | 1.8→1.3倍 | |
| C | 417→289名(69%) | 1.9→2.9倍 | |
| D | 227→208名(92%) | 1.5→3.0倍 | |
| E | 306→207名(68%) | 1.9→6.4倍 |
日本女子大学附(川崎市多摩区)はアメリカの大学でキリスト教とともに先進的な女子教育のあり方を学んだ成瀬仁蔵によって設立された日本最古の女子大の付属校で、明治34年(1901年)大学の設立と同時に高等女学校として開校しています。当時の日本の女子教育の水準を考えると、開校当初から高等教育へ接続することを前提とした中等教育は画期的なもので、「社会の発展に貢献できる人」「国際的視野が持てる人」を育てることが教育目標とされるなど、明治期に設立された英語教育を中心とするリベラルアーツ教育(教養教育)の「お嬢様学校」とはかなり色合いが異なる学校です。(成瀬仁蔵はキリスト教の牧師ですが学校はミッション校ではありません。)
ここ数年は応募者減少、緩和傾向が続いていましたが、外部の合同相談会への積極的な参加や西生田講堂の建設費の償却が終わり学費を低減したこともあり、昨年から入試は1回が少しずつ増加傾向にあります。偶然ですが2回の応募者、受験者、合格者が前年と全く同数でした。繰り上げは23名で前年より2名多くなっています。

神奈川学園
神奈川学園(横浜市神奈川区)は横浜駅から徒歩圏内の唯一の私立中学で、神奈川の女子中では数少ない非宗教系の学校です。2000年から始動した「21世紀教育プラン」は2008年から第2ステージ、2011年には第3ステージに入り、出口の大学合格実績でも成果が出てきていています。2012年からの3年間で、国公立大が7→7→10名、早慶上理大が10→40→29名、GMARCH大は57→80→106名と大きく伸び、今年の現役四大進学率は過去最高の89.6%でした。今後は新カリキュラムの効果で国公立大進学と理系進学がさらに伸びて行くものと思われます。
なお今年文科省からSGH(スーパーグローバルハイスクール)アソシエイト校の指定を受けています。入試では前年応募者を減らしましたが、今年は4回の入試すべて応募者が増え総数で53%の大幅増です。受験者の学力層も上がって難易度も上昇しています。
横浜女学院(横浜市中区)は山手の丘にある4校の女子校の1つで横浜共立学園に隣接しているキリスト教主義の学校です。2013年春は東工大、東京医科歯科大、北大に各1名、東北大2名、早慶上智大27名、GMARCH大31名など大学合格実績を大きく伸ばしましたが2014年入試では帰国入試を含めた総数で1,543→1,199名と22%の減少です。1日午後のBが併願者の多い山手の丘の他の3校の受験者減に連動して減るのは当然ですが、2日のCも31%の大幅減です。しかしC・D・Eは合格者を絞っているためむしろ倍率は上がっています。現在の高2が卒業する2016年あたりから国公立大の合格者が飛躍的に伸びることが予想されています。
2015年入試ではAの定員を5名減員、Cを5名増員、Eを10名減員、また午後入試のBとCの試験科目を2科・4科選択入試から算数・国語の2科入試に変更します。
| 横浜英和女学院 | A1 | 66名(新設) | 1.8倍 |
| A2 | 126→155名(123%) | 1.9→1.8倍 | |
| B | 108→184名(170%) | 2.0→1.6倍 | |
| C | 194→186名(96%) | 1.6→1.9倍 | |
| 清泉女学院 | 1期 | 171→150名(88%) | 2.1→2.0倍 |
| 2期 | 222→252名(114%) | 2.4→2.3倍 | |
| 聖園女学院 | 1次 | 103→109名(106%) | 2.6→2.6倍 |
| 2次 | 139→145名(104%) | 2.4→2.3倍 | |
| 3次 | 215→200名(93%) | 2.0→2.0倍 | |
| 4次 | 124→136名(110%) | 2.6→1.6倍 |

横浜英和女学院
創立134年目の緑豊かな蒔田(まいた)の丘のプロテスタント系ミッション校横浜英和女学院(横浜市南区)は創立130周年記念事業として進められていたキャンパス再開発の一環として昨年中高の新校舎が完成しました。入試では2012年から2年連続で応募者の減少が続き生徒募集では苦戦していましたが、今春入試では2月1日に午前入試A1を新設し、1日午後のA2、2日午後のBも上位校との併願者が増えて大きく応募者数を回復し、A2、B、Cは倍率も上昇しボーダーの難易度も上がっています。
2015年は2月1日が日曜日のため1日の午前は入試を行わず、かわりに2日に午前入試を新設します。各回の定員配分の変更もあり注意が必要です。
さらに今年の6月になって青山学院大学の系属校提携の最終協議段階にあるという重大発表があり、7月18日には正式に「協定書」が締結されました。実は青山学院も横浜英和女学院もほぼ同時期に米国のメソジスト会の宣教師によって設立された学校です。
以下に「系属校」化についての重要なポイントをまとめておきます。
- 2016年4月より青山学院大学の「系属校」となる。学校経営は今まで通り「学校法人横浜英和学院」が行う。
- 2016年4月より「青山学院横浜英和中学校・高等学校」と校名変更。
- 2018年4月入学の中1生より共学化。
- 2016年入学生より進学条件を満たせば全員青山学院大学へ進学できるようになる。
- 進学条件は2015年1月ごろ決定予定。もちろん進路希望に応じた他大学進学も可能。
- 2016年以前の入学生の推薦等の扱いについては、2015年1月ごろ決定予定。
- 基本的な教育方針は変更しない。
- 一部で相模原市の青山学院大学淵野辺キャンパスへの移転が噂されていたが、校地の移転はしない。
- 校訓・校歌・校章・制服の変更はなし。
- 57年間続いている給食も継続する。(共学化以降の男子向けメニューは検討する)
- 学校行事の運営やクラブ活動は共学化に配慮して工夫し整備する。
- 海外の姉妹校(現在共学校1校、女子校3校)については新たに共学校を加えていく予定。

聖園女学院
みその台の高台にあるカトリック・ミッション校の聖園女学院(藤沢市)は同じカトリック系の湘南白百合、清泉女学院や聖セシリア女子との競合がありますが、今春入試では前年を上回る応募者を集めています。近年では山手学院、湘南学園、森村学園などの共学校との併願者も増えているようです。
2015年入試では大きな変更があります。前年は1日午前、2日午前・午後、3日午前と4回の入試でした。2015年入試では4回の試験回数は変わりませんが1日、2日両日に午前・午後に入試を行い3日はやめて2月2日で入試を終了することになります。これにより湘南白百合や鎌倉女学院の入試日変更のため1日午後や2日の午前・午後は応募者が増える可能性が高く注意が必要です。
また聖園女学院と愛知県の有力私大との新たな関係が7月7日になって発表されました。こちらは「系属校」化ではなく2016年4月に名古屋市のカトリック系の南山(なんざん)大学と法人合併することを前提とした協議開始です。聖園女学院と南山大学はともにヨゼフ・ライネルス神父を創立者とする学校で、5年前の2009年に聖園女学院の経営母体の「聖心の布教姉妹会」が経営から退くことを決めていて、南山大学が経営を引き継ぐことになったもので、すでに南山学園の理事が聖園学院の理事として就任しています。背景には今まで学校経営を担ってきた修道会のシスターの高齢化や後継者難があるようです。このような事態はこの学校に限ったことではなく、今後同様のことがおこる可能性がありそうです。(かつてカトリックの女子校の校長は例外なくシスターでしたが、近年では聖職者ではない一般人の先生が校長になるケースが増えています)
なお法人合併後も教育方針や教員組織、諸規則は変更せず今まで通りの学校運営が行われるとのことですから、共学化されることはないものと思われます。
次の3校はすべてカトリック系のキリスト教主義学校ですが、簡単に入試状況を見ておきましょう。
| 清泉女学院 | 1期 | 171→150名(88%) | 2.1→2.0倍 |
| 2期 | 222→252名(114%) | 2.4→2.3倍 | |
| 聖セシリア女子 | 1次 | 164→142名(87%) | 3.1→2.9倍 |
| 2次 | 274→236名(86%) | 1.9→2.4倍 | |
| 3次 | 259→226名(87%) | 2.1→2.0倍 | |
| カリタス女子 | 1回 | 109→112名(103%) | 1.9→2.0倍 |
| 2回 | 234→209名(89%) | 2.4→2.0倍 | |
| 3回 | 140→156名(111%) | 3.6→2.1倍 |
清泉女学院(鎌倉市)は大船の高台の戦国時代の城跡にあり見渡す限り緑に囲まれ自然に恵まれた学校です。校長が須田和男先生に変わったころから大学進学指導や広報活動にも積極的に取り組むようになったようで、難関大学実績も少しずつ上がり、この春は京大、一橋大、お茶の水女子大、東京農工大、東京海洋大など国公立大の実績も出ています。今春入試は1期12%減、2期14%増で合計では前年並みでした。 2015年入試では湘南白百合と鎌倉女学院の入試日移動に対応し1期を2/1→2/2とします。しかし前回のミッション・ショックの年に2/3→2/4とした2期は2/3のままとなるため2日・3日の連続入試となります。

聖セシリア女子
聖セシリア女子(大和市)は中学募集の定員が105名と小規模な学校です。特定の教派・教団によって設立されたミッション校ではありませんが、創立者の信仰によるカトリック精神に基づいた教育が行われています。また少数の高校募集を行っていましたが、2013年から高校募集を停止し完全中高一貫校になっています。2014年入試は3回の入試とも10%以上の応募者減ですが、その内訳を見ると2科受験生は微増で、4科受験生の減少が大きくなっています。
2015年入試では1次の定員を5名減、3次を5名増員と定員配分の変更があります。また帰国生入試を12月21日に新設。試験科目は算数・国語・英語から2科目を選択、面接は保護者同伴で、英語の出題レベルは英検3級程度です。

カリタス女子
カリタス女子(川崎市多摩区)も中学募集の定員が110名と小規模な学校です。併設の短大が閉校になりますが、今までもほとんど進学者はいなかったので実質的には進学校です。2013年入試で応募者を大きく減らしましたが、2014年入試でも総応募者が微減。
予想に反し定員を増やした2回が予想に反し大きく減り、またリベンジ受験者が多く、重複受験者を除く実人数はかなり減っているようです。これは受験生のエリアが重なっている世田谷区の恵泉女学園と多摩市の大妻多摩との競合によるものと思われます。
2015年入試では数年ぶりに午後入試を復活し、3回の日程を前倒しします。
| 1回 | 2/1午前、4科→2/1午後、2科 |
| 3回 | 2/6→2/5 |
また今春、東大・京大・一橋大合格者が各1名出ていますから、注目度が高くなっていて応募者を回復する可能性があります。
(3)共学校
神奈川の私立中学は東京と同様に伝統校やトップレベルの学校はほとんどが男子校か女子校で、共学校の多くは大学付属校です。トップレベルに位置するのは次の1校だけです。
| 慶應湘南藤沢 | 1次 | 713→655名(92%) | 2.0→1.9倍 |
| 2次 | 289→280名(97%) | 2.3→2.2倍 |
慶應湘南藤沢(藤沢市)は1次、2次の2段階選抜なので1次は応募者の前年比ですが、2次は受験者の前年比です。2段階選抜のため前年までは1次試験から2次の合格発表までの期間が長く(2/2~2/7)ここ数年1次試験を合格しても2次試験を欠席する受験生が増えていました。2014年入試では2次の日程を2日間短縮する入試改革の結果、2次試験の欠席者は52→39名と減り、欠席率(2次欠席者/1次合格者)も15→12%と下がり、この入試改革は一定の成果を収めたようです。

慶應湘南藤沢しかし応募者自体の減少傾向は続いていて、男子が3年連続の減少で今年は6%減、昨年は微増だった女子は11%減とかなりの減少です。ただコアな受験者層は健在なのか難易度の低下はほとんどないようです。2015年入試では入試日を2月2日に移動するフェリス女学院などの有力な女子校と1次の入試日が重なりますから、女子の応募者はさらに減ることが予想されます。
次に慶應湘南藤沢以外の大学附属校の入試結果を見ておきます。
| 中央大学附横浜 | 1回 | M | 314→268名(85%) | 2.7→2.3倍 |
| F | 275→287名(104%) | 2.4→2.1倍 | ||
| 2回 | M | 527→456名(87%) | 3.6→2.9倍 | |
| F | 551→509名(92%) | 3.8→3.7倍 | ||
| 3回 | M | 394→349名(89%) | 14.6→7.4倍 | |
| F | 404→359名(89%) | 16.4→9.0倍 | ||
| 日本大学(日吉) | A | 629→567名(90%) | 2.3→2.1倍 | |
| B | 802→750名(94%) | 4.3→2.9倍 | ||
| C | 751→705名(94%) | 5.4→4.0倍 | ||
| 日本大学藤沢 | 1回 | 329→270名(82%) | 2.7→1.9倍 | |
| 2回 | 428→384名(90%) | 4.5→3.0倍 | ||
| 東海大学付相模 | A | 65→217名(82%) | 1.5→1.3倍 | |
| B | 325→255名(78%) | 2.4→1.2倍 ※受験者は半減 |
||
ご覧のとおり主要な大学付属校はすべて応募者を減らしています。これは神奈川に限ったことではなくここ2~3年の全般的な「大学付属校ばなれ」ともいえる現象です。この原因はいくつか考えられますが、今までも何度か述べてきたように、以下の2つが主な要因でしょう。
- ①有名大学付属校の多くは学費が私学の平均的よりかなり高めで、好況だった時期はよかったのですが、リーマンショック以降の経済状況のなかで避けられているようです。
- ②6年後の進路選択を考えて、有名私立大学の付属校より国公立大など幅広い進路に対応できる進学校系を選ぶ家庭が増えていることもあります。

中央大学附横浜
中央大学附横浜(横浜市都筑区)は2012年の共学化、2013年の新校地への移転によって爆発的な人気となりましたが、今春は応募総数で男子が13%減、女子は6%減とかなり減っています。これは高倍率に対する敬遠もありますが、大学の方針転換によって付属色が強くなり、進学校志向の受験生が減っているという要素もあるようです。とりわけ男子にその傾向が顕著です。
日本大学(横浜市港北区)の応募者減は、都筑区に移転してきて近くなった中央大附横浜と2016年の共学化に向けて新校舎建設中の法政大第二という付属校同士の競合が厳しくなっているのが主な要因です。前年は男女ともに減りましたが、今年は応募総数で男子が14%減、女子はやや回復して3%増と男女で異なる傾向です。これは法政大第二(現在は男子校)の影響を強く受けているためと思われます。
なお日大への推薦率は55%と首都圏の日大系列校の中では低目ですが、他大学進学が増えていて、前年は東大1名、東工大2名、東北大1名など難関国公立大の合格実績を伸ばしましたが、今春は早慶上智大が11→26名、GMARCH大は34→114名と難関私大実績が大きく伸びています。

日本大学藤沢
日本大学藤沢(藤沢市)は中学開校が2009年ですから今年で6学年がそろい、来春には1期生が卒業します。2014年入試では人気が上がっている逗子開成や湘南学園の影響を受けたのか応募者を減らしています。2回の合計で男子が14%減、女子は13%減です。日大への推薦率は48%で首都圏の日大系列校では最も低い水準です。2015年以降は中高一貫の卒業生により、さらに高いレベルの他大学進学が増えることが予想されます。
東海大学付相模(相模原市)は中堅大学付属校の多くが特進コースの設置や他大学進学対応のカリキュラム導入など半進学校化への道を模索するなかで、他の東海大系付属校と同様に中高大10年一貫教育を謳い、東海大学への進学を前提とした付属色の強い学校づくりをしています。その当否は別として、受験者が6年後に東海大学へ進学する希望者層に限定されて、併願受験者に選ばれなくなっているようで、他の東海大系付属校と同様に応募者が減り続けています。応募者がA,Bともに20%前後の減少ですが、実受験者では2回の合計で393→275名と30%減です。第一志望者中心の入試ですから、Bの受験者はほとんどがAの不合格者で、難易度が緩和しているようです。
次の2校は付属校ですが、実際にはほぼ進学校化している学校です。
| 神奈川大学附 | A | 851→698名(82%) | 3.7→2.0倍 |
| B | 791→667名(84%) | 5.5→3.7倍 | |
| C | 676→557名(82%) | 22.0→14.0倍 | |
| 関東学院 | 1期A | 184→193名(105%) | 2.0→2.1倍 |
| B | 478→455名(95%) | 1.7→2.2倍 | |
| C | 404→365名(90%) | 2.1→2.3倍 | |
| 2期 | 257名(新設) | 2.0倍 |

神奈川大学附
神奈川大学附(横浜市緑区)は併設の神奈川大進学者がこの3年間で12→8→1名と急減しています。今年の応募者減はここ数年応募者増、倍率上昇、難化傾向が続き、特に前年の応募者急増によってチャレンジ層に敬遠されたものです。
今春は東大合格者が3→0→3名と回復、さらに京大1名、東工大3名、東北大4名、北大2名など国公立大合格者が38→74名とほぼ倍増、早慶上智大も70→124名と大きく伸ばしていますから、2015年入試で応募者が増える可能性大です。なお2015年入試よりB、Cの入試日を1日ずつ前倒しします(B 2/4→2/3、C 2/6→2/5)。この入試日変更は公立一貫校(特に横浜市立南高附中学)との併願者が多く、手続き終了後に多数の辞退者が出て困っていましたから、それを避けるために公立一貫校の入試日(2/3)にBをぶつけたものです。またCの日程変更もこれにともなうものです。この入試日程変更によって併願校が変化することが予想され、入試状況にどのような影響があるか注意深く見ていく必要があります。
関東学院(横浜市南区) は三春台の丘にあるプロテスタント・ミッション校で、併設の関東学院大への推薦率は3%です。今春は東大に1名合格者を出しました。カリキュラムの改革や、外部から進路指導の経験豊富な人材を入れたりして進学校化を進めています。まだ難関大実績が多いとは言えませんが、今後さらに伸びて行くものと思われます。入試では第一志望者の多い2月1日午前のⅠ期Aがやや増えています。上位校との併願者の多い午後のBはやや減っていますが、合格者を大きく絞り込んで倍率が上昇し厳しい入試となっています。2期は5日→7日と入試日を移動して山手学院と重なり応募者が30%の大幅減ですが、実受験者は予想を超える120名でした。
2015年入試では2月1日が日曜となるためいくつかの変更があります。
| 1期A | 2/1午前 4科 70名→2/1午後 2科 50名 |
| B | 2/1午後 2科 50名→2/2午前 4科 70名 |
| C | 2/3午前 60名 変更なし |
| 2期 | 2/7午前→2/6午前 |
これを見ると募集の中心が1日から2日になりそうです(以前は2日入試校でした)。
最後に進学校系の学校を見ていきます。まず完全な共学校で比較的ソフトなイメージの3校です。
| 山手学院 | A | 316→339名(107%) | 2.4→2.3倍 |
| B | 682→726名(106%) | 1.7→1.8倍 | |
| C | 462→439名(95%) | 3.8→3.7倍 | |
| 後期 | 506→542名(107%) | 3.9→4.9倍 | |
| 湘南学園 | A | 535→488名(91%) | 2.7→2.0倍 |
| B | 355→329名(93%) | 4.1→3.1倍 | |
| C | 358→299名(84%) | 4.2→3.5倍 | |
| D | 333→333名(100%) | 5.2→8.5倍 | |
| 森村学園 | 1回 | 141→182名(129%) | 2.2→2.6倍 |
| 2回 | 250→255名(102%) | 2.8→2.9倍 | |
| 3回 | 288→318名(110%) | 3.0→4.6倍 |

山手学院
山手学院(横浜市栄区)は明るく元気の良い校風の人気校で、時代に先駆けて高2で全員参加の北米研修を40年以上実施しています。また現在では中3での全員参加のオーストラリア・ホームステイも行っています。さらに近年では「国際交流」とともに「進学指導」にも力を入れ、ここ2年間の現役4大進学率は92%という高い水準です。進路先は早慶上智大やMARCH大などの私立大が主力ですが、難関国立大の合格者も少しずつ出てきています。今春の難関大学の実績はふるいませんでしたが、中高一貫体制へのシフトを強めており今後さらに伸びて来るものと予想されます。
今春の入試ではC以外の3回で応募者が増えていますが、昨年入試で応募者が急増して倍率が上がった神奈川大付や湘南学園から受験者が回ってきたためでしょう。倍率は後期を除き前年並みで難易度もほとんど変化していないようです。2015年入試では後期を2月7日→6日に1日前倒し、また2科・4科選択入試だったA,Cと後期を4科入試に変更します。

湘南学園
湘南学園(藤沢市)は湘南の高級住宅街として知られる鵠沼(くげぬま)にあり、かつては裕福な家庭の子女が通う学校というイメージが強かったのですが、現在の生徒はほとんど一般家庭の普通の子供たちです。学校改革によって進学校への転換を図っていましたが、2010年4月に山田明彦先生が校長に就任以来(山田先生は校長就任以来、学校のHPに掲載している「校長通信」を登校日は毎日(!)更新しています。しかも各回とも結構な内容とボリュームです。)、教職員間の風通しがよくなり全員がひとつの方向へまとまっていこうという機運ができて、それが学習指導・進路指導でも良い結果を生んだのか、2012年には東大2名、一橋大1名、東工大2名、早慶上智大64名など大学合格実績を大躍進して大人気となり、翌年の2013年入試では応募者が総数で70%増と激増し、難易度も上がりました。さすがに2014年入試ではチャレンジ層に敬遠されたようで、応募総数が8%減ですが、この3年間の応募総数の推移は、929→1,581→1,449名ですから今年が8%減と言っても2年前までの水準とは全く異なります。単に人数が増えただけではなく受験者層が上がっていますから、以前の感覚で受験するのは危険です。なお2015年の入試要項は変更ありません。
森村学園(横浜市緑区)は中学からの募集が約90名と小規模募集の学校です(併設小からの進学者を含めて1学年約200名)。1978年に東京の高輪から現在地に移転し女子校から共学校になって40年近くたちますから、すっかり神奈川の共学校として定着しています。2010年には創立100周年記念事業として新校舎が完成しました。校風や生徒たちの雰囲気など湘南学園と非常に似ていて、学校改革によって進学校に転換したのも湘南学園とほぼ同時期です。近くに神奈川大附、桐光学園、桐蔭学園、あるいは隣接する東京(校門を出て1分も歩けば東京都町田市です)の桜美林や帝京大学などの共学系の有力校があり毎年どこかと競合していますが、このところは神奈川大附と桐光学園との競合が目立っているようです。2012年、2013年と応募者の減少が続きましたが、2014年入試では応募総数で11%増とかなり回復しました。難易度はほとんど変わっていないようです。今春は国公立大学合格実績が過去最高で東工大2名、東北大2名、秋田大医学部1名、山形大医学部1名など含めて27→30名でした。2015年入試では3回を2月5日→4日に変更しますから、併願校が変化する可能性があり注意が必要です。
次に男女で生活する校舎と授業のクラスが別という「別学」「併学」などと呼ばれている2校です。
| 桐蔭学園 | 中等 | 1次 | 174→163名(94%) | 6.3→7.3倍 |
| 2次A | 231→253名(110%) | 3.7→3.6倍 | ||
| 2次B | 423→440名(104%) | 3.8→3.7倍 | ||
| 3次 | 398→436名(110%) | 3.8→4.1倍 | ||
| 男子 | 1次 | 183→176名(96%) | 1.8→1.5倍 | |
| 2次A | 230→251名(109%) | 1.6→1.7倍 | ||
| 2次B | 449→460名(102%) | 1.8→1.7倍 | ||
| 3次 | 412→428名(104%) | 1.9→1.9倍 | ||
| 女子理数 | 1次 | 45→38名(84%) | 8.4→8.3倍 | |
| 2次A | 72→79名(110%) | 3.3→3.8倍 | ||
| 2次B | 92→113名(123%) | 2.7→2.6倍 | ||
| 3次 | 93→87名(94%) | 3.6→4.0倍 | ||
| 女子普通 | 1次 | 56→41名(73%) | 1.1→1.3倍 | |
| 2次A | 85→83名(98%) | 1.1→1.3倍 | ||
| 2次B | 109→115名(106%) | 1.7→1.8倍 | ||
| 3次 | 113→100名(88%) | 1.7→2.7倍 | ||
| 桐光学園 | 1回 | M | 242→279名(115%) | 1.8→2.1倍 |
| F | 111→142名(128%) | 1.4→1.5倍 | ||
| 2回 | M | 317→373名(118%) | 1.7→2.0倍 | |
| F | 157→203名(129%) | 1.3→1.5倍 | ||
| 3回 | M | 349→452名(130%) | 1.6→2.2倍 | |
| F | 167→208名(125%) | 1.4→1.7倍 |
桐蔭学園(横浜市青葉区)は厳密に言えば男子校である中等教育学校と男女併学の中学校の2つの学校ですが、入試は一体として行われており、ここでは便宜上あわせて見ていきます。入試は以下のような仕組みで行われています。まず1次、2次A,2次B、3次はすべて入試日・時間帯・入試問題が同一で、男子なら中等教育学校を第1志望、中学校を第2志望として受験することができ、(実際多くの受験生はこのパターンで受験しています。ただし第1志望を中学校、あるいは第2志望なしも可能です)、試験の成績によって第1志望の中等教育学校で合格、または第2志望の中学校へスライド合格、あるいはどちらも不合格という判定となります。女子は中学校しかありませんが、女子部には理数コースと普通コースがあり、男子の中等教育学校と中学校に相当し、男子と同様に第1志望、第2志望の判定が行われます。男子の中等教育学校と女子の理数コースは他の学校の特進コースと思えばよいでしょう。
入試状況は前年の応募者は男女ともに減少しましたが、今年は男子がやや復調し、女子は理数コースの2次A・Bで増えていますが、普通コースが定員減のため相当に減少しています。難易度は男子が前年並み、合格者を絞り気味にした女子はボーダーあたりが前年より厳しかったようです。
なお今年で創立50周年を迎えたのを機に、教育の内容や方法について抜本的な改革が始動しています。その全体像をお伝えすることはできませんが、グローバル化への対応、センター試験の廃止と達成度テストの導入など大きく変わる大学入試への対応、中高一貫教育の基本的システムの見直し、ICTを活用した授業方法の改善、キャリア教育と学校行事の体系化・有機化などにわたる大きな改革となり、今後の桐蔭学園の動向が注目されるところです。

桐蔭学園
入試についてもこの学校改革に連動して2015年入試から非常に大きな変更があります。最も重要なのは2月2日に午後入試(国語・算数・英語から2科目選択)を新設することと、5日に4次(4科目)を新設すること、および入試問題の変更です。
これにともない各回の定員配分も変わります。詳細は割愛しますが2月1日の1次、2日の2次午前・午後の定員を総数で110名減らし、3日の3次と5日の4次の定員は110名増やして後半日程に定員の比重を移しているのが注目されます。
入試問題では論述を含む記述形式の問題を3割程度出題し、解答に応じた部分点も付けます。また今まで中等教育学校、中学校男子部、女子部すべて共通問題でしたが、来年から女子の算数の一部が別問題となります。
*桐蔭学園の入試データについては以下のことに注意してください。
例えば今年の入試で最も応募者が多かった3日の中等教育学校2次Bの受験者273名と中学校男子部2次Bの受験者241名は、実際には相当な人数が重なっているため、2月3日に受験した男子の実人数は273+241=514名ではなく273名(+α)です。(中等教育学校のみ、あるいは中学校のみを志望した受験生の人数は公表されていないため正確な人数は算出できません)また倍率についても中等教育学校については問題ありませんが、中学校は前記の表の1.7倍というのは形式的なもので、実際には第1志望の中等教育学校で合格した73名(-α)は第2志望の合否判定から除かれますから、中学校の判定を受けたのは中学校受験者241名から73名(-α)を引いた168名前後(これも正確な人数はわかりません)で、中学校2次Bの合格者は140名ですから本当の倍率は1.2倍程度ということになります。
スライド合格の判定を行う学校では倍率の算出の仕方が難しいのですが、特に桐蔭学園の男子の場合は入試システムが2つの学校にまたがっていて分かりにくくなっているので注意が必要です。
桐光学園(川崎市麻生区)は前年の入試で応募総数が9%減、受験総数で17%も減りましたが、2014年入試では4回すべての入試で男女とも応募者が増えて、応募総数で23%増、受験総数は30%の大幅増となり一昨年を上回る好調な入試となりました。この応募者数の回復は、前年の倍率低下に対する好感とともに、2013年春の大学合格実績が、東大6名、東工大16名、東北大5名、北大2名、名古屋大2名、九大2名など旧帝大クラスで合計33名、国公立大合計で147名、早慶上智大259名など好調を維持していることもあるでしょう。また競合する神奈川大附や洗足学園が難化して敬遠した受験生が回ってきた可能性もありそうです。今春の大学合格実績も最難関の旧帝大クラスが33→36名と増え、私大でも明大、中央大の合格者が全国で一位になるなど好調でしたから2015年入試でも人気を維持しそうです。
(おわり)
[次回予告] 「2014年 大学合格実績が伸びた中高一貫校、その躍進の秘密を探る」
大学合格実績については、いろいろな視点、切り口での分析が可能ですが、次回は幅広い視点から大学合格実績の伸びているいくつかの学校をケース・スタディとして取り上げ、その実績伸長の背景を探ってみます。